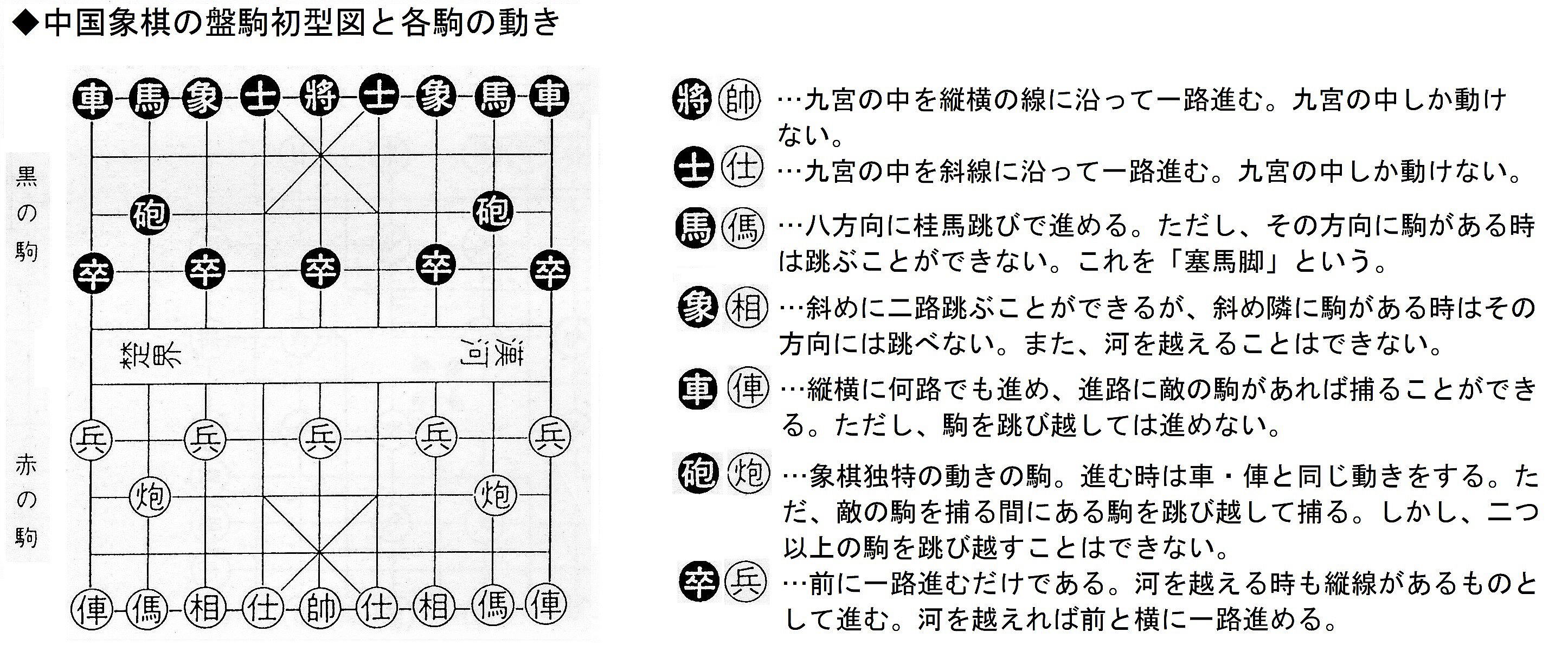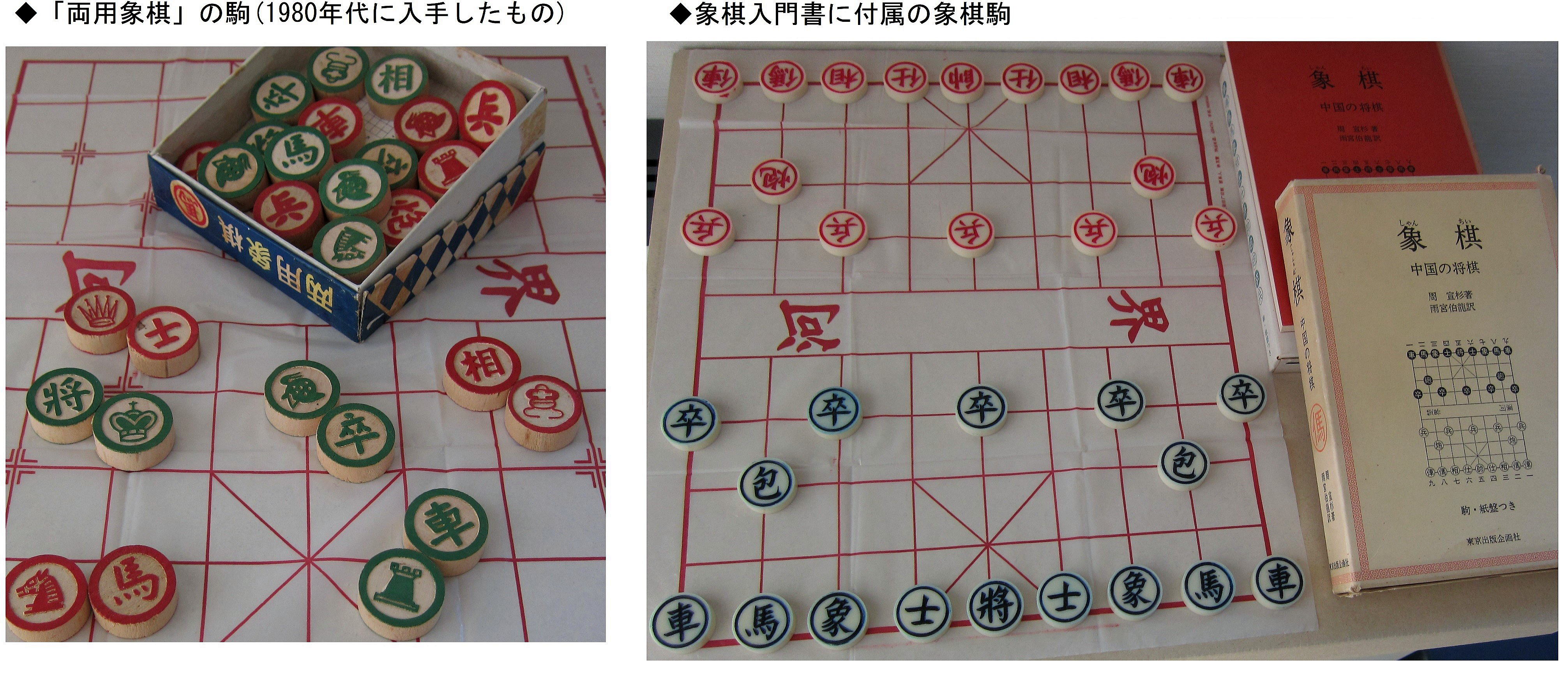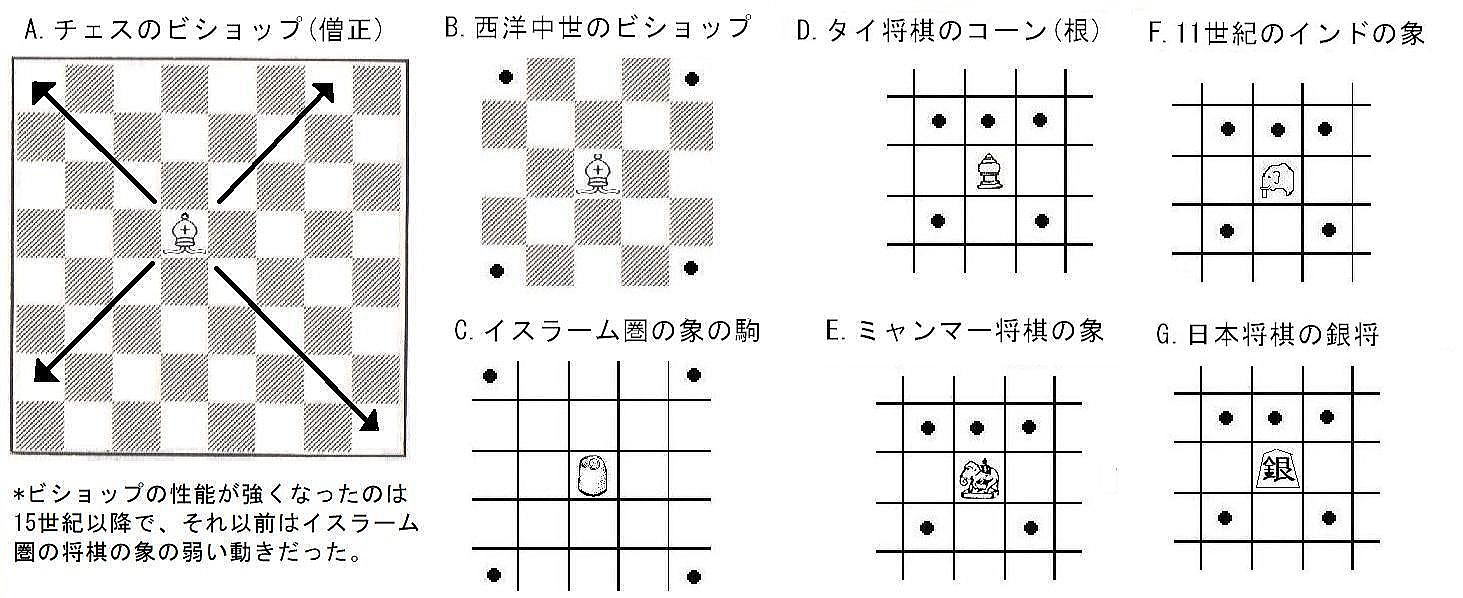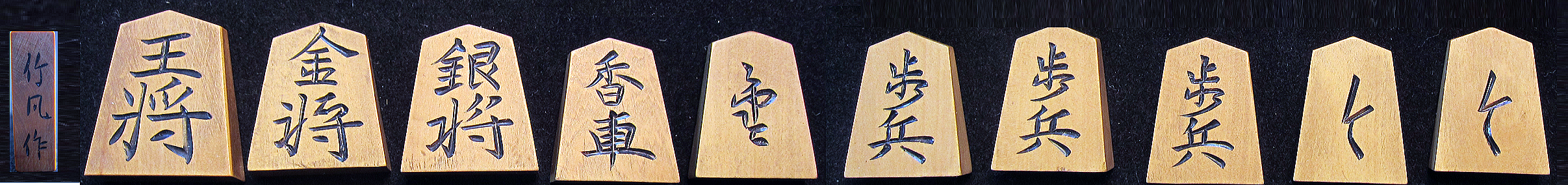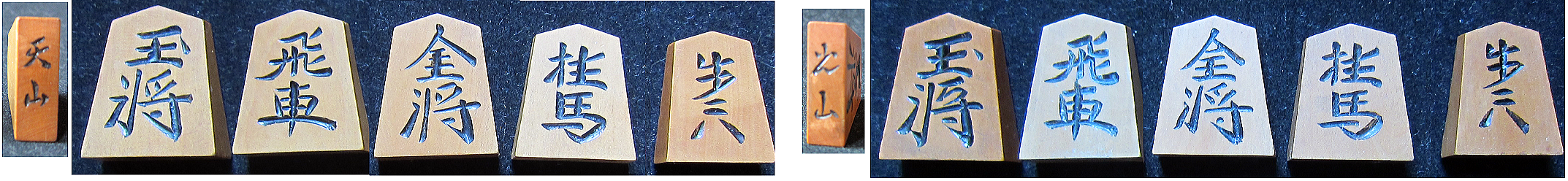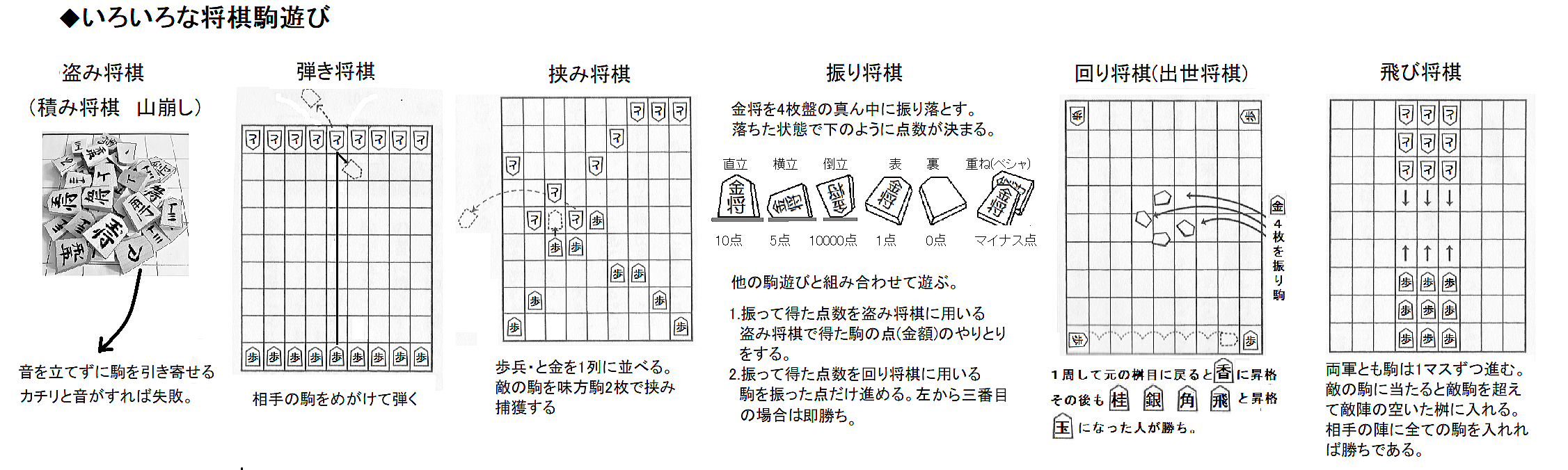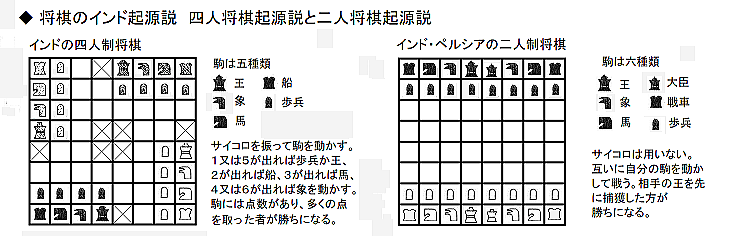�鉺���O�O�x������@������D�ҁ@�O�R(��������)
�@
��������̂�����i���̂P�j�@��������̂������i���̂Q�j
��������̂������i���̂R�j�@��������̂������i���̂S�j
��������̂�����i���̂T�j�@��������̂������i���̂U�j
��������̂������i���̂V�j�@��������̂������i���̂W�j
��������̂�����i���̂X�j�@��������̂�����i���̂P�O�j
�ԊO�҂��̂P�@�ԊO�҂��̂Q�@�ԊO�҂��̂R�@�ԊO�҂��̂S�@�ԊO�҂��̂T�@
��������̂�����i���̂P1�j�@��������̂������i����1�Q�j
��������̂������i����1�R�j�@��������̂������i����1�S�j
��������̂������@�i���̂P�j
���͂��߂�
�����́A�����̖ʔ��������Q�[���ł���A�×����`�����ꂽ�䂪���̕����ł��B�����āA�����̊y���݂ɂ͍H�|�i�Ƃ��Ă̔Ջ�̌������𖡂키�Ƃ����ʂ�����܂��B����͌����Ċ����ւ̐��i�Ƃ͖����ł͂���܂���B
���đ�R�\�ܐ����l�͏����t�@���ւ̍u�b�̒��ŁA�u���͂̏�B�ɂ́A�ǂ���������Ƃ��厖�ł��v�ƌ���Ă����܂����B�u�ǂ���ň����ɐ^���Ȏv�������߂Ďw���ΕK�����͂��L�т�͂��v�Ƃ����v�����������̂ł��傤�B�����ł͏�����̐��E�ɂ��āA���̈�[�����ē��������Ǝv���܂��B
��������̑f�ނ̂��낢��
������ɂ́A�ł������ȃX�^���v���v���X�e�B�b�N���͂��܂��āA�v�����m���ǂɗp���鍂����Ɏ���܂Ŏ��ɑ����̎�ނ�����܂��B
�ؐ��̋�̍ގ��́A�����Ȃ��̂ł̓z�I�E�}���~�E�T�N���E�c�o�L�E�}�L�E�J�G�f�Ȃ����g���܂����A��������ɂ��c�Q�ނ����p����Ă��܂��B���̢�c�Q�ޣ�ɂ͎l�̎�ނ�����܂��B
(1)�V�����c�Q�c�����i�p�̋�ށB����A�W�A�Y�̖؍ނŁA�u�N�`�i�V�v�̖̈��ł��B�u�{���k�v�ɔ�ׂ�Ɩ؎��ɔS�肪�Ȃ��F���������܂��B���i�͈����ł������A�ߔN�^�C�ŗA�o���ւ���ꂽ���ߓ��肪����ɂȂ��Ă��܂��B
(2)�������k�c�����嗤�Y�̖{���k�ށB���Y�̃c�Q�ɔ�ׂĂ������ł��B�ގ��ɂ��Ȃ���������܂����A�ߔN�͗ǎ��Ȃ��̂������A������̍ޗ��ɂ��p�����Ă��܂��B
(3)�F�����k�c������ށB�ł������g�����ނƈ��F�ɕω����w����𖣗����܂��B
(4)�䑠�����k����ɓ��̌䑠���Y�B�ō����̋�ށB�ؖ�(���ځE�Ք��E�ۂȂ�)�̔����������͂ł��B
��������E�����E����グ��
�@�X�^���v���v����͈ꉞ���O����ƁA������x�{�i�I�ȏ�����́A��̂��肩�猩��ƁA
(1)�������@(2)������@(3)���薄�ߋ��Ɛ���グ��A�Ƃ���3�̎�ނɕ��ނ���܂��B
�����̎�ނ̈Ⴂ����̒f�ʐ}�Ŏ����Ă݂܂��傤�B
�O���[�̕�������̖ؒn�ŁA��������������L�������Ȃǂ̓h���ł��B

(1) �����������ؒn�ɕ�������ʏ��܂ł̋�ڎ��ŏ��������̂ł��B���ē�k���E�������ォ��]�ˊ����܂ł͖��M�Ƃ̏�������������d����܂����B��ɍ]�ˌ������́A��O��p�̉������Ƃ��ē��E�d���ŏ�����A���ł�����������́A�V���˓��ŏ����������悤�ɂȂ�A���ɓ`�����Ă��܂��B
��������(�������ȃV�����c�Q�ނɐV���h���ŏ����グ��ꂽ���̂�����)�@
�@�@
�@(2) ���������ؒn�ɋ������������\���Ē���A����h���Č����o���A����Ղ��������܂��B�����c�Q�̋�ؒn�ƒ���Ղɓh��ꂽ���̑ΏƂ��������A�u������Ƃ͒����ł���v�ƍl����l����ʂɂ͑����悤�ł��B
���Ă͋�E�l���蒤������܂������A���݂ł́A�قƂ�ǂ̒����͋@�B�ɂ���Ē���ꂽ���̂ł��B�܂��A�蒤��̎��ォ��A����̎�Ԃ��ȗ������邽�߂ɁA��̗������肪�l�Ă���Ă��܂����B
��𐳊m�ɒ��������̂��u�㒤���v�A��◪�������̂��u�������v�A���Ȃ�ȗ��̓x����������ɑ傫�����̂��u�������v�ł��B
�����̏����t�@���́A�����ȃv���X�e�B�b�N���X�^���v���n�߁A�₪�Ē��������߂�悤�ɂȂ�܂����A���̎��Ɏ�ɂ���̂��������������̒����̂��Ƃ������悤�ł��B
�������̂��낢���@�E������i�X�ȗ�����Ă����l�q������������
1.�㒤���
�@�@�@�@�@
2.�������
�@�@�@�@�@
3.�������
�@�@�@�@�@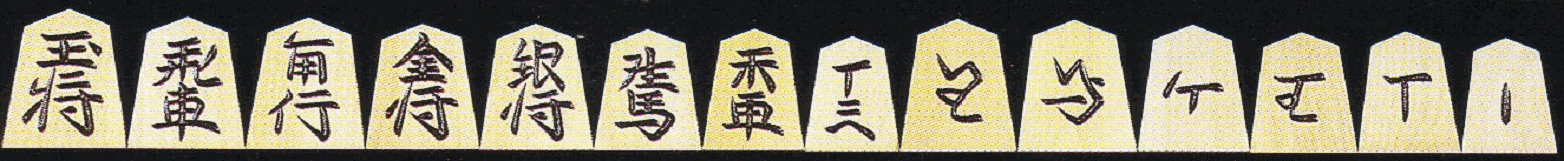
4.�������
�@�@�@�@�@
(3) ���薄�ߋ�Ɛ���グ������ؒn�ɋ������ŁA�����Ɏ��ߍ��݁A���S�Ɋ������Ă��琅���ɂȂ�܂Ō������Ďd�グ�����̂��u���薄�ߋ�v�ł��B���̒��薄�߂������Ɏ��G�M�Ȃǂ�p���Ď��ŋ�������グ���̂������グ�ŁA�v�����m�̌�����ǂɂ��p�����A������̍ō����i�Ƃ���Ă��܂��B�����i�́A�ꌩ����Ə�����Ɍ����܂����A��������������オ���Ă��Č|�p�I���͋C������܂��B�����A�o���オ��܂ł̍H���əˑ�Ȏ��ԂƘJ�͂�v���邽�߁A���i�͔��ɍ����Ȃ��̂ƂȂ�܂��B
�Q�l�܂łɁA����E������E�����̎����ʐ^�����Љ�܂��傤�B��ނ͂�������䑠�����k�ނł��B����̏��̂́A�v���X�e�B�b�N��ł���ԃ|�s�����[�ȏ��́E�u�ъ�(����)�v�ɂ��܂����B(�����ъ��ł����̂ɔ����ȃj���A���X�̈Ⴂ�����邱�Ƃ����炩���߂����Ƃ�肵�Ă����܂��B)
�O�̋�̎�ނ̈Ⴂ��������悤�ɏ����傫�߂̉摜�ł����������B
������
�@�@
�������� (�܂�����̒�����������Ƃ��Ȃ��̂ŁA����ɐ��㒼�O�̍��ʐ^������������)
�@�@
�@�ꌩ�X�^���v��Ɍ����܂����A�������ՂɎ����͎��Ɠu�����������u�K��(���т��邵)�v�߂ăJ�`�J�`�Ɋ������Ă���s�J�s�J�ɂȂ�܂Ō������Ċ������܂��B����������A�����������L���C�ɏo�邩�ǂ�����ڗđR�ƂȂ邽�߁A������̂���ԓ���Ƃ����l�����܂��B
�������
�@�@
�����Ŏv���o�b���܂߂ĂЂƂ��ƁB
����20�N�ȏ�O�A���D���ŏ��������n�߂����̂��Ƃł��B�s���Ŏ�̋���i�W������A�����Ŏ����Ɠ����悤�ɍ�i�߂Ă���ꂽ�����N�y�̕��ƁA��ɂ��Ă��ꂱ��b�������@�����܂����B�܂��삯�o���̑f�l�������������y���C�����Łu���͓���Ǝv�����ǁA�����͐������Ă݂����v�ƌ������Ƃ���A���̕��́u���������Ȃ͎̂�Ԃ��|���邩��ł��B�ł��{���ɓ���̂͒����̕����Ǝv���B���������ꂢ�ɂł���悤�ɂȂ�A�Z�p�I�ɗD��Ă��邱�Ƃ�������v�ƌ����܂����B�����āA�������̑���ꂽ������̊g��ʐ^�������ĉ������܂����B���̒�����̎��͎��R�ŁA�Ȃ߂炩�ȋȐ������������悤�ȕM�v�������Ă��܂����B�]�Q���鎩���ɂ��̕��́A�u�����ł͒���͂܂��܂����Ǝv���Ă����ł���v�Ƌ����܂����B
���N�セ�̕��͏������҂Ƃ��Ċm�łƂ��������āA�s���ō�i�W���J����܂����B������i�W�̓W����͂��ׂĒ���Œ�����͈������܂���B���R��q�˂�ƁA�u�����͂��������Ă��܂���B��͂蒤���͐��゠���Ă̒������Ǝv���܂��B���܂͒��肾���ɂȂ��Ă��܂��܂����v�Ƃ̂��Ƃł����B�����ƒ����ɑł����ނ��ƂŒ���̋Z�p�����Ȃ�̍��݂ɓ��B�������Ƃ����������̂ŁA������́u���Ɓv���đ�D���Ȓ����ɏW�����Ď��g�ނ悤�ɂȂ����̂��ȁA�Ǝ����Ȃ�ɉ��߂��܂����B
���̌㎩�������̖��͂Ƀn�}���Ē���琷����ɐi�݁A15�N�ȏオ�߂��܂����B������ł͕K���u�����v�̒i�K������A���̎������̎d�グ��������ƑΖʂ���킯�ł����A���̓s�x��͂莩���̒���̋Z�p�̖��n����Ɋ����Ă��܂��B������Ƃ��Ă̊����i�͉i���̉ۑ�̂܂܂ɂȂ��Ă��܂��B
��������̂������@�i���̂Q�j
��������̗��j(1)�@�@�������玺���E�퍑�����
�@�䂪���Ō��݊m�F����Ă���ŌÂ̏�����́A11���I���E��������̋�ł��B���͓ޗǁE�������������Ŕ��@���ꂽ���̂ŁA�܊p�`�̖ؒn�Ɍ��݂Ɠ�������n�ŏ�����Ă��܂��B�u�؊ȁv�Ƃ����؎D���ė��p�����Ǝv����f�p�ȑ���ł����A�����炭�������̑m������������������ŏ����ɋ����Ă����̂ł��傤�B�܂��A�قړ�����ƌ��������B�E����̒������ł��o�y���Ă��܂��B���̂��Ƃ���11���I�ɂ͏��������{�e�n�ōL���V��Ă����ƍl�����Ă��܂��B
���������ŏo�y����������̗��@(����G��w�����̋N���x(���}�Ѓ��C�u�����[)�̌f�ڐ}���)
�@�@�@�@
�@�������������f�p�ȋ�Ƃ͕ʂɁA�����ƍ����ȋ���������͂����Ƒz�肷��l�����܂��B���Ƃ����̓��L�Ȃǂɂ́A�V�c��֔������b�Ȃǐg���̍����l�X�������ŗV�Ƃ����L�q�������܂��B�Ⴆ�Γ�����Ƃ́A1�J����5����֔����b�̌�O�ŏ������w���Ă��܂����A�㒹�H��c���ߐb�����ɏ������w�����Ă��̊��͂ɔ�]���������L�^���c����Ă��܂��B��c�̌䏊�ɂ͌�ՂƋ��ɏ����Ղ��������Ă��܂����B���������g���̐l�X���p�����Ջ�́A����ɑ�����������̍����i�������ƍl����̂����R���Ƃ����������ł���ł��傤�B
�܂��A���q�����k������̕��|��i�̒��ɂ́u�����|���v�Ƃ����ꂪ�o�Ă��܂��B���|���ėV�Ԃ��߂ɂ͗������������ׂ�K�v������܂����A�������̋�ł͗�������̂����J�ł��傤�B��͂肠����x�`�̐�������s���킽��悤�ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ƒz������܂��B�܂��A��k�����ɂ͏�����̎��̏������ɂ��ďq�ׂ������̖{������Ă��܂��B�f�p�ȃC���X�^���g���{�i�I�ȋ�ւƏ�����i�����Ă������̂�������܂���B�����āA��������ɂ͌��Ƃ����̊Ԃŏ����̋�����s�����Ƃ����s���A���ɔ\�M�Ƃ̊��|������͂��Ȃ蒿�d����܂����B
16���I�ɂȂ�Ə����̋���̐��ƂƂ��ĂԂׂ��\�M�Ƃ������܂��B���̑�\�҂��A�����[���ł���������������(1514�`1602)�ŁA�ނ͒����ɉ����āA�E�l�ɑ��点����ؒn�ɖn�⎽�řˑ�Ȑ��̋�����s���܂����B�����̏������u��������v�́A�ō����i�Ƃ���A���̈˗���͓V�c�E���Ƃ�喼�����ł����B���ɖL�b�G���Ɠ���ƍN�E�G�����q�͍ő�̌ڋq�ŁA�������������̏������L�͎҂ւ̑����i�ɗ��p�����ƍl�����Ă��܂��B
���u��������v(���{���{���E�������_�{��)�@
�@�@ �@�@
�@�@
�@�@�@���w���{�̔��p 32 �V�Y��x(������)���@�@�@�@�@�@�@�@�@����͐��������͂��ĕM�҂����삵�������ł�
�@��������̗��j(2)�@�@�]�˂��疾������
�]�ˎ���ɏ������L�����y����ƁA�E�l�������ǎ��̋��悤�ɂȂ�܂����B�₪�č]�ˎ���̒����������ɂ����Ē������ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ɛ��肳��Ă��܂��B�������ɂ͏����̉ƌ��Łu������v��������悤�ɂȂ�܂����B���́u������v����A���ݍō�����Ƃ����u�����v�����܂ꂽ�ƍl�����Ă��܂��B
(�E�����ƌ����������Ƃ���钤����E�u�������`�v�̎ʐ^���C���^�[�l�b�g�Ō��邱�Ƃ��ł��܂�
URL�c
www.geocities.jp/monkey007no1/koda/kigu/oohashi/hiyoji.html
)
�]�ˎ���A��������̒��S�n�͑�㌗�ł����B���ł͋�̑f�ނƂ��āA��O�����̃c�o�L�E���i�M�ȂǂƋ��ɁA�����ȋ�̂��߂ɎF�����k���p�����Ă����悤�ł��B�]�ˌ���Ɍ��ꂽ�����́A�����̏����̒��ł����X�T���ȑw���p��������������Ǝv���܂��B���ɂ͍��������I�ɑ���H�[���������Ƃ����Ă��܂��B�܂������Ȓ���璤��̎�Ԃ��Ȃ��������̋�����̒���Ƃ��čl�Ă����悤�ɂȂ����Ǝv���܂��B����������������̋�́A�u����v�Ƃ��u��㒤��v�̋�ƌĂ�܂����B���n���ɍ����`���u���u�v�͂��̌n���̏��̂Ƃ����Ă悩�낤�Ǝv���܂��B
�܂������̏����ɏ������L�܂�ƁA��O�����̈����ȏ��������ɑ�ʂɋ��߂���悤�ɂȂ�܂����B�����ł��̉��������Y�n�ƂȂ����̂����k�̕đ�˂�V���˂ł��B�����̔˂ł́A���E�Ƃ��Đ���ɏ����̋������悤�ɂȂ�܂����B�}�L��z�E�m�L�Ȃǂ̈���̖ؒn�ɋ���𑐏��ŏ����������̏�����A���݂̓V���̏�����̃��[�c�ł���Ƃ���Ă��܂��B
�@�����́u���u�v�̒���@�@�@�@�@�@�@�@���V���̓`���I�ȑ����̏����� (������)�@
�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�����R��l�w������̐��E�x(�����V��)���@�@�@�@�@�@�@�@���V���s���������ق̃p���t���b�g���
�������ɂ����Ă��A���ς�炸������ƍ�����̐��Y�̒��S�n�͑��ł����B����ɑ��āA�����ȑ����̏�����Y�̒��S�n�������V���ł́A������x���̑g�D���m�����A���̐��Y���ő��▼�É��𗽂��悤�ɂȂ�܂����B�������A��O��͓V���ő���ꂽ�ɂ�������炸�A�≮��ʂ��ē�������̐��X�܂���S���ɔ̔����ꂽ���߁A���̍��͓V�����Y�ł��邱�Ƃ͈ӊO�ɒm���Ă��܂���ł����B
�E�u������̗��j�v�ɂ��Ă͂���ȍ~�������܂����A���L�̎������Q�l�ɂ��Ă��܂��B
�W�e�ʂɂ͐S��芴�Ӑ\���グ�܂��B�Ȃ��A�����̂����A���͓��肵�₷�����̂ł����A���͂����ւ�Q�l�ɂȂ�܂����A��ɂ���̂�������̂ł��j
�� �w�V���s���������فx�p���t���b�g(�����قɂĔ̔�����Ă��܂�)
�� ����G��w�����T�E�U�x(�@����w�o�ŋ� 1977, 1985�N)�E�w�����̋N���x(���}�� 1996�N)
�� ���R��l�w������̐��E�x(�����V�� 2006�N)
�� �w��̂����₫�x(��o�ʼn� 1996�N)
��
�F�V�Ǒ��w�����Ӂx(�����ӊ��s�� 1981�N)
�� �w�V���̏�����ƑS����Տo�y��|������̃��[�c��T��x(�V���s����������
2003�N)
�� ���Ɩ�K�˂ģ(�w�ߑ㏫���x1999�N�`2002�N�f�ڋL��)
�� �L��P���E�͈�M�F�u��������v(�w�ߑ㏫���x2006�N�`2008�N�f�ڋL��)
�� �{��וv��V��������Y�n�̕ώ��(�w���m�����w������41(�Љ�Ȋw��)�x1992�N)
�� �V���s�������H�ό��ہw�V���Ə�����x(1991�N)
�� �C���^�[�l�b�g�T�C�g�w��̎��x(http://8ya.net/suiki/)�@
�� �C���^�[�l�b�g�T�C�g�w����}�Ӂx(http://meikoma.com/)
�� �C���^�[�l�b�g�T�C�g�w����W���x(http://www.geocities.jp/monkey007no1/koda/kigu/kigu.html)
��������̂������@�i���̂R�j
�@���ߑ�̏�����i1�j�@������̖����̓o��@�L�����R�Ɖ���ꍁ
�@�吳����̔����珺�a�ɂ����ď�����̍H�l�ɂ͎��X�Ɩ����������A�ނ�͑����̌�������̐��ɑ���o���܂����B���̒��Łu�ߑ㏫����̑c�v�Ƃ��]�����̂��A�u���R�v�̍������e�q�E�L�����Y�g�i1862�`1940�j�ƖL�������Y�i1904�`1940�j�̓�l�ł����B
�@���̑��Y�g�́A�����ł͋��Ȃ������悤�ł����A�o�c����Ջ�X�ŐE�l���ق��ċ�点�A����o������ɂ́u���R�v�̖������܂����B�܂��A��̏��̂̑n��ɗ͂����A20��ވȏ�̏��̂��w�L�����꒟�x�ɂ܂Ƃ߂܂����B���̒��ɂ́A�u�ъ��v�u�������v�u�����q�����v�u�H���v�ȂǏ�����̏��̂Ƃ��āu��ԁv�ƂȂ������̂�����܂��B����ɑ��Y�g�́A���k�ނ̑f�ނƂ��Ă̔������ɒ��ڂ��A���܂ł͎̂Ă��邱�Ƃ̑����������ڈȊO�̖ؒn�̒��Ŕ������͗l����������̂��u�Ք�(�Ƃ��)�v�A�u��(����)�v�ȂǂƖ������A������ނƂ��Ĕ���o���܂����B�ނ́A�H�|�i�Ƃ��Ă̏�����Ɍ|�p�I���l��^�����̂ł��B
�@�����āA���Y�g�̉��ŗc����������n�߁A�\�㔼�ɂ͒��ꗬ�̐E�l�ɐ��������̂����q�̐����Y�ł����B�ނ͎O�\�㔼�̎Ⴓ�ŖS���Ȃ�܂������A�ނ��₵���u���R��v�̋�͍��ł����W�Ɛ����̖��i�ƂȂ��Ă��܂��B�ߔN�s�u�ԑg����ł��Ӓ�c��ɏo�i���ꂽ�L�����R��̐����ɂ͓r�����Ȃ������ȕ]���z���o�āA�����҂̕��X���������܂����B
���L�����Y�g�Ɛ����Y�@�@�@�@���L�����ꎆ���̈ꕔ�@�@�@�@����ؒn�E�Քǁ@�@�@����ؒn�E��
�@ �@�@
�@�@ �@
�@ �@�@�@
�@�@�@
�@�@�@�@�@�i�w��̂����₫�x(��o�ʼn�)���j
�@�L�����q�Ƃقړ�����Ɋ����̂��A��͂蓌���E�ʼnF�c�쒬�ŔՋ�X���o�c���Ă�������ꍁ���q(����E���ܘY�F1866�`1921�A���E�K���Y�F1899�`1939)�ł��B
�@����ƖL���Ƃ͌𗬂��������Ƃ������A�݂��ɋ����ċ�̏��̂�n�삵�����Ƃ��m���Ă��܂��B�Ⴆ�u�ъ��v�Ƃ����������ł��L���Ɖ���ł͑S���قȂ鏑�̂��l�Ă���܂����B�����ŁA���݂͉��삪����o�����u�ъ��v�̕����u����ъ��v�ƌĂԂ̂����킵�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�����̋�ōł��L���Ȃ̂́A�����A���������u���l���v�ł��B���̋�͐��Ԃ��Ȃ������A���Ɋ��ꂽ���̂ŁA���݂ł����l��̑�1�ǂŕK���g�p����邱�ƂɂȂ��Ă��܂�(�C���^�[�l�b�g�T�C�g�w��̎��x�̒��Ɏʐ^������܂��̂ł����������BURL��http://8ya.net/suiki/meiko/okuno/index.html�ł�)�B��K�̏��̖��͖w�Ǐ����Ă��܂����A���Ắu�@���D�v�ƋL����Ă��܂����B�@���Ƃ͍]�˖����́u�����v�E�V��@��(1816�`59)�̂��Ƃł����A���ۂɏ@���������������̂̋�����p�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�]�ˌ���́u�����v�Ƃ�����̕��������삪�A�����W���A���̑n�쏑�̂��u�@���D�v�Ɩ��������A�Ƃ��������L�͂ł��B
�����㉜��ꍁ�@�@�@�@�@�����R�̢�ъ���Ɓu����ъ��v
�@ �@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@
�@�@�@�@ �@�@
�i�w��̂����₫�x(��o�ʼn�)���j�@�@�@�@�@�@�@
���ߑ�̏�����i2�j�@���a�̓�����̖������� �\ �ؑ��E�e���E�ÎR�E�|��
�@���䂪�����p�Ђ��畜�����Ă������ŁA������̐��E�ł����X�Ɩ�������������悤�ɂȂ�܂����B���̒��Ŋ��ɐ�O����m���Ă�����t���ؑ����r(1908�`84)�ł��B�ނ͏��N����ɖL���̂��ƂŒZ���ԏC�Ƃ�������A�����ɓƗ����ĉ����ɔՋ�X���J���܂����B�����ɂ͎��Z�̏\�l�����l�E�ؑ��`�Y (1905�`86)�̌��|������܂����B���l�̈Ќ��������Đ펞��������ɂ����Ĕނ̋�͈ꐢ���r���܂����B���̍����ؑ��̐Ⓒ���Ƃ���A�E�����钍�������Ȃ����߂ɑ��̐E�l�ɉ��������������̂����������Ɖ]���Ă��܂��B�ؑ����l�̏�����̂����u�ؑ����l���v�̋�́A�ؑ����������邱�Ƃ̋��������̂ł����B�Ȃ��A�ؑ���ƌ������אg�ŌX�̏��Ȃ���`���m���Ă��܂����A���������`�͌���ɂȂ��č̗p���ꂽ���̂ł��B
�����ؑ����r�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ؑ����l���̎��ꎆ�@�@�@���ؑ����r��E�ؑ����l��
�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@ �@�@�@�@
�@�@�@�@
(�w���l : ���̓`���ɐ�����l�����x���)�@�@�@�@�i�w��̂����₫�x(��o�ʼn�)���j�@
�@���a30�N��ɓ���Ɩؑ��ɑ����ċ{���e��(�{���F�����Y 1928�`72)���u�V�ˋ�t�v�Ƃ��ċr���𗁂т�悤�ɂȂ�܂��B�ނ̕��E�{���֎O�Y�̓v�����m�̖T��펞������������Ă��܂����B�Ƃ��낪��㏺�a22�N�ɋ}���������߁A�q���̊����Y����w�����߂Č���p���܂����B�ނ͓w�͂ɓw�͂��d�˂āA�₪�ċ�t�E�e���Ƃ��ē��p���������ƂɂȂ�܂����A���͈ȑO����ނ̋߂��ɂ͋��̒B�l�Ƃ����ׂ��l�������܂����B���̐l���Ƃ͖L���Ƃŋ���Ă�������ÎR(�{���F�H�j
1904�`91)�ł��B�ÎR�́A��O�t���̖L�����q���������ŋ}��������A�⑰�̍���ɉ����u���R�v���̋�葱���邽�߂�10�N�ȏ�ɂ킽���Đs�͂��܂����i�Ȃ��A�ÎR���ւ�������R���̋�́u���R�ÎR�̋�v�Ƃ������Ă��܂��j�B�ÎR�́A�{���̕��E�֎O�Y�������n�߂���������̃R�c�������Ă����̂ŁA�֎O�Y�̎�����q���̉e���ɂ��l�X�̏��͂������Ɖ]���Ă��܂��B���������q�����w�i�ɁA�{���́A�Z�p�I���r��ς݂Ȃ���A�����O�̒T���S�Ŏ��E��ؒn�̌`�E�ގ��E���̂Ȃǂɂ��Ă��������d�˂āA�Ǝ��̉₩�ȍ앗���m�����܂����B�������ď��a30�N��ɋ{���̋�́A�����Ƃ������甲�Q�̕]������悤�ɂȂ�܂����B�������A�|�p�Ɣ��̂ɑS�����̍�i�������Ȃ��A����ɐɂ��܂�Ȃ���Ⴍ���ĖS���Ȃ������߁A�u�e����v�́A���݂ł��N�W�Ƃ̐l�C�i���o�[�����̖���ƂȂ��Ă��܂��B
�@�Ȃ��A�e�������E����������炭�̊ԁu�{���v���̋�͑����܂������A����͋���ÎR�̎�ɂȂ���̂ł��B�ÎR�́A�L���̂��Ƃł͒������`���Ă��܂������A���ɂȂ�Ɛ���̋Z�p���ɂ߁A���̍��ɂ͊��ɋ�t�Ƃ��Ĉꗬ�̒n�ʂ��m�����Ă��܂����B��������܂�43�ŋ}�������{���̈⑰�̋��n�������˂ċ~���̎�������ׂ̂��̂ł��B���̌�ÎR�͋�t�̑��l�҂Ƃ����悤�ɂȂ�܂����B�������A�ނ̐^�����́A�e�̍�Ǝ�����܂߂āA���U�فX�Ƌ�葱�����_�ɂ���Ǝv���܂��B���̈Ӗ��ŐÎR�����u�^�̖����v�̖��ɒl����ƍl����l�������悤�ł��B
�@�����āA���a�Ō�̓�����̖�������|�|��(1914�`2005)�ł��B���X�����_�c�ŋ����̎q�ł������A���k�ނ��������ʼn������Ă����E�l�̏��������珫����̑�������w�т܂����B��Ђŕ��̋����̐V���Ɉڂ�A�������̂܂܈�Ƃŋ��͂��Ȃ����葱���܂����B�u�|���v��́A���ݓ��ڒ|��(��|���o�j��)�Ɉ����p����Ă��܂��B
�@�����Ŏ��グ��������̖��������������������ȍ�i�ɂ��ẮA�O�Љ���C���^�[�l�b�g�T�C�g�́w��̎��x�E�w����}�Ӂx�Ȃǂō������邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A���̂����L���E����E�{���ɂ��ẮA�ȉ��̃T�C�g�ɂ���ɏڂ����L�q������܂��̂ŁA�S���������̕��͂������������A�Q�l�ɂȂ����ĉ������B
�E�u�L�����R�@��t�v�ihttp://www.toyoshimaryuzan.com/�j
�E�u����ꍁ�@��t�v(http://www.okunoikkyou.com/)
�E�u�{���e���@������t�v�ihttp://www.miyamatueisui.com/�j
�����{���e���@�@�����쒆�̋�߂����ÎR�@���e���̋ъ��ƐÎR�̋ъ�(�ʏ��ƕ���)
�@ �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@
�@�@
�i�w��̂����₫�x(��o�ʼn�)���j�@
�@�Ȃ����Љ�������̂����A����ÎR��̐����́A���Ȃ�O�ɐX���A�Ɋ���A���݂ł����A�̑��̌����Ȃǂŗp�����邱�Ƃ�����Ƃ������Ƃł��B�捠�ӏ܂���@�����A�q������ƁA���Ȃ�Â���ŗ��̐��ʂ͐��グ���������Ȃ肷�茸���Ă��܂����A�_�炩�ȕM�v���������錩���ȋ�ł����B���̂ق��A���A�ɂ͋{������(�e���v�l)�E���䍁���E��c��M��̐�������Ă���A�������d�v�ȑǂŎg�p������ł��B����ɍ�N�����̖���ɉ����A��J�ǗY�������|�|����̐����Ȃǂ�����܂����B�����̖���ɂ��Ă��捠�q�����邱�Ƃ��ł��܂����̂ŁA�₪�Ă���������ł��̃y�[�W�ł��Љ�ł�������Ȃ��A�ƍl���Ă���܂��B
�@�Ȃ��A���̃y�[�W�ł͂��ꂩ���������ɂ��Ďv���܂܂ɐF�X�Ȃ��Ƃ��q�ׂĂ����܂����A���ɂ͕M�҂̌���v�����݂����Ȃ�܂܂�Ă��邩������܂���B����ʓ_�͂��e�͂��������K���ł��B
�@����͏�����̌̋��Ƃ��Ēm����V���̋��̗��j�ɂ��ďq�ׂĂ݂����Ǝv���܂��B
��������̂������@�i���̂S�j
���V��������̓W�J
(1) �������X�^���v���
�R�`���̓V���ł́A�����ېV����������m����S����Ƃ����肪����ł����B�������Ɋ��s���ꂽ�w�؍ރm�H�|�I���p�x(1912�N�E����{�R�щ)�ɂ��A�V���̏�������҂�13�˂ő���10�˂������Ă���A��̐��Y���u�V�����ߔ����胀�g�C�t�v�ƋL����Ă��邱�Ƃ�����A���ɂ��̍��V��������}���ď�����̍ő�̐��Y�n�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�������܂��B
�����A���ł͑�O�����̋���łȂ��A�����f�ނ̎F�����k��p��������������Ă����̂ɑ��āA�V���ł̓}�L(�}���~)��z�E�m�L�̂悤�Ȉ����ȍގ��ɒ��ڑ����ŋ���L������������ł����B�������đ�O�����̈����ȏ�����̍ő吶�Y�n�ɐ������钆�ŁA��ؒn�̐��`���s���u�ؒn�t�v�Ƌ�������u�����t�v�̕��Ƃ��i�݂܂����B������t��̉��̓k����u�����q�v�Ƃ����A�ł������ȋ�́A�w�����������K���x�̑ʒ��ŏ������Ƃ�����܂����B�q�������ɂ́A�܂���ԊȒP�ȁu�Ƌ��v���������A�����q�Ƃ��Č����݂̂���҂̒��ɂ́A�������獁�ԥ�j�n��⏫�������p�s���ԂƐi�݁A�ʏ���������l�O�̐E�l�ƂȂ����҂����܂������A�n���܂łɂ�10�N�ȏ��v�����Ƃ���܂��B
�������ď��a�̏��ߍ��ɂ͓V���̏������́A�]���Ґ���������q�����܂߂��300���߂��𐔂��A���Y����70���g����܂łɒB����܂łɐ������܂����B�����A�Ɠ��H�Ƃ͖≮�ɂ���Ă���̑O�݂��ɂ���Đ��藧���Ă������߁A����I�ɂ���߂Ĉ������i���i�������t�����Ă��܂����B���̂��ߐe���ɂȂ��Ă������͂���߂ĖR�����u��͕n�R��炵�v�Ƃ����̂����Ԉ�ʂ̕]���ł����B
�Ȃ��A��̎����w�؍ރm�H�|�I���p�x�ɂ́A���̏�����Ɋւ��āu�ߗ������j���Ǐ��L�g�e���(�S��)�����ȃe�扟�V�^�����m���s�X�v�Ƃ����L�ڂ�����A���łɖ�������ɂ͑��ŃS�����p������X�^���v��(����)����l�Ă���A�ȗ͉��Ƒ�ʐ��Y�ő�O��̎�͂ɂȂ�͂��߂Ă������Ƃ�������܂��B��㔭�̃X�^���v��́A�����炭�V���̓`���I�ȏ�����ɂ��Ȃ�̑Ō��ƂȂ����Ǝv���܂��B�������₪�ēV���ł��S�������A���w���ɃX�^���v��点��悤�ɂȂ�ƁA�H���̍��͖����ŁA���a���߂܂łɂ̓X�^���v��ł����S�ɑ�������悤�ɂȂ����悤�ł��B
(2) �ؒn����̋@�B���ƒ����̂͂��܂�
�����̖�����吳�N�Ԃɂ����ď������ؒn����̍H���͏����@�B������A���a�����ɂ���ʐ��Y���\�ɂȂ��ēV���͏�����̐��Y���ő��̎Y�n�����|����悤�ɂȂ�܂����B�܂��吳��������́A����̕���ł���������̂��i���̍�������߂������݂������܂����B��͈�ӑ���̋Z�p�����p����������ł����B�܂��������A�O����グ������ꍁ�̍H�[�œ����̍�����̐���Z�p���w�сA������҂�����܂����B�����̋�͑��̒�������錩���ȏo���h���ł����B�������A�c�O�Ȃ��琧��ʂ�����ꉿ�i�����ɍ����������߁A�V��������̎嗬�Ƃ͂Ȃ�܂���ł����B����ł��A�ȗ͉��̉\�ȗ������肪�l������ƁA���Y���ł͏�����(53.7%)��X�^���v��(42.4%)�ɔ�ׂ�Ƃ����͂�(3.8%)�ł͂���܂������A�V���ł����������悤�ɂȂ�܂����B
�E�\1 ��O�̓V���̏�����̎�ޕʐ��Y���Ɛ��Y�z(�w�҂����ɂ�鏺�a11�N�̌��n��������)
| �ގ��E��� |
���Y�g�� |
���z(�~) |
�̘H |
�@���ގ��ʂ̏�����Y��(�s�R�����������)�@�@�@
�@�@�@�p(�z�I�m�L)�c450,000�g (63.6%)�@�@
�@�@�@�t�A(�n�r��[�n�N�E���{�N])�c85,000�g (12%)�@
�@�@�@�(�}�L[�}���~])�c170,000�g (24%)�@�@�@
�@�@�@���k(�c�Q)�c2,000�g (0.3%)�@
�@����ޕʂ̏�����Y��(�s�R�����������)�@�@
�@�@�@������c380,000�g (53.7%)�@�@
�@�@�@�X�^���v��c300,000�g (42.4%)�@�@�@
�@�@�@����c27,000�g (3.8%) |
| ꠏ����� |
150,000 |
9,300 |
�S�� |
| ꠒ��� |
20,000 |
5,000 |
�S�� |
| �t�A������ |
80,000 |
3,200 |
�S�� |
| �t�A���� |
5,000 |
800 |
���E���� |
| �p������ |
150,000 |
2,850 |
�S�� |
| �p�� |
300,000 |
4,800 |
������ |
| ���k���� |
2,000 |
1,600 |
�S�� |
| �s�R������ |
278,000 |
7,506 |
�S�� |
(�R���\��Y�u�W���I�X���R�`���V�����̒����v�ɂ��)�@ (���̕\�̐��l����v�Z��������)
�E��O�̓V���̏������Ɋւ�����l�X�̂�����
�@�@�@ �@�@�@�@
�@�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@
��ؒn������u�ؒn�t�v�@ �@�����́u�����q�v�ɂ�����@�@����������u���t�v
�i��������@�R���\��Y�w���k�̑��X�x(�P�t�t���[ 1943�N���j���)�@
(3) �펞��������̎���ƓV���̏�����
���a���펞�̐����ł́A������Ԗ�܂̒��̒�ԏ��i�Ƃ���A������ƃX�^���v��𒆐S�Ƃ��ēV���ł̏�����Y�͂���ɋ}�����܂����B���̍��͉Ɠ��H�ƂƂ��Ă̋�����t����]�����Ă��ǂ����Ȃ��悤�ȖZ�����������悤�ł��B�������Đ펞���ɁA�V���͑S���̏�����̐�����9���ȏ�Ƃ����Ɛ�I�n�ʂ��m�����܂����B
�E�펞���̈Ԗ�܂Ə�����@(�V���s���������ق̃p���t���b�g���)
�@�@ �@�@�@
�@�@�@
�s��ɂ��ꎞ�I�ɏ�����̐��Y�͌������܂������A1950�N�ォ��̌o�ϐ������ɔ����]�ɂ̊g��ŏ��������y���A�قƂ�ǂ̉ƒ�ɕK���܂肽���ݔՂƋ��������قǂɂȂ�܂����B���̕\2������ƁA�V���̏�����Y�̃s�[�N��1965(���a40)�N���ŁA����700���g���鏫����V���ő����Ă��܂����B���������̍��̏�����̉ƒ�ւ̕��y�̎���́A�����ȃX�^���v��ł���A�V���`���̏�����͔N�X���Y�ʂ��ቺ���Ă����܂����B�����ĕ\3�����������Ƃ���A�₪�Đ��Y���ʂŒ���ɂ�������悤�ɂȂ�A����1980�N���ɂ͏�����̍H�l���킸�������ɂ܂Ō������Ă��܂��܂����B
�\2 �V���̏�����ʂ̐��̐��Y���ځ@(�u�V���s�j�v�E�u�s�H�Ɠ��v�v�Ȃǂ���쐬)�@�@�@
|
1951 |
1956 |
1960 |
1962 |
1965 |
1970 |
1974 |
1980 |
1985 |
1990 |
1995 |
2000 |
2004 |
|
(S26) |
(S31) |
(S35) |
(S37) |
(S40) |
(S45) |
(S49) |
(S55) |
(S60) |
(H2) |
(H7) |
(H12) |
(H16) |
| ���Y�z(���~) |
2000 |
3000 |
6000 |
8500 |
10200 |
21100 |
�\ |
47131 |
28794 |
32981 |
31547 |
21498 |
17258 |
| ���Y��(���g) |
�\ |
224.6 |
500 |
600 |
700 |
450 |
280 |
250 |
130 |
100 |
100 |
80 |
50 |
�\3 �������ޕʂ̐��Y���̐���(1956�N��1974�N)
| �N�x |
���Y���� |
��̎�ޕʂ̑g�� |
| �X�^���v�� |
������ |
���� |
| 1956�N |
2,246,000�g |
1,710,000�g |
450,000�g |
73,000�g |
| 1974�N |
2,800,000�g |
2,630,000�g |
10,000�g |
160,000�g |
(4) ����̑S������
������x�\2������ƁA���̏�����̐��Y���ʂ̃s�[�N��1965�N��700���g�ł����A���z���猩��ƃs�[�N��1980�N�ŁA���Y���ʂ�250���g�Ƃ��Ȃ茸�����Ă���̂ɋ��z�͖�4.5�{�ɂȂ��Ă��܂��B�o�ϐ����ɔ������������̉e�����������Ƃ͎v���܂����A�����t�@���̚n�D����O�i���璆�����i�Ɉڂ�n�߁A�X�^���v��ɑ����č����Ȓ���̔�d�����܂������߂��낤�ƍl�����܂��B����ɍ��������̌���ɔ����Ē���̐l�C����荂���ȏ��i�Ɉڂ��čs���܂����B��̑f�ނ́A�����Ȓn���ނ����v�����m���p����ō����̖{���k��ɋ߂����̂����߂���v����A�V�����c�Q(����A�W�A�Y�̃c�Q�Ɏ����؍�)���l�C���W�߁A�ȑf�ȗ�������ɑ����Ă�⍂���ȏ㒤��̕��������悤�ɂȂ�܂����B
�������āA�蒤��ł͂ƂĂ�����̎��v�ɑΉ�������Ȃ��Ȃ�ƁA�����ōl�Ă��ꂽ������̋@�B���肪�V���ɂ���������܂����B���̋@�B�́A�ȒP�Ɍ����Ɛ��}�ɗp����g����Ɏ����@�B�ŁA�\�ߊg�債����������{�[�h�̕����ƁA�ׂɋ�ؒn�̏�Ɏ��Ȉ�@�ɂ���悤�ȃh�������Z�b�g�����������琬���Ă��܂��B�@�B�𑀍삷��l�́A�{�[�h�̑O�ɍ����āA�R���p�X�̐�[�����Ń{�[�h�̋�����Ȃ���܂��B����Ɨׂ̋�ؒn�̏�ɃZ�b�g���ꂽ�h�����������l�ȓ����Ń{�[�h�̕����𐳊m�ɏk�������������čs���܂��B�������Đ��m�Ȏd�オ��̒���ꖇ���o���オ��܂��B�蒤��ɔ�ׂ�ƁA�n���̒��t���K�v�Ƃ����A�����������g����������܂ł̎��Ԃ��啝�ɒZ�k�����̂ŁA�@�B����̋�̔䗦�͂ǂ�ǂ܂��čs���܂����B�ߔN�����͑S���Y���z��70���ȏ���߂Ă��܂����A����95���ȏ�͋@�B�Œ����Ă��܂��B�蒤��ŋ���Ă���̂��A��͂育�������̖����Ɍ�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�E�V���ő���ꂽ����@�蒤��Ƌ@�B����
�E�V�����c�Q�̎蒤���(����V���)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�E�V�����c�Q�̋@�B������@
 �@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@
(�Ȃ��V���ł̏�����Y�z��1980�N��4��7�疜�~�]�_�Ɍ����X���ƂȂ�A1985�N�ɂ�3���~�̑������荞�ނ悤�ɂȂ�܂����B���̌�1990�N��O���ɂ����ĉ������̂́A90�N�㖖����͍Ăь����������A2004�N�ɂ͐��Y���z��2���~�������1��8�疜�~�A���Y���50���g�܂ŗ������݂܂����B)
(5) ���H�����̊���
�V���͐��Y���œ��{��̏�����Y�n�ł������A�ō�����̐����Ɋւ��ẮA�ȑO���瑢���Ă����ɂ�������炸�A���炭�v�����m�̑Ǘp�̍�����Ƃ��ĔF�m�����ɂ͎���܂���ł����B1951�N�̑�1�����6��(�ؑ����l�Ίۓc���i��)���V���ŊJ�Â��ꂽ���ɂ��n����t��̐����͑Nj�̌��ɂ͂Ȃ������̂́A�����Ńp�`���ƔՂɓ��Ă�ꂽ�����ō̗p����邱�Ƃ͂���܂���ł����B�����n���̎���t�ŁA��Ɂu����̖��H�v�ɑI��邱�ƂɂȂ�ɓ��v���t(�{���E�F�����F1918�`97)�́A�u�V���̐����͂ǂ����Ă��߂������̂��A���Ƃ��Ă����R��m�肽�������B���R�̂킩��Ȃ��̂��A��ԉ����������v�Ƃ��̎��̐S�����q�����Ă��܂�(�w���̋Z�ƌ`�x2001�N�E�u�k�Њ�)�B
���̋��J�Ɖ��������o�l�ɂ��ēV�����H�l�����͌��r�Ɍ��r���d�˂܂����B�悤�₭1980�N2���������5��(���������Α�R�\�ܐ����l��)�ɁA1���ڂ����ł����v���t��̋�̗p����A���߂ă^�C�g����œV����p�����܂����B�����ċv����̐����͗��N�̖��l���2��(�������l�ˎR���i��)�ł��Nj�ɑI��܂��B��������������ɂ��āA���䍁���t(�{���F�d�v��)�A����d���t(�{���F�a�j��)�A����G��t�i�{���F�M���Y���j�A���ʗ��Z�t(���)�ȂǁA�R�`���̋�t�ōō������̋���Ƃ��������œo�ꂵ�A���Ɂu�V����͑�O��v�Ƃ����C���[�W����V����܂����B�����āA���a���畽���̐��ɂȂ�A���ݏ����̃^�C�g����ł́A�V���𒆐S�Ƃ���̎�ɂȂ�삪�ł������p������悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�Ȃ��A�V�����͂��߂Ƃ���R�`���̏�����Ɋւ��ẮA�C���^�[�l�b�g������m�邱�Ƃ��ł��܂��B
�E�R�`���ӂ邳�ƍH�|�i (https://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110010/kogeihin/sp03-1.html)
�E�R�`����������g���̃z�[���y�[�W�@(http://tendocci.com/koma/)
�E�V���s�u�V���Ə�����v(https://www.city.tendo.yamagata.jp/tourism/kanko/tendo-syougikoma.pdf)
�E�d���̋�u���O(http://kikusuinokoma.blog.fc2.com/)
�E���ʗ��Z�����T�C�g(http://kodamaryuji.jp/)
��������̂������@�i���̂T�j
��������̏��̂ɂ���
��������̏��̂̓W�J
�@������̏��̂ɂ͎��ɑ����̎�ނ�����܂����A���̑����͋ߑ�ɂȂ��Ă����t�����ɂ���čl�Ă��ꂽ���̂ł��B���̍ێQ�l�Ƃ��ꂽ�̂́A�]�ˊ��ȑO�̏�����̏��̂ł����B���̒��ōł��Â��̂����̃R�����́u��2��v�ŏq�ׂ����������ł��B
�@���ď�����͔\�M�Ƃ̌��Ƃ��]�Z�Ƃ��ď��������̂ł����B���̑�\�҂�16���I���̌����[���E�����������ł��B���{���{���̐������_�{�ɂ́A�����̐��삵���������̋�ƒ������̋�₳��Ă��܂��B�����͌�������ł��Â��`���i�̏�����ł��B
�@���̑��ɐ������_�{�ɂ͌����̋L�����w�����n���L�x�Ƃ����j�����`�����Ă��܂��B����ɂ��ƌ�����1590(�V��18)�N����1602(�c��7)�N�܂ł�13�N�ԂɎ���735�g�̋�𐧍삵�܂����B���ꂾ���ł������ł����A�ނ̎�ɂȂ鏫����͂�����������Ƒ��������ƍl�����Ă��܂��B������1514(�i��11)�N�̐��܂�ł�����A�w�����n���L�x���L���n�߂��Ƃ���70��㔼�ɂȂ��Ă��܂����B����܂ň�x��������������Ƃ��Ȃ������l�����ˑR�ˑ�Ȑ��̏�����𐧍삵���ƍl����͕̂s���R���낤�ƍl�����邩��ł��B
�@�܂��A�ނ͌��X�������Ƃ̐��܂�ł͂Ȃ��A�O�𐼉Ƃ���{�q�Ƃ��Č}����ꂽ�l���ł����B�����āA�c���ɓ��������b�̎O�𐼎���(1455�`1537)�̓��L�ɂ͐N���ォ��ӔN�܂ŏ��Ȃ��Ƃ�20�g�ȏ㏫������������Ƃ����L�������邱�Ƃ��ł��܂��B�����͐������Ƃ̒��q�ƂȂ��Ă�����p�ɂɎ����@��K��Ă��܂��̂ŁA�c���̔ӔN�̋����ڂɂ���@���������������܂���B�����̏������͎Ⴂ������s���Ă����\�����傫���悤�Ɏv���܂��B
�i���{������ψ���ҏW�̍��q�E�w��������x(2009�N)�A�F�V�Ǒ����́w�����Ӂx(1981�N)�E
�@�u���������T��v(�w���{�����Ƃ��Ă̏����x(2002�N)����) �̑��ɁA�����̓��L�w�������L�x
�@(���Q���ޏ]������E���m�Њ�) �Ȃǂ��Q�l�ɂ��܂���)
�@�Ƃ�����A�����M�̢�����������ɓ`�����Ă���A���ꂪ������̏��̂̌������Ƃ����\���͑傫���ƍl�����܂��B������Ƃ���҂Ȃ�N�ł���x�́A��������̏��̂ŋ���Ă݂����ƍl����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�M�҂����ۓ�x�قǃg���C�����̂ł����A�c�O�Ȃ��ƂɎ��ې��삵����́A�����Ė����̂����o���h���Ƃ͂Ȃ�܂���ł����B
�@8�N�O�ɑ��{���{���Ő�������̓W�������A�͂��߂Đ�������̎������ӏ܂���@��Ɍb�܂�܂����B�ʐ^�B�e���֎~����Ă��܂����̂ŁA�قɂ��̈�ۂ���������Ƃ炦�悤�Ɗ���Â炵�Ċӏ܂��܂����B����ɓ��肵����������A������x��������̏��̂Ő������Ă݂悤�ƍl����悤�ɂȂ�܂����B�������Ċ��������̂����̋�ł��B�����������Ƃ͉_�D�̍����Ƃ������Ƃ͖��炩�ł����A������x�̒B�����邱�Ƃ��ł����Ǝv���Ă���܂��B
�@

�@�@�@�������������2012�N�ɐ��삵���O�R��̐����(�F�����k��)
�@�]�ˊ��ɓ���Ə����̗��s�ɔ����A���Ƃ̔\�M�Ƃ����łȂ��A����̐�Ǝ҂Ǝv����l�X��������悤�ɂȂ�܂����B�Ⴆ�A�u�r���v�Ƃ������Ɖԉ�����K�ɋL���ꂽ������������g�ƒ��������g���m�F�ł��܂��B�܂��A�����Ƃ̑勴�Ƃ̕����̒��ɑ�X�̉ƕ�Ƃ��āu��K�M�v�̋�̋���������Ƃ��L����Ă��܂��B����ɍ]�ˌ�����疖���ɂ����āu�����v�u�^���v�u�����v�Ȃǂ̖���������������Ă��܂��B�����͏��̖��ł���Ƌ��ɁA������𐧍삷���Ǝ҂̍H�[����\�����̂������Ǝv���܂��B(�Ȃ��A�u�r���v���̋�Ȃǂ̉摜�́u��̎��v�̃T�C�g���猩�邱�Ƃ��ł��܂��Bhttp://8ya.net/suiki/siryou/siryou/15tosimitu.html)
���ߑ�ȍ~�̏�����̏���
�@�������鏫����̑��ʂȏ��̂̂قƂ�ǂ́A�吳���珺�a�����ɂ����ĖL�����R�E����ꍁ���͂��߂Ƃ����t�����ɂ��n�삳�ꂽ���̂ł��B�������A������̏��̂��L�������ꎆ�́A�e�H�[�Łu��O�s�o�v�Ƃ���Ă��܂����B���̂��߁A�ǂ̂悤�ɂ��Đ��삳�ꂽ���́A�u�钆�̔�v�Ƃ��Ĉ�،���邱�Ƃ͂���܂���ł����B�]���Ĉȉ��ɏq�ׂ鏑�̂̐����Ɋւ���b�ɂ����Ȃ�s�m���ȗv�f���܂܂�邱�Ƃ͔ے�ł��܂���B
�@���̂̎�Ȃ��̂����ɋ����܂����B�����̒��ŁA�ł��Ђ낭�e���܂�Ă���̂́A�u�ъ��v�u�������v�u�����q�����v����H���v�̎l�̏��̂ŁA�u�l�发���v�Ƃ��Ă�邱�Ƃ�����܂��B�܂����������グ�����Ǝv���܂��B
(1)�u�������v�̏��̂ɂ���
�@�@
�@�@�@�O�R��u�������v���̂̐����(�䑠�����k�ށ@2016�N�ɐ���)
�@���̏��̂́A�v���X�e�B�b�N��ɂ��̗p����Ă���̂ŁA�ł��L���m���Ă�����̂�������܂���B�u�������v�̖����琅���������M�̋���ɂȂ��Ă���Ǝv��ꂪ���ł����A�����M�Ƃ͑S���قȂ���̂ł��B�吳����ɖL�����R���������Ƃ����u��������[�����r���M���v�̋���ł��`����Ă��邱�Ƃ���A���̏��̂́A�L�����Y�g�������̑��̌��r�M�̋�����Q�l�ɂ��đn�삵�����̂��A�Ƃ����������o�Ă��܂����B���������r�͑�[���ł͂Ȃ����[���ł����̂ŁA���̕\�L�͌��ł����A���ۂ̌��r�M�̋����͎ʂ������̂��ǂ������m���ł͂���܂���B�������A���̏��̂��L���̑n�삵�����̂ł���\���͑傫���Ǝv���܂��B
�i���R��́u��������[�����r���M�Ձv��̎ʐ^�̓C���^�[�l�b�g�́u��̎��v�Ō��邱�Ƃ��ł��܂��ihttp://8ya.net/suiki/meiko/ryuzan/index.html�j�B�܂��A���R�ɂ́u���������[�����r���M�Ձv�̋������܂��B������͑��Y�g�̑��q�̐����Y���₵����i�ŁA�������点������𗽂����i�Ƃ����ėǂ��Ǝv���܂�
�B��̉摜�̓C���^�[�l�b�g�́u����W���v�ł��������� �BURL��http://www.geocities.jp/monkey007no1/koda/kigu/toyoshima/minase/hiyoji.html�ł��j
(2)�ъ��ɂ��ā@�u�ъ��v�E�u���F�v�E�u����ъ��v
�@�@�@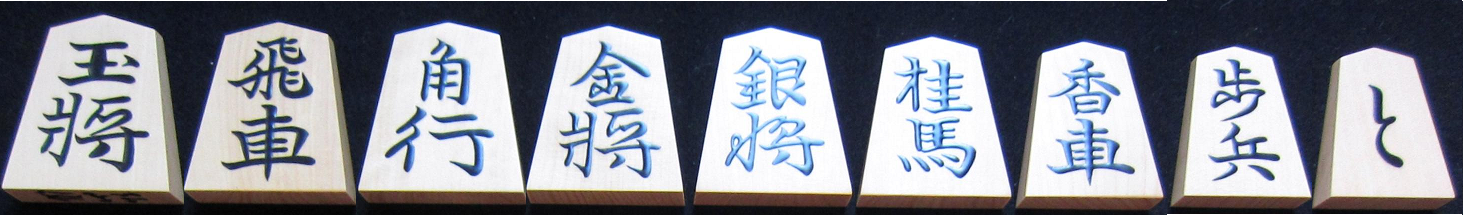
�@�@�@�@�O�R��u�ъ��v���̂̐����(�䑠�����k�ށ@2015�N�ɐ���)
�@�����炭�������鏫����̏��̂̒��ōł��������ʂ��Ă��鏑�̂ŁA���̐���҂͖L�����Y�g�ł��B�ނ̈₵���u�L�����ꎆ���v�ł͂��̏��̂��u�㐅���V�c���M���v�ƏЉ�Ă��܂� (���ꎆ���̉摜��http://meikoma.com/image/toyoshimajibocho/l/kinki.gif��������������) �B
�@�L���Ƌъ��̏��̂ɂ́A���̂悤�ȃG�s�\�[�h���`�����Ă��܂����B
�@�s���ď����Ƃ̑勴�{�Ƃɑ�X�ƕ�̋�`�����Ă����B�L�����Y�g�́A���̋�̎ʂ��邱�Ƃ��˗�����A�������ċ�ꎆ���쐬���ꂽ�B�����A�V�c�̖����L�����Ƃ͈ꑽ���̂Łu�ъ��v�Ɩ��t�����c�c�B�t
�@���̗R���b�́A�����炭�����ϐ�L�҂̎R�{����(�y���l�[���u�V�瑾�Y�v)������t�{���e�������畷��������b�����ɂȂ��Ă��܂��i�����̂�����́A�w���������j�x(1972�N)�A�w����101�b�x(1980�N)���������������j�B���̘b�́A�G�s�\�[�h�Ƃ��Ă͋��ʂ��Ă���悤�Ɏv����̂ł����A�������^�₪����܂��B�ׂ����_����������肪����܂��A��Ȃ��̂��ȉ��ɗ��Ă݂܂��傤�B
���勴�{�Ƃ̉ƕ�̋�͖{���Ɍ㐅���V�c�M�̋�Ȃ̂��H
�@���s�̒��O�ň��̗V�|�t�ɂ����Ȃ������勴�Ƃ̎҂��֗�����钼�M�̏������q�̂��邱�ƂȂǗL�蓾��̂ł��傤���B�펯�I�ɂ��̉\���͂��Ȃ�Ⴂ�悤�Ɏv���܂��B�������A���̌�z���V�c�͏������D�Ƃł������A�䐅���V�c�͓��ɊS�������Ă��Ȃ������Ƃ���Ă��܂��B
���㐅���V�c�̕M�łȂ��Ƃ���A�N�̕M�ɂȂ��Ȃ̂��H
�@�勴�{�Ƌ����̋�́A�ؑ��\�l�����l����A���Ɋ���A���ď��������قɁu�`�E�㐅���V�c���M���v�Ƃ��ēW������Ă��܂����B���a�̖����ɏ������ƂŌ����Ƃ̌F��Ǒ����́A���̋���Ӓ肵�A�^�����Ȃ����������������������ł���A�ƌ��_�Â��Ă��܂��B�L���͐���������������ɃA�����W���ċъ��̏��̂�n�삵���̂ł��傤���B(�u�`�E�㐅���V�c���M��v�͌��݂ǂ��ŏ�������Ă��邩�͕s�ڂł����A�F�̃u���O�ɂ͓��������B�����ʐ^�����J����Ă��܂��̂ł����������Bhttp://blog.goo.ne.jp/ykkcc786/e/90039510b450c6b3a4cbb9ce08c84fda)
���u�ъ��̋�v�ɂ͖L���������ɑ���ꂽ���̂�����
�@���݂ł́A�u�ъ��v�Ƃ����ΖL����̏��̂��v�������ׂ�����命���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������L�������̏��̂ŋ��n�߂�����\���N�ȏ�O�Ɂu�ъ��̋��v�ƌĂꂽ�����܂����B����́A��c�̑f���ƂŌ�ɔ��i�ɐ������|���N��(���E���F�F1877�`1947)������37�N(1904)���n��K�ꂽ�֍������Y(�\�O�����l�F1868�`1946)�ɑ��������M�̋�ł��B�֍��͂��̋�����p���A�s����X�ŏ������d�˂��̂ŁA�l�X�͖������G���������R�̢�т̌����ɋ[���Ă��̋���u�ъ��̋�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ�܂����B�u�ъ��̋�v�Ƃ́A���̖��ł͂Ȃ��u���^���Ăԋ�v�Ƃ����Ӗ��Ō��ꂽ�̂��Ǝv���܂��B
�@���݂͒|���̍����̂��āu���F�v�̏��̖�����ʓI�ł����A�u�ъ��v�ƌĂꂽ��̒��ōł��Â��̂͊ԈႢ�Ȃ����̟��F���̋�ł��B
�@�@�@
�@�@�@�O�R��u���F�v(�֍��ъ�)�̐����(�䑠�����k�ށ@2013�N�ɐ���)
���u����ъ��v�Ɓu�L���ъ��v�ɂ���
�@�u�ъ��v�ɂ͂�����A����ꍁ���吳����Ɂu�ъ��v�Ƃ������Ŕ���o�������̂�����܂��B���݂́u����ъ��v�ƌĂ�邱�Ƃ������̂ŁA�s���삪�L���́u�ъ��v�ɑR���č�������̂ł���t�ƍl������������悤�ł��B��ɏЉ���R�{����̒����ɂ��A
�@�u�L�����ƋZ�����������쎁�͋ъ���̐l�C�ɒǐ����悤�ƁA�����������̐�����v���������B�c�Ђ����ɋъ��Ɏ����������������߂��B�O�����Ђ��̏����ւ̖�������ɋ߂��A�c���쎁�́A������ؗp�����v
�Ƃ����L�q������܂�(�w����101�b�x)�B�����A�O�����e���̏����ւ�����������Ă������ۂ��ɂ��ẮA�R�{�����u�^���͒肩�łȂ��v�Ƃ��Ă��܂��B�܂��A�L���́u�ъ��v���{���ɉ���́u�ъ��v�ɐ旧���č��ꂽ�̂��ɂ��Ă��^�₪����܂��B������̌����Ƃ̒��ɂ́A����̋ъ��̕�����ŁA���̔���s�����ǂ������̂ŖL�����R���ċъ��̏��̂�o�����̂��A�Ƃ������������������܂��B(����ɂ��Ă��A�u����W���v�������������B)
(http://www.geocities.jp/monkey007no1/koda/kigu/toyoshima/kinki/hiyoji.html)
�@�@�@
�@�@�@�u����ъ��v�̏���
(3) �u�����q�����v�ɂ��ā@�u���̐����v�Ɓu�����̐����v
�@�@�@
�@�@�@�@�O�R��u�����q�����v�̐����(�䑠�����k�ށ@2014�N�ɐ���)
�@�u����ׂ�����₷�v�Ƃ��u�݂Ȃ��Ƃ̂Ђ傤������₷�v�Ƃ��ǂ܂�Ă��܂��B�A�j���w3���̃��C�I���x�̒��ŁA�v�����m�������ǂ����ʂɂ͋�̎��ɂ��̏��̂��p�����Ă����̂ʼn����Ă�����������Ǝv���܂��B��ɐ����E�D��ȕ��͋C������A��`�ɍł��K���������̂Ƃ������Ă��܂��B�N���͌Â��A�]�ˊ����炠�������̂Ƃ���Ă��܂����A�c�O�Ȃ���R���ȂǏڂ������Ƃ͕������Ă��܂���B�]�ˊ��ɂ͑��Ɂu�����v�Ƃ������̋�����H�[������܂������A�u�����v�Ƃ������̋�����H�[���������̂ł��傤���B�܂��A�u�����q�v�Ƃ͕��Ƃ̖���A�z�����܂��B����������Ƃ����������̖��M�Ƃ����āA�u�����v��̍H�[���A���̖��M�Ƃ̖��������Ĕ���o������������̂�������܂���B��������́A�S���̑z���ɂ����܂���B
�@���݉�X���ڂɂ���u�����q�����v�̐��݂̐e�́A�L�����Y�g�ł��B�������A�u�L�����ꎆ���v�ɂ́u�����v�Ƃ̂L����A�u�����q�v�̋L�ڂ͂���܂���B(http://www.meikoma.com/toyoshimajibocho.html#kiyoyasuhoso)
�@�u�L�����ꎆ���v�ɂ́A������u�����v���̏��̂����߂��Ă��܂��B���ꂪ�A���݁u�����̐����v�ƌĂ�鏑�̂ŁA������́u�����v�̕����D�ޕ��������悤�ł��B�u�����̐����v�Ƃ��ċߔN�ł��悭�m���Ă���́A�V���̖��H�E�ɓ��v���t�����삵����ł��B�v���t�́A�����q�����ł����i�𐧍삵�Ă��܂������A�^�C�g������s�u���p�����ꍇ�A�����q�������������̕�����ʂɗǂ��f��ƍl�����̂ł����B�v����̑��������̋�́A�����킪�V���ōs���鎞�ɂ͖���̂悤�ɗp�����Ă��܂��B
�@10�N�߂��O�̂��Ƃł����A���̋v����̑���������f�ڂ��ꂽ�{(�w���̋Z�ƌ`�@1�����{�ҁx�u�k�Њ��E2001�N)�����R�ڂɂ���@�����܂����B���������̋�͂���܂łɂ����������Ƃ͂������̂ł����A�u���������x�����Ă݂����v�Ƃ����C�����������Ȃ萧�삵���̂����̋�ł��B
�@�@�@
�@�@�@�@�O�R��u�����v(����)�̐����(�䑠�����k�ށ@2010�N�ɐ���)
(4)�u���H�v�̏��̂ɂ���
�@�@�@�@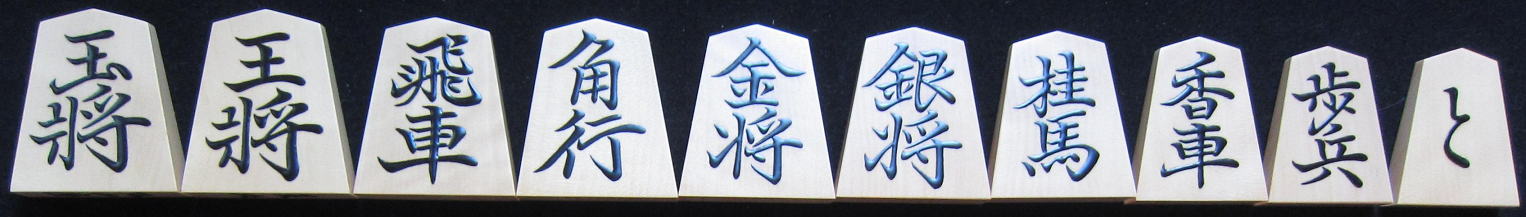
�@�@�@�@�O�R��u�H�v�̐����(�䑠�����k�ށ@2015�N�ɐ���)
�@������̏��̂̒��ōł̐l�C�̍������͉̂��ł��傤���B�����Ԑ̘̂b�ł����A������̈��D�Ƃ̒c�̂��A���P�[�g�����������Ƃ���A�ł������̕[���W�߂��̂��u�H�v�̏��̂ł����B�����Łu�����q�����v�u�������v�u�ъ��v�̏��Ɂu�l�发�́v����ʂ��߂܂���(�w�������E�x1988�N7�����̋L�����)�B�s���ؗ�ȕH�̏��̂̋�����̎w����̐S�������t����̂ł��傤���B
�@���H��(1766�`1833)�́A�]�ˌ���z��̐l�Łu�����O�M�v�Ə̂��ꑽ���̖�l�ܐ�Ə̂��ꂽ�قǂ̖��M�Ƃł��B���̏��͔̂ނ̖����������Ă��܂����A�H�Ύ��g������������Ƃ����킯�ł͂���܂���B�吳���ɓ`���̊��m�E��c�O�g�̎x���҂ŏ�����ɑ��w�̐[���������l���Z�i�Ƃ������m���A�H�ΕM�̏�����{�Ȃǂ��當�����E���o�����̂̌��^�𐧍삵���̂��N���ł��B���l���́A�L���ɐ�����˗����A�������ĕH�̎��ꎆ�Ə�����a�����܂����B
�@ �H�̋�́A����ɂ���Đ��삳��܂����B�����������Ɏ�|���������Ȃ����̂ł����A����삪�o�ʂł���̂ɑ��A�L����͋ʂƉ��ő����Ă���Ƃ����傫�ȈႢ������܂��B�������A���̉��Ƌʂ��S���قȂ鎚�ɂȂ��Ă���Ƃ�������ڂɒl����Ƃ���ł��B
�@���ɍ]�˖�������`������Â����̏��̂��Љ�܂��傤�B
(5)�u�����v�ɂ���
�@�@�@
�@�@�@�@�O�R��u�����v�̒���(�䑠�����k�ށ@2013�N�ɐ���)
�@�����̋�́A�����吳���܂ł͍ł��l�C���������Ƃ���Ă��܂��B�������D�ƂƂ��Ă��m���Ă��������̍K�c�I��(1867�`1947)���u�c���ʏ������D�ސl�̗p����́A�����A�^���A�����Ȃǂ̑����n�q(��̂���)�Ȃ�B�����͐^���Ƃ菟��A�^���͈�����菟�ꂽ��v(�w�����G�b�x1901�N)�Əq�ׁA�����̋�����ł������]�����Ă����Ƃ������Ƃm�ɏq�ׂĂ��܂��B
�@��ɏq�ׂ��R�{����(�V�瑾�Y)���́A�u�����v�̋�Ƃ��̐���҂ɂ��Ă��������A���̗R�������Ȃ�ڂ����q�ׂĂ��܂��B����ɂ��ƁA��������ېV���ɂ����ċ����̋�ő听�������l���͕��ƂŊ|��ˎm�̍b�ꎁ��(1827�`1873)�Ƃ����l���ł����B�����͍]�˂ő��Ƃ̗{�q�ƂȂ�܂������A�{�Ƃ͘\���R�������E�ɗ��炴��܂���ł����B���̓��E�̈�ɏ����̋�肪����܂����B�ނ������H�[�ő���ꂽ��̖����u�����v�������̂ł��B�ނ͋��̍˔\�Ɍb�܂�Ă����̂ŁA�₪�Đ�ォ��u�����v�̖����������ڂƂȂ�܂����B������͍��l���ĂсA�L��]��قǂ̗��v�邱�ƂɂȂ����Ƃ���܂��B
�@���ڋ����E�����͖���6�N�ɑ��E���Ă��܂��B�������A�I���̕��͂�����ƁA���ꂩ���30�N�o���Ă�������̓i���o�[�����̋�̕]���Ă��܂��B�����炭�A�����̍H�[�Ŏ����ȗ��`����ꂽ����Z�p���Q���Ă����̂ł��傤�B�����āA���̂��H�[�Ǝ��́u�������v�Ƃ��ē`�����Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������āA��Ɍ�����悤�ȁu�����v�̏��̂��m�������̂ł͂Ȃ����v���܂��B�吳���珺�a�ɂ����Ă��A�������̋�͈��̐l�C��ۂ��Ă����悤�ł����A����Ɂu�l�发�́v�̋�ɉ�����āA���݂͂��܂葢���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
(6)�u�����v�Ɓu�@���D�v�ɂ���
�@��̘I���̕��͂̒��Łu�����v�ɂ͋y�Ȃ����̂́A���s�̋���Ƃ��ċ������Ă���̂��u�����v�ł��B�u�����v�̖�����K�ɋL���ꂽ��ɂ͍]�ˎ������Ɛ��肳�����̂�����܂��B�����A�u�����v�Ƃ����̂��H�[�̖��Ǝv���܂��̂ŁA�����������邩��Ƃ����āA���̂������Ƃ͌���܂����B���̍��͍]�˖����Ɛ��肳��钆������̏��́A�E�͑吳���ɑ���ꂽ��̏��̂ŁA��������u�����v�̖��ł������Ȃ�̈Ⴂ�����邱�Ƃ�������܂��B����Ɂu�����v�ɂ͑����̂ŋ���L�������̂�����A���̑����̂̈������Â��V���̑�����̋N�����Ƃ�������������悤�ł��B
�@�@�@
�@�Ȃ��A���̃R�����̑�3��ŏЉ���悤�ɁA�����A�����́u���l��v�̏��́u�@���D�v�́A�u�����v���̋�����^�Ƃ��ĉ��삪�A�����W�����n�쏑�̂ł��B
�@�@�@
�@�@�@�O�R��u�@���D�v�̐����(�䑠�����k�ށ@2014�N�ɐ���)
�@�Ō�ɂ��̑��̎�ȏ��̂�������Љ�����Ǝv���܂��B�Q�l�܂łɂ����������B
�@�Ȃ��A���ɗᎦ�����e���̂̋�́A�w��̂����₫�x�Ɍf�ڂ��ꂽ�̂��̂ł��B
�@�@�@
��������̂������i���̂U�j
��������̉��i�i�O�ҁj���y��̏ꍇ
�@�@���͂��߂ɁF������̉��i�ɂ���
������ɂ́A�����ȑ�O��獂���Ȑ���グ��Ɏ���܂ʼn��i�ɑ傫�ȊJ��������܂��B�Â�����̏����t�@���ɂƂ��Ă͐��\���~����S���~�ȏ�̐�������[�P]���Ƃ͔��Ώ펯�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂����A�����ɏڂ����Ȃ����̒��ɂ́A��g�����~���������邱�Ƃ��M�����Ȃ��Ƃ������������܂��B����͂�����l�i�̊ϓ_���珫����̂��Ƃ��l���Ă݂����Ǝv���܂��B
�@�܂��l�X�̃��x���̏���������̎s�̉��i���猩�Ă݂����Ǝv���܂��B�������A�������炢�̕i���Ǝv���鏤�i�ł��̔��X�ɂ���Ď��ۂ̉��i�ɂ��Ȃ�̂��������܂��B�����ł͗l�X�̎�ނ̏�����ɂ��āA���݃C���^�[�l�b�g�ȂǂŔ̔�����Ă��鉿�i�ׁA�������Ɉꗗ�\�ɂ��Ă݂܂����B���i���ɂ��ẮA�����܂ł��f�l�����ׂ�����ł̋����͈͂ł̎Q�l����ł������s���m�ȓ_�������ƍl���Ă���܂��B���̂��Ƃ́A���炩���߂��f�肵�����Ǝv���܂��B
�@�Ȃ��A����ɉ����A��r�̂��߂ɁA������厏�f�ڂ̍L���ⓖ���̕M�҂̋L���Ȃǂɂ���āA��30�N�O�̏��a�������̋�̉��i���č\�����ďЉ���Ă��炢�܂����B�����������ꂽ�����Ƃ��Ȃ�s�m���ȋL���ɂ����̂ł��̂ŁA���̓_�Ɋւ��Ă��������������B
�@���i�̂��ƂɌ��炸�A�����ŏq�ׂ����ƂɊւ��Ă��C�t���̂��Ƃ�����A�����Ă���������ΕM�҂Ƃ��Ă͂����ւ肪�����v���܂��B
�@�Ȃ��A�\�̒��̍��[�̗�Ɏ�������̃��x���ɂ��ẮA���S�җp�̈����ȋ��C�����N�A�����B�����N�A�����ȋA�����N�A�ō������S�����N�Ƃ��Ă݂܂����B
|
|
��̑f��
|
��̎��
|
���݂̉��i�� (�C���^�[�l�b�g�Ŕ̔�����Ă��鉿�i�����Ƃɂ��܂���)
|
��30�N�O�̉��i(�����̐�厏�Ȃǂ��Q�l�ɂ��܂���)
|
|
C
|
�v���X�e�B�b�N
|
���`���`�㐻
|
600 �` 1200�~���x
|
600 �` 1000�~���x
|
|
C
|
�v���X�e�B�b�N
|
����(������)
|
4��~��㔼 (�u�������v�u�H�v)
|
3��~(40�N�O��2��~)
|
|
C
|
�z�I�E�A�I�J
|
�X�^���v��
|
1600�~���x (1100�`2000�~�ȏ�)
|
�\(��~�O�� �M�҂̋L��)
|
|
C
|
�J�G�f
|
�菑����
|
2400 �` 2700�~���x
|
�\
|
|
C
|
���E�J�G�f
|
�����E����
|
4��~�`6��~���x
|
�\(1500�~���x �M�҂̋L��)
|
|
BC
|
�J�G�f
|
�����E�㒤
|
7��~�`9��~���x
|
�\
|
|
BC
|
�V�����c�Q
|
������
|
1���~�O�� (����̔̔���)
|
�\(3��~�` �M�҂̋L��)
|
|
B
|
�V�����c�Q
|
����(�@�B��)
|
9��~���x (����̔̔���)
|
4��~���x
|
|
B
|
�V�����c�Q
|
����(�@�B��)
|
1���~���x (����̔̔���)
|
5��~���x
|
|
B
|
�V�����c�Q
|
�㒤(�@�B��)
|
1��3��~���x (����̔̔���)
|
7��~�`1���~�O��
|
|
B
|
�V�����c�Q
|
����(�@�B��)
|
1��6��~ (�u�ъ��v�E�u�������v�Ȃ�)
|
�\(1��2��~ �M�҂̋L��)
|
|
B
|
�{���k(�䑠��)
|
������
|
2���~�ȏォ (�̔���͋ɂ߂ď��Ȃ�)
|
�\
|
|
B
|
�{���k(�䑠��F��)
|
�㒤(�@�B��)
|
2��7��`3���~�ȏ� (��XHP���)
|
2��5��~���x�`
|
|
A
|
�{���k(�䑠��)
|
����(�蒤)
|
6���`12���~ ���͂���ȏ�
|
3��5��~�`
|
|
A
|
�{���k(�䑠��)
|
����
|
11���`18��5��~ ���͂���ȏ�
|
4���`7���~
|
|
AS
|
�{���k(�䑠��)
|
����
|
22���`80���~�ȏ�
|
15���`60���~�ȏ�
|
�P�D���y��@���S�Ҍ����̈����ȋ�@�X�^���v��ƃv���X�e�B�b�N��
�@���S�Ҍ����̈����ȋ�Ƃ����A�N�y�̕��̒��ɂ́A�q���̍��ɑʉَq���ȂǂŔ̔�����Ă����X�^���v����v���N��������������Ǝv���܂�(�M�҂������I�ȏ�O����g30�~���炢�̋�����L��������܂�)�B���̌㕨�����M�̎�����o�āA������̒l�i�͊i�i�ɍ����Ȃ�܂����B������21���I�ɓ����Ă�������ŋ߂܂ŁA��g100�~�̃X�^���v���������Ă���܂����B���Ȃ葢��̑e����ł����A�ǂ͏\���\�ł��B�Ⴂ���̒��ɂ͏������o���n�߂����ɂ��̋��p����[�Q]����������Ǝv���܂��B���ݍ��Y�̖ؐ���̒l�i�́A�X�^���v��ł�1000�~�ȏオ�w�ǂł�[�R]�B��g100�~�̉��i�ݒ�́A�����ȂNJC�O�H��Ő������Ă������炱���\�ł����B�~������̏I���Ƌ���100�~�̉��i�ێ��͓���Ȃ�A���݂ł͖w�nj������邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�܂����B
�@����100�~��������A�v���X�e�B�b�N�̋���܂߂Ă��A500�~�����̋�������邱�Ƃ͂��Ȃ����悤�ł��B��r�I�����ȃv����̏ꍇ�A��③��̑e�����̂���1000�~�ȓ��̕i������܂����A�W���I�Ȑ��i��1000�~��A�������̂ł�4000�~��㔼�̂��̂�����܂�[�S]�B
�@�v���X�e�B�b�N���������n�߂��̂�1953�N��[�T]�Ƃ���Ă��܂����A�ŏ��͖ؐ���Ɣ�ׂĊ����Ȃ����A�ϗp����������Ă���(����₷������)���ߕ��y��̎嗬�ɂ͂Ȃ�Ȃ������悤�ł��B���������̌�i�������Ȃ���サ�A1970�N��ɂ͖ؐ��X�^���v��ƑR�ł���܂łɂȂ�܂���[�U]�B��̕\�����������悤�ɁA����30�N�Ԃʼn��i�ɑ傫�ȕϓ��͌���ꂸ�A�ł����肵�₷�����i���ێ����Ă��܂��B�e�폫�����Ŏg�p����邱�Ƃ������A���݂͕��y��Ƃ��Ă͍ł��L���s���킽��悤�ɂȂ�܂����B
�@�ؐ����̏ꍇ�A�b�����N�̕��y���ɗp������͈̂����ȍގ��ł��B���̂����ł�����̍ގ����z�I�ŁA�̂����X�^���v���̑f�ނł����B�X�^���v��́A���Ă͂������̒��ōł������ł������A�v����ɔ�ׂĐ����ߒ����̐l�I�v�f�̊������傫�����߁A���a�̖����ɂ̓v����������i�����������ɂȂ�܂����B�����͂܂��ؐ�����D�ރt�@�������������̂ŁA������x�v����ɑR�ł��Ă����Ǝv���܂��B�������A��������ɂȂ���X�^���v��ƃv����̉��i���͏������g�����čs���܂����B�������A�葢��̂��߃L���C�ȃv����Ɣ�r���đ���Ƀo���������邱�ƂŌh������邱�Ƃ����������̂��A�ؐ��X�^���v��̔���s���͂���ɐL�єY�ނ悤�ɂȂ�܂����B
�@���X�^���v��ƃv���X�e�B�b�N��
�@���a�̎���̃X�^���v�� �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�A100�~�V���b�v��@�@�B�����v����@
�@�@�@(�V�����������كp���t���b�g���) �@�@�@�@�@�@�@�@�@ (2005�N����)�@�@�@�@(�M�ґ�)�@
�@�@
2�D���y��璆����ց@�@����ƒ���̏ꍇ�@
�@���ɓ`�������������グ�܂��傤�B����̖ؒn�́A���Ă̓z�I�ȂǍł������ȑf�ނ��p�����Ă��܂������A���݃z�I���p�����邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�A�����Ȃ��̂ł��J�G�f�ނ����p����Ă��܂��B�܂��A�����Ȃ��̂ɂ̓V�����c�Q[�V]��ؒn�Ƃ�����̂�����܂��B���݉��i�т́A�J�G�f�̏����g2�`3��~�䂭�炢�ł����A�V�����c�Q�̏���̕��́A���a���̖��ɂ�3��~���炢�A���N�O�܂ł�5��~���x�������̂ɁA���݃V�����c�Q�ނ��i���ƂȂ��Ă��邽�߂P���~�O��ƂȂ��Ă��܂��B����̏ꍇ�A�J�G�f��͕��y��Ƃ����܂����A�V�����c�Q��͕��y��ƒ�����̋��E�ɂ������ƍl���Ă悢��������܂���B
�@�J�G�f�̏����2�E3��~�Ƃ������i�́A�������y��̃X�^���v���v����̖�2�{�ł��B���̂悤�ɉ��i�����傫�����Ƃ��l����A����̔����ŃX�^���v���v����ɑ����ł��ł��Ȃ��͖̂����ł��B����������̗��j�����Ă��A�V���ɂ����Ă͐�O���炷�ł�����̔䗦�̓X�^���v��ɔ�ׂĂ��Ȃ艺����Ă���A�o�ϐ������ɂ͋}���ɒቺ���邱�ƂɂȂ�܂���
(���̓_�Ɋւ��ẮA���̃R�����́u���̂S�v��������������) �B
�@����ł����a����܂ł͏���ɂ͍������l�C������A���N�������̏�������Ă��܂����B������40�N�ȏ�O��1973�N��NHK�e���r�̔ԑg�w�V���{�I�s�x���V���̏����������グ�����ɁA�u�����t�v�̎�ˉi�O[�W]���E�������q(���E���R�t)���فX�Ǝ��ŋ������������l�q���`����Ă��܂���[�X]�B���̃X�s�[�h�͔��ɑ����A�����グ���̖����͈�����ϖ���S���i�O�\�g�j�ƏЉ��Ă��܂����B�܂��A�����������t�̈ɓ����Y�����A��厏�w�ߑ㏫���x�f�ڂ̃C���^�����[�̒��ŁA�Ⴂ���͈�����ό\�g���������Ƃ��������Əq������Ă��܂�[�P�O]�B
�@�����Œ��ڂ��ׂ��́A����̔��ȑ����́A�����������Ȃ����ƂōH�����҂��K�v���琶�܂ꂽ���̂������̂��Ƃ������Ƃł��B�����āA���̂悤�ɋ��ٓI�ȑ����ŏ����グ�Ă���ɂ�������炸�A���̕M�v�ɑe�����S��������ꂸ�A���̎C��Ȃǂ͌����Ƃ�����������܂���B�܂���������ɂ́A�`���H�|�i�̖��킢������܂��B��g41���̋�ؒn�ɍI�݂ȕM�v�ŋ�������E�l(���t)�̋Z�̍I�݂����l����ƁA����̉��i�͂����ƍ����Ă��悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@���`���H�|�i�̏���
�@�ʏ����������閼�H�̋Z(1973�N)�@�A�V�����c�Q�̏���(�m����)�@�@
�B�V�����c�Q�̏���(���R��)
�@�@(�wNHK�V���{�I�s
���|�ɐ�����x)�@ (���a����̍삩)�@�@�@�@�@�@ �@(���݃l�b�g��Ŕ̔�����Ă����)
�@�@
�@�����̏ꍇ���y��́A����(�u���ցv�u�V���v�Ȃ�)��J�G�f�Ȃǂ�ؒn�ɗp���ė������ő����܂��B���݂͂��ׂċ@�B����ł����A�����I�O�ɂ͂��ׂĎ蒤��ő����Ă��܂����B���t�̍H���͍��ł͍l�����Ȃ����炢�Ⴉ�����悤�ŁA��E�l�́A�����̂����ˑ�Ȑ��̋�炴����A���̂��ߏ����ł��H����Z�k����H�v���d�˂Ă��܂����B���������������̈�̍H�v�ł��B���̑��ɓ��R�Ȃ��珑��̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA���������ƕ����ő����Ă��܂����B�e���E�E�l�͋ʏ��E��ԁE�p�s�Ȃǂ�A���債���Ă̒�q�͗�������̕���(�\���u�s�O�v�A���́u�E�v)������Ƃ��납��Z�p���Ă����܂���[�P�P]�B�����������ƕ�������ł����̂ŕ��y�N���X�̗��������͂悭����Ƌʂƕ��Ƃł��Ȃ蒤��̍I�ق�������̂�����܂����B
�@�������A���ɂ͏����Ȃ���蒤��ŕ�������ʏ��܂ň�g�S�Ă̋�閼�H�����܂���[�P�Q]�B���̏ꍇ�ؒn�͊���J�G�f�Ȃǂł͂Ȃ��A�V�����c�Q�ȏ�̑f�ނ��g���Ă���܂����B������́A���y��ł͂Ȃ������������̃����N�ɕ��ނ���܂��̂ŁA��ɏڂ����q�ׂ����Ǝv���܂��B
�@���ݎs�̂���Ă��鉿�i�т́A�������3000�~��㔼����4000�~��A������8000�~���炢�܂łɂȂ�܂��B�����̎ʐ^�́A���Ċw�Z�̕������Ŏg���Ă����N�㕨�̗�����(�ł��ȒP�Ȏ��ɗ������u�����v)�̋�ł��B�蒤���Ǝv���܂����A�����̂悤�ɖؒn���`�ƒ���ɂ��Ȃ���������A���ƕ����̒Z���������Ă���悤�ŁA���܂�o���̗ǂ���Ƃ͎v���܂��� (���l�̍�������g������A�w�Z�őǂ��d�˂邤���ɍ����荇���Ă��܂����̂�������܂���) �B�����̕��y��͒���ł����̂悤�ȃ��x���̋���������悤�ł��B���ݗ����̒���́A�ؒn�̐��`��������@�B�ɂ���đ����Ă��܂��B�ގ��͓����悤�Ȉ����Ȗ؍ނł����A�@�B����ł�����ؒn�����������͏��Ȃ��A���ꂢ�ȋ�ƂȂ��Ă��܂��B�E���̎ʐ^�̋�́A�C���^�[�l�b�g�̔�����Ă���5��~�O��̃J�G�f�ނ̍�����ł����A���Ă̕��y��x���̒���Ɣ�r����Ƌ@�B�ɂ���̐���Z�p������I�Ɍ��サ�Ă��邱�Ƃ��ǂ�������Ǝv���܂��B����ɓ����悤�ȍގ��ő���ꂽ�㒤�̋�́A8��~��㔼�ȏ�̉��i�Ŕ̔�����Ă���悤�ł��B
�@���̂悤�ɍl����ƁA�u���������P���~�ɂ͓͂��Ȃ����i�v�Ƃ����A���̂����肪���y��̉��i�̏���Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�������ȑf�ނő���ꂽ�������̋�
�@�蒤�̍�����(1970�N�㐧�삩)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�@�B����̍�����(���ݔ̔�����Ă������)
�@�@
[�Q] �ŋ�TV�����E�̓V�ˁE���䑏���v������W���Ă����uNHK�X�y�V�����v�����Ă����Ƃ���A���������������100�~�V���b�v����g���ďI�Ղ̋ǖʂ��������Ă���l�q���f���o����Ă��܂����B���̋�͂��Ȃ�ϐF���A�܂������u���p�̋�v�ƕ]����̂��ӂ��킵���قǒ��N�g�����܂�Ă����悤�Ɍ����܂����B�����āA�����ɓ����v���̊����̌��_�������悤�Ɏv���܂����B
[�R] ����v���Ԃ�ɓ��}�n���Y�̃Q�[�������ɍs���@�����܂����B�����ŏ������T���Ă݂�ƁA�ؐ��̋�̓X�^���v��������Ȃ��A���i�͈�g2000�~�ł����B
[�T] �{��וv�u�V��������Y�n�̕ώ��v(�w���m�����w������ 41 �Љ�Ȋw�ҁx1992�N)
[�U] ���������ʃT�C�Y�̃v���X�e�B�b�N��ł悭�ǂ���悤�ɂȂ����̂�1970�N��̂��Ƃ������悤�ɋL�����Ă��܂��B����ȑO�ɂ��v����͂������̂ł����A���̎嗬�͏��^�̌g�я����̃}�O�l�b�g������Ǝv���܂��B�������A����͔����I�߂��O�̂���ӂ�Ȏ����̋L������������Ȃ̂Ŋm�����Ƃ͂����܂���B�ؐ���ɂ��ẮA�����Ƃ����D�E�N�W�Ƃ������A���Ђ�l�b�g�Œ��ׂ���Ȃ�̂��Ƃ�������̂ł����A�v����ɂ��ẮA�Ⴆ�Ύ�Ȑ����Ǝ҂�N�Ԕ̔����̐��ڂƂ����������I�Ȃ��Ƃł��璲�ׂĂ��Ȃ��Ȃ�������܂���ł����B�������̃R�����������̕��̒��Ƀv����Ɋւ��Ă����m�̂��Ƃ�����A�����Ă��������܂��悤�A���肢�������܂��B
[�V] �u�V�����c�Q�v�ɂ��ẮA����u�����̏�����v�ŏڂ������b���܂��B
[�W] ��ˉi�O���͏��a42�N10��26���t�́w���{�o�ϐV���x�f�ڂ́u�����A�\�N�v�Ƃ������͂̒��Ŏ��Ȃ̏��t�l����U��Ԃ��Ă��܂� (�z�q�M�`�ҁw�������M����W�x�O�ꏑ�[�A1998�N�A����)�B���̒��Łu���̏����Ă����O�\��͎O��ܕS���v�̋������ŏ������Əq�ׂĂ��܂��B
[�X] ���̌�NHK��2008�N5���ɕ��f���ꂽ�w�V���{�I�s�ӂ����сx�̒��œV���̏����������グ�Ă��܂��B��O�����̋@�B����H�[�̌��i�A���������Ɠ`������̖����̎p�A��t��ڎw����҂̎u�Ȃǂ��`����Ă��܂����A�ԑg�̒��قǂɂ͓V���Ə�����Ɋւ��l�X��`����35�N�O�̋��삪�}������Ă��܂����B�V��̕��́A�����ɂȂ�������������Ǝv���܂��B
[�P�O] �u��Ɩ�K�˂� 6 ������@�ɓ����Y�̊��v(�w�ߑ㏫���x1999�N10�����@182��)
[�P�P] ����F��(���E�V���t)�ɂ��A���w����ɂ͗�������̕���(�u�s�O�v)���������10�g400������悤�ɂȂ��Ă����A�Ƃ������Ƃł�(�w����͓V�ɏ��闳�ɂȂ�x(2002)���͂��Q��)
[�P�Q] NHK�w�V���{�I�s�x�ł́A����Ȗ��H�̑�\�Ƃ��ĐX�R�c�O��(���E���R�t)���Љ��Ă��܂��B�X�R���ɂ��Ă͎��X��ɏڂ����q�ׂ܂����A�����ŐG��Ă��������̂́A���́w�V���{�I�s�x�̒��ŁA�������t�̒��ōŏ�N���X�������X�R���������㒤��Ȃ��g�A��������Ȃ��E�O�g�̋��≮�ɔ[�߂ē����H�����A���a48�N�̎��_�ňꂩ���܁`�Z���~�������A�Əq�ׂ��Ă��邱�Ƃł��B��������́A����������Ɋւ��l�X�̓���o�Ϗ����Ɍ��������̂������Ƃ������Ƃ������ł���Ǝv���܂��B
��������̂������i���̂V�j
��������̉��i�i���ҁj������̏ꍇ
�@�قƂ�ǂ̏����t�@���́A�v���X�e�B�b�N��X�^���v���n�߂āA�����Ȓ���~�����Ȃ��Ă�����������悤�ł��B�����āA���ɂ͓�������ł���������ȍގ��̃c�Q���̋������߂�������܂��B�����c�Q��ƂȂ�A�����O���Y���u�V�����c�Q�v��̏ꍇ�ł�1���~�O���ȏ�A���Y�̉��k(�{���k)�ނ̋�Ȃ痪������ł�2���~���A�ƒl������悤�ɂȂ�܂��B
1.�V�����c�Q�̒���
�@�����ŁA����܂ʼn��x���o�ꂵ�Ă����u�V�����c�Q�v�̋�ɂ��ď������b�������Ǝv���܂��B
�@��ʂɁu�V�����c�Q�v�Ƃ́A�����ȓ��{�Y���k�̑���ɋ�ؒn�ɗp�����铌��A�W�A�Y�̖؍ނ̑��̂ł��B���{�Y�̉��k�ނ��c�Q�Ȃł���̂ɑ��A�A�J�l�ȃN�`�i�V���̖؍ނȂ̂ŁA���m�ɂ̓c�Q�Ƃ͂����܂��A�����k���Ȃ̂Ɖ��k�ɗގ������F�������Ă���̂Ńc�Q�̑�p�i�ƂȂ��Ă��܂�[�P]�B������̑f�ނƂ��ẮA�����������Ȃǂŗp�����A�V���ł͐���1958�N�������ؒn�ɓ��������悤�ɂȂ�܂���[�Q]�B�Y�n���^�C�E�J���{�W�A�E�x�g�i���E�C���h�l�V�A�Ȃǂ�����A���ꂼ��̎Y�n�ōގ��ɔ����ȈႢ��������悤�ł��B
�@��ʂɃV�����c�Q�͓��{�Y���k�ɔ�ׂ�ƌ����͏������A�N�����o�߂���ƍ�����ł���̂ō�����ɂ͕s�����ł���Ƃ���Ă��܂��B�����̐}���́A�J���{�W�A�ƃ^�C�̃V�����c�Q��ؒn�ł��B�ʐ^�ł͐F�̈Ⴂ�������邾���ł����A���ۂɖ̖��킢�͂��Ȃ�قȂ��Ă��܂��B
���V�����c�Q�̖ؒn�i�J���{�W�A�Y�ƃ^�C�Y�j �@�@�@ ���o�N�ɂ��ϐF�����蒤��̃V�����c�Q��@
�@
�@�E���(�^�C�Y�Ǝv����)�V�����c�Q�̋�ؒn�ő���ꂽ�o���̒���ł��B�o�N�ω��ŕϐF���������A�����Ă��甼���I�ȏ�̎����o�߂��Ă���Ɛ����ł��܂��B�⏫�ƍ��Ԃ͕����ŕ����͒����ł����A�O��Ƃ��@�B���肪���������ȑO�̎蒤����Ǝv���܂��B����̋Z�͌����Ƃ����ׂ��ŁA�����炭��g�̒������l�Œ���グ��悤�Ȗ��H�̎�ɂȂ���̂������̂ł��傤(�蒤���S������̖��H�ɂ��Ă͎���ڂ����q�ׂ����Ǝv���܂�)�B
�@�V�����c�Q��ؒn�̂����A�ł������̊������߂�̂̓^�C�Y�ł��B���́u��������̂�����v�ł��u����4�v�ŏq�ׂ��悤�ɁA1960�N��㔼����70�N��ɂ����Ē���̔��オ�}���������A�唼�́A�^�C�Y�̃V�����c�Q�ؒn[�R]�Œ���ꂽ��ł����B�����āA�₪�ċ@�B���肪�������ꐶ�Y���������A�R�X�g�������邱�ƂŁA��葽���̏����t�@��������őǂ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����i1980�N��ɃV�����c�Q��́A����̏ꍇ��3��~�O��ŁA����̏ꍇ��4��~(����)����1���~(�㒤)���炢�ōw���ł����悤�ł��j�B
�@�������̌�A���l��h�~����ړI�Ń^�C���{���V�����c�Q�ނ̗A�o�S�ʋ֎~���A���̌㑼�̓���A�W�A��������̗A�����啝�ɐ����悤�ɂȂ��āA�V�����c�Q�ނ̐V�K����͂��Ȃ荢��ɂȂ�܂����B���݂��u�V�����c�Q�v�̒���́A9��~(����)�`1��3��~(�㒤)���炢�̉��i�тŎs�̂���Ă���悤�ł����A���̖w�ǂ����Ă̋��삩�A�A�������~���ꂽ��ؒn��p�������̂��A�����ꂩ���낤�Ǝv���܂��B�V�����c�Q�̑���ɖ{���k�̒[�ނ⒆�����k�̔ڍނ𗘗p���邱�Ƃ��l�����܂����A����ł����Ȃ�̒l�グ�͔������܂���B�V�����c�Q�ނ�������A�����̏�����̉��i�т̑唼���߂�1���~��̋���w�����邱�Ƃ͓���Ȃ��Ă��܂��܂��B�����ŁA�V���ł̓V�����c�Q�ɑ���f�ނƂ��āu���܊�(�I�m�I���J���o)�v�����Ă��鏫������X[�S]������܂��B
�@���ɁA1980�N��ɋ@�B���ő���ꂽ�ƌ�����V�����c�Q�̒���̐}�����f�������Ǝv���܂��B����2005�N���ɋߐ�̑�|�����������ɏo�Ă�����������ł��B��(���̎�����X��20�N�قǑO�Ƃ������b�ł���)�����D���̑��y���������Ē��x�݂Ȃǂɂ�����g���Ċy����ł����Ƃ������Ƃł����B��͌��Ǐ����D���̕M�҂��������܂����B���Ȃ�o�N�ω����Ă���A�ł��邾�����������Ă��ꂢ�ɂ��č����g���Ă��܂��B�M�Ҏ��g�̍w��������ł͂���܂��A����1980�N�㑢��ꂽ���̂ł���A�����炭�����̉��i��5��~�O�ゾ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�܂��E�͕M�҂�1984�N���ɐ�ʃ��J�̏�����ً߂��̈͌鏫���p�i�X�ōw��������ł��B���i�͊m��1���~���炢�ł����B���̏�ɋъ��E�������Ȃǂ̏������V�����c�Q�ށu������v��1������~�������悤�Ɏv���܂��B�F�������ǂ������̂ł��̏㒤��I�сA���̌�20�N�ȏ㈤�p���邱�ƂɂȂ�܂����B���v���A���̍�����M�҂̏�����y���n�܂����悤�ł��B
���V�����c�Q�̕�����i�@�B���@1980�N�ォ�j�@ ���V�����c�Q�̏㒤��i�@�B���@1984�N�w�����������j�@
�@ �@�@
�@�@
2.�{���k�̒���
�@�u�{���k�v�Ƃ����\�L�͐����̖��̂ł͂Ȃ��A�V�����c�Q���c�Q�Ȃ̐A���ł͂Ȃ��̂ɑ��āA�u�{���̃c�Q�v�Ƃ����Ӗ��ŁA���Y�̃c�Q�����w�����߂ɗp�����Ă�����̂ł��B�c�Q��������̑f�ނƂ��ė��p����Ă����̂́A���Ȃ�Â����ォ��̂悤�ŁA���̃R�����́u����2�v�ł��Љ��16���I�����̓`���i�̐�������̓c�Q�ނő���ꂽ���̂ł����B���̌�A�]�˂ł͈ɓ������̃c�Q��������ɗp������悤�ɂȂ�A���n���ł͎F���Y�̃c�Q����ނɗ��p����Ă����悤�ł��B�������ɂȂ�ƁA�L�����Y�g���ؖڂ�͗l�̔������ɓ����̂���䑠���Y�̃c�Q�ɒ��ڂ��Ĕ���o�������߁A�䑠���c�Q���F���c�Q�����Y�c�Q�̓��u�����h�ɂȂ�܂����B�ŋ߂ł͂��̓��̍��Y�c�Q�ɉ����A����������i���̗ǂ��c�Q�ނ�����悤�ɂȂ�܂����B�����Y�̉��k�́A�u�������k�v�ƌĂ�u�{���k�v�Ƃ͌Ă�܂��A���^�����c�Q�Ȃ̖؍ނł��B�A�������͍��Y�̃c�Q�ɔ�ׂĕi���ɂ��Ȃ荷���������悤�ł����A���݂́A���Y�c�Q�Ɣ�ׂĂƂ��ɑ傫�ȈႢ�������邱�Ƃ͓���Ɖ]����܂ŕi�������サ�Ă��܂�[�T]�i�������ĕi�������サ�Ă��邱�Ƃ������āA�������k�̖ؒn�́A���i�I�ɈȑO�������߂ɂȂ��Ă��܂����A����ł����Y�c�Q�̋�ؒn�ɔ�ׂĂ��Ȃ�i���ł��B�u�{���k������v�ƕ\�L����Ă��鏤�i�̒��ɂ��A���͍��Y�c�Q�ނł͂Ȃ������c�Q�ő����Ă�����̂����邩������܂���B�ꉞ�v���ӂł��j�B
�@�Ƃ���ŁA�����ōĂы�̉��i�ɒ��ڂ��A������̉��i�т��m�F���Ă��������Ǝv���܂��B�M�҂Ƃ��ẮA������̉��i�т̉����͂P���~�]��A�����2��5��~����3���~���炢�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̏��3���~�Ƃ�����̉��i������ƁA�@�B�����̋�ł�����{���k�̏㒤�������̋��z�ōw�����邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B����ɂ���2�A3��~�o����3������~����A(�������E�ъ��Ȃǂ�)�@�B����̖{���k��������w���\�ł��傤�B���̂悤�ɍl����ƁA���z�ɂ���3���~�v���X�}�C�i�X����~���x�Ŕ�����[�U]�u�@�B���̖{���k��v�Ƃ����̂�����������̏�����ƍl���Ă悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���̐}���́A��̃V�����c�Q�㒤��w����2�N��1986�N�ɓ��肵���F���{���k�̏㒤���ł��B�����炭�@�B����̋�Ǝv���܂��B��ؒn�͕s�����Ŕڂ������������߂��A�{���k�ɂ��Ă͒l�i��������2���~�ɂ͒B���Ȃ������悤�ɋL�����Ă��܂��B�w�����Ă���30�N�ȏ�ǂɎg�p���Ă��܂����A�N�Ƌ��ɖؒn�̐F���������F�ɋ߂Â��Ă��܂����B�V�����c�Q�̋�̏ꍇ�́A�ؒn��������ł��邽�߁A���̋�̂悤�ȐF�����ɂȂ���̂͂��Ȃ菭�Ȃ��Ǝv���܂��B��K�ɒ���ꂽ�u�z�R�v�Ƃ́A�V���̏������X�̖����ł��B�z�R��́A�@�B�ɂ�鐳�m����Ȓ���ō������D�Ƃ������獂���]���Ă��܂��B
�@�@
�@�����{���k���3���~�O��Ƃ����l�i�́A�����̖R��������ł͏o��ɋy�э��ɂȂ�悤�ȉ��i�ł��邱�Ƃ��m���ł��B�����̑Nj�Ƃ��ẮA�唼�̏����t�@���̓V�����c�Q�ł��\�������ł���ł��傤�B�������ؒn���{���k�ł���A������ł��g�p��5�`10�N�ƒ��N�ɂȂ���ꂾ���o�N�ω��ɖ��킢���o�Ă������Ƃ������Ǝv���܂��B�����ŁA�ꐶ�̗F�ƂȂ鏫����͂�͂�{���k���������Ƃ����ׂ��ł��傤�B
�@�������A���̂�����̉��i�̋����ɓ���鎞�ɂ͂��Ȃ�̐T�d�����K�v�Ȃ��Ƃ��m���ł��B�����Ŏv�����܂܂ɁA����w������ۂɒ��ӂ��ׂ����Ƃ��ȉ��ɋ����Ă݂悤�Ǝv���܂��B
(1) �M���̂�����X�ōw������B
(2) �K����̍ގ����m�F���Ă���w������B
(��́u�c�Q�v�u���k�v�u���k�v�̓V�����c�Q�̂��ƂŁA�u�{���k�v�\���������Ă����S�ł��܂���)
(3) ���ڌ����������������̋�E�ؒn�̂Ђъ���E���̔����E�����Ȃǂ��悭�m���߂�B
�@�������A�����܂ł��M�҂̋����m����o������Q�l���x�ɋ��������Ƃ���ł��̂ŁA�����͍��������Ă��l���������B�܂��A�������A����炾���ɗ��ӂ���Ώ\�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ������Đ\���グ�Ă��������Ǝv���܂��B
[�P] �c�Q�̊w���́ABuxus microphylla
var.japonica�ł��BBuxus���c�Q�ȃc�Q����\���܂��B�����A�V�����c�Q��Gardenia
collinsae�ŁA�c�Q�Ȃł͂Ȃ��A�J�l�ȃN�`�i�V���̐A���ł��B�V�����c�Q�͈�ӂɂ��p�����܂����A��ӋƊE�ł͌�������ψ���̎w���Łu�A�J�l�ށv�ƕ\�������悤�ɂȂ��Ă��܂��B
[�Q] �_�����ȎR�ыǕҁw�؍ރm�H�|�I���p�x(1912)�@574�łɑ��̏�����̍ޗ��Ƃ��āA�u�F���y�L��Y�v�́u���v�̑��A�u��x���v�u����ނ��v���Ꭶ����Ă��܂��̂ŁA�V�����c�Q�����X���ŏ�������ɗ��p����Ă������Ƃ͊m���ł��B�܂��A�V���ŋ�ؒn�ɃV�����c�Q����������n�߂������ɂ��ẮA�{��וv�u�V��������Y�n�̕ώ��v(�w���m�����w������ 41 �Љ�Ȋw�ҁx1992�N)���Q�Ƃ��܂����B
[�R] ��ʂɍ��Y�̉��k�̋�́A��ɕK���u�{���k�������v�ƕ\������Ă��܂��B����ɑ��āA�V�����c�Q��́A�u���k�v�ƕ\������邩�A�܂��͒P�Ɂu���k�v�ƕ\������邩�A�����ꂩ�ł� (�u���k�v�Ƃ����\�����ꂽ��̍ގ����A���Y���k�ނł��邱�Ƃ͖w�ǂȂ��ƍl���������悢�Ǝv���܂�) �B
[�T] �u��Ɩ�K�˂āv(�w�ߑ㏫���x�A�ڃR����)��1��`6��̒��̉L��P�����́u�c�Q�̂��b�@����1�v����u����5�v�ɑ����̂��Ƃ��������܂����B(�w�ߑ㏫���x1999�N5�����`1999�N10����)
[�U] �C���^�[�l�b�g�Œ��߂Ă݂�ƁA�����i�Ŗ{���k�̖�����(�@�B����)�����������������i�Ŕ����Ă���ꍇ������悤�ł��B�������A�l�b�g�ł̍w���ɂ͂���Ȃ�̃��X�N���o�債�Ă����K�v������܂��B
��������̂������i���̂W�j
��������̉��i�i��ҁj������獂�����
1. �L���Ӗ��ł̍�����
�@�t�@���̒��ɂ͎�������Ă���ƁA�v������������ɍ��߂āA�����Ɩ{�i�I�ȋ�~�����Ȃ�l�X�����܂��B�Ⴆ�A�V�����c�Q�̒������肵�ăp�`���Ǝw���čŏ��́u��͂�c�Q��̋����͂����ˁv�Ɖx�ɓ����Ă��Ă��A�₪�ĉ��������ł��Ȃ����̂������A
�@�@�@�u��̍ގ��͗A����(�u�V�����c�Q�v)�ł͂Ȃ����Y�̉��k(�u�{���k�v)�łȂ��ƃ_�����v
�@�@�A�u�������͘_�O�ŏ㒤��������Ȃ��A�u�������v�u�ъ��v�Ȃǂ̖��Œ�������~�����v
�ȂǂƁA������̒��ł�����ʂ̋�����߂悤�Ƃ���ꍇ������܂��B����ɁA
�@�@�B�u�@�B�Œ�������ł͂Ȃ����Ƃ̎蒤���~�����v
�Ƃ����i�K�ɖڕW���G�X�J���[�g���Ă����ƁA��������ł��@�B����Ǝ蒤��Ƃ̊Ԃɂ͑傫�ȉ��i��������܂��̂ŁA�ő�������̉��i�тɂ͎��܂�Ȃ��̈�ɓ��荞�ނ��ƂɂȂ�܂��B�����
�@�@�C�u�����ƍ����Ȓ������v�����m���ǂɎg�������~�����v
�Ɛi��ł����A���߂��̉��i�͓V��m�炸�Ƃ������ƂɂȂ��Ă䂭�̂́A���ΕK�R�Ƃ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ł́A�������X�Ɉ���i��ō�����̓�������Љ�悤�Ǝv���܂����A���̑O��������ƍ�����̋��E���ǂ̕ӂ肩��������x�m�F���Ă݂܂��傤�B�܂��u����6�v�ɋ�����������̃����N�ʉ��i�\����{���k�ނ̋�Ɋւ�镔�����o���čČf���܂��B
|
|
��̑f��
|
��̎��
|
���݂̔̔����i�@
|
��30�N�O�̉��i
|
|
B
|
�{���k(�䑠��)
|
������
|
2���~�ȏォ (�̔���͋ɂ߂ď��Ȃ�)
|
�\
|
|
B
|
�{���k(�䑠��F��)
|
�㒤(�@�B��)
|
2��7��`3���~�ȏ� (��XHP���)
|
2��5��~���x�`
|
|
A
|
�{���k(�䑠��)
|
����(�蒤)
|
6���`12���~ ���͂���ȏ�
|
3��5��~�`
|
|
A
|
�{���k(�䑠��)
|
����
|
11���`18��5��~ ���͂���ȏ�
|
4���`7���~
|
|
AS
|
�{���k(�䑠��)
|
����
|
22���`80���~�ȏ�
|
15���`60���~�ȏ�
|
�@�u������v�̃C���[�W�͏������D�Ƃ��ꂼ��ɂ���ĈقȂ�܂�����A�N�����[���ł��閾�m�ȋ��E�����������Ƃ͂����ւ������Ƃł��B�N�W�Ƃ̕��X�̊Ԃł́A�^�́u������v�Ƃ͕]���̊m�����������̎�ɂȂ����̂��Ƃ��ƁA���Ȃ���肷�錩�����������߂Ă��܂��B���������������Ƃ�A��ʂɂ͍�����Ƃ���鐷���̒��ł������͂��̋������ɊY�����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��i�����ĒN�𖼏��Ƃ��邩�ɂ��Ă��A�N�W�Ƃ̒��ł�����������Ă��܂��j�B
�@��ʂ̏����t�@���̒��Ő������������̕��͂��������ł��傤�B���ɏ������Ă���Ƃ��Ă����ۂɑǂɗp���Ă�������͂���ɏ��Ȃ��Ǝv���܂��B�����͑Ǘp�̋�Ƃ��������ӏܗp�̋�Ƃ����ꍇ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����ɐ����̒��ŁA���R�A�����A�e���A�ÎR�Ȃǂ̂��Ă̖��H�͂������̂��ƂȂ���A���݃^�C�g����ǂȂǂŗp�������|���A�d���A�G���A���ʗ��Z�Ȃnj���̖��H�̍���A�t�@���ɂƂ��Ă͎�����ڂɂ���@���w�ǂȂ��Ƃ����̂����Ԃł��傤�B�]���āA������̊T�O��]��ɋ������肵���ꍇ�́A������ʐ^�W��C���^�[�l�b�g���̐}�������̂��̂ɂȂ��Ă��܂��悤�Ɏv���܂��B���ەM�҂̏ꍇ�ł��A���ꗬ�̖��H�����̋�̒��Ŏ����������̂́A�W�������X�Ŕq���������̂����\�g���炢��������܂���B���������킯�ŕM�҂ɂƂ��ẮA�������������삵�����v������ɗp����ꂽ��A����ɃI�[�N�V�����ȂǂŏN�W�Ƃ������č��z�̓��D��������Ȃǂɂ��āA���ꂱ��]�����邱�ƂȂǍŏ����疳���Șb�ł��B����疼�H�̎�ɂȂ��͕ʊi�́u�ō�����(����)�v�Ƃ��ĕX�I�ɁuS�����N�v�Ɉʒu�Â��A�����ł͂��̕]���≿�i�тɂ��ďq�ׂ邱�Ƃ͍T����ׂ����낤�Ǝv���܂��B
�@�����ŁA���̍��ŏq�ׂ鍂����(�uA�����N�v) �Ƃ́A��ɑǂɗp�������ŁA������Ƃ̋��E�����������������肩�珫���t�@������������Γ���ł��鉿�i�̒���E������E�����܂ł��w���Ƃ��l���������B��̓I�ȉ��i�т��l����ƁA������Ƃ̋��E�ɂ��ẮA��̕\���̓�i�ڂƎO�i�ڂ̊ԁA���Ȃ킿�{���k����̒��ŁA�@�B����Ǝ蒤���̊Ԃ�3���~�߂��̊i�����������Ƃɒ��ڂ��A�����ɋ��E����ݒ肵�Ă݂����Ǝv���܂��B
�@�C���^�[�l�b�g�œs���̔Ջ�X��V���̋���X�̏�����Љ������ƁA�蒤��ƌ������̉��i�͂����ꕔ��������6���~�ȏ�ŁA�������̂�12���~�ȏ�ƂȂ��Ă��܂� (�ȉ��ɎQ�l��Ƃ��āA��������X�̃T�C�g��URL�������������܂�)�B
�s�� �E��v�ی�ՓX�chttp://igo-shogi.game.coocan.jp/
�E�R��ՓX�chttp://www5b.biglobe.ne.jp/~goban/s1go11af.html�@
�V�� �E�������g���Xhttp://www.shogi-koma.com/shopping/?mca=101&ca=1436171145-837956
�@���ɂ������ȏ�������Љ�E�̔�����C���^�[�l�b�g�T�C�g�́A�s�����͂��ߑS���ɐ���������܂��B�����͊ȒP�ɂł��܂��̂ŁA�S�̂�����ɂ������߂��܂��B�܂��A�\�̒��̒��������̉��i�тɂ��Ă������̃T�C�g�Ŋm���߂邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�u�t�@������������Γ���ł���v���z���ǂꂭ�炢���͂��Ȃ������ł����A�s�̂���Ă��鐷���̒��ōł����肵�₷����̉��i�т����20���~��O���ʂ��Ǝv���܂��B�����ŁA���̂����������l����A�����N��̏���ɂ��čl�������Ǝv���܂��B
2. ������̉��i�͂ǂ̂悤�ɂ��Č��܂�̂�
�@�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A��g100���~�߂����鍂�������ƕ����ƐM�����Ȃ��Ƌ��������������悤�ł��B�����ł́A�܂��K���ȏ�����̉��i�́A�ǂ̂悤�ɂ��Đݒ肳��邩���l���Ă݂����Ǝv���܂��B���������܂ł̗���͑�G�c�Ɏ��n��ł����ƁA
�@�u������(�ؒn�t�ɂ�鐬�`)����ؒn��(��t�ɂ����)�����������(�Ջ)���s�̋��v
�ƂȂ�܂����A���ꂼ��̒i�K�����i�Œǂ��ƁA
�@�@�@���ޗ�(���k��)�̉��i
�@�@�A��ؒn�̉��i(�@�{�ؒn�t�̍H��)
�@�@�B��̎d�����i(�A�{��t�̍H��)
�@�@�C��̏������i(�B�{�≮�̗��v�{�����X�̗��v)
�@�����ł͂܂�������ɂƂ��Ă݂����Ǝv���܂��B�܂���̍ގ�����n�߂܂��傤�B��\�]�N�O�ɕM�҂���̋����n�߂����A����A�W�A�Y���V�����c�Q�̋�ؒn��Ջ���X����1�g3��~�O��Ŕ̔����Ă������������Ƃ�����܂����B�����炭�������V���̏�����̃V�����c�Q�̖ؒn���i�͂���������Ȃ��z�������̂��낤�Ǝv���܂�(���݂͗A�o�֎~�ނ̂��ߓ��肪����Ȃ��Ă���A���đ�ʂɎd���ꂽ�X�g�b�N�����Ȃ茸�����Ă���悤�ł�)�B
�@�{���k�̏ꍇ�̋�ؒn���i�͂ǂ̒��x�ł��傤���B������ؒn����I�ɐ�������X�ɂ��ƁA�䑠���Y���k�ނ̖�����41��(�]�����1��)������Ɖ��i�͍ł��������̂ł�2���~�ɋ߂��A���ڂ̖ؒn��������Y��ɑ�����ƂȂ�ƁA���i�͂���ɒ��ˏオ����3���~�ȏ�ɂȂ�Ƃ������Ƃł�(�A�}�`���A��舤�D�Ƃ̒c�̂Ȃǂ���w������ꍇ�͗����Γx�O�����Ă��܂��̂ŏ��������Ȃ�܂����A�ǂ�ȂɈ����Ƃ����ڂ���1������~���x���낤�Ǝv���܂�)�B�ڍނ�ؒn�ɂ����ꍇ�͖{���k�̋�ؒn�̉��i�����Ȃ�̒��x�܂ŗ}���邱�Ƃ��ł��܂��B���Ă͖��ڂ��������̒[�ނ��瑢�����ڂ̋�ؒn����r�I�����ŁA�ڌ�����̖{���k����g1���~�ȓ��̏ꍇ������܂����B�����V�����c�Q���i���ɂȂ����e�����A���݂͓��肪����ɂȂ��Ă��܂��B
�@���ɖ��ڂ̋�ؒn��2���~�Ƃ��āA���̖ؒn���i�ɋ�t�̐���o��(�H��)����悹���邱�ƂɂȂ�܂��B����������킯�ł����A���ݒ����95���ȏ�͋@�B����ł��B�@�B����̍H���́A��g��~�ȉ�[�P]�ƋL��������������܂����A��͂�@�B����̍H�����������������������㒤�������Ɖ搔��������Ԃ�������قǍ����Ȃ�͂��ł��B�������Ē�������ɂ���Ɏ�(�@�B����̏ꍇ�͐l�H�h��������)�����A��������Ɏd�グ�̖����������܂��B���ăV�����c�Q�ނ��L�x���������������i�́A������(�����E�����E����)��4��~����6��~�A�㒤��8��`1���~���x�������悤�ł��B�d���ꉿ�i�����̔��z�ƍl����ƁA2��~����5��~���炢�Ɛ����ł��܂��B���݃V�����c�Q�@�B����̉��i�͂���������Ȃ荂�z�ɂȂ��Ă��܂��B���̎傽��v���́A�f�ނ̃V�����c�Q�����荢��ɂȂ������ƂȂǂ��ƍl�����܂��B�܂��{���k��̏ꍇ�A���i�͋@�B����̏㒤��2��5��`3���~���x�A�������E�ъ��Ȃǂ̖����͂����������悤�ł��B
�@�@�B���肪���������ȑO�͂��ׂĎ蒤��̋�ł����B���R�Ȃ���A�H�������̐����ɒB���Ȃ��ƁA������̐���Ƃ����E�Ƃ����藧���܂����B���ċ�t�̍H���́A���ł͍l�����Ȃ����炢�Ⴂ���z�ł����B���݂��蒤���̍H���͌����č����͂���܂��A����ł���g5���~�ȏ�ɂ͂Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������ċ�ؒn��ɍH���������ĎZ�o�����d���l�ɂ���ɖ≮�Ɣ̔��X�̎�蕪��������ƁA�{���k(�F�����k�E�䑠�����k)�蒤��̕W���I�Ȕ̔����i�����ς��邱�Ƃ��ł��܂��B��G�c�ɉ]���āA���ڂ̎蒤���̉��i�т́A�Œ�ł�6�A7���~�A���̒ʂ�����t�̍�ł����10���~�ȏ��Ƃ����Ƃ���ł��傤�B����ɋ�ؒn���Ք��E�Ԗ��E�ۂȂǍ����ɂȂ�A����ł�20���~�ȏ�̋������������܂����B
�@������E�����ɂȂ�Ɗ����܂łɗv���鎞�ԂƘJ�͂͂���ɑ��傷��̂ŁA���̂��߂̍H���̑傫�������R���i�������グ�邱�ƂɂȂ�܂��B������̍H���͍Œ�ł�7�A8���~�A�����Ƃ��Ȃ�ΐ���H���͂���ɑ����권��߂��̊��Ԃ�v���܂��̂ōH���͍Œ�ł���g10���~�ȏ�[�Q]�A���̂���H�l�̏ꍇ��30���~�ȏ�ɒB����ƍl�����܂��B�܂��A�����E�����̏ꍇ�ɂ́A���ڂɌ��炸�A�Ք��E�ۂȂǍ����ȋ�ؒn�ő����邱�Ƃ������A���̏ꍇ�����R�����i�̉��i�����ˏオ�邱�ƂɂȂ�܂��B
3. �蒤��̖��H�����̖��Z
�@�����ł͂��Ē���̖��H��搂�ꂽ�l�X�̋Z���Љ�����Ǝv���܂��B�����I�O�܂ł̒���͂��ׂĎ蒤��ő����Ă��܂����B�����ȑf�ނ̕��y�i�̏ꍇ�́A���ƕ����ő����A�ł������ȃc�Q�̋�͈ꗬ�̐E�l(���t)���ʏ���������܂ň�l�Ŏ蒤�肵�Ă��܂����B�����c�Q�Ƃ����Ă��A���Y�̖{���k�͍����Ȃ̂Ő��͏��Ȃ��A�唼�́u�c�Q��v�Ƃ͑O�Љ���u�V�����c�Q�v���蒤��Ő��삵�����̂ł����B�ꗬ�̒��t�Ƃ����Ă��A�����̍H���͔��ɒႩ�����̂ŁA�����̂����ˑ�Ȑ��̋�炴��܂���ł����B�����āA�����ł��H����Z�k����H�v���d�˂Ă��܂����B�������A������������̍H�v�̈�ł����A���ꂾ���ł͂���܂���B���t�̒��ɂ́A������������鎞�ɁA���ꎆ��\�炸��ؒn�ɒ��ڋ��グ�閼�������܂����B1973�N���f��NHK�w�V���{�I�s�x�́A����Ȗ��H�̑�\�E�X�R�c�O��(���E���R�t 1900�`1980)[�R]�́u������(�͂����ڂ�)�v�Ƃ�����z��������̋Z���Љ�ꂽ(���R�t�̔������̋����オ�����}�������̇@�Ɍf���܂����̂ł���������)�M�d�ȋL�^�ł��BTV���f�㐔�N�o���Ă���o�ł��ꂽ�{�̒��ŁA���̋Z�͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂ��Ă��܂��B
�@�u�X�R����͓V���ł������Ȃ��������̒B�l�ł���B����ɂ����ɂ͕\�����ʔ��������\��t���Ă���B���t�́A���ʁA���̎��̏�ɃS����ŕ����������A������Ȃ����Ē����Ă����̂����A�X�R����̓S������g�킸�A�����̂܂܂Œ���̂ł���B�v
�@(�wNHK�V���{�I�s�@��4�W�@���|�ɐ�����x(�V�l�������ЁA1978�N) 61��)
�@�X�R�t���8�ΔN���ɂȂ�܂����A��͂蒤��̖��H�Ƃ��Ēm��ꂽ�����Î�(���E(����)�V���t 1914�`74) �ɂ��A��́u�������v�Ɠ����悤�Ȓ���̖��Z������܂����B�w�������E�x���ŁA�V��t�̂��q���̍������쎁
(���V���t 1950�`)�́A���̂悤�ɖؒn�ɏ��̂�\�炸�ɋ��Z�@���u������(�����ڂ�)�v�ƌĂсA���オ�����⒆���͂��̒�����ő����Ă���[�S]�Əq�����Ă��܂��B���́A���N�M�҂��n���̒��w�̏��������������w�����Ă����������܂ɁA�ӊO�ɂ��u�V����v�Ƃ������̂��闪������(����)�̋����g���Ă����̂����܂��� (���̐}���A������������) �B�����ŁA�ȑO�s���œV��������܂���������ɓ��V��t��̏㒤��ɂ́A��K�Ɂu�V��v�Ƃ̂ݒ����Ă��āA�����̒�����ɂ́u�V���v�ƒ����Ă������Ƃ��v���o���܂����B�����܂ł��\���ɉ߂��܂��A�u����������ƁA���̒����������V��t����������ŁA������̋������Ȃ��v�Ƒz�����܂����B����V��t[�T]��1974�N�ɑ��E����Ă��܂��̂ŁA��������삪�����Ƃ���A����N��́A60�N�ォ��70�N�㏉��������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�J��Ԃ��܂����A�����̋�̉��i�͍��������Ȃ�����A�����g�̍H���͐M�����Ȃ����炢��z�ł����B�u����6�v�̒�12�ł��Љ�܂������A�wNHK�V���{�I�s ���|�ɐ�����x�́A�X�R�����㒤��Ȃ�����g�A�����E�����Ȃ��`�O�g�̋���Ė≮�ɔ[�i���A��J���Ŗ�Z���~�̍H�������A�Ɠ`���Ă��܂��B��������v�Z����Ə㒤���g�̍H���͓��~�A�����͈�g��~���炢�������Ɛ���ł��܂��B����V��t�������N���X�̒��t�������Ǝv���܂��̂ŁA���l�̍H���������ƍl�����܂��B�����̒��t�̍H���͔ނ�̌����Ȓ���̋Z�ɂƂĂ��ނ荇�����z�ł͂Ȃ��������Ƃ͊m���ł��B�܂��A�ˑ�Ȑ������Ȃ��K�v�����������Ƃ���A���̎蒤���̏o���h���ɂ͂��Ȃ�̂�������������Ƃ��z���ł��܂��B�������A�ނ疼�H�̑S�����ォ�甼���I�̎����߂��A���݂��̑�z�����蒤��̋Z�͋�̈��D�Ƃ�������ĕ]�������悤�ɂȂ��Ă��܂�[�U]�B���R��E�V���Ȃǂ̒���(���ɏ㒤�ȏ�̋�)�ɂ̓I�[�N�V�����Ȃǂł��Ȃ荂�z�̒l�������Ƃ�����Ƃ����Ă��܂��B���Ē�����Ƃ��ꂽ�ނ�̎蒤�������������������͔��ɏ��Ȃ��Ǝv���܂����A���̒��Ɍ��ݏN�W�Ɛ����̋���邩������܂���B�Â�������������̕��͈�x�ʏ��̋�K���m�F���Ă݂Ă͂������ł��傤���B
�@�Ȃ��A��ؒn�ɒ��ڔŖؓ��ĂĒ���Z�́A���݂���p����Ă��܂��B���̑�\�Ƃ�������̂�����F��(���E�V���t1935�`)�ł��B�M�҂�10�N�ȏ�O�ɓs���ŊJ�Â��ꂽ�u�V����܂�v�œV���t�ɂ���������Ƃ�����܂��B���͂��̏����O�ɁA�t�̎��`�w����͓V�ɏ��闳�ɂȂ�x���w�����邽�ߌ䎩��ɒ��ړd�b�������ɁA�߂������̂��ߏ㋞�����ƕ����ĉ��ɋ삯�����̂ł����B�V������͕M�҂̂��Ƃ������Ă����A���t�̋���ꖇ�����Ă�낤�Ɖ]���ĉ�����A�u���N�̓g���N������v�Ɗ��x���f��������n�߂܂����B�����Ȃ��܂�����ȋ�ؒn�ɔŖؓ������点��ƁA���錩�邤���ɕ\�ʂɂ́u���v�̎����A���ʂɂ͕M�҂̖�������グ���Ă����܂����B
���V���蒤���̖��Z�@�������ƒ���
�@����オ�����u�������v�̏�����@�@�@�A�u������v�H�̗�������@�@�@�@�@�@�@�@�B������̊��x��
�@
(���R��@�w�V���{�I�s�x1973�N���)�@�@(���w�Z�Ŏg���Ă���u�V���v�̋�)�@�@�@�@(�V���t�ɂ��)
�@���ݒ���̑�ƂƂ��Ė��������X�̂����O�������Ă����܂��B�V���Ƃ��̎��ӂł́A��ŋ���������F��(�V���t[�V])�A�������쎁(���V��t[�W])�̑��ɁA�͖�O��(���E���R�t[�X] 1936�`)���L���m���Ă��܂��B�܂��A����M���Y��(���E�G���t 1946�`)������̖����ł����A�ȑO���琷���ɏd�_��u���Đ��삳��Ă��܂��B
�@�ߔN�͓V���ł�������̒���H�l�������Ă��܂��B��������q�̂悤�ɁA����̍H���͌��݂ł���g�����~�Ƃ��������ŁA�ƂĂ��蒤��̋Z�ɒނ荇���Ƃ͂����Ȃ����z�ł��B���̔��ʁA����w�����闧�ꂩ�炷��A��g10���~���鉿�i�͒���̒l�i�Ƃ��Ă͍������ĂȂ��Ȃ��肪�o���Ȃ��̂��m���ł��B�ƊE�ł̋@�B����D�ʂ̌`���͗h�邬�Ȃ����̂�����܂��B���������̒��ŋߔN�ł́A�e�n�ŏ������̈��D�Ƃ̒�����ǎ��̒���𐧍삷���Ƃ���[�P�O]���o�ꂵ�A���̊��������ڂ����悤�ɂȂ�܂����B
4. ������Ɛ����̉��i�ɂ���
�@������E�����ɂȂ�Ɗ����܂łɗv���鎞�ԂƘJ�͂͂���əˑ�ƂȂ�܂��B
�@������̊T�v�ɂ��ẮA���̃R�����́u����1�v�̒�����ɂ��ďq�ׂ�������������x��������������Ǝv���܂�[�P�P]�B�\�ʂ��ؒn�̕�������(�K��)�Ŗ��߂����������ɑS�������ňꌩ�X�^���v��ł����A����ɂ��Ă����߂ɂ��Ă����ɍ����Z�p��K�v�Ƃ�����̂ł��B��ՂɃs�^���Ɩ������A���ۂ̑ǂɍœK�ł���Ƃ����]��������A���l�D�݂̂����Ƃ��]���Ă��܂��B���N�O�����ݏZ�̍��̘b�ł����A�L�i�҂̒m�l���爤�p�̒�����������Ă������������Ƃ�����܂����B���R���R�\�ܐ����l���̒�����ŁA�m�l�́u���̕ł��v�Ɖ]���Ă����܂������A�܂��������H�̎�ɂȂ錩���ȋ�ł����B���̌��R��̋�̏ꍇ�������ł����A�ǎ��Ȓ�����́A���������Ƀ��C�g�ĂĊg�勾�Ō��Ă������Ȍ�������ł��܂��A����̃��C��������߂đN���ɗ���Ă��܂��B�����ɂ��o��������܂����A����𐧍삷��ꍇ����̌㎽����O�ɓ_�����ďC���̂��ߓ�x���肷�邱�Ƃ�����܂��B����ł͊�����������x����ɂ��M�v�̗��ꂪ�ڗ����Ƃ͂���܂���B�Ƃ��낪�����ł͂��ꂪ���̂䂪�݂ɂȂ��Č���Ă��܂����Ƃ�����܂��B�ȑO���ł����b�ɂȂ������X�̕�������A�u�����͂��܂����������Ȃ��̂ň�ԓ���B�ł��Z�p�̍I�ق��͂�����o��̂���������B�v�Ƃ������b���f�������Ƃ�����܂��B�����ɔ�ׂ�Ɛ���ߒ��͒Z�����̂́A����߂č����Z�p���K�v�ł��邱�Ƃ��l����ƁA����̏ꍇ������t�̍H�������z�ɂȂ�͓̂��R�ł��傤�B
�@�����̏ꍇ�H���͍Œ��g10���~�ȏ�Ƃ����Ă��܂��B��ɁA��ʂ̏����t�@���ł�����������Γ���ł���悤�Ȑ����̉��i�́u20���~��O���v���炢�ł͂Ȃ����Əq�ׂ܂����B�������A����Ɏs�̉��i��24���A�d���������̔�����12���Ƃ����ꍇ�A��ؒn���ň���3���~�N���X���Ƃ��Ă���t�̍H����9���~�ŁA��ł����Œ��̍H����10���~�ɒB���܂���B�����炭���̏ꍇ�H������z������̂ŁA��t�������葱���Đ������ێ����邱�Ƃ͂���߂ē���ƌ��킴��܂���B�����炭�A�W���I�Ȑ����̉��i�͂���������������N��ɂȂ�͓̂��R���Ƃ������Ƃ������ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�Ƃ͂����A�C���^�[�l�b�g�̔�����Ă��鐷���̒��ɂ�20���~�����̉��i�̏��i�������܂��B���̂悤�ɔ�r�I�����Ȑ����̔������v���̈�ɁA�ߔN������Ƃ�����X���������A���������l�X�����D�Ƃ䂦�Ɏ荠�ȉ��i�ɐݒ肵�Ă���ꍇ�����邱�Ƃ��������܂��B�܂��A���X�����ʉ��i�ȂǂƖ��ł���10���~��Ő�����̔����Ă���P�[�X������悤�ł��B���X�ɂ�邱���������i�ݒ�͂ǂ����ĉ\�ɂȂ�̂ł��傤���B
�@�����܂ł������ɂ����܂��A��ɂ͕��ƕ����ɂ���Ĉ�����x�̃R�X�g���팸����\�����l�����܂��B����������̍H���ɂ́A����̍�ƒi�K���܂܂�Ă��܂��B���ݑ����̏�����H�[�ł͒�����@�B����ōs���Ă��܂��B�����ŁA�����̐���ɂ����āA����̍H�����@�B����ɂ��Ċȗ�������Έ�����x�R�X�g�̒ጸ���}���̂ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B�����߂Ɩ����̍H�����H�[�ŕ��Ƃ�������ł��R�X�g�̈��k���\�ƂȂ�Ǝv���܂��B�����čŌ�̍H��������t���S������A�����������ƕ����ɂ�舽����x�̉��i�ቺ���\�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����A���肵�₷�����i�̐����s��ɏo����Ă��闝�R����̂悤�ɐ������邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�����܂ł́AA�����N�̍�����ɂ��ďq�ׂĂ��܂����B����A�����N�Ƃ́A�蒤��̒���璤����A����Ɉ�ʂ̏����t�@��������ł��鉿�i�̐����܂ł��l���܂����B��܂��ȉ��i�тʼn]���A6�A7���~���x����20���~��̋�Y������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@����ȏ�̉��i�̋�́A�uS�����N�v(�ō�����)�Ɉʒu�Â�����킯�ł����A���̃����N�̋�́A�M�҂̊��o�ł́A�Ǘp�̋�Ƃ��������ӏܗp�̋�Ƃ����Ă悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��̎蒤���̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA��������C���^�[�l�b�g�Ō�������Ɛ��X�̃T�C�g������ۂ̖��H�ɂ����Ɖ��i�����邱�Ƃ��ł��܂��B�Ⴆ�A��̐R��ՓX�̂ق��A
�E���{�����A���f�W�^���V���b�v�@https://item.rakuten.co.jp/shogi/1708912/�@
�E�۔���ՓX�@http://www.maruhachigobanten.jp/shogi.html�@
�E�O���ՓX�@http://www.maezawa-goban.co.jp/koma/koma.html�@
�Ȃǂ�����܂��B�Q�l�܂łɌf���Ă��������Ǝv���܂��B
�@�Ō�ɕM�Ҏ��g�����삵�������ɂ��Ă����������G��Ă��������Ǝv���܂��B�M�҂���ŏ������n�߂Ă���20�N�ȏ�̍Ό����߂��܂����B�r�����琧��̒��S�́A�����Ɉڂ�悤�ɂȂ��Ă���܂��B���m�ȍ�ᐔ�ɂ��Ă͋L�^���̂��Ă��Ȃ��̂ł����A����܂Ő����𐔏\�g�͑������Ǝv���܂��B�����̏o���_�͂����܂ł���ŁA�Ǘp�̋�������ő���̂���{�ł����B���ꂪ�N���d�˂�ɂ�āA�����Ȃ�����X���琷���̐�������߂�ꂽ���Ƃ�����܂����B�����i�̔̔����i�ɂ��Ă͑S��������܂��A���삪S�����N�ɒB���邱�Ƃ͂��蓾�܂���̂ŁA���炭�ł������ȕ��ނ̐����Ƃ��Ĕ̔����ꂽ�̂��낤�ƍl���Ă��܂��B�����������グ��̂����A2�̍��̊������̎ʐ^������܂��̂ł����������B
���M�҂̎��쐷���
�@�䑠�����k�ށE���ہE�ъ�����(2010�N�O��ɐ���)�@�A�䑠�����k�ށE���ځE�ъ�����(2015�N����)
�@
�@�ǂ�����䑠�����k�ނ̋ъ��̐����ł����A�����ڂ̈�ۂ͂��Ȃ�قȂ�܂��B�����10�N�߂��O�ɐ��X�̕�����̈˗��ő�������ł��B�X��̕����Ⴂ������N�W���Ă���ꂽ�䑠�����k���ۂ̋�ؒn��C���ꂽ���̂ł����B����܂Ŗ��ڂł̐���͉��g����|���Ă��܂������A���ۂ̖ؒn�͍����Ȃ����A���肪���Ȃ����Ƃ���Ă����̂ŁA�ؒn��q���������Ɂu�������{���ɂł���̂��v�Ƌْ��������Ƃ������Ă��܂��B���̋���܂߂āA�����Ȃ���ʔ����͗l�̏o��ؒn(�Ք����ږ�)�ł̋����������Ƃ�����܂����B�����A���̃^�C�v�̑f�ނő�������́A�����i��Ղɕ��ׂ����͔������̂ł����A�ǂ����Ă���̖͗l���ڂɂ��Ă��܂��A���Ԃ��|���Ă�������ǂ���̂ɂ͂��܂�����Ă��Ȃ��ȁA�Ƃ����̂������Ȉ�ۂł����B���̈Ӗ�����]����͂�ǂɍœK�Ȃ͖̂��ڂ̋�̕����낤�Ǝv���܂��B�Ⴆ�ΉE��̋���̈��ł��B3�N�قǑO�ɁA���ڂ̖ؒn�Ɏ��̐��グ�����܂荂���������ƂȂ�����ۂɎd�グ�����Ƃ������Ă��܂��B�ǂ̍ۂɋÎ����Ă��Ă��ڂ̕��S�ɂȂ�Ȃ���Ǝv���Ă���̂ł����A�������ł��傤���B
[�P] �w�ߑ㏫���x���ɘA�ڂ���D�]�������R�����u��Ɩ�K�˂āv�̒��ɂ́A�u�@�B����͈�g���S�~�v�Ƃ����L�ڂ�����܂�(2000�N6�����f��)�B�M�҂́A���̋��z�͂����炭��������̏ꍇ�̍H���ł͂Ȃ����ƍl���܂����B
[�Q] �O�o�u��Ɩ�K�˂� 24 �ؒn�Ƌ�̒l�i�v(�w�ߑ㏫���x2000�N5�����f�ځ@135��) �Q�ƁB
[�S] ���R��l�u�}�C�y�[�X�̋�t������̓V�ꇁ�v(�w�������E�x1993�N12�����f�ځ@151�Łj�Q�ƁB
[�U] ����̈��D�Ƃ̊Ԃł́A�u�ꕐ�R�E��V��E�O�j�R�v�ƒ���̖��H���O�l���邱�Ƃ�����悤�ł��B��`�O�̐����͔N�㏇���������̂ł��B�j�R�t(���ˏ�ێ��@1922�`2001)�́A��l�ڂ̏���V��t����8�ΔN���ł����A����̋Z�͐�y��l�ɕC�G����Ɖ]��ꂽ���ł��B�j�R��̒���́A�Ջ�̊Ԃŕ]���������A�M�҂�30�N�قǑO�ɋ���̐��X�ŋ�����������A��g�\���~���鉿�i�Ŕ����Ă��܂����B����ł�����Ȃɍ����̂��A�Ƃ����̂����̎��̕M�҂̋U�炴��C�����ł������A�X�̕��͂�������������悤�ŁA�u�j�R����̂��͓̂V���̒���ł��Q���Ă��܂�����ˁv�Ɖ]���Ă����܂����B���̌�j�R�t�����E�����Ɠs���̐��X�Ōj�R��̎��������邱�Ƃ͏��Ȃ��Ȃ�܂����B�������M�҂̋�蓹�y�̔M�����܂�ɂ�A����Ɍj�R�t�̒���̌�������������悤�ɂȂ�܂����B���߂Č������̍��̌j�R��͌����č��������ł͂Ȃ������A�Ƃ������Ƃ��m�M�ł���悤�ɂȂ����̂ł��B�j�R�t��̒���̐}���́A�C���^�[�l�b�g�Ō������Ă��Ȃ��Ȃ������ł��Ȃ��悤�ł����A�ЂƂ���http://rupe.exblog.jp/22143081/ �̒��Ɍ��邱�Ƃ��ł��܂����B�S�̂�����̕��͂����������B
[�X] ���R��̏�����̐}���́Ahttp://www.maruhachigobanten.jp/shogi_k21.html
�������������B
���R�t�́A�R�`�ōH�[���������o�c��������d�j��(���E�����t1922�`88)�Ɏt�����A�O�\���߂��Ă����t�ɂȂ����x�炫�̐l�ł����A���̒���̋Z�͓V���Ō��ݍō���ƕ]������Ă��܂��B�ȑO�w�ߑ㏫���x�̎�ނɑ��āA���R�t�͊����ȋ���ڎw���p��������Ă��܂��B���̒��Œ��ڂ��ׂ��́A���Ďt�̑��������Ɋ��S�ɋψ�ȑ��肾�����Ƃ����̂ŁA�u�蒤��łȂ��@�B����ł͂Ȃ����v�Ɖ]��ꂱ�Ƃ��������A�Əq�����Ă��邱�Ƃł�(�u��Ɩ�K�˂� 9 �����ȐE�l�|�����߂āv�w�ߑ㏫���x1999�N1�����f��)�B�ߔN�w�������E�x�̎�ނɑ��ẮA�u�����������s���Ă���蒼�����ł��Ȃ�����⒤����̂ق�����i�Ƃ��ĉ��l������Ǝv���Ă��܂��v�ƌ���Ă����܂�(�w�������E�x2015�N6�����f��)�B
[�P�O] ���D�Ƃ̏�����肪����ɂȂ��Ă����̂͏��a50�N��ȍ~�̂��Ƃ������Ƃ����Ă��܂��B���݂͍���������ƂƂ��Ċ�������Ă���F��Ǒ�����ɂ́u��Â�����y���މ��v�����܂�A����s���i�W�J�ÂȂǂ������Ȃ��܂����B�����ɂȂ�Ƃ���Ɂu����������v���͂��߂Ƃ��āA�������̈��D�Ƃ̒c�̂������A�₪�ăA�}�`���A���D�Ƃ̎�ő���ꂽ��̒��ɁA���Ƃ̐����ɔ���悤�ȏo���h�����ƕ]��������i��������悤�ɂȂ�܂����B
[�P�P] ������̐���ߒ��ɂ��Ă͈ȉ��̎���������܂��B�������A���͌��݂��s�̂���Ă��܂��B���͂ǂ�����ڍׂ��q�ׂ����̂ł����A�c�O�Ȃ��獡�ł͓��荢��ł��B
�� ���R��l�w������̐��E�x(�����V���@2006�N) 26�27��
��
���������w��̂����₫�x(��o�ʼn�@1996�N)
86�ňȉ�
��
�L��P���E�͈�M�F�u��������@��13��@������̍����v(�w�ߑ㏫���x2007�N6�����f��)
��������̂������i���̂X�j
���X�x������̐����
�@�N�W�Ƃ̕��X�����߂�悤�Ȗ��H��̋�́A���̃R�����ň������Ƃ͓���Ƃ������R�ŁA�O�����A�ʊi�́u�ō�����(����)�v�Ƃ��āuS�����N�v�Ɉʒu�Â��܂����B�c�O�Ȃ���A��X��ʂ̏����t�@������������S�����N��̎�����ڂɂ���@��͑����Ȃ��̂����Ԃ��낤�Ǝv���܂��B�����ŁA�����S�����N�Ƃ͂����Ȃ���������܂��A����ɋ߂�������̎�������Љ�����Ǝv���܂��B
�@�ȑO����A�X�x������ɂ͍����ȋ�t�̕�������ꂽ��������g������炵���ƕ����Ă��܂����̂ŁA����������w�̂��߂ɔq���������Ǝv���Ă���܂����B�K���x������̓ޗlj����t�͂��炲�������A��N4���ɂ������̐�����q�����邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�����Ă�����������͑S����7�g����܂����B
�@
�����ÎR��@�ъ����@�@�A�{��������@�H�Ώ��@�@�B����������@������
�C ��|�|����@�������@�@�D��|�|����@���\��
�E ��c��M��@�������@�@�F��c��M��@�����q�������@�@
�@�ޗlj�����̂������ł́A�@�`�E�͂�����������̈����Ƃ̕��X������ꂽ���̂ŁA�F�͌��A�̓n�ӎO�Y��������̋�Ƃ������Ƃł����B
�@������N�W�Ƃ̕��X�̕]����ɂ͂����ւ������̂�����Ɖ]���Ă���܂��̂ŁA����獂���ȍ�҂̎�ɂȂ��ł��A�܂��܂��u����v�̐����ɂ͎����Ă��Ȃ��ƕ]����邩������܂���B�������M�҂̖ڂ��炷��A7�g�̋�͂ǂ�������ȋ�ł����B
�@�܂��A�ŏ��ɕM�҂̖ڂ��������̂́A�@�̐ÎR��ł��B�����̎ʐ^�������������B
�E�X�x������̐����@�@����ÎR��@(�E�͎��̎C�茸������̗������@�����E���n�E�Ƌ�)
�@�@�@
�@�u�ÎR�v�Ƃ́A���̃R�����̑�3��́u������̖��������v�̒��Ŏ��グ�����l��t�E����H�j��(1904�`91)�̂��Ƃł��B�ނ͋ߑ㏫�����҂̑�\�Ƃ�������L�����R(���Y�g�E�����Y�e�q)�̉��ŋ�����`���n�߁A���q���������ő��E���Ă���͖L���Ƃ̂��߂ɗ��R������ꂽ��葱���܂���[�P]�B�܂��A���u�V�ˋ�t�v�Ƃ��ċr���𗁂т��{�������Y��(���E�u�e���v)���Ⴍ���ĕa�̂��ߋ}���������ɂ��c���ꂽ�Ƒ��̗͂ɂȂ�܂����B
�@���̍��܂ł̐ÎR�́A���Â��ōT���߂Ȑl���������āu�m��l���m��e�̖��H�v�Ƃ����C���[�W���������悤�ł��B�������e���S����́u���㐏��̋��Ɓv�Ƃ����]������܂�A�v������̑ǂł��ÎR��g�p����邱�Ƃ������Ȃ�܂����B�������đ��l�҂Ƃ����悤�ɂȂ����ÎR�ł����A��^���ؒn�̍ގ��Ȃǂɂ��ẮA�e���̂悤�Ȃ��������������Ƃ͈�Ȃ��A�˗���̐��X�ɔC���A����ɉ������������Ă����悤�ł��B���̂��߁A�ÎR��̖ؒn�͌Ք���ۂȂǂ̍����ȍގ������ł͂Ȃ��A���ɂ͔ڌ�����̈����Ȗؒn�ő���ꂽ���̂�����܂����B
�@�X����̐ÎR������������u�ڌ�����̋�ؒn�̐ÎR��v�̈��������܂���B�ؒn�ɖ��ڍނ����ڂ������A���������Ȃ���������܂��B���N�̎g�p�̂��߂��ؒn�ɂ͑�����������A���グ�����ɂ����Ȃ�C�茸�������̂�����܂��B���ɗ��̎��͖w�ǒ����ߏ�Ԃɋ߂����̂�����܂����B��Ԃ��l������ƏN�W�Ƃ̌������ڂł͂��قǍ����]���Ƃ͂Ȃ�Ȃ���������܂��A�����I�ȉ��l�͍����Ǝv���܂��B�ÎR��̐����[�Q]�́A����܂Ő��X��W����Ŋԋ߂Ŕq���������̂́A����������g�p���w�ǖ��g�p�̂��̂ł����B����̂悤�ɉi�N���p���ꂽ��Ԃ̐ÎR��������̂͒������o���ł����B
�@������D�Ƃ̊Ԃł́A�{���e�����V�ˋ�t�Ƃ��čō��̕]�����邱�Ƃ������悤�ł����A��t�̊Ԃł͐ÎR�h����l�������Ƃ������Ă��܂��B������̓`�����p���ł������|�|���t(���ځE��|���o�j��)�́A���āw�ߑ㏫���x��[�R]�̃C���^���B���[�ɓ����āA���������̏���|�����ł����h����̂́u����ÎR�ł��v�A�u���̕��̐���グ�͈Ⴂ�܂��B�ꐶ����Ēǂ����邩�ǂ����B���ꂭ�炢�f���炵����t�ł��v�Ɩ������Ă����܂����B
�@���ɔ�����ƍ�����̐������������������B
�E�X�x������̐����@�A�F�{��������E���H�Ώ�(��)�@�@�B�F���䍁����E������(�E)
�@�@�@
�@����̇A�̋�́A�{���e�����̕v�l�E�o�����i���E�����t�j�̍�ł��B�e���ɂ��Ă͊��Ɂu����3�v�ŏЉ�܂������A1972�N�ɂ��܂�Ȃ���}�����A�₳�ꂽ�o���v�l�̑O�ɂ͉e�������O���ɎĂ�����̒�������������܂����B����ÎR���ȂǁA���͂̐l�X�̋��͂������āA�o�����́A���̌������E���̈�������w�͂ɓw�͂��d�˂āA���Ɂu�����v�̍��Ő����𐧍삷��悤�ɂȂ����Ƃ����Ă��܂�[�S]�B���̕H�Ώ��̋�����������ꓬ�̉ߒ��Ő��ݏo���ꂽ���̂�������܂���B����悭����ƁA���͔C���ɑ���ꂽ�悤�ȑf�p�Ȉ�ۂ��܂��B
�@������������̐����́A��ɏ����A���ɏ������������Ŏg�p�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B���̒��ɂ́A�������O��i���p�̋�Ƃ��Đ�厏�ŏЉ�ꂽ[�T]���������܂��B
�@�B�̋�̍�҂͍����t[�U](����d�j�� 1922�`88)�ł��B�V���ɐ��܂�A���X�����̖���Ƃ��Ēm���Ă��܂������A��ɐ�����ɏd�_��u���悤�ɂȂ�܂����B��R�\�ܐ����l�Ɛe�����A1982�N�Ɂu���������v�̖�����K�ɒ��邱�Ƃ�������A�V����̒n�ʂ̌���ɑ���̌��т��c���܂����B1984�N�ɂ͎R�`�s�Ɉڂ�A���ƕ����̍H�[�u�������v���\�������ȉc�Ƃɗ͂𒍂��܂������A�ɂ��������N��60�㔼�ŕa�v����܂����B
�@���̐����́A���̂ɍ����t���g�̏���p�������̂ł����A��Җ��Ɂu���������v�ƋL����Ă��邱�Ƃ���ӔN�̍�Ǝv���܂��B
[�Q] �Ȃ��A�ӔN�����̍��܂�Ƌ��ɐÎR��̋�ɂ͊��ł͂Ȃ����Ǝv������̂��o���悤�ɂȂ����Ƃ����Ă��܂��B�������M�҂ɂ͐ÎR��̐^��Ȃǂɂ��Ă��b�����邱�Ƃ͕s�\�ł��B�����A�����������Ǝv������������ꂽ���̐ÎR�t�̔������������`�����Ă��������Ǝv���܂��B�ÎR�t�́A�u��肽���l�͂�������ƁA�܂�ňӂɉ�Ȃ��悤�ł������v(�w��̂����₫�x62��)�Ƃ����܂��B
[�R] �w�ߑ㏫���x2006�N11�����f�ځu��������@��6��v���Q�Ƃ��܂����B
[�S] �����t�ɂ��ẮA�w�ߑ㏫���x1986�N9�����u��̑���W�v���́u�e���Ƌ��Ɂ@�{�������̊��v���Q�Ƃ��܂����B
[�T] �w�������E�x2000�N2�����f�ځE�u���ʊ��@������v���Q�Ƃ��܂����B
[�U] �����t�ɂ��ẮA�O�f�w�ߑ㏫���x�E�u��̑���W�v���́u�����̋�Əo����v���Q�Ƃ��܂����B
�E�X�x������̐����E��|�|����@�C�F������(��)�@�@�D�F���^��(�E)
�@�@�@
�@�C(����)�ƇD(�E��)�̋�͂�������|���t��̋�ł��B�u�|���v�́A�V�����O���s�ݏZ�̕��q���̋�t�A����̑�|���ܘY��(1914�`2006)�Ɠ��ڂ̓��o�j��(1944�`) �̍��ł��B����|���t����t�̓�����ݎn�߂��o�܂ɂ��ẮA���̃R�����́u���̂R�v�ł��ق�̏����G��܂����B��O����풆�ɂ�����8�N�ԕ����߁A�悤�₭�������Ė{�i�I�ɋ�肪�ł���Ǝv�����Ƃ��a20�N3���̓�����P�ł��ׂĂ������A�̋��̎O���ɑa�J�����ɂȂ��Ė{�i�I�ɋ�������悤�ɂȂ�܂����B��������̍��͐������Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA������7������ӂ�9���܂œ����A�������͈��7�g�������Ƃ������������ł��B�M�����Ȃ��d���ʂ̑����ɋ����L�҂ɁA����́A�u�����͋������������ˁB�������Ȃ���Ύq�ǂ������H�킹���Ȃ����낤���B�v�Ƃ��Ƃ��Ȃ��ɓ����Ă��܂��B����̎d�������Ĉ�������ڂ��₪�ē����̘V�܌�ՓX�ł̏C�Ƃ̌�A����p���Ō��݈��𑈂����l��t�Ƃ��Ċ��Ă����܂��B���NHK�e���r�́w���̚�x�ŏ��������W���ꂽ��ŁA�H���i���������p�̋�Ƃ��āA(�����炭���ڍ삩�Ǝv���܂���)�|����̔����������Љ��Ă��܂����B�F����̒��ɂ������ɂȂ������������Ǝv���܂��B
�@���āA�X�x������̓�g�̋�́A�����ł��傤���A����Ƃ����ڍ�ł��傤���B���q�����āA���̐���N��́A���Ȃ�ȑO�܂ők���悤�Ȉ�ۂ��܂����B�܂��A�ޗlj��t�͂���A���ꂽ���D�Ƃ̕��̂��Ƃ����f������ƁA�����̉\�����傫���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�����A���ڂ���҂ł���\�����\���l�����܂��B
�@�Ȃ��A�E��̋�̏��̂́u���\(���^)�v�Ƃ������Ȃ�Ɠ��̏��̂ł��B�N�W�Ƃ������Ƃ�����ɂ͂��Ȃ�l�C������̂ł����A�������w���l�ɂ͌h������邩������܂���B�Ƃ��낪�A�ޗlj��t�͂̂��b�ł́A����v�����m�̐搶���X����Ɏw���ɗ���ꂽ�ۂɁA�킴�킴���̋��I��Ŏw���ĉ������������ł��B�u���͓��N�搶�Ȃ�ł���B�v�ޗlj�����̂������͑S���\�z�O�̂����O�ł����B
�E�X�x������̐����E��c��M��@�E�F������(��)�@�@�F�F�����q������(�E)
�@�@�@
�@�E�E�F�̋�̍�҂͋��ɓV������M�t(��c���� 1947~)�ł��B��M�t�́A�C���^�[�l�b�g�Ɂu��t��M�̐��E�v�Ƃ����T�C�g(https://www2.hp-ez.com/hp/komashi-isshuu/page5)���J�݂���Ă��܂��B��M�t�͓V���ł��L���̋�t�ł����A2000�N��̏��ߍ���̐��E����6�N�قǗ���Ă��������ł��B���̌�J���o�b�N����A�ȑO�̂悤�Ɍ����ȋ�𑗂�o���Ă����܂��B�t�̋Z�@�ōł��悭�m���Ă���̂́A��̕\�ʂƗ��ʂ��P���悤�ɖ�����Ă��邱�Ƃł��B���̌����Ȏd�グ�́u���ʖ����v�ƌĂ���M�t�Ȃ�ł͂̎d�グ�ł��B
�@���āA�E�́u�����v�A�F�́u�����q�����v�Ƃ������ł��B���̂͂悭���Ă��܂����A�����ȈႢ������悤�ɂ������܂��B�ޗlj��t�͂̂��b���f��������ł́A��̐���N��́A�����Ƃ����Ȃ�ȑO�܂ők�邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����A�E�ƇF�Ƃł͋�ؒn�̌`�ɂ������ȈႢ���������邱�Ƃ���A�قȂ鎞���ɐ��삳�ꂽ�\��������悤�Ɏv���܂��B
�@�F�̋�͖ؒn�̖͗l�������Ă���A�t�͂̂��b�ł����i�I�ɍł�������Ƃ������Ƃł����B
�@�ȏ�A�X�x���Ŕq�������V�g�̐��������Љ���Ă��������܂����B�������w���̖T�炲���͂����������ޗlj��t�́A�ǒ��̎x��������̊F�l���ɐS��芴�Ӑ\���グ�܂��B
�@�@�����A�܂�����ɂ���ł��邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B�����ݏZ�̊F�l�Ŗ�����������̕��́A����HP�̌f���ɂ�������邱�Ƃ�S�҂��ɂ��Ă���܂�
��������̂������i����10�j
���鉺���O�O�x���̐����
�@�X�x������ɑ����āA����͕M�҂����ݏ�������鉺���O�O�x��[1]�����̒���������Љ���Ă������������Ǝv���܂��B���̋�͐����ł����A�ؒn�̍ގ����s�����Ȃ������N�̎g�p�Ōo�N���������A����N�W�Ƃ̕��X�����߂�悤�ȕ]���z�̍�����ł͂���܂���B�����A��̍�҂������炭�V���̖����ƌ����A���삳�ꂽ�̂�1960�N�ォ����ȑO�Ɛ��肳��邱�Ƃ���A�������̗��j���l�����ł����ւ�M�d�Ȏ����ƂȂ�̂ł͂Ȃ����ƍl���A�����Ă��̃y�[�W�Ŏ��グ�邱�Ƃɂ������܂����B
�@�܂���g40���̋�̐}���������������B
�@�@�@
�@�M�҂����̋�Əo������̂�2016�N�t�̂��Ƃł����B�x���̗��ɎQ�������Ƃ��A�����̕�����u�x���ɂ���ȌÂ������̂ł����A���Ă��炦�܂��v�Ƃ������b������A�����ÁX�Ŕq�����܂����B��́A�v���X�e�B�b�N��̔��Ɏ��߂��Ă���A�ꌩ����ƒ��N�̎g�p�Œ����������Ë�Ƃ�����ۂł����B�������A��K�ɂ������u���R�v�̖��ƎC�茸�蔍���ꂽ���グ�̎�����ڌ��āA�����̎����͋�ɓB�t���̏�ԂɂȂ��Ă��܂��܂����B�����āA�ǂ����Ă��̋�鉺���x���ɏ��������悤�ɂȂ����̂��A���̊Ԃ̎����Ƃ��m�肽���Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B
�@���̌�A�W�e�ʂ��炱�̋�Ɋւ��邨�b�����낢��Ƌ����Ă��������܂����B�������ɂ��āA���̋�鉺���O�O�x���Ɋ����悤�ɂȂ��������������Z�ɏq�ׂĂ݂����Ǝv���܂��B
�@���X���̐����́A�O�O�s�ݏZ�̈��鏫�����D�Ƃ̕��̏����i�ł����B���̕�������A����ƌĂ��Ă��������܂��BA����͎R�`���V���s�̂��o�g�ŁA���Ȃ�̏����t�@���������Ƃ������Ƃł��B���a40�N���A����Ƃ悭�������w���ꂽ���̒��ɓ����O�O��w�̊w���Ō�Ɍ����ŋ��������ꂽB�搶�����܂����BB�搶�̂��b�ł́A�u�����Ƃ̑ǂł����̋�悭�p�����Ă����B���̍������Ȃ�g�����܂�Ă�����Ƃ����L��������v�Ƃ������Ƃł����̂ŁA���̋�͏��Ȃ��Ƃ������I�ȏ�O�ɑ���ꂽ��ł��邱�Ƃ͊m�����낤�Ǝv���܂��B���̌㎞�͗���A���N�O�Ɉ����Ƃ�����A�������������܂����B�����āA���Ƒ�����u�₳�ꂽ��������D���̐l�����̖��ɗ��ĂĂق����v�Ƃ������k����B�搶���͂��߂Ƃ���W�̕��X�́A���̂��ӌ��������߂ɓ����s���ŏ�������̎t�͂����Ă����O�Y�s����(�������l�E����)�ɂ��̋��������ƍl���A�O�Y��������̋������邱�Ƃɂ��܂����B���̌�O�Y����́A�鉺���x���Ŏt�͂ƂȂ�A����ɔ����A���̋���鉺���x���̏�����ɂȂ���������
�T�˂��̂悤�Ȍo�܂��낤�Ǝv���܂��B
�@���āA����ώ@����Ƃ��������������邱�Ƃ�������܂��B���̂�����Ȃ��̂��������
�@�@�@(1) �����ł��邪�A���Ȃ葽�N�ɂ킽��g�p�Ő���̎��͎C�茸���Ĕ����ꂽ�ӏ��������B
�@�@�@(2) �傫���́A�ǂ̎�ނ̋����ʂ̋��������ȏ㏬���������ؒn���p�����Ă���B
�@�@�@(3) �ؒn�͂����炭�䑠���Y�̖{���k�����A�Ք��E�E���ۂȂnj��݂͒�������ɗ��p�����M�d�ȑf�ނ�p����������锼�ʁA�ڍނ��p�����Ă���A���Ȃ�s�����ł���B
�@�@�@(4) �o�ʂŁA�ʏ��̈���̋�K�Ɂu���R�v�Ƃ�����Җ�������B
�@�@�@(5) ���̂ɂ��Ă͋�K�ɋL����Ă��Ȃ����u����ъ�(������)�v�Ƃ������̂ɗގ����Ă���B
�������Ƌ⏫(�s�����̖ؒn�ƎC�茸�襔����ꂽ���ɒ���)�@�@�@���ʏ��̋�K
�@�@�@ �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@
�@�E����̖������R�͔����I�O�ɐ������Ă���
�@�ŏ��ɋ�̍�҂ɂ��Ďv���Ƃ�����q�ׂĂ݂����Ǝv���܂��B�u���R�v�̍�������t�͎O�l���܂�[2]�B�O�l�Ƃ������炭�V���ŋ�������V�܁E�������X(��̕���������)�Ɖ��̐[����t�ŁA����܂ł��̃y�[�W�ł��q�ׂĂ��܂������A�����Ƃ̎�ˉi�O���E�����̕��q��l�ƒ����Ƃ̐X�R�c�O���ł��B���̒��Œ�����ꂽ���͐X�R�c�O�������ł��B�����炭���̕��R��̋�̍�҂��X�R�c�O�����Ƃ������Ƃ͊m���ł��傤�B
�@�X�R���́A���a�̎���Ɏ蒤��̋���Œm��ꂽ���ł���[3]�B���̒���̋Z�́A������̖��H�����̒��ɂ����̂���{�ɂ����҂������Ɠ`������قǂ̖����ł����B�������A�����̓V���̋�E�l�����́A��O�����̋��𐔂ł��Ȃ����Ƃ����߂��Ă��܂����B���R���̒�����A���̑唼��ꠂȂǂ̈����Ȗؒn�ɗ����̂Œ���ꂽ���̂ł����B����NHK�́u�V���{�I�s�v�́A�X�R��������������Ă��Ȃ�������\�����ؒn�ɒ��ɒ������ĂđN�₩�ɒ���o���u��������v���s����ʂ��L�^���Ă��܂��B��������͑씲�����E�l�Z�ł����A��������ɑ����̂�����o�邱�Ƃ͔������܂���B�܂��A�ؒn���̂��̂��i�^�Ő�o���ꂽ���̂������̂ŁA�傫�����K�������ψ�ł͂���܂���ł����B���\�N�ɂ킽���ęˑ�Ȑ�����ꂽ���R��̒����̒��ŁA�t�̎����̋Z��]���Ƃ���Ȃ��������������ȍ��͂����͂��ł������Ǝv���܂��B����䂦�ɂ����A���k�ɑ���ꂽ�����Ȃ����R��́A�N�W�Ɛ����́u����v�Ɖ]���Ă悩�낤�Ǝv���܂��B
�@�����āA�M�҂��ŏ��ɂ��̋���������ɐS�̒��ɕ����̂́A�u�����s����̖��l�E���R�t�������I�ȏ�O�ɐ������Ă����Ƃ́c�B�v�Ƃ������Q�̎v���ł����B
�@���ł����V���͍����Ȑ����Œm���Ă��܂����A�s�풼��̍��͓����̋�t�����鍂����Ƃ͊i�i�̍�������܂����B1951�N�ɓV���ŏ��߂ă^�C�g����(������)���s��ꂽ���A�n���̋�t�����삵���������g���Ăق����Ƃ̐\���o����Î҂�A������S������ɂ���Ȃ������̂͂悭�m��ꂽ�b�ł��B�悤�₭1980�N�̉�����ŁA1���ڂ����ł������A�V���̋�t�E�ɓ��F�����i���E�v���j����̐����^�C�g����ɗp������悤�ɂȂ�܂����B���̊�30�N�߂��A�V���̋�t�����͋��J���˂ɂ��ēw�͂ɓw�͂��d�˂Ă����Ƒz������܂��B�v���t�͌��X����̐E�l�������l�ł����A����̐E�l�̒��ɂ��������Ă����l�����܂����B���Đ�厏�w�ߑ㏫���x�ɘA�ڂ��ꂽ�u��������v�Ƃ����R�����̒��ŁA��������Ƃ̉L��P�����́A�u����̓V��v�̖��Œm���鍲���Î���1960�N�㏉�߂ɐ����𐧍삵�����Ƃ��q�ׂĂ����܂�[4]�B���̂Ƃ��w�ߑ㏫���x���Ɍf�ڂ��ꂽ�ʐ^������ƁA�V��t�������ɂ����Ă����Q�̋Z�p�������Ă������Ƃ�������܂��B�R�����͂���ɑ����āA�V��ƕ��я̂���镐�R�ɂ������̍�Ⴊ���������Ƃ��q�ׂĂ��܂��B�����c�O�Ȃ���A���̕��R��̐����ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������ɂ��Ă͑S���ӂ���Ă��܂���B�������́u���R��̐����v���Ⴆ�Α����p�̋�ł������Ƃ���A���ׂĂ̋�ɍE���ۂ�Ք��̖ؒn�������Ďg���Ă��������Ȗ�������̂�������܂���B�����A���܉�X�̖ڂ̑O�ɂ���Ë�͖ؒn�̍ގ������Ȃ�s�����Ȃ̂ŁA�����炭�������������p�̍ō���������\���͍����͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�@����Ȃ��Ƃ��z�����Ȃ��炱�̋�߂�̂��y�������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�E��̏��̂Ɋւ��邱��
�@���ɋ�̏��̂ɂ����ڂ��Ă݂����Ǝv���܂��B�ʏ��̋�K�ɂ͏��̖��͂���܂��A����ꍁ���u�ъ��v�̖��ő����Ĕ���o�����n�쏑�́A���݂́u����ъ��v�����́u�����ցv�ƌĂ�Ă��鏑�̂̂悤�Ɍ����܂��i���̏��̂ɂ��Ắu����5�@������̏��̂ɂ����v�������������B�u����ъ��v�Ɓu�����ցv�̊W�ɂ��Ă͏���������悤�ł�[5]�j�B�����炭����̑n�쏑�̂��V���̋�ɗp������悤�ɂȂ������ƌ��Ă悩�낤�Ǝv���܂��B
�@�吳�̏��ߍ��V���̋�����Ƃ̕������O�Y�Ƃ����l���㋞������̍H�[�ŏC�Ƃ����āA�����ɓ�����̐���Z�p��`���܂����B�����炭����̋Z�p�Ƌ��Ɏ��O�Y����V���̋�t�����Ɏp���ꂽ���̂ɁA���̉���ъ��̏��̂��������̂��낤�Ǝv���܂��B���R���̒���̂����ō����́u�����v�̋�́A���̉���ъ��Ȃ��������ɔ��ɂ悭���Ă��܂��B
�@���͂��̕��R���̌Ë�̏Љ�́A��N�H�����炸���ƍl���Ă����e�[�}�ł����B�����čl������̓I�ɂ܂Ƃ܂��čs���ɂ�āA�����ł��A���́u����ъ��v�����́u�����ցv�̏��̂Ő������Ă݂悤�Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B����ꍁ�̋ъ���́A�ʐ^�ł����ӏ܂������Ƃ�����܂��A�����Ղ�Ǝ����g���Đ��グ�Ă���Ƃ�����ۂ�����܂����̂ŁA���������i�̍�������߂Ɏ����g���Ă݂܂����B�Ƃ��낪�����̌������X�ł͎��̐��グ�͓�����Ȃ��킵�܂������A�捠�悤�₭�t�̖K��ƂƂ��Ɋ������邱�Ƃ��ł��܂����B�������A�����ɂ����R��̌Ë�ɂ��S���y�ʐق������ł����A������̕�������ˊ肦��K���ł��B
�@�@�@
[1] �鉺���O�O�x���́A���ݍO�O�s�ɂ���B��̓��{�����A���x���ł��B���̊����Ȃǂɂ��ẮA�u�����A�鉺���x����HP�v(URL�chttps://sites.google.com/site/xihongjiangqidaochang/home)�������������B
�@�x���ł͖��T�y�j��16������́u���v�̂ق��A���T���j��18������́u�����̏W���v�A���T���j���Ɛ��j����16�`18���ɂ́u�q����������v���s���Ă��܂��B���͎�ɍO�O�s�����́u�߂�[������v�l�����肵�Ă���܂��B�O�O�s�y�ыߍx�̕��X�ŏ����ɊS���������̕��́A�������Ō��\�ł��̂ŁA���C�y�ɂ����ł��������B�܂��A�x���̌m�Âł́A�{�i�I�ǂ̕��͋C����������悤�ɁA�ꕔ�{�Ђ̔ՂƖ{���k�̋��p���Ă����������Ƃ��ł��܂��B
�@�Ȃ��A�֑��ł����A�x���̏�����̂���6�g�́A�x������̈˗��ɂ��M�҂����삵���䑠�����k�̒���ł��B�u�鉺���O�O�x���^�x������̓Ƃ茾�H�v�Ƃ����u���O�ɂ́A��̐}�����Љ��Ă���܂��̂ŁA���Η�����������K���ł��B(http://reirou777.seesaa.net/article/444749412.html�ق�)
[2] �{��וv�u�V��������Y�n�̕ώ��v(�w���m�����w������ 41 �Љ�Ȋw�ҁx1992�N)13�`14�ŁB
�@�O�l�̢���R��̂������݂���������Ă��鏑���t����ڕ��R��̎�˔����́A�V���̕����������̢�����m��ł��B�܂��A���Ɍ̐l�ƂȂ��Ă��钤��t�u���R�v�̐X�R�c�O�����ANHK��V���{�I�s��̒��ŁA��������������������̑O�g�ł��颕������X��ɔ[�߂�p���L�^����Ă��܂����B�����̂��Ƃ���A�����炭�O�l�́u���R�v�t�́A�������X(��̉�����)�ƌq����̐[���E�l�ŁA����̂Ɂu���R�v�Ƃ������𖼏���Ă���Ǝv����̂ł����A�������ł��傤���B
[4] �L��P���E�͈�M�F�u��������@��21���@�V���̋�t�E�V���v(�w�ߑ㏫���x2008�N2�����f��)���Q�Ƃ��܂����B�����ɂ́A����V��t(�����Î�)��̓�g�̐����̐}�����f�ڂ���Ă��܂��B��g�͏���V��t�̃I���W�i������(��V���ۣ)��1964�N���ɓ����I�����s�b�N�̋L�O�i�Ƃ��ăA�����J��g�قɑ��悳�ꂽ�F�����k�����B������͓V�������̂�1967�N�����삳�ꂽ�Ǝv����F�����k�����ł��B���Ƃ��e����ÎR��̖���ɕC�G����قǂ̏o���h���Ɏv����̂ł����A�c�O�Ȃ��炻��ɑ��������]���鎖�͂ł��܂���ł����B����V��t��41���̑g��삩�������ɐ�ւ��A��N���74�N�ɋ}�����ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�����ł��̐������U�Ō�̍�i�̉\��������Ə�����Ă���܂��B
[5] �u��������@��5��v(�w�ߑ㏫���x2006�N10�����f��)�ɂ͉���ъ��Ə����ւ̊W�ɂ��ċ����[���L��������܂��B�����ł́A����|���̑�|���ܘY�����A���N����ɉ���ꍁ�̍H�[�ŋ�E�l�����Ă��������������̏��̂̎��ꎆ����������v���o������Ă����܂��B�������͂��̎��u����͈�ʂɏ����ւƂ��č���Ă��邪�A�������{���̖��O���B�v�ƌ����Ă��������ł��B���̌�A���ܘY���͒|���쏸���̒��𐧍삵�Ă��܂��B�M�҂̎茳�ɂ͂��āw�������E�x(1984�N5����)�Ɍf�ڂ���Ă�������Ջ�X�̍L���ʐ^�̂Ȃ��̢�|���쏸������̒���̐}��������܂��B���̐}���͑N���Ȃ��̂ł͂���܂��A��ʂɁu����ъ��v�̖��ŌĂ�鏑�̂Ƃ͑S���قȂ���̂ŁA�u���F�v�̏��̂ɔ��ɂ悭���Ă��܂��B
�E�L���Ɍf�ڂ��ꂽ�u�|���쏸�����v�̋�̐}��
�@�@�@
�@���̐}������A���ď��N����̒|���t����������u�����ւ܂��͏����̎��ꎆ�v�͎��͟��F���̎��ꎆ�������Ɛ�������̂͂�����邩������܂���B�������A�t�ɉ���ъ��C�R�[�������ւƑ��f���邱�Ƃɂ����ۂ��ׂ����̂�����Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���܂��B
�@�Ȃ��A���݂̓��ڒ|���t(��|���o�j��)���u�������v�̋�𐧍삵�Ă����܂��B�������A�C���^�[�l�b�g�Ŕq���������A���̋�̏��̂͟��F�̏��̂ł͂Ȃ��A���炩�ɉ���ъ��Ɠ������̂ł� (����URL������������) �BURL�chttps://item.rakuten.co.jp/shogi/380055/�@
��������̂������@�ԊO�҂P�F�������Ƒ叫���̋�ɂ���
�@���ߍ�����u������̕]���v���e�[�}�Ɏ��ێs�̂���Ă���l�X�ȏ�����̉��i�𒆐S�ɏq�ׂĂ݂����ƍl���Ă��܂����B�����A���y��獂����܂ŏ�����̒l�i�Ɋւ�����͂��܂�ɂ��ˑ�ŁA���ׂ�Β��ׂ�قǁA���Љ�邽�߂̎�̑I���͂��Ȃ����A�扄��������Ȃ��Ȃ�܂����B�ߓ����ɂ����������ł���܂��̂ŁA�����炭���҂����������B
�@�����ŏ����e�[�}��ς��āA�ԊO���Ƃ��āA���j�㌻��ꂽ��^�����ނƂ��̋��ɂ��ďq�ׂĂ݂����Ǝv���܂��B�����Ƃ����Q�[���́A��������N�O�̕����������ɂ͊��ɗV��Ă������Ƃ��������Ă��܂��B���̗��j���������߂Ă݂�ƁA���ݎ��������y����ł����40���̏����̑��ɂ��A�l�X�Ȏ�ނ̏����ނ����������Ƃ��m���Ă��܂��B����́A�����̏����ނ̋���Љ�Ă��������Ǝv���܂��B
1�D���^�����Ƒ�^����
�@�䂪���ŏ����Ƃ����Q�[������������V��Ă������ɂ��Ă͖��m�ł͂���܂��A�x���Ƃ�11���I�̔��A��������̌���ɏ������������Ă������Ƃ́A������̋L�q����������j���̏o�y������m���ł��B
�@�����ł́A11���I�㔼�Ƃ����w�V���y�L�x�Ƃ��������̒��ɁA�a�̂≹�y�ȂǗl�X�̌|�\����ɏG�ł��l�����u�͌�v�u�����v�Ȃǂɂ��D��Ă��邱�Ƃ��L����Ă��܂��B�����c�O�Ȃ��ƂɁA���́u�����v�������Ȃ�Q�[�����������͈�؋L����Ă��܂���B
�@�����j���̍ŌÂ̎���Ƃ��ẮA1992�N�x���������Ŕ��@���ꂽ15���̏����o�y��������܂��B�ꏏ�ɓV��Z�N(1058�N)�ƋL���ꂽ�؊Ȃ��o�y���Ă��邱�Ƃ���A��̔N��͂قڊm�肵�Ă��܂��B�u��������̂�����@����1�v����������������A�������̏o�y��ɂ́A�u�ʏ��E�����E�⏫�E�j�n�E�����v�̂T��̋�m�F�ł��܂��B�قړ����ォ������̎���ƍl�������������̈�Ղ���́u�����v�̋���o�y���Ă��܂��̂ŁA������܂߂ē����̏����ɂ��ʁE���E��E�j�E���E���U��̋���������Ƃ͊m���ł��B�������A���݂̏����ɂ���u��ԁE�p�s�v�̋�͑S���o�y���Ă���܂���B��������A
�@�@(1) 11�E12���I���̏����ɂ͔�ԁE�p�s�͑��݂��Ȃ�����
�Ƃ����z��͑����̉\���������Ă���Ƃ�����ł��傤�B
�@�܂����̌㌻�s�����ɂ͊܂܂�Ȃ��u���v�u�����v�Ƃ���2��ނ̋�o�y���Ă��܂��B�����̏����ɂ͂����̋����܂܂�Ă����̂�������܂���B�����A����2��́A��Ɂu��^�����̋�v�Ɋ܂܂�Ă��܂��B�����ʼn\���Ƃ��āA(1)�̏��^�����Ƃ͕ʂ�
�@�@(2) ���炩�̑�^�������V��Ă���
�Ƒz�肷�邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@����12���I�̍���b�̓�������(1120�`56)�́A���L�w��L�x�̒��ŁA������c�̌�O�Łu�叫�����w���Ď������������v�ƋL���Ă��܂��B���̋L���́A���(2)�̑z��𗠕t������̂��ƌ����č����x���Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�܂��A12���I�ɏ����ꂽ��̏��������Ɋ��q���ɕҎ[���ꂽ�w���x�Ƃ�������������܂����A���̒��ɂ����^�Ƒ�^�̓��ނ́u�����v���Љ��Ă��܂��B12���I�Ƃ����Ε��������ł�����A���̏��ɋL���ꂽ�������u���������v�u�����叫���v�ƌĂ�邱�Ƃ�����܂��B�w���x�̊Y�������́A���N�O�ɍ����������قŊJ�Â��ꂽ�u�����ނ����ނ����W�v�œW������Ă��܂����̂ŁA������������������B
�@���w���x�u�����v
�@�@
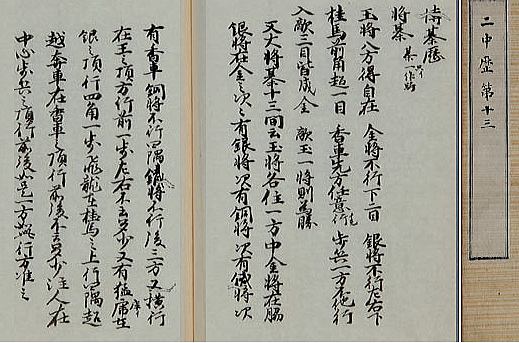
�@�����ł́A�u�����v�Ƃ͋ʁE���E��E�j�E���E����6��ނ̋��p����Q�[���ł��邱�Ƃ���������Ă��܂��B6��ނ̋�̓����͌���̏����ƑS�������ł��B�܂��A�G�w�Ɏ�����ɏ��i����(����)�̂�����Ɠ����ł��B
�@�����A�傫�ȈႢ������܂��B
�@�@(1) ��ԂƊp�s�̋L�ڂ��Ȃ��B��Ԋp�s�Ƃ������̂Ȃ������������\�����傫���B
�@�@(2) ����̎O�i�ڂ���G�w�Ƃ��Ă���ƌ����A�����͓�i�ڂł͂Ȃ��O�i�ڂɕ���ł����Ɛ����ł���B
�@�@(3) �Ō�̌��́u�G�̋�ʈꖇ�ɂȂ�Ώ����ɂȂ��v�Ƃ����Ӗ��Ǝv����B��������Ďg�p���郋�[���ł���A���̂悤�ȏ܂őǂ��������Ƃ͂Ȃ��B
�@�@�@�]���Č���Ƃ͈قȂ�A�ߊl�����G�̋���g�p���Ȃ��u��̂ă��[���v�̏����������\�����傫���B
�@���D���̕M�҂́A�\���N�O�ɁA����̑f�ނŁu�����v�̋�����A�J�n�ǖʂ̋�̔z�u�����Ă݂܂����B���̓�̐}�̂����A���Ắu��������̏����v�Ƃ��ĉE�̐}���f�����邱�Ƃ����������悤�ł����A�w���x�̋L�q�ɏ]�����̔z�u�̕����������ƍl���ėǂ��ł��傤�B
�@���w���x�̏��^�́u�����v�@���^�z�u�̍Č�
�@�@�@�@ �@
�@
�@�w���x�ł́A���Ɂu�叫���v�Ƃ�����^�̏������Љ��Ă��܂��B
�@���������犙�q���ɂ����Ă��̂悤�ȑ�^�������������Ă������Ƃ�������܂��B���c�ꋞ�����́A��̓�����������O�Ŏw�����̂����̃^�C�v�̑叫���������ƍl���Ă��܂����A�m���ł͂���܂���B�w���x�̕��ʂ���ɂ���ƁA�叫���́A13�~13�̔Ֆʂ�p���鏫���ŁA��ԉ��i�������E�S���������A��i�ڂɂ��z�ԁE�E�ҌՁE���s���z�u����܂��B�O�i�ڂ̕����̗�̒����̏�ɂ����l�̋����܂��B��݂͌���34�������v68���̏����ł��B�����A���̑叫���ɂ���ԂƊp�s�͓o�ꂵ�Ă��Ȃ����Ƃ͒��ڂ��ׂ��ł��傤�B
�@���̎ʐ^�́A�����悤�ɕM�҂�����̑f�ނő������u�叫���v�̋�Ƃ��̊J�n�ǖʐ}�ł��B
�@���w���x�́u�叫���v�@���^�z�u�̍Č� �@
�@�@�@�@
2�D�叫�����璆������
�@���̌㊙�q����̎��@�W�̕����ɂ������Ɍ��y�����L�q������܂��B���ɁA���q���13���I���̕����w���ʏ����W�x�Ƃ��������ɂ́A�叫���ɂ��Ĉȉ��̂悤�ȋL�q������܂��B
�@�u�叫��@���ҁ@�X�X�X�X�@�@���ԍ��ԔV�j�����@�ރ\�P�e��ԃ��@���惊���c�@���l�p���V���n�X�������@���j�n���x���v
�@���̋L���ɓo�ꂷ��叫���̋�́u�����v�u�����v�u����v�u���l�v�u�p���v�u�j�n�v��6��ނł��B�w���x�̑叫���Ɣ�r����ƁA���Ԃ͖z�ԁA���l�͒��l�������������\��������̂ŗǂ��Ƃ��Ă��A��Ԃ��p���͑S���V���ȋ�ł��邱�Ƃ͖��m�ł��B��������w���x�叫���ɑ���V�^�̑叫�����o�ꂵ���\����ǂݎ�邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̐V�^�叫���������Ȃ���̂��͖��m�ł͂���܂���B�����A�퍑����ȍ~�ɂȂ�ƁA���6��ނ̋��S�Ĕ������u�叫���v�����������݂��Ă������Ƃ͒m���Ă��܂��B���̂Ȃ��ōł���̏��Ȃ��̂��A�݂���65�����A���v130���̑叫��(��ۋY)�ł��B���̐}��16���I���ɕM�ʂ��ꂽ�叫��(��ۋY)�̏��^�z�u�̐}�ʂł��B�Ֆʂ�15�~15�A��̎�ނ�29��ށA�G�w(�����炭�ܒi��)�ɓ��������ɁA���i��������܂��B���Ɂu�����v���G�w�ɓ���Ƌʏ��Ɠ�����E�u���q�v�ɐ���A���l���Q�������ƂȂ�܂��B���̋130���̑叫�����w���ʏ����W�x�̑叫���ł��邩�ǂ����͕�����܂��A���̂悤�ȑ�^���������q����ɐ������Ă����Ƃ�������ׂ����Ƃł��B
�@���130���́u�叫��(��ۋY)�v�@���^�z�u�@�i�����������ɂ���j
�@�@�@�@
�@�������A�����ނ������A�]��ɂ�����ł��邱�Ƃ��l����ƁA��͂�130���̑叫�����Q�[���Ƃ��Ď��ۂɗ��s�������Ԃ͂���قǒ����͂Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ŔՖʂ���������������炵�ėV�т₷�������V�^�̑�^�������l������悤�ɂȂ����̂��Ǝv���܂��B���ꂪ12�~12�̔Ֆʂɋ92���ŗV�ԁu�������v�ł����B��������14���I���̕����ɂ��̖����L����A15���I�ɂ͌��Ƃ═�Ƃ̊Ԃł��Ȃ�L�����y���A���Ɍ��Ƃ̊Ԃł�16���I�ɂ����ď��^�̏�����������ɋ������Ă����ƍl�����Ă��܂��B�]�ˎ���ɓ���A���s�̋40���������嗬�s����悤�ɂȂ�ƁA�嗬����͊O�ꏭ�������ނ��Ă����܂����A����ł��]�ˌ���ɂ����Ȃ葽���̐l�X�̊Ԃŋ������Ă��܂����B
�@�ȉ��ɐ����������̕M�ʂ���������(���ۋY)�̏��^�z�u���f���܂��̂ł����������B
�@���92���́u������(���ۋY)�v�@���^�z�u�@�i�����������ɂ��j
�@�@�@
�@�������́A��̎�ނ�21�Ƒ叫���ɔ�ׂ��Ȃ菭�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����A�����ȊO��17��ނ̋�̐��l�����ꂼ��قȂ��Ă��āA�叫�������͂邩�ɖʔ����Q�[���������Ǝv���܂��B���ۂɍ]�ˊ��ȍ~�ɒ������̑NJ������₳��Ă��܂����A�萔��300���400��ȏ�ɋy�Ԃ��̂��������悤�ł��B�i�M�҂�30�N�قǑO�ɗF�l�ƒ��������w�����o��������܂����A���Ȃ葁�w���̂��肾�����̂ł����I�ǂ܂ł�2���Ԃقǂ�����A���Ă��܂������Ƃ��L�����Ă��܂��B�j
�@�������̎w�����ɂ��ċ����̂�����́A�u���{�������A���v�̒��́u�������u���v����������������A�Ǝv���܂��B
(http://www.chushogi-renmei.com/kouza/kouza_main.htm) �܂��A�������A���̃T�C�g�ɂ́u�R�����v�̒��Œ������ȊO�̑叫���ނɂ��Ă��T��������܂��B
3�D��������Ƒ叫����
�@�������́A�����ȍ~����ɋ���_�n���Łu�����Ə����v�Ƃ��ėV��Ă���A���̑�R�N���\�ܖ��l(1923�`92)���A�C�ƒ��ɒ������ɂ��Ȃ�v���������������������Ƃ��m���Ă��܂��B���̌���ꕔ�̈��D�Ƃ̊Ԃŋ������Ă��܂������A�قƂ�ǖY�ꋎ��ꂽ�Q�[���ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B���̏�ɂ��ݒ������ɐe���ޏ����t�@���������ł����₻���ƍl�����̂���R���l�ł����B���̖��l�̃A�C�f�B�A�ɋ��͂����̂��s���̔Ջ���X�E�����h���X�ł��B���������Ջ�̐������i�߂��A���Ɂu�������Ջ�Z�b�g�v���s�̂����Ɏ���܂����B
�@���͂��߂Ďs�̂��ꂽ���y�i�̒������Ջ�Z�b�g�i1987�N���w���������́@��̓v���X�e�B�b�N�j
�@�����ł܂��܂��A���ƒ�������Ɋւ���̘b��������ĉ������B
�@�M�҂��������̃Z�b�g���w�������̂͏��a���㖖���̂��ƂŁA�s���_�ے��̉���J���^�X�Ŕ����܂����B��̓v���X�e�B�b�N�ŔՂƂ̃Z�b�g���i��\6000�~�������ƋL�����Ă��܂��B���X�̘b�ł́A�u�ȑO�̓V�����c�Q�̒����������\25,000�~�Ŕ����Ă�������ǂ��A����̐E�l�������̂��������Č��݂͓��ׂ��]�߂Ȃ��v�Ƃ������b�ł����B�����Ńv��������̂ł����A�����̓c�Q�̒����������ɓ��ꂽ���Ǝv���܂����B
�@�@�@�@
�@���ꂩ�琔�N���o�������̎���ɂȂ��āA�B��̒�������̐����̔��X�E�����h���X��K�˂�ƁA�����V�����c�Q�̒����������̔����Ă���Ƃ̂��b�������̂ŁA�����������邱�Ƃɂ��܂����B�w���������̒������̋�߂Ă��炭�͉x�ɓ����Ă����̂ł����A���傤�ǂ��̍��A�������̎�ɂ͂܂荞�ݐF�X�ȏ��̂̋�̐�������Ă����M�҂́A���̈���ŁA��x�͋92���̒������̋�������ő����Ă݂����Ƃ��l����悤�ɂȂ�܂����B
�@�������A�����n�߂Ă݂�ƁA�]�����������93���̋�ؒn����ނ��Ƃɑ�����̂͂Ȃ��Ȃ�����A���̉�ɂ������������ĔЕz���Ă��������A�Ջ���X����Z�ʂ��Ă�������肵�܂����B�܂���̑������������S�I�ɑ���̂́A���S���傫���̂Œʏ��40��������T�牽���������삷��A�Ƃ����u�Ȃ������v�̎�@���̂��đ����Ă݂܂����B���N�����s����̂̂��A�悤�₭�����͂܂��Ȓ������̋�ł���悤�ɂȂ�܂����B���̇@�̉摜��2002�N���ɐ��삵�����̂ŁA���ʂ���h��ɂ����������̒����ł��B��̑f�ނ̓V�����c�Q�ŁA���͍̂����h���X���̋�̏��̂����肵�܂����B���̎�h��͈˗���̂��ӌ��ł����A��F�̖{���̏ꍇ�͈�����͗ʂɌ�����̂ŁA���\���ɐl�H�̃J�V���[�h�����g�p���邱�ƂɂȂ�܂����B�@
�@���@�������̒���i2002�N�����삵�����́@���F�\�ʂ̏��^�z�u�@�E�F�Ֆʍ����̗��ʁj
�@�@�@
�@�܂��A�A�̉摜�͓������ɑ������������̒�����ł��B������̕��́A�{���ɓu�̕����������T�r�������x�����߂đ��������̂ł��B�������̕��y�̂��߂ɏo�ł��ꂽ�������̓��发�w�͂��߂Ă̒������x(2003�N)�ɋ�̎ʐ^�Ƃ��Čf�ڂ��ꂽ���̂ł��B
�@���̒�����������́A�܂��܂��̏o���Ǝv���Ă����̂ɁA�v���������m�l���璤��̐������Ă��ƖJ�߂��Ċ������������Ƃ��������L���ł��B
�@���A�������̒�����(�������M�҂����삵������)�@�@�E�͂��̋�f�ڂ��ꂽ���������发
�@�@�@�@ �@�@
�@�@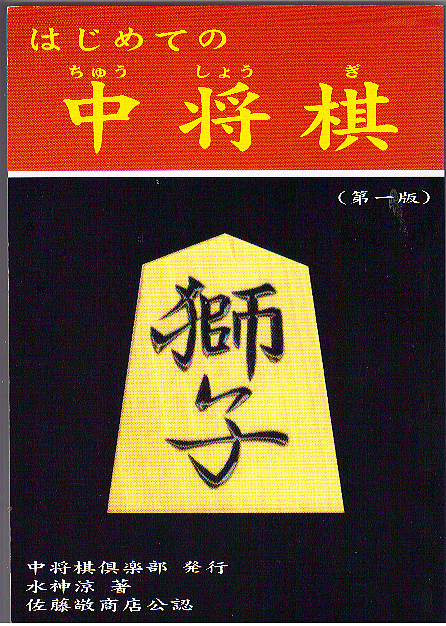 �@�@
�@�@
�@����܂ŕM�҂����삵���������̋�͂��̓�g���܂߂Ă�10��߂��ɋy��ł���܂����A���̂����������2��ŁA������2�삠��܂��B�������ɐ����̏ꍇ�́A�Ō�̎��̐��グ�͐�́u�Ȃ������v�̎�@�ł͎d�グ�ɂ�����傫���Ȃ�̂ŁA�W�����čs���܂����B����ł���̖����������A�唼�̋�������搔�̑������̂Ȃ̂ŁA�����܂Ő�������v���܂����B���͂��̐�����̂������߂ɑ�������g�ł��B���X�͒���Ƃ��đ����Ă����̂ł����A�r���ł������̂��Ɛ���ɂ��Ă݂悤�ƕ��j�ύX�ő���܂����B���̂́A�s���E�����̑O���ՓX�����̏���(�]�˖����Ɛ���)����{�ɂ��Ă��܂��B��K�ɂ́A���̋�H�[�E�u�����v�̖����L����Ă��܂��B
�@���B�������̐����i2007�N�����삵�����́@���F�\�ʂ̏��^�z�u�@�E�F�Ֆʍ����̗��ʁj
�@�@�@
�@���̒����������̐���ŁA�����Ƃ��ẮA�s���Ȃ���ꉞ�̒B�����܂����B�������A���̍����猻�s������̐���ɂ܂��܂��v������悤�ɂȂ�A��^�̏����̐���͂��낻�뒪�����Ƃ����v���������悬��悤�ɂȂ�܂����B�����ŁA���傤��2009�N���Ɉ˗��̂������叫���̐����������������̏��̂���{�ɂ��Đ��삷���Ƃ����d���������A�������̂̒���������������ƕ��s���đ����Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B
�@���̎����A������ł�����u�Ȃ������v�͂ł��܂���ł����B���ʂ̏������̓X�g�b�v�ŁA1�N�ȏ��^��������̓��X�ł����B���Ȃ茵��������ł������A2010�N�ɂ͑叫���ƒ������̐������������邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�������đ�^�����ނ̐���Ɉ���������M�҂́A�җ���@��5�N�O������͕��ʂ̏����݂̂ƌ��߂܂����B���ݑ�^�����ނ̋��͈�؍s���Ă���܂���B
�@�Ō�Ɏ���̑叫����������������������Ǝv���܂��B���̐}�́A����܂ŎO�g������130���叫���̋�̂����A2008�N���ɐ��삵�����̂ł��B��ؒn�̓V�����c�Q�ނŁA��̏��̂͐����������{�ɂ��܂����B���̒���ꂽ�̂ŁA���̐���̑叫���������ł����Ǝ����Ƃ��Ă͍l���Ă��܂��B
�@���130���́u�叫��(��ۋY)�v�@���^�z�u�̍Č��@�i�V�����c�Q�E����j
�@�@�@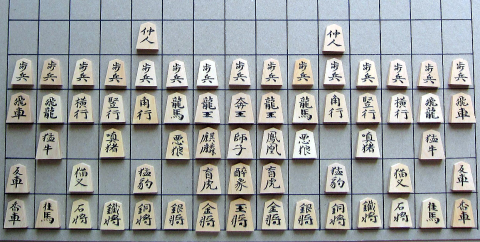
��������̂������@�ԊO�҂Q�F�`�F�X����̂�����
�@����Ǝ���͔ԊO�҂̑����Ƃ��Đ��E�Ɏ�����L���āA�e���̏����ނ̋���Љ�Ă��������Ǝv���܂��B���E�̏����ނ̒��ł����Ƃ��悭�m���Ă���̂̓`�F�X(Chess)�ł��B�����̈��D���T�˓��{�Ɍ����Ă���̂ɑ��āA�`�F�X�͐��E180�J���ȏ�ɕ��y���Ă���A���Z�l������3���l�Ɛ��v����Ă��܂��B���̂��߁u�Q�[���̉��l�v�ƌĂ�邱�Ƃ�����܂��B�����āA�C�O�̏����ނ̓`�F�X�����ł͂���܂���B�����t�@���ł���A�����ł��̂���u�ۊ�(�V�����`�[�FXiangqi)�v�Ƃ������O�̓Ǝ��̏������V��Ă������Ƃ������m�̕��������Ǝv���܂��B�䂪���Ŏ��ۂɒ����̏ۊ��̑njo���̂�����͋H�ł���A�ۊ��̔Ջ�̌`�p��[�����������Ȃ������唼�ł��傤�B�������A�ۊ��͒����{�y�݂̂Ȃ炸���E�e���̒����n�̐l�X�̊Ԃł͍L���������Ă��܂��B���̋��Z�l���́A�����炭�`�F�X�������Ă���A��5���l�Ƃ������v������܂��B
�@���̂悤�ɁA�`�F�X�ƒ����ۊ������{�̏����̒��Ԃł��邱�Ƃ͈�����x�F�m����Ă���Ɖ]���Ă悢�ł��傤�B�����������ȂǔՖʃQ�[�����D���Ȑl�ł��A���E�ɂ̓`�F�X�E�����ۊ��E���{�����̑��ɂ������̍��ł��ꂼ��Ǝ��̏����ނ�����A�����̏����ނɂ͂��ꂼ����F�̂����p�����Ă���Ƃ������Ƃ܂ł����m�̕��͈ӊO�ɏ��Ȃ��Ƃ����̂����Ԃł͂Ȃ��ł��傤���B�M�҂͈ȑO����`�F�X�̗��j�␢�E�̏����ނɂ��ċ���������A���ɂ���珫���ނ̋�Ɋւ��Ă��������ׂĂ݂����Ƃ�����܂��B�����ŁA����́u�`�F�X�Ɛ��E�̏����ނ̋���̂�����v���e�[�}�ɂ��Ă݂悤�ƍl���܂����B
�@�ŏ��ɐ��E�̏����ނōł��L���m���Ă���`�F�X�́u����̂�����v����n�߂܂��傤�B
�@�܂��M�҂̏�������`�F�X�̔Ջ�̎ʐ^�������������B
�@�@�@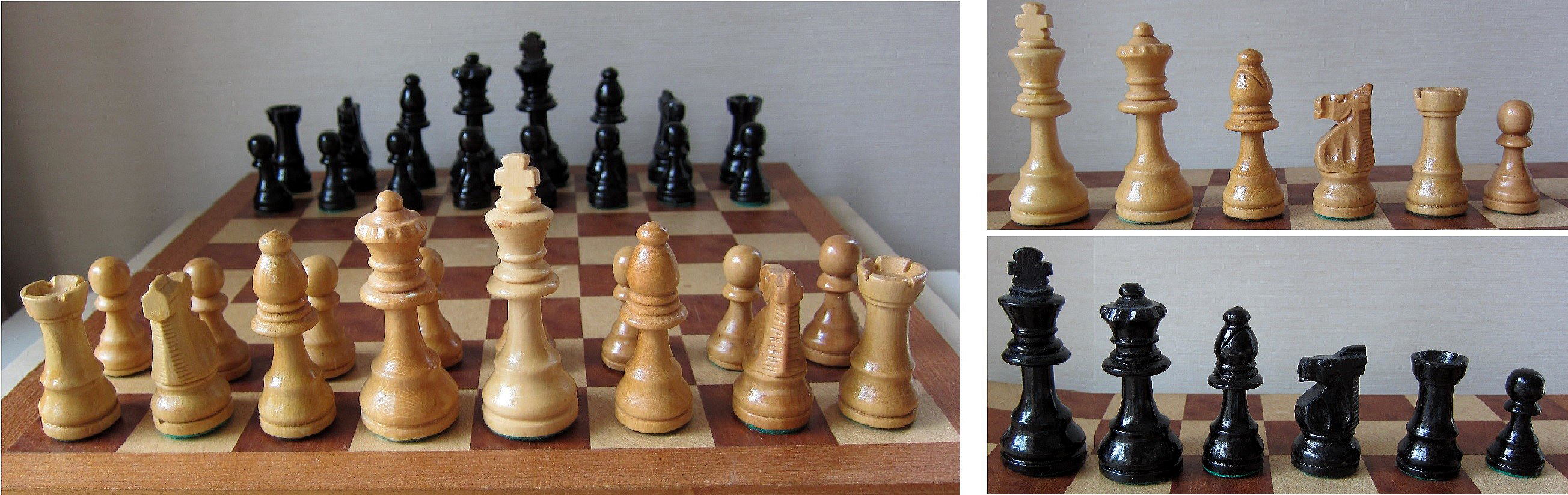
�@���̃Z�b�g�́A10�N�ȏ���O�ɋ��ł����b�ɂȂ��Ă����s���̔Ջ���X�œ��肵�����̂ł��B���[���b�p���̍����i�ɂ͋y�Ȃ����̂́A������x�{�i�I�ȕ��͋C�̂����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@���̎ʐ^�́A�J�ǎ��̋�̔z�u�������Ă��܂��B�s���͗l��8�~8�̔Տ�ɔ������R�������������Ă��܂��B����2��ڂɕ���(Pawn)�����сA���̌��ɂ͉�(King)�E����(Queen) �𒆐S�ɂ��č��E�ɑm��(Bishop)�E�R�m(Knight)�E�鈽���͓�(Rook)��2������ł��邱�Ƃ͒N�ł������m�Ǝv���܂��B�����A���߂ă`�F�X�ɏo��������ɁA�L���O�ƃN�C�[���̈ʒu�����R�ƍ��R�Ŕ��ɂȂ��Ă���(����Q���EK�E�A����Q�EK���Ō݂��Ɍ��������`�ɂȂ��Ă���)���Ƃ�s�v�c�Ɏv�����Ƃ����L�����������̕�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���͕M�҂����̈�l�ŁA�`�F�X���o���n�߂����ɁA�L���O�ƃN�C�[���̔z�u�ɖ����Ă���ƁA�u�J�ǎ��ɋ����ׂ鎞�́A���̃N�C�[���𔒂̃}�X�ڂɍ��̃N�C�[�������̃}�X�ڂɒu���A�Ɗo�����v�Ƌ���������̂ł����B
�@����6��ނ̋�̌`���������E��̎ʐ^�������������B��̒i�����̋�ʼn��̒i�����̋�ł����A6�Ƃ��ꌩ���������ŋ�̎�ނ����Ăɕ�����`�ɂȂ��Ă��܂��B�����猩�Ă����ƁA�L���O�̋�͈�ԍ��������蓪�ɉ������ڂ��Ă��܂��B���ɃN�C�[���̋�͓�Ԗڂɍ����A�������(�@��)�����ڂ��Ă��܂��B���ׂ̗̃r�V���b�v�̋�͎i�����̌`�ɂȂ��Ă���A�߂̐ꍞ���������Ă��܂��B�i�C�g�̋�͔n�̓����̌`�Ŗ��炩�ɋR�m��\���Ă���A���[�N�͓��̌`�ɂȂ��Ă��܂��B�Ō�Ƀ|�[���͍ł��������P���Ȍ`�ŁA���̌`�͂����炭�Ŏ�̋�̕\���Ȃ̂ł��傤�B���̋�`�͖{�i�I�ȍ������q���p�̊ߋ�̋�Ɏ���܂œ��l�Ȃ̂ŁA�`�F�X��̌`�͑S�Ă��̃p�^�[�����Ǝv���邩���m��܂���B���͌��ݕ��y���Ă��邱�̋�^�́A19���I���ɂȂ��Ă���l�Ă��ꂽ���̂ŁA�u�X�g�[���g��(�X�^�E���g��)�X�^�C��(Staunton Style)�v�ƌĂ��ߑ�I�ȃ^�C�v�̃f�U�C���ł��B���[���b�p�̃`�F�X��̗��j���������ׂĂ݂�ƁA���̃X�g�[���g���^�̈ȑO�ɂ��A6��ނ̋�����������m����R�m��饕����̋�̓I�Ȏp�ł͂Ȃ��ȒP���ĂȌ`�ŕ\��������^���������������Ƃ������Ƃ�������܂��B����������^�́A�u�ȈՌ^�̃`�F�X��(Conventional Chessmen)�v�Ƒ��̂���܂��B�����āA�`�F�X�̋�̂��ׂĂ����̂悤�ȊȈՌ^�ł͂���܂���B�`�F�X��ɂ́A����R�m�Ȃǂ̋�̓I�Ȏp�������u�`�ی^�̃`�F�X��(Figural Chessmen)�v�ƌĂ��^�C�v�̋������܂��B�`�F�X�̗��j�ׂ�ƁA���̌`�ی^�̋�͂��Ȃ�Â����琔���������Ă��܂����B
�@���ݐ��E�ŌẪ`�F�X��Ƃ����Z�b�g�́A1977�N�ɒ����A�W�A�̌Ós�T�}���J���h�ߍx�Ŕ��@���ꂽ����8���I���́u�A�t���V�A�u�̋�v(�����̐}��)�ł� �B����������܂ł���������키�҂����̋�̓I�Ȏp��\���������ƂȂ��Ă��܂��B�܂����[���b�p�����̃`�F�X��̒��ōł��悭�m���Ă�����̂ɁA1813�N�ɃX�R�b�g�����h�k�̗����Ŕ������ꂽ�u���C�X���̃`�F�X��v������܂�
(�E���̐}���͂��̕����i)�B���̋�͖k�C����C�X���[�����E�܂ōq�C���Ēʏ��E���Ղ����Ă����k���̃m���}�������ɂ����12���I���ɑ����X�R�b�g�����h�ɓ`����ꂽ�ƍl�����Ă��܂��B�����������j�I�������ȊO�ɂ��A�`�ی^�̃`�F�X��͌��݂ł������Ă���A�Ⴆ�A�A�j����f��̃L�����N�^�[�̎p�⒆�����m�̉����̌R���̎p�������`�F�X��̔�����Ă��܂��B�����͑ǂɂ͕s�����ł����A�N�W�Ƃɂ͐l�C������A���蕨�ȂǂɑI��邱�Ƃ�����悤�ł��B
�@�`�F�X��̗��j�E�}��1�@�����A�W�A�ƃ��[���b�p�̌`�ی^�`�F�X��̗�
�@�@�@
�@���������`�ی^�̋�ɑ��āA���ۂ̑Ǘp�̃`�F�X��́A���E�����E�m���E�R�m�E��E�����̂U��ނ̋���A��̓I�Ȏp�ł͂Ȃ��A���Ȗ��Ȍ`�ŕ\�����Ă���A��ɏq�ׂ��悤�Ɂu�ȈՌ^�̃`�F�X��v�ƌĂ�܂��B�`�F�X�͌��X�����ɃC�X���[�����E���烈�[���b�p�ɓ`����ꂽ�Q�[���ł����A��^���C�X���[�����E�ɗ��ʂ�����^���������ꂽ�Ǝv���܂��B�C�X���[�����E�̋�́A���E��b(���m�ł͌�ɏ����̋�ɂȂ���)�E�����Ȃǂ̎p�����ۉ�����A���ꂼ��̓������Ȗ��ɕ\�����ꂽ�`�ɂȂ��Ă��܂��B����́A���k�Ȍ`�ۋ�ǂɓK���Ă��Ȃ��Ƃ������ۓI���R�ɉ����A�������q���������ւ����C�X���[���̋������e�������Ƃ��l�����Ă��܂��B�Ⴆ�����̐}���̓C�����̈�Ղŏo�y����9�`11���I���Ɛ��肳���`�F�X��̖͑��i�ł����A���̋�͋ʍ��̌`�A��b�̋�͑�b�̍��ŕ\����Ă��܂��B�܂��A��(���[���b�p�ł͑m��)�̋�͓�̓ˋN�̂��锼���`�ƂȂ��Ă��܂��B���̓�̓ˋN�͏ۂ̉�̕\�����Ƃ�������������܂��B����ɁA�R�m�̋�͔n�̗֊s�A��̋�̓C�X���[�����E�̏�Ɍ�����Ԃ̌`���Ȗ��ɕ\�����ƍl�����܂��B�Ō�ɕ����̋�͏����Ȋp�������c���̔����̌`�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������̂ł����A���̏������P���Ȍ`���Ŏ�̋�̕\����������܂���B�܂��A�E���̐}���͒����̃h�C�c�̌Ï邩�甭�����ꂽ�`�F�X��̖͑��i�ł��B���̋�́A��̃C�����̏o�y��ɂ��Ȃ�ގ������`�ɂȂ��Ă��āA��Ɍ��郈�[���b�p�̋ߌ���̃`�F�X��Ƃ͑傫���قȂ�`�ł� �B���̋�ȊO�ɂ����[���b�p�e�n�ŃC�X���[�����E�̋�̌`�ɂ悭�����`�F�X������o�y���Ă��܂��B�ȈՌ^�̋�̌`�̌����̓C�X���[���̃`�F�X��̌`�������Ƃ����\���͂��Ȃ�傫���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�`�F�X��̗��j�E�}��2�@�C�X���[���̊ȈՌ^�`�F�X��̎���(��������o�y��̕����i)
�@�@ �@
�@
�@�`�F�X�����[���b�p�ɕ��y����ɂ�āA�C�X���[���̃`�F�X�ɖO������Ȃ����̂��������l�X�̊ԂɃ��[����啝�ɉ��߂悤�Ƃ��铮�����N���܂����B�Ⴆ�A�C�X���[�����E�ł́A��b�̋�͎߂P�}�X�ڂɂ����������A�ۂ̋�͎�2�}�X�ڔ��ōs���邾���ŁA�ǂ�������ɗ����̎ア��ł����B��̌Ăі��͏����Ƒm���ƕς���Ă��A15���I�O�����܂ł͓�̋�̓����͎ア�܂܂ł����B�Ƃ��낪15���I��������̓C�^���A��X�y�C���Ȃǂ̍��X�ŁA���݂̏�����m���̂悤�Ȕ��ɋ��������őǂ��s����悤�ɂȂ�܂����B�܂�����ɐ旧����13���I���ɂ́A�������ŏ��ɓ������ꍇ��2�}�X�O�i�����Ă��悢�ƋL��������������A���̃��[�����ꕔ�̍��ŔF�߂��Ă����悤�ł��B�`�F�X�̏����������o�ł����ɂ�āA���߂͏]���^�̃��[���őǂ��s���Ă����n���ł��V�������[���ł̌������������D�܂��X�������܂��āA�������ߑ�̃`�F�X�ɋ߂Â��Ă����܂����B
�@��̌`���C�X���[���^�̋��n�܂��āA���������[���b�p�Ǝ��̂��̂ɕς���čs���܂����B13���I�㔼�X�y�C�����̖��ō��ꂽ�V�Y���̎ʖ{�ɂ́A�`�F�X�̊G�}�������f�ڂ���Ă��܂��B�����ɕ`���ꂽ��̌`�ɂ́A��L���}��2�Ɏ������C�X���[���^�̃`�F�X��ɂ��߂����̂��������܂��B����A15�`17���I�̃`�F�X�̖{�ɕ`���ꂽ��̌`����́A�C�X���[���^�Ƃ͈قȂ��ۂ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����A�����̋�̌`�ɂ͋��ʐ��͔F�߂�����̂́A�����ɈقȂ��Ă���A��������A���̎���͑Ǘp�̋�̌`���e���E�e�n���ƂɈقȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����������ł���Ǝv���܂��B
�@�`�F�X��̗��j�E�}��3�@��������ߑト�[���b�p�̃`�F�X��̌`(�����Ɍf�ڂ��ꂽ��̌`����)
�@�@�@
�@�ו��ňقȂ�_���c���Ȃ�����A�V�����`�F�X�̃��[���́A17�18���I�ɂ̓��[���b�p�S�y�ɋ}���ɍL����܂����B���̎���Ƀ`�F�X�̐�i���ƂȂ����͉̂p�E���̗����ł����B���ɃC�M���X�ł͑����̃`�F�X���D�Ƃ��ǂɏW�܂郍���h���̃J�t�F�̒��Ƀ`�F�X�N���u���g�D����A�������������Ƌ��ɋZ�ʂ̐����͌��サ�A�V�˂Ǝ]������悤�ȃv���[���[������܂����B�t�����X�ł��p���̃J�t�F�Ő���ɑǂ��s���A�`�F�X�N���u���g�D�����悤�ɂȂ�܂����B�p�E�������ł̃`�F�X�N���u�̑n���Ɖ���̋}���ȑ����ɂ���āA�n���ł̂ݒʗp�������[���͂����č������[���̓��ꂪ�i�݂܂����B�܂��A�n�������v���[���[�̑����������œ����ɉ���ɂȂ��Ă������߁A�ނ炪�ǂ��d�˂邱�ƂŃ`�F�X��i���̉p�E���ł̃��[���̓��ꂪ��������悤�ɂȂ�܂����B����ɁA��i���p���̂������������͌�i�̍��X�ɂ������e����^���܂����B19���I�ɂ̓h�C�c�ł��X�C�X�ł��`�F�X�N���u���n�݂����悤�ɂȂ�܂����B
�@�`�F�X�N���u�̑g�D�̓`�F�X�̏����̂������傫���ς��܂����B����ȑO�͑ǂɂ͏�ɋ����q����ꏟ�����v���[���[���q������Ƃ����q���̖ʂ�����܂����B�N���u�ł͂����p���A���z�ȓ��������������ɂ��ăN���u���̑��ł̗D���҂���҂ɖ��_�Ə܋���^����Ƃ�������������܂����B����ɂ���ă`�F�X�͓q������a�m�̚n�݂ɕς������ɐi�ނ��ƂɂȂ�܂����B���[���b�p�̃`�F�X�͂��̈Ӗ��ł����݂̎p�ɂ��Ȃ�߂Â����Ƃ����Ă悢�Ǝv���܂��B
�@���āA19���I�̃��[���b�p���\����`�F�X��̌`���O�Љ�Ă����܂��傤�B�����̓h�C�c�ō̗p����Ă�����̌`�ł��B1616�N�Ƀh�C�c�Ŋ��s���ꂽ�w�`�F�X�����͉��̗V�сx�Ƃ��������ŏЉ�ꂽ�̂ŁA���҂̃O�X�^�t�E�Z���k�X(Gustavu Selenusu)�̖�����u�Z���k�X�X�^�C���v�ƌĂ�Ă��܂��B�Ԃ��v�킹��ג�����`����C�M���X�ł́u�`���[���b�v�X�^�C���v�����́u�K�[�f���X�^�C���v�Ƃ��Ă�܂����A�I�[�X�g���A�E�I�����_�Ȃǂ̃`�F�X��̌`�ɂ��e����^�������̂ł��B���̓�͂Ƃ��ɉp���̃J�t�F�Ń`�F�X������Ɏw���ꂽ����ɗ��s������`�ł��B�ǂ�������s�̒��S�ƂȂ����J�t�F�ɗR�����閼�O�ƂȂ��Ă��܂��B�����̋�̌`�́A�C�M���X�́u�Z���g�E�W���[�W�X�^�C��(St.George Style)�v�ƌĂ�܂����A����́A19���I�O���Ƀ����h���̗L���ȁu�Z���g�W���[�W�E�`�F�X�N���u�v�Ő���ɑǂɗp����ꂽ���߂��̖��ŌĂ�܂����B�C�M���X�����ł͑嗬�s������^�ŁA�������̌�ɃX�g�[���g���^�̋�����Ă��Ȃ���A�₪�ă`�F�X�̌����ǂɗp�������ɔF�肳��Ă�����������܂��� �B�O�Ԗڂ̓t�����X�Ń`�F�X�ǂ̒��S�ɂȂ����u�J�t�F��h�������W�����X(Cafe du la Regence)�v�ŗp�����Ă������Ƃ���u���W�F���V�B�X�^�C��(Regency Style)�v�ƌĂ����̂ł��B������̓Z���g�W���[�W�^�����X�ɍL�͈͂ɗ��s������`�ŁA���[���b�p�嗤�݂̂Ȃ炸�A�����J�嗤��A���W�F���A��x�g�i���Ȃǂ̐A���n�ɂ����y���܂����B20���I�������܂ł̓`�F�X��̃O���[�o���X�^���_�[�h�ɂȂ邩�Ǝv��ꂽ���̋�`���A���ۃ`�F�X�A��(FIDE�FFederation Internationale des Echecs)���X�g�[���g���^��������̋�ɔF�肵�Ă���͐������}���ɐ����A���݂̓X�y�C����L�V�R�ł������������Y����Ă���ɂ����܂���B
�@�`�F�X��̗��j�E�}��4�@�X�g�[���g���^�̓o��ȑO�Ɋe���ő�\�I�Ƃ��ꂽ�`�F�X��
�@�@�@
�@�����ŃX�g�[���g���^�̃`�F�X��o�ꂵ���o�܂ɂ��Ď�Z�ɏq�ׂ܂��傤�B��ɋ������A19���I���\����p�E���E�Ƃ̎O�̋�͂�������\�����̂Ȃ��������`�ł������A���Ȃ�̍����������ɐ�[������Ă���A�Ⴆ�Ύw���肪��������ꍇ�Ȃǂɂ��w���ɂ������������Ƒz���ł��邩������܂���B����ɈقȂ鍑�̃v���[���[���ΐ킷��@������Ȃ�ƁA�݂��Ɋ���e�������̌`�̋�ł̑ǂ��咣���ĕ�������ꍇ���l�����邽�߁A�e���Ǝ��̋�`�����V���ȊȈՌ^�̋���߂���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�X�g�[���g���^�̃`�F�X��o�ꂵ���̂ɂ͂��������w�i������܂����B���̋�̓C�M���X�̃V�F�C�N�X�s�A���̔o�D�Ŋw�҂̃n���[�h�E�X�g�[���g��(Howard Staunton 1810�`1874)�̖��ɗR��������̂ł��B�ނ̓`�F�X�N���u�̗L�͂ȃ����o�[�ł�����A1843�N�ɉp���l�Ƃ��ď��߂ăt�����X�̋�����ނ��ă��[���b�p�̍ŋ��҂ƔF�߂��`�F�X�t�@���̑��h���W�߂Ă��܂����B1849�N�ɏۉ��ؐ��i�Ȃǂ̐����Ђ��c��ł����W�����E�W���N�X(John Jaques)���A�e�ʂ̃W���[�i���X�g�ł���i�T�j�G���E�N�b�N(Nathaniel Cook)�̍l�Ă����f�U�C�������ɂ��āA�V���ȃ`�F�X��̔̔��ɓ��ݐ�܂��� �B���̂Ƃ��ނ�̓X�g�[���g�����g����̐��E�����āA���̐V�����`�̋�Ɂu�X�g�[���g���X�^�C���v�Ƃ������O��t�����̂ł��B�X�g�[���g���̖����̉e���͑傫���A�������ꂽ�V���Ȍ`�̋�̔���s���́A�C�M���X�݂̂Ȃ炸���[���b�p�e�n�ŋ}���ɐL�тĂ����܂����B1913�N�Ɍ������ꂽ�w�`�F�X�̗��j�x�̒��ŁA���҂�H.J.R.�}���[�́A�u���ۂ̑ǂɂ͖w�ǂ̃v���[���[�́u�X�g�[���g���^�̃`�F�X��v�̎g�p��I�Ԃ��낤�v�Əq�ׂĂ��܂��B���̍��ɂ̓X�g�[���g���^�����|�I�ȑ����h�ƂȂ��Ă����̂ł��傤�B�V���ȋ�^�����������߂��v���Ƃ��āA�����ԑǂ̑����ɔ����ĐV���ȃ^�C�v�̋�̕K�v�������܂��Ă������ƁA����ɉp�E���E�ƗL�͎O���̑�\�I�ȋ�ɐ�ɏq�ׂ��Z�������������Ƃ����������Ƃ͂ł��܂���B�������������A���̋�̃f�U�C�����A�ꌩ�ŊȒP���Ăɋ�̎�ނ����ʂł���Ƃ����_�ŏ]���^�����i�i�ɗD��Ă����̂��ő�̗v���������̂ł��傤�B
�@���W�F���V�B�^��Z���k�X�^�̋�́A20���I����������܂ł̓��[���b�p�嗤�Ȃǂł͏����Ȃ���Nj�Ƃ��Ă��g���Ă����悤�ł��B�������A1924�N�Ɍ������ꂽ���ۃ`�F�X�A�����A�X�g�[���g���^���g�[�i�����g�p�̐����ȋ�Ƃ������߁A�Ǘp�̋�Ƃ��Ă͋}���Ɏp���������ƂɂȂ�܂����B���ł͈ꕔ�̈��D�Ƃ��Ϗܗp�̏N�W�i�Ƃ��ċ��߂�ꍇ�������Ȃ��Ă��܂��B
�@�Ō�ɓ��{�Ŏs�̂���Ă���`�F�X��̘b�ɖ߂�܂��傤�B
�@��ŏЉ���M�ҏ����̋�́A�Ջ���X�̂���l�̘b�ł́A���Ȃ�ȑO�ɖ{�ꉢ�B�̃`�F�X�Z�b�g�ɑR���đ�p�̍H��ɑ��点�Ĕ����������i�Ƃ������Ƃł����B���̊ߋ�[�J�[�̎q�������`�F�X�Z�b�g�����������߂ł����A���B�̃Z�b�g�ɔ�ׂ�Ƃ��Ȃ�荠�ȉ��i�ݒ�Ŕ���o����܂����B������������Ă��鉢�B�Y�̋�ɔ�ׂ�Əd�ʊ��͖R�����̂ł����A�Տ�ɕ��ׂĒ��߂邾���ł͖{�i�I�ȕ��͋C������܂��B���X�ł͂��Ȃ���҂��Ĕ��������̂ł����A���ۂɂ͂���قǔ���s���͐L�тȂ������悤�ł����B
�@�ŏ��͕s�v�c�Ɏv�����M�҂ł������A���낢��ƍl�������ɁA����͓��{�̏ꍇ�`�F�X�Ə����Ŏ��v�̎��ɑ傫�ȈႢ�����������炾�낤�A�Ƃ������_�Ɏ���܂����B���������v�������̖��ł͂���܂���B���v�̌X���������Ƃ͑傫���قȂ�悤�Ɏv����̂ł��B���{�ɂ���萔�{�i�I�ȃ`�F�X���D�Ƃ����邱�Ƃ͊m���ł��B�����A�M�S�Ȉ��D�ƂƂ��Ȃ�A�ǂɗp����̂͂�͂胈�[���b�p�̍����ȃu�����h�i�������悤�ł��B���̈���Ŋߋ�[�J�[�̈����ȃ`�F�X�Z�b�g�̎��v�������x���邱�Ƃ������ł����A���̒��ԂɈʒu����悤�ȋ�̎��v�͂���߂ď��Ȃ��悤�ł��B�`�F�X�̏ꍇ�͏����t�@���Ƃ͈قȂ�A���S�҂��������������Ƃ��Ă��A��������i�K�I�ɖ{�i�I�ȋ�����߂�Ƃ��������ɐi�ނ��Ƃ͂قƂ�ǂȂ��̂�������܂���B
�@�ȏ�u�`�F�X����̂�����v�Ƒ肵�āA���낢��ƎG���Ȃ��Ƃ��q�ׂĂ��܂����B�������M�҂́A�`�F�X�̊��͂��܂������̏��S�҃��x���Ƃ��������łȂ��A���m�̃`�F�X�j��`�F�X��̌`�Ɋւ��Ă��A�����j�⏫����̏ꍇ������w�m�����R�����Ǝ��o���Ă���܂��B�����炭����ٕ��̒��ɋL�������Ƃɂ́A����^�╄�̂����Ƃ����X����Ǝv���܂��̂ŁA�����������������X�͐��C�t���̓_�Ȃǂ��u�X�����E��HP�f���v�ɓ��e���ĉ�����悤�A���肢�������܂��B
�Ȃ��A�ȉ��̎������Q�l�ɂ����Ă��������܂����B���҂̕��X�ɐS��芴�Ӑ\���グ�܂��B
�y�Q�l���ځz
����G��@�w�`�F�X�x(�@����w�o�ŋ� 2003�N)
�@����G��@�w�����̋N���x(���}�Ѓ��C�u�����[ 1996�N)
�@�W�F���[���E���t���@�w�`�F�X�ւ̏��ҁx(�����Е��ɃN�Z�W�� 2007�N)
�@�w���E�̃`�F�X�E�����W�U�x(��㏤�Ƒ�w�A�~���[�Y�����g�Y�ƌ��������ʓW���}�^ 2010�N)
�@�~�ьM�@�u�`�F�X�̋�ꂱ��v(http://daiki-ken30.sunnyday.jp/program/wp-content/uploads/2016/09/�`�F�X�̋�ꂱ.pdf )
�@�w��p�����ق̔��x(��p�����ُo�ŋǁE�ق�Ջ���J�������� 1994�N)
�@H.J.R. Murray�@A History of Chess�@(Oxford
University Press 1913)
�@Gareth Williams
Master Pieces (Viking Studio,
Newyork 2000)
�@Colleen Schafroth�@The Art of Chess�@(Harry
N. Abrams, Newyork 2002)
��������̂������@�ԊO�҂R�F�����̃V�����`�[
�@�O��q�ׂ��悤�ɁA���E�̏����ނ̒��Ń`�F�X�ƒ����ۊ��ɂ��Ă͈�����x�m���Ă��܂��B�������A���ɂ������̍��œƎ��̏����ނ�����A�����̏����ނɂ͂��ꂼ����F�̂����p�����Ă���Ƃ������Ƃ܂ł����m�̕��͏��Ȃ��悤�ł��B�����ŁA����͒����̏ۊ�(�V�����`�[)�Ƃ��̋�ɂ��ďq�ׂ����Ǝv���܂��B�����Ď���́A�����ȊO�̃A�W�A�e���ł��܂��������Ă��鏫���ނƂ��̋�����グ�����Ǝv���܂��B�j
�������ۊ�(�V�����`�[)�Ƃ��̋�
�@�M�҂��w���̍�����A�����ɂ������ɗނ���Q�[��������Ƃ������Ƃ͒m���Ă��܂����B����������͔��R�ƒm���Ă����Ƃ��������ŁA�Ղ��̓��������ɂ��ẮA���m�ɗ������Ă��܂���ł����B�悤�₭��\��̏I���߂��ɂȂ��āA����G�ꎁ�́w�����x(�@����w�o�ŋNJ��A1977�N)��ǂ�ŁA��������(�ۊ��E�V�����`�[)�̊T�v��m��A���ɒ��N�����E�r���}�E�^�C�E����A�W�A�̍��X�Ȃǂɂ����ꂼ��Ǝ��̏���������Ջ����Ƃ������Ƃ����߂Ēm��Ɏ���܂����B���̌�}���قȂǂŒ��ׂĂ݂�ƁA�V�����`�[(�ۊ�)�ɂ��Ă͂�����x�̐��̕���������A������ǂ�ł���ɂ��̓������������Ă��܂����B
�V�����`�[(�ۊ�)�̔Ջ�́A���E�̏����ނ̒��ł��Ȃ�Ǝ��̂��̂ɂȂ��Ă��܂�(�~�ьM���w���E�̏����x(�����V���Њ��A1997�N)���Q�l�ɂ��܂���) �B���̓����̒��Ŏ�Ȃ��̂��������Ă����܂��傤�B
�@�@�@����}�X�ڂ̒��ł͂Ȃ��Տ�̐��̌�_�ɒu���B��͐����i�ށB(���̐}��������������)
�@�@�A�Ղ̏㉺������4�̃}�X�ڂɎΐ��������Ă���B���̋����u��{(�`���E�O��)�v�Ƃ����B
�@�@�B�Ղ̒������ɂ͉�(�z��)�܂��͉͊E(�z�W�F)�Ƃ�����悪����A���������̕����ɕ�����Ă���B
�@�@�C��͊��q(�`�C�Y)�ƌĂ��B�~��(�~��)�`�ŕ\�ʂɋ�̖����Ԃƍ��ŏ�����Ă���B(�Ԃ����)
�@�@�D���̑��ɁA���Ɛ��Ƃ��Ԃɋ��u�����ɑ�����̂͋ւ���Ƃ�������s������̃��[��������B
�@���ɃV�����`�[(�ۊ�)�̊J�n�ǖʂƊe��̓������������܂��̂ł����������B
�@�@�@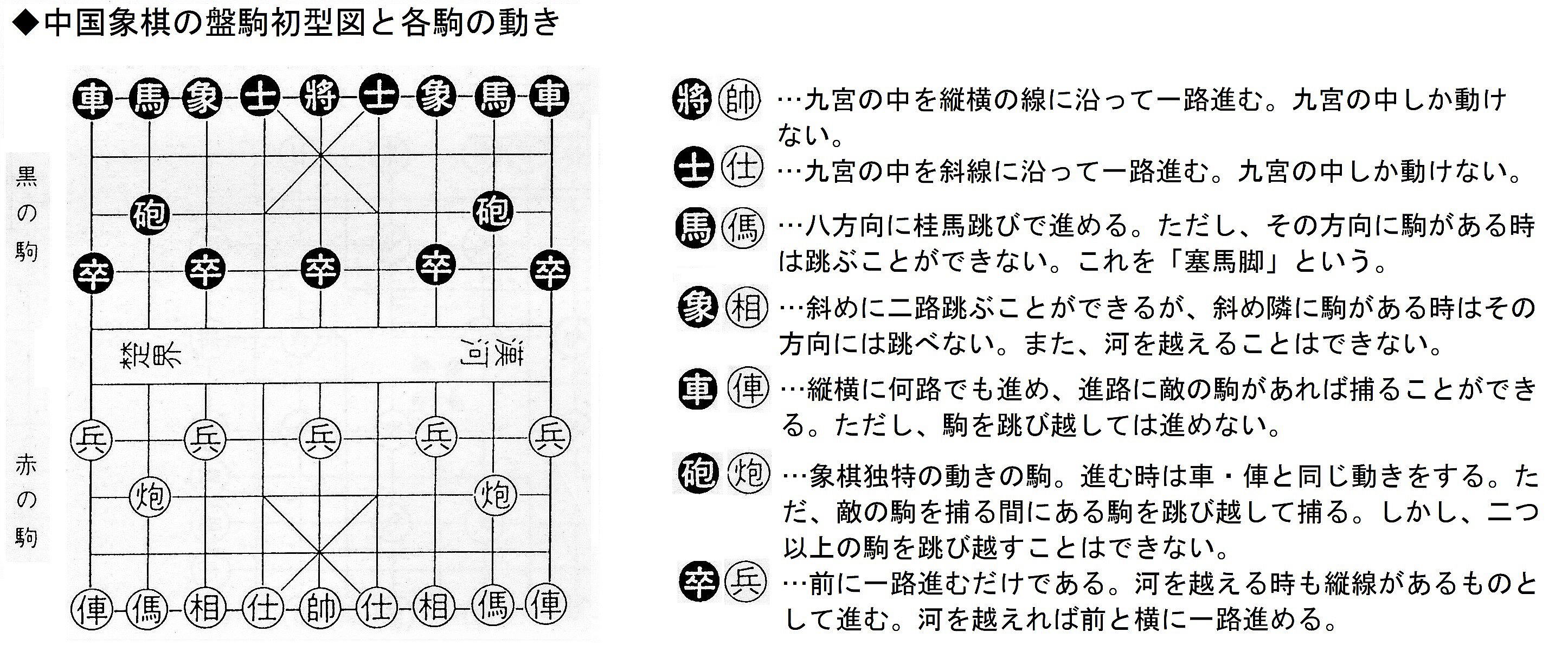
�@�M�҂��V�����`�[�̋����肵���̂͂��ꂩ�牽�N���o����1980�N�㔼�̂��Ƃł����B�����x���ɂȂ�Ƃ悭�o�����Ă������}�n���Y�̃Q�[���p�i�R�[�i�[�̈�p�ɔ̔�����Ă��܂����B�������́u���p�ۊ��v�Ƃ������������i�ŁA�~��(�~��)�`�̋�̕\�ʂ̓V�����`�[�̋�A���ʂ̓`�F�X�̋�ɂȂ��Ă��܂�
(�����̐}���ł�) �B���i��300�~�ƈ����������̂ő����ōw���������Ƃ��o���Ă��܂��B���̋�̒��ɂ͕��^�Ƃ��Ď����̔ՂƏ��S�җp�̑ǃ��[���������Ă���A�A��Ă�������ׂ܂����B���̌�A�������Ԃ̒��Ɏw������m���Ă���l�����āA�ꎞ���ǂɋ����܂����B���̎��A�����ŋ��̋�̎Ԃ���낤�Ƃ���ꍇ�͕K��������Łu��(�a����)�v�Ƃ��u�h��(�`�`��)�v�ȂǂƑ���ɒm�点�郋�[���������Ƌ�����ꂽ���Ƃ��y�����v���o�ł��B�����A���̋�͑Nj�Ƃ��đS�����͂Ȃ��̂ł����A��(��)�̋���R�Ƃ���ɂȂ��Ă���̂�������Ȃ��悤�Ɏv���A�s���̓`���Q�[�����X�≡�l�̒��؊X�ŃV�����`�[�̋��T���悤�ɂȂ�܂����B�ł����ۣ�Ƣ��������łȂ��A���̋���A�������ǂ�����ɂ���悤�ɁA��m��Ƣ�d��A��n��Ƣ?(�l�ɔn�̎�)��A��ԣ�Ƣ�ޣ�A��C(��)��Ƣ�{��ƕʂ̊����ɂȂ��Ă����̃Z�b�g�����z�ł������A�Ȃ��Ȃ�������܂���B�悤�₭�Ï��X�ŋ��R�����čw�������w�ۊ��@�����̏����x�Ƃ������S�җp�̓��发�ɕt���Ă����v���X�e�B�b�N��قڋ��߂���������Ă��܂����B(���̐}���ł�)
�@�@�@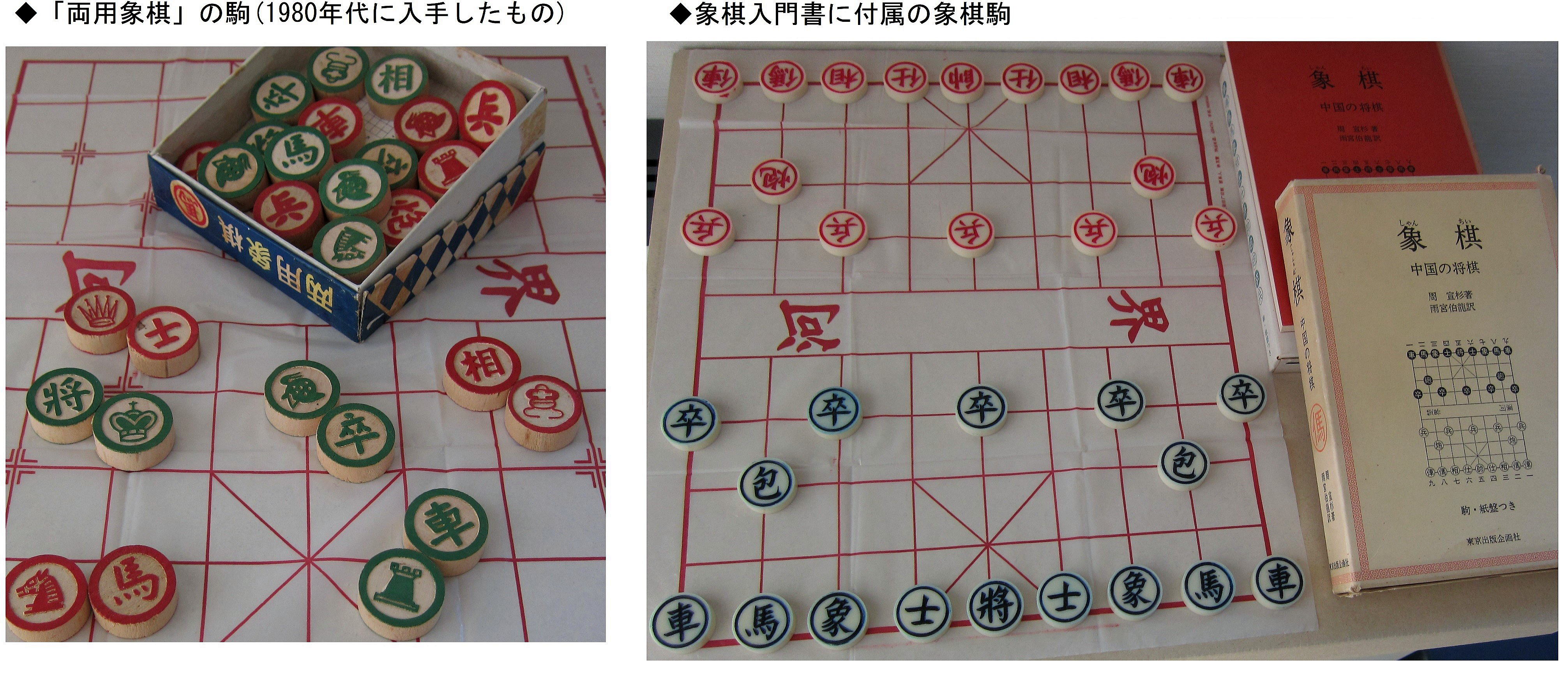
�@�Ƃ��낪�ŋ߂ɂȂ��āA���݂͒����嗤�ł����ۑ��̏�ʂł��m�E�n�E�ԁE�C�ɂ��Ă͓����������p�������̕�����ʓI�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ�m��܂����B����������̊����\�L�́A�ǂɎg�p�������p����łȂ��A������Ϗܗp�̍����ȋ�ɂ������Ă��܂� (���̐}���������������B���̐}���͗����ɏo�ꂳ�ꂽ�O�O�s�̓c���Ă��炨�肵�����̂ł��B�c������ɂ͐[�����Ӑ\���グ�܂�)�B
�@�V�����`�[�̋�́A���݂������s���̓`���Q�[�����X�⏫���Ջ���X�ȂǂŔ̔�����Ă���\��������܂��B�܂��A�y�V��A�}�]���ȂǃC���^�[�l�b�g�V���b�v�ł�����\�ł��B�荠�ȉ��i�ōw���ł�����̂����邩�Ǝv���܂��̂ŁA�����̂�����͂������Ă݂ĉ������B
�@�@�@
���V�����`�[�ƃ`�F�X�̔�r
�@�����Ń`�F�X�Ɣ�r���Ȃ���A�V�����`�[�̔Ջ���E�̏����ނ̒��ł��Ȃ�Ǝ��̂��̂ł��邱�Ƃ��ēx�m�F���Ă��������Ǝv���܂��B��\�I�Ȃ̂́A���̏��_�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@(1) �`�F�X����̋�ł���̂ɑ��āA�V�����`�[��͕���ȕ\�ʂɕ����ŋ���L�������̂ł���B
��������������́A���E�e���̏����ނ̒��ŁA�V�����`�[ (�����ق�)�A�`�����M (���N����)�A����(���{)�Ɍ����Ă���B
�@(2) �`�F�X��Տ�̃}�X�ڂ��ړ�����̂ɑ��āA�V�����`�[�̋�͔Տ�̐��̌�_�ɒu����A������ړ�����B���̂悤�ɋ������̂́A�V�����`�[�A�`�����M
�A�V���b���� (�J���{�W�A)�Ɍ�����B
�@(3) �`�F�X�̃L���O�ɓ������(���̢����ƐԂ̢���)����߂�ꏊ�́A�u��{�v�Ƃ���9�̓_�Ɍ�����B���̂悤�ɃL���O�̓�����ꏊ���������肷�郋�[�����Ƃ��Ă���̂́A���E�̏����ނ̒��ł��V�����`�[�ƃ`�����M�����ł���B
�@(4) �Ղ̒����ɓG�Ɩ����̗̈���颉ͣ���ݒ肳��Ă���B�Ղ̒������ɂ����������̂��鏫���ނ̓V�����`�[�����ł���B
�@�V�����`�[�̗��j�I�N���ɂ��Ă͏���������A�V�����`�[�̔Ջ�̓Ǝ������ǂ̂悤�ɂ��Č`�����ꂽ���ɂ��ẮA����͊m�����Ă͂��܂���B�ȉ��ɃV�����`�[�Ƃ��̔Ջ�̗��j�ɂ��ďq�ׂ邱�Ƃ́A��ɕM�҂̉����Ƒz���ɂ����̂ł��邱�Ƃ�\�߂��f�肵�Ă��������Ǝv���܂��B
���V�����`�[�̗��j���l����
�@�����Տ�̃Q�[���ł��͌�͗��j�������ƌÂ��A�I���O���狻�����Ă����Ƃ�����������܂��B����ɑ��ăV�����`�[(�ۊ�)�́A���Ȃ�V��������̃Q�[���ł��B��ۊ���Ƃ����ꎩ�̂͋I���O�̌ÓT�I�����̒��ɂ������܂����A����́u�ۉ吻�̋�v�Ƃ����Ӗ��̌��t�ŁA�����ނ̋�ł͂Ȃ��A�����炭�S���ʂ̃Q�[���̋�ƍl�����Ă��܂��B�I���O�ɃV�����`�[�����݂��Ă��Ȃ��������Ƃ͊m���ł��傤�B
�����قƂ�ǂ̐l�X���A������o�y��猩�āA�x���Ƃ��k�v����(960�`1127�N)�̖����A����11���I������12���I�����ɂ͌��s�Ƃقړ��l�̔Ջ�ŃV�����`�[���V��Ă����̂͊m�����ƍl���Ă��܂��B
�@�V�����`�[���V��n�߂������́A���̖k�v���㖖������ǂ��܂ők�邱�Ƃ��ł���̂ł��傤���B
�����ł́A���j���̒��ɓ�k������(439�`589�N)�����̖k�������̕��邪�w�یo�x���u�q�����Ƃ����L�q������A��������A���邪�u�ۋY�v�Ɖ]���Q�[�����l�Ă��A���ꂪ������k�v�̎���ɕϗe���ăV�����`�[(�ۊ�)�ɂȂ����Ƃ����N��������������悤�ɂȂ�܂����B�������炳��ɐi��ŁA���؎v�z�̉e�����炩�A����̑n���������́u�ۋY�v�Ƃ����Q�[�����C���h��y���V�A�ɓ`����ꂽ�A�]���Ă��ꂪ�`�F�X�ȂǏ����ނ̋N���ł���Ƃ��������N�������������܂����B
�@��ʂɐ��E�̌����҂̊Ԃł́A�`�F�X�̋N���̓C���h���̓y���V�A�ł��낤�Ƃ��������L�͂Ȃ̂ł����A�����N�����͂��̐����̎咣�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����ł�20���I�ɂȂ��Ă������ޒ����N�������x�z�I�ł������A�������ɋߔN�ɂȂ��āA�V�����`�[�͌��X�C���h��y���V�A����`����ꂽ�����ނ��N���ł���A���ꂪ�����œƎ��̕ϗl�����邱�ƂŌ��݂̂悤�Ȍ`�ɂȂ����A�Ƃ������E�̑吨�ɉ������������L�͂ɂȂ����܂��B
�@����Ƀ`�F�X�̋N�����C���h(�����̓y���V�A)�ɋ��߂�Ƃ����ʐ���O��ɂ��ăV�����`�[�̗��j���l���Ă݂܂��傤�B���݂܂œ`�����镶��������ƁA�`�F�X��6���I���܂łɃC���h��y���V�A�ŗV��Ă������Ƃ͊T�ˊm���ł��B�܂��A���E�ŌÂƂ���钆���A�W�A�E�T�}���J���h�x�O�o�y�́u�A�t���V�A�u�̋�v(�ԊO��2������������)��7�`8���I���Ɛ��肳��Ă��܂��B�����A�W�A�ɂ�6���I�㔼����g���R�n�V�q���̓˙����������鍑���ɉh���Ă��܂����B�˙��x�z���ɒu���ĕی삵���C�����n�̃\�O�h���l�̌��Պ����ɂ���Ē����A�W�A�ƒ����Ƃ̌��Ղ��i�݁A���̒��ő����̕����������ɓ`�����܂����B���̒��ɏ����ނ��������̂�������܂����B�������������ɐ��������Ƃ��������杂ɂ͏����ނ̔Ջ�Ƃ��ڂ������̂��o�ꂷ�镨��������܂��B����̔N��ɕs�m����������悤�Ȃ̂Œf��͍T���܂����A���㖖�����܂łɃV�����`�[�̌��^�ƂȂ�悤�ȏ����ނ������ɓ`�����Ă����\���͏\������Ǝv���܂��B
���V�����`�[����������ߒ���z������Ɓc
�@��ŏq�ׂ��悤�ɏ����ނ̋N�����C���h�܂��̓y���V�A�ɑz�肵���ꍇ�A�`�d�o�H�̏o���_�̋�͗��̋�����\���͑傫�����낤�Ǝv���܂��B���ꂪ�����o�Ėk�v���㖖���ɂ͋�͉~��(�~��)�`�̕�����ɂȂ��Ă���A���s�Ɠ����悤�ɔՏ�̐���i�ނ悤�ɂȂ��Ă��܂����B�}�X�ڂ��ړ����Ă������̋��C�ɉ~�`�̕�����ɂȂ�A�����ɐ�����悤�ɂȂ����\��������܂����A�������̒i�K���o�ċ�̎p���ω����Č��s�̂悤�ȉ~�`�̕�������܂ꂽ�ƍl���邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B
�@��̌`��̕ω��ɂ��ĕM�҂́A�Q�[���̕��y�ɔ����ė��̒�����ȗ�������K�v�����������Ƃ����̗v���̈�������̂ł͂Ȃ����A�ƍl���Ă��܂��B�����A�W�A�̋�͏ۉ奏b���Ȃǂ̍ގ����đ���ꂽ���k�ȗ��̒���Ȃ̂Ŕ��ɍ����ȋM�d�i���������Ƃł��傤�B���ɂ���������`�����āA�x�z�w�̐l�X�̑�����Ϗ܂ɂ͗p�����Ă��A�命���̐l�X�ɂ͂ƂĂ���̓͂��Ȃ����̂������Ǝv���܂��B����ł��ۊ��̌��^�ƂȂ������̃Q�[�������y����悤�ɂȂ�ƁA���ۂɑǂ��鑽���̐l�X�����肵�₷���P���Ȍ`�̋���߂���悤�ɂȂ����A�Ƃ����͗e�Ղɑz���ł��܂��B�������ĊȈՌ^�̋����ꂽ�̂������̂��ƂȂ̂��A�܂������A�W�A���琼����o�Ē����Ɏ���o�H�̒��łǂ̕ӂ�ł̂��Ƃ������̂��͕�����܂���B��������ȈՉ����悤�Ƃ������ɁA���̔Տ�Q�[���ŗp�����Ă����P���Ȍ`�̋�Q�l��ɂȂ����̂�������܂���B�����A�W�A�ł������ł���s����Տ�Q�[���̋�ɂ͂��낢��Ȍ`������A���̒��ɂ͗l�X�̌`��̋�ƕ���ŁA�G������F�ŋ�ʂ���~�`���̋������܂����B�V�����`�[�Ǝ��̉~��̋�`�͂��̂悤�Ȍo�߂��o�Đ��܂ꂽ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�������Đ��܂ꂽ�ȈՋ�ɉ~��̌`�������āA���̕\�ʂɋ�̎�ނ������\���A�ۊ��̑Nj�Ƃ��Ďg�p�\�ɂȂ�܂��B���E��b�E�ہE�n(�R�m)�E�ԁE�����̐}����`���ċ����������Ƃ��A�u���v�u�m�v�u�ہv�u�n�v�u�ԁv�u���v�Ɗ����������Ď������Ƃ����肦���Ǝv���܂��B����ɁA�Жʂɐ}����`���ЖʂɊ������������Ƃ��\�ł����B�����o�y��̒��ɂ͂����������ʏ����̋�(���̐}��)�����Ȃ�̐������܂��B�Ȃ��}��(�G)�ŋ���\�����ƂŁA������p���Ȃ�����Ƃ��ǂ��\�ƂȂ�܂��B�`���ȗ��Q�[���̕��y�ɔ����ċ�~�`�ɕω���������A���l�Ɛ����̐l�X���ǂ���@����������̂�������܂���B
�@�@�@
�@��ɏq�ׂ��悤�ɁA���s�̃V�����`�[�ɂ͂���ɂ������Ǝ����������܂��B���̂����ő�̂��̂́A��̈ړ����Տ�̃}�X�ڂ���}�X�ڂɐi�ނ̂ł͂Ȃ��A���̌�_�����_�ɐi�ނƂ����_�ł��B����������̓����̑�]���Ɖ~�`������̐����́A�ǂ��炪��ɋN�������Ƃ������̂ł��傤���B�͌�̉e���̉��ɗ����̑�ϊv���قƂ�Ǔ����ɐ������Ƃ�������������܂����A����I�ȗ��R�Ƃ܂ł͂����Ȃ��Ǝv���܂��B�~�`������}�X�ړ��ɒu���ꂽ�i�K���������\�����A���̋��}����Տ�̐��̌�_�ɒu���ꂽ�i�K���������\�����S�ے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�Ǝv���܂��B
�@����ɔՏ�Ɂu��{�v�Ɓu�͊E�v�̐ݒ�A�u�C�v�̋�̓o��Ȃǂ��o�āA11���I���̖k�v�������ɂ͌��s�ɋ߂��`�̃V�����`�[�����������Ƃ����̂��A���݈�ʂɔF�߂��Ă��錩���̂悤�ł��B�������A�����̕ω��ɂ��Ă����̑O��W�ɂ��Ă͖��m�ɂȂ��Ă��܂���B���㒆���ŔՋ�Ȃǂ̏o�y�������邱�ƂŃV�����`�[�j�̌������傫���O�i����\�����傫���Ǝv���܂��B
�@����́A�ȉ��̎������Q�l�ɂ��܂����B���҂̕��X�ɐ[�����Ӑ\���グ�܂��B
�� ���鐙(�J�{������)�w�ۊ��x(�����o�Ŋ��ЁA1973�N)
�� ���c���O�w���E�̃Q�[�����T�x(�������o�ŁA1989�N)
�� �~�ьM�w���E�̏����x(�����V���ЁA1997�N)�@ (����L���Ƌ����̉����ł�2000�N�Ɋ��s�����)
�� ����L�w�����̏ۊ��x(����o�ŁA2000�N)
�� ����L�w���m�̏����x(��㏤�Ƒ�w�A�~���[�Y�����g�Y�ƌ������A2007�N)
�� ����G��w�����̋N���x(���}�ЁA1996�N)
�� �ؑ��`���w����g�p�̓�x(���{�����A���A2001�N)
�� �ɓ��ό��u�����T���@23�v(�w�����W���[�i���x1987�N11�����f��)
�� �����N��u�Î��ۊ��Ə����̓`���v(�w�l�Êw�W���[�i���x1998�N3�����f��)
�� �����N��E�{���W��u�v��ۊ���Ƃ��̐��i�v(�w�V�Y�j����14�x�A2002�N�f��)
�� �����N��u�����`���čl�v(�����l�Êw�������I�v�w�l�Û{�_���x��36���A2013�N�f��)
�����V���Ђ́A�����点���̊����t�́E���ˏr�m���i�ɂ���đn�݂���A����܂ő����̏����W�̐�发�����s���Ă��܂����B�����ŏЉ���w���E�̏����x�́A�`�F�X���͂��߂Ƃ���S��ވȏ�̏����ނ�ԗ��I�ɏЉ���M�d�Ȗ{�ł��B���̖{�́A��ɉ���L���Ƃ̋����Ƃ��ĉ�������Ĕł���܂����B�X�����}���قɂ�1997�N�̏��ł���������Ă��܂��B�����}���ق̑����͍Ŋ��̌����}���ٌo�R�ő݂��o�����邱�Ƃ��\�ł��̂ŁA�S�̂�����͐���ǂ��������B
���݃V�����`�[�̍��ۑ��œ��{��\�Ƃ��Ċ���Ă���c���Ď��Ɏf�����Ƃ���ł́A���ʼn����ɐ鍐����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������ł��B���������āA�V�����`�[�͐��X���X�Ǝw���ׂ����Ƌ����邽�߂ɃG�`�P�b�g�Ƃ��Ă����������s���������̂�������܂���B
1970�N��������𐳏퉻�ɔ����F�D�u�[���̒��ŔC�V������ۊ��Ջ�Z�b�g����������Ă��܂��B�͂��߂͔���s�����ǂ��A�S�ݓX�ȂǂŔ̔����ꂽ���Ƃ��������悤�ł����A���̌㔄��グ�͌������Ă��܂��܂����B���������ɓ����Ă��s���̓`���Q�[�����X(���c��̉��삩�邽�X)�ɂ͏펞�u����Ă��܂����B�Ղ͐܂肽���݂̔Ղŋ�̓v���X�e�B�b�N���̕�����ł����B���̃Z�b�g�́A�Ղ��������肵������ł������A��̕������ԁE�n�E�C�̋�œ����������p�����Ă������߁A�w���Ɏ���܂���ł����B10�N�قǑO�ɂ͂��̐��X�Ō��������̂ł����A�c�O�Ȃ��琔�N�O�ɗ�����������͂��łɔ̔�����Ă��܂���ł����B���ł��l�b�g�I�[�N�V�����Ȃǂɏo�i����邱�Ƃ�����悤�ł��B
1990�N�����Ǝv���܂����A�s���̒������А��X�ōw������縎����ҁw�ۊ��헪�x(1988�N)�Ƃ����{���M�ҏ����̗B��̃V�����`�[��@���发�ł��B�����ł̋�́A������A�m��d�A�ۥ���A�n�?(�l�ɔn�̎�)�A�ԥ�ށA�C��{�Ɨ��R�ňقȂ銿�����p�����Ă��܂��B�܂��A�������w�������p���̃V�����`�[���发�hChinese Chess�h(TUTTLE,1985)�Ƃ����{�ł́A�m�E�n�E�ԁE�{�̎l�̋��œ����������p�����Ă��܂��B
���N�́u20��X�����܂�v�̊��ŏ��S�Ҍ����̃V�����`�[���勳�����J�Â���Ă��܂����B�w������Ă����̂́A��ɋr��2�ł��Љ���c���Ď��ł����B�p�����Ă�����́A���炭���y�p�̋�Ǝv������̂ŁA�����̕\�L�͐ԍ����R�Ƃ��u�m�v�E��n��E�u�ԁv�E��C��Ɠ����ɂȂ��Ă��܂��B���w���Ă����M�҂��u�����̏����ł͗��R�ňقȂ镶�����p������̂��������Ǝv���Ă����̂ł����c�B�v�Ɛq�˂�ƁA�c������̓����́A�u���ۑ��ł͗��R�Ƃ��m�E�n�E�ԁE�C�Ɠ��������ŕ\�L������g���Ă��܂��v�Ƃ������̂ł����B�����āA��p�ł͗��R�ňقȂ镶�����\�L����Ă��邱�Ƃ����邪�A�嗤�ł͏��Ȃ��悤���A�Ƌ����Ă���܂����B�������ɃV�����`�[�̏ꍇ���R�̋�͐Ԃƍ��̐F�œG��������ʂł���̂ŁA���ۂ̑ǂŎl�̋��ŕʂ̕������g�p����K�v�͂���܂���B�ނ��뗼�R���������p����\�L�@�̕����A�Q�[���̍��ۉ��Ƃ����ϓ_�ł��D��Ă���Ƃ����Ă悢�ł��傤�B
���ۉ䂪���ŋߔN���s���ꂽ�V�����`�[�̉���{�ł͗��R����������p�����Ă��܂� (����L���́w�����̏��ۊ��x�A�w���m�̏����x�����̗�ł�)�B
�x�g�i���ł̓V�����`�[�̗�������ށu�J�[�g���v�Ƃ��������ނ��嗬�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A����ł͗�����������ɓ`����ꂽ�V�����`�[���ω�������`�����W�[(�����ۊ�)�����O�܂ōL���������Ă��܂����B������̏����ނ͔Ջ���w�������V�����`�[�ɔ��ɗގ����Ă���A�����ł́A�L���Ӗ��ŃV�����`�[�̕��ނɊ܂߂čl���܂����B�`�����W�[�ƃJ�[�g���ɂ��Ă͑O�f�w���E�̏����x132�E133p�y�сw�����̏��ۊ��x��88�`91p��98�E99p�������������B
�퍑����̖����̎��l�E����(BC342�`277)�́w�^���x�ɢ�����ۊ��A�L��������Ƃ�����傪����܂��B�܂��A�O�������̕����w�����x�ɂ��퍑�̗L�͏���Џ��N(BC3���I)�̈�b���Љ�钆�ŁA��ۊ��킷��Ɖ]���\��������܂��B
�����j���ł́A�����e�n����͖k�v���������v�����Ɛ��肳���ۊ��̋�o�y���Ă��܂�(����̐}�����ȉ���HP�ł����������Bhttp://history.chess.free.fr/xiangqi-old-pieces.htm )�B�܂��A�����j���Ƃ��ẮA�����������������l�̗����Ƃ̍�i�ɏۊ��Ղ����s�Ɠ��l�̌`�ŕ`����Ă��܂�(���̐}���́Ahttp://history.chess.free.fr/xiangqi.htm �ł���������)�B�����̂��Ƃ���A�x���Ƃ�11���I�����܂łɂ́A���s�̃V�����`�[�Ɠ��l�̂��̂��������Ă����Ɛ��肵�č����x���Ȃ��Ǝv���܂��B
�u�鐧�یo���A�W�S���u���v(�w�����x����)�B���̢�یo����̂��͖̂S�����ē��e�͑S���s���ł����A�֘A�̕������炱����u�ۋY�o�v�Ƃ��錩��������܂��B����Ɂu�ۋY�v�������̃Q�[���ށA�������ۊ��Ɏ����Q�[���̂��Ƃł͂Ȃ����Ƃ������肪���܂ꂽ�̂ł��傤�B�������ĕ���ɂ��ۊ��̑n���Ƃ��������o�Ă��܂����B
�@�����A��یo��܂��́u�ۋY�v�Ɋ֘A���镶���ɂ͈ՁE�m��E�V���Ɋւ���͂łĂ��܂����A���s�̏ۊ��Ƃ̊֘A���Î�����悤�Ȏ���͈����܂���B����䂦�u�ۋY�v�����Ɉ����̃Q�[�����Ƃ��Ă��A�����ނƂ͑S�������ł���ƌ���ׂ��ł��傤�B(�ɓ��ό��u�����T���@23�v�A�y�іؑ��`���w����g�p�̓�x���Q�l�Ƃ��܂���)
�Ⴆ�A1991�N���̒��@�����w�����ۊ��j�x�ɂ́A10���I�㔼�́w�����䗗�x�ɂ́u�����鑢�ۋY�v�Ƃ����L�q������Əq�ׂ��Ă��܂��B(����G�ꎁ�́w�����̋N���x���Q�Ƃ��܂���)
�`�F�X�̒����N�����͒����l�݂̂Ȃ炸���[���b�p�l�ɂ���Ă��������Ă��܂��B���̑�\�Ƃ�����̂��A�C�M���X�̉Ȋw�Z�p�j�w�҂̃W���Z�t�E�j�[�_��(1900�`95)�ł����B�ނ͑咘�w�����̉Ȋw�ƕ����x�̒��ŁA���m�̊w�҂�����������`�F�X�̃C���h�N����������������ł���Ƒނ��A���ʕ���ƏۋY�Ƃ̊ւ���ۋY�Ɛ肢��V���w�Ƃ̊ւ����������Ă��܂��B(�w�����̉Ȋw�ƕ����x�u�掵���@�����w�v�v���Њ��A1991�N)
20���I�����A�����A�W�A�E�g���t�@���̃V���N���[�h�v�� �����������̈�Ղ���A�R�悵����m�̏����Ȓ��������@����A�h�C�c�̕��ɋL����܂����B���̎p�̓A�t���V�A�u�̃`�F�X��ɔ��ɂ悭���Ă��܂�(http://history.chess.free.fr/first-persian-russian.htm)�B���̏������A�T�}���J���h���瓌��2000�L���߂������ꂽ���̒n�܂œ`����ꂽ�`�F�X��Ȃ̂�������܂���B
�c�鑾�@�̖��ɂ��k�v������ (977�`983)�Ҏ[���ꂽ�w�����L�L�x���ڂ́w�����^�x�Ƃ��������������ł��B���̏����͓����������ɍɑ����������m�}(779�`847)�̍�Ɠ`�����Ă��܂��B���̒��ɂ́A����R���ɏZ�����Ƃ����j�������̌R�c�̐퓬���J��L���錶�e���������Ĝܜ����Ă������A�����S�z�����e���̎҂��R���̏������@�����Ƃ�����̏ۊ��ՂƋ��Ɠ��̏ۊ���o�Ă����Ƃ������ꂪ����܂��B�e���́A���������e�̒��Ō����Ɖ]���A�R�n���ԕ����̐i�R����l�q���ۊ���̓����Ǝ��Ă��邱�ƂɋC�t���A�@��o�����Ջ��p�������Ƃ���A�����͌��N�����߂��Ęb�͏I���܂��B����̌��{�͎U�����Ă��邽�߁A�w�����L�L�x�Ɏ��߂�ꂽ�L�q�����ۂɋ��m�}�̍�ł��邩�ǂ����Ɋւ��āA����ɂ��̐����N��ɂ��Ă��A������x���ۂ����Ă����K�v������܂��B�������A�������̖������܂łɂ̓V�����`�[�̌��^�ƂȂ鏫���ނ������ŗV��Ă����\���͑傫���悤�Ɏv���܂��B
(�Ȃ��A�����̕���ɂ��ẮA�O�f�̖ؑ��`���w����g�p�̓�x50�`51p������������)
�����ʼn~�`�̃Q�[�����p����Տ�Q�[���͐���������Ǝv���܂����A���ł��ł��L���Ȃ͈̂͌�(�͞�)���낤�Ǝv���܂��B�͌�͞��q(���)��Տ�̐��̌�_�ɒu���Ƃ����_�ł����s�̃V�����`�[�Ɠ�������������̂ŁA�~�`��̐����Ɉ͌邪�傫���e�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ��������͂��Ȃ�L�͂ł��B�������A�ȈՌ^�̋���������̂��������Ƃ͌���܂���B�����A�W�A���璆��������o�R�����`�����[�g�̂ǂ����ł���\��������܂��B���͈͌�̈╨(�~�j�`���A�̌�Ղƌ��z�ɕ`���ꂽ�͌�})�����������̃g���t�@���ߍx�ł��o�y���Ă���A�����ł���͂�͌�̉e����z���ł��邩������܂���B�����A�J�Ԃ��ɂȂ�܂����~�`�̋��p����Տ�Q�[���͑��ɂ�����A��͂�f��͍T����ׂ����Ǝv���܂��B
���s�Ɠ��������\�L�݂̂̏ۊ���͏o�y���Ă��܂����A�}���݂̂��\�L���ꂽ��͏o�y���Ă��܂���B
���̐}���Ɗ����̕��p���ꂽ��̑��݂���A���s�̏ۊ�����Ɏ���܂ł̊ԂɁA
�@(�`��������)���̋� �� �A�~�`�}���� �� �B�~�`�}����������p��(�\�Ɨ�) �� �C(���s��)�~�`������
�Ƃ����i�K�I�ڍs���������̂ł͂Ȃ����A�Ɛ��肷�錩��������悤�ł��B�������\�ʂɐ}���������`����A������������Ă��Ȃ��~�`��̏o�y�Ⴊ�Ȃ��̂ŁA���̑Ó������m���߂邱�Ƃ͂ł��Ă��܂���B
�ؑ��`�����͑O�f�w����g�p�̓�x�̒��ŁA�~�`��������Ɛ���̌�_�����_�ւ̈ړ��ւ̓]���͓����ł������ɈႢ�Ȃ��Ɖ]�������������Ă��܂�(����81p�Q��)�B
��������̂������@�ԊO�҂S�F�A�W�A�̏����ނ̋�(1)�`�����M�ƃV���^��
�@���E���̊e���ł́A�`�F�X�E�V�����`�[�̑��ɂ��l�X�̏����ނ��������Ă��܂��B���ɁA�A�W�A�ɂ͎��ɗl�X�̓������鏫���ނ������܂��B����Ǝ���͂����̂����A��Ȃ��̂Ƃ��Ē��N�����E�����S���E����A�W�A�̏��������Љ�����Ǝv���܂��B
�@���̑O�ɏ����ނ̋N���Ƃ��ꂪ���E�ɍL�����Ă��������j�ɂ��ĊȒP�Ɍ��Ă��������Ǝv���܂��B
�͂��߂Ɂ@�\�@���E�̏����ނ̋N���Ƃ��̓`�d�ɂ���
�@���E�̏����ނ̋N���Ɋւ��ẮA�C���h��y���V�A������Ȃǂ��l�����Ă��܂����B�����̒��Ō��ݍł��L�͂Ȃ̂̓C���h�N�����ł��B���̐��́A�ŌÂ̏������Ñ�C���h�ŋ�����ꂽ�Ƃ�����`���g�D�����K(chaturanga)��ƌĂ��Տ�Q�[�����Ǝ咣������̂ł��B���̃T���X�N���b�g��͌��X�u�l�̕���v�Ƃ����Ӗ��ŁA�]���āA�C���h�̓`���I�Ȏl�̌R���I�Ґ��A���Ȃ킿�������E�ە����E�R�����E��ԑ��̎l�R�ɂ��Ґ����w���Ă��܂��B���̌R���p��͋I���O����L���p�����Ă��܂����B
�@���Ñ�C���h�̌R���Ґ���`�����ΌA���@�̕���
�@
�@�Ƃ��낪�A���́u�`���g�D�����K�v�Ƃ����{���R���p�ꂾ�������t���Q�[���̈Ӗ��ŗp����ꂽ������7���I�Ɍ����܂����B����́A�헐�̑������k�C���h�������n���V�����@���_�i(606�`47�݈�)�ɂ���ē��ꂳ�ꂽ���A������̎��l�o�[�i���̑�ȉ��̕��a�Ȏ������^������i�w�n���V���`�����^�x�ŁA���̒��ɂ͎��̂悤�Ȍ��t������Ă��܂��B
�u����(�̑�ȉ���)�������ł́A���(������)�������̖\�͓I�ȑ����͌����Ȃ��Ȃ����B����l�R(�`���g�D�����K)�̕Ґ��̓Q�[���Ղ̏�ɂ��邾���ł������B����v
�u�Q�[���Ձv�Ɩꂽ�̂̓T���X�N���b�g��u�A�V���^�[�p�_(ashtapada)�v�ł��B���̌�͋I���O�ɐ��������p�[����̌��n���T�w����ʌo�x�̒��Ɍ����܂����A�u8�~8�}�X�̃Q�[���Ձv���w���Ă��܂��B���̌o�T�ŕ��ɂ͒�q�����ɑ��ēq���⏟�����ɒ^���ďC�s�����낻���ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ɖ��߂Ă���̂ł����A���̏C�s�̎ז��ɂȂ鏔�X�̗V�т̍ŏ��ɋ������Ă���̂����̃A�V���^�[�p�_��p����Q�[���ł����B�}�X�ڂ̐��̓`�F�X�ՂƓ����Ȃ̂ŁA���Ă̓C���h�ł͊��ɋI���O�ɏ����ނ��V��Ă����Ƃ��錩��������܂����B�������A�Q�[���j�̌����҂̑吨�́A�����ނ̐������I���O�ɋ��߂邱�Ƃɔے�I�ł��B�I���O�ɃC���h��8�~8�̔Ղ�p�����Q�[�����V��Ă������Ƃ͊m���ł����A������`�F�X�̂悤�ɁA��ނɂ���ē����̈قȂ���p���ĉ���ǂ��l�߂�Տ�̐푈�Q�[���Ƃ͑S���قȂ�Q�[���������ƍl�����Ă��܂��B����ɑ��āA��ɋ��������l�o�[�i�̌��t����́A�u����8�~8�̔Տ�Ŏl��̌R����p���Đ키�Q�[���v�Ƃ����C���[�W�������яオ���Ă��܂��B��������A���j�Ƃ����́A�x���Ƃ�7���I�܂łɂ̓C���h�ŏ����ނ̃Q�[�����s���Ă������Ƃ͊m�����Ɛ��肵���̂ł��B
�@����Ƀy���V�A�̌ÓT�̋L�q����A�����ނ̃Q�[�����u�`���g�����O(chatrang)�v�Ƃ������O��6���I���ɃC���h����y���V�A�鍑�ɓ`����ꂽ�\�������肳��܂����B�y���V�A��7���I���ɃC�X���[�����͂ɖłڂ���܂������A�����ނ͒�������ɓ`����A��V���g�����W(shatranj)��Ƃ��đ嗬�s����悤�ɂȂ�܂����B�����ăC�X���[�����E���璆�����[���b�p�ɓ`����ꂽ���̃Q�[������`�F�X���������܂��B
�@���̂悤�ɃC���h�N�����ɗ����ď����ނ̓`�d�ƃ`�F�X�̐����ߒ��𐄒肵�Ă݂܂����B���̌o�H�̓C���h���琼�Ɍ��������̂ł����A���ɃA�W�A�e���ɂ͈ȉ��̕\�Ɏ����悤�ɓƎ��̏����ނ�����A��̐��Ɍ������[�g�ȊO�ɂ��A�k�����̃��[�g�Ɠ쓌�����̃��[�g�����邱�Ƃ������ł��܂��B
�@�����E�̎�ȏ����ނƂ��̋�
|
�Ñ�C���h�̓`���I�R���Ґ�
|
��
|
�ږ⊯
|
�ە���
|
�R�n��
|
��ԑ�
|
������
|
���̑�
|
|
�C���h
|
�`���g�D�����K(����)
|
��
|
�ږ⊯
|
��
|
�n
|
���
|
����
|
�\
|
|
�y���V�A
|
�`���g�����O(����)
|
��
|
��b
|
��
|
�n
|
���
|
����
|
�\
|
|
�T�}���J���h�i�A�t���V�A�u�̋�j
|
��
|
���q
|
��
|
�n
|
���
|
����
|
|
|
�C�X���[��
|
�V���g�����W
|
��
|
��b
|
��
|
�n
|
��
|
����
|
�\
|
|
���[���b�p
|
�`�F�X
|
��
|
����
|
�m��
|
�R�m
|
��
|
����
|
�\
|
|
����
|
�V�����`�[(�ۊ�)
|
�����
|
�m��d
|
�ۥ��
|
�n
|
�ԥ��
|
�����
|
�C��{
|
|
���N����
|
�`�����M(����)
|
����^
|
�m
|
��
|
�n
|
��
|
�����
|
��
|
|
�����S��
|
�V���^��
|
�M��
|
��
|
�p�k
|
�n
|
����
|
���q
|
�\
|
|
�~�����}�[
|
�V�b�g�D�C��
|
�剤
|
����
|
��
|
�n
|
���
|
����
|
�\
|
|
�^�C
|
�}�b�N���b�N
|
�N
|
��
|
��
|
�n
|
�D
|
�L
|
�\
|
|
�W������
|
�`���g��(�J�g�D��)
|
��
|
���R
|
��
|
�n
|
���
|
����
|
�\
|
|
���{
|
����
|
�ʏ�
|
����
|
�⏫
|
�j�n
|
����
|
����
|
��Ԋp�s
|
�@�����ނ��`�d���Ă��������C�����[�g�́A�ȉ��̎O�ʂ肾�����ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B
(1) �����[�g����C���h �� �y���V�A �� �C�X���[���� �� ���[���b�p���i�`�F�X�̐����j
(2) �k���[�g����C���h �� (�y���V�A) �� �����A�W�A �� ���� �� ������ (�ۊ�(�V�����`�[)�̐���)
(3) �쓌���[�g����C���h �� (�x���K���E�X�������J) �� ����A�W�A (�~�����}�[�E�^�C�����Ȃǂ̐���)
�@�A�W�A�̏����ނ̂�������Љ��̂́A���N�����̏����E�`�����M�ƃ����S�������E�V���^���ł��B�`�����M�́A�V�����`�[�Ƃ̗މ����������Ȃ̂ŁA�k���[�g�ŃV�����`�[�̌��^������������Œ��N�ɓ`����ꂽ�\�����傫���ł��傤�B�`�����M�͖k���[�g�̓��B�_�̈�ł����Ƃ�����ł��傤�B
����ɑ��ăV���^���̋�͗�������ŁA�ꌩ�����Ƃ��뒆���ۊ��Ƃ͑傫����������Ă��܂�����A���̌o�H�Ńy���V�A����`������Q�[����������܂���B�������A�k�̌o�H�Ɏx����z������A������̃��[�g�ɉ����ē`����ꂽ�ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B
�@����ɓ쓌���[�g�œ`����ꂽ���̂ɂ́A�~�����}�[�E�^�C�̏����̂ق��ɁA�}���[�E�C���h�l�V�A�̏����ނ�����܂��B�����ɂ͂��ꂼ��Ǝ��̋�p�����Ă��܂��B���̒��ɂ̓��[���b�p�̐i�o�̉e���ŊT�˃`�F�X�Ɠ����w�����ɂȂ��Ă�����̂�����܂����A���X�̓C���h����`����ꂽ�����ނ����ɂ���ƍl�����܂��B����瓌��A�W�A�̏����ނɂ��ẮA������グ�邱�Ƃɂ������Ǝv���܂��B
1.���N�����̏���(�`�����M)�Ƃ��̋�
�@�M�҂͓�\��㔼�ɂȂ�܂ŁA���N�����ɂ��u�`�����M�v�Ƃ����Ǝ��̏����ނ̃Q�[��������Ƃ������Ƃ�S���m��܂���ł����B�悤�₭��\��̏I��荠�ɑ���G�ꎁ�́w�����x(1977�N���B�O��Љ�ς�)��ǂ�ŁA���߂ă`�����M�̑��݂�m�����M�҂́A���̎w������Ջ�ɂ��Ă��A�����Ə������Ǝv���܂����B�������A�s���̓`���Q�[�����X�ɂ́A�����ۊ��̔Ջ�͔����Ă��܂������A���N�����ƂȂ�Ƃ��X�̕����u�u�������Ƃ�����܂��A�S��������܂���v�Ƃ��������ł����B�܂��A�}���قɂ��W�����͂Ȃ��Ȃ���������܂����B
�@���̌�A���܂��ܒ��N�j�ɏڂ������ƒm�荇���@�����܂����̂Őq�˂Ă݂�ƁA�`�����M�͒��N�����ł͂ƂĂ��|�s�����[�ȃQ�[�������V�Y�@�Ȃǎ��ۂ̏ڍׂ͕�����Ȃ��Ƃ����������ł����B����ł��m�l�́u�Ջ����ł��Ȃ������ׂĂ݂悤�v�ƌ����Ă���܂����B���̌㐔�N�o���ď��a�̏I��荠�A�������q�˂����Ƃ�Y��Ă����̂ł����A��̒m�l����u���ɂ��钩�N�̖����ߑ��▯�|�G�݂̓X�ňȑO�����Ă����悤���v�Ƃ�����͂��܂����B�����ŁA�����Ă�������X�ɍs���ăv���X�e�B�b�N���̃`�����M�����w�����邱�Ƃ��ł��܂����B�Ղ̕��͂��Ȃ荂���ōw����f�O�����삷�邱�Ƃɂ��܂����B�������ĔՋ�͑����܂������A��̓����ɂ��ẮA���Ȃ��Q�l�����̒��ɂ���͂��ȏ��𗊂�ɂ��āA�������ԂƋ��Ɏ�T��ʼn��x��������Ă݂܂����B����������ł͂ƂĂ��ǂƂ͂����Ȃ������Ǝv���܂��B
�@�����̎���ɓ���ƁA�`�����M�Ɋւ���{�����������s�����悤�ɂȂ�܂����B2000�N�ɂ͔Ջ�t���œ��发�����s���ꂽ�̂ōw�����܂����B���̎��ɓ��肵���ՂɁA�ȑO���ōw�������v���X�e�B�b�N���z�u�����̂������̎ʐ^�ł��B���̓��发�����Ȃ���A���̔Ջ�𗘗p���ď��Ղ̋�g�����x���w���i�߂邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B���Ƃ����Ĉ�x�́A�`�����M�ŏ����𑈂��ǂ����������̂ł����A���܂��ɋ@��͖K��Ă���܂���B�܂��A�{�i�I�Ȗؐ��̒�������肵�����̂ł����A�\�E���ł��̔�����Ă���X��������͓̂���悤�ł��B�����Ƃ̕��̏����i�␢�E�̏����̓W����Ŕq���������Ƃ͂���̂ł����A�����ɓ���Ɏ����Ă���܂���B
�@���āA�`�����M�ɂ́A�ȉ��Ɏ�����̊�{�I�ȓ_�ŃV�����`�[�Ƌ��ʂ������������܂��B
�@ �Տ�̃}�X�ڂ̒��ł͂Ȃ����̌�_�ɒu���ꂽ�������B
�A �Ղ̏㉺������4�̃}�X�ڂɎΐ��������Ă���A���Ƒ�b�̋������̂͂��̋��������ł���B
�@���̓�̓�����L���鏫���ނ́A�V�����`�[�ƃ`�����M�����ł��B�]���āA��̃Q�[���ɂ͐[���މ���������Ƃ����܂��B�`�����M�̌Â������͏��Ȃ��A�Q�[���Ƃ��Đ����������j�I�o�܂ɂ��Ă͖��炩�ł͂���܂��A12���I���܂łɂ͒������璩�N�����ɓ`����ꂽ�Ƃ���Ă��܂��B���Ȃ蒷�����j��L���邱�Ƃ͊m���ł�����A���R�Ȃ���V�����`�[�Ƃ͈قȂ����������������܂��B
�@�ȉ��ɂ��̓Ǝ����̂�����ȓ_�����q�ׂ܂��i�ڍׂ͍Ō�Ɏ����Q�l���ڂŊm���߂ĉ������j�B
�@ �V�����`�[�Ƃ͈قȂ�A�Ղ̌`�͏c���ł͂Ȃ������ł���B�܂��A�Ղ͉͊E�ŋ���Ă͂��Ȃ��B
�A ��͔��p�`���嗬�ł��� (���������m�Ȍ��܂�͂Ȃ��A�~�`��Z�p�`�A�̎}���ɂ��������̑f�p�Ȃ��̂�����)�B�\�ʂɋ�̖����ԂƐŏ�����Ă���B(�Ԃ͞����Ő͑����B�����ł�)
�B �n�ƎԂ̋�̓����̓V�����`�[�Ɠ��������A���̑���5��̋�̓����̓V�����`�[�Ƃ͈قȂ�B
�i���́u�`�����M�̔Ջ�Ƌ�̓��������v�������������B�Ȃ��ڍׂ͎Q�l�����Ŋm���߂ĉ������B�j
�C �J�ǎ��ɔn�Əۂ̋�����ւ��Ĕz�u�ł���(�������A�n�n�E�ۏۂ̔z�u�͋֎~�ł�)�B
�D �w������p�X���邱�Ƃ��ł���B�o�������Ƀp�X������Έ��������ɂȂ�B
���`�����M�̔Ջ�Ƌ�̓�������
�@
�@�Ō�Ƀ`�����M�̋�ɂ��ď����q�ׂĂ݂����Ǝv���܂��B��̊؍����v����͔��p�`�ł����A��ɏq�ׂ��悤�ɁA��`�Ɋւ��錈�܂肪����킯�ł͂Ȃ��A�ؐ��̏ꍇ�͘Z�p�`��~�`�A�����͒P�ɖ̎}����������̂��̂�����悤�ł��B�Â��͖̎}���ɂ��A���̕\���ɕ����������ċ�ɂ����Ƃ���Ă��܂��B��ނ́A�R��Ɏ�������u�l�Y�̖v���D�܂�܂����B���̃l�Y�̎}�͗�ɂ���Ɣ��p�`�Ɏ����`�ɂȂ�܂��B�܂��A��[�����畺���Ǝm�̋�����܂��B���ɁA�����������߂̕������ɂ��Ĕn�E�ہE��E�Ԃ̋�Ƃ��܂��B�����āA�}�̍�������������ł����������̓L���O�ɓ����銿�^�̋�Ƃ��܂��B���̂悤�ɑf�p�Ȃ����ŋ�����̂ŁA�`�����M�̋�͎�ނɂ���đ傫���̈قȂ锪�p�`�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ�����������悤�ł��B
2.�����S���̏���(�V���^��)�Ƃ��̋�
�@�M�҂������S�������E�V���^���̂��Ƃ����߂Ēm�����̂́A����G�ꎁ�́w�Տ�V�Y�x(1978�N)�̒��̋L�q��ǂ��ł����B�Ղ̓`�F�X���l�s���͗l�A�r�V���b�v�̋�p�k�̌`�ɂȂ��Ă���ʐ^�����āA�����Ƃ��Ắu�����S�������́A��̌`�������ԈقȂ��Ă��邯��ǎw�����̓`�F�X�ƂقƂ�Ǔ������낤�v�Ƃ�����ۂ������܂����B
�@���̌�w�������E�x��1994�N11�����Ɋ��m�̖ؑ��`����i�ɂ��u�����S�������@�V���^���v�Ƃ������|�[�g���f�ڂ���A�����ǂ�œ��������S���ł͎l��ނ̏����ނ��V��Ă��邱�Ƃ�m��܂����B���Ȃ킿�A(1)�u�`�F�X�v�E(2)�u�`�F�X�Ɠ��������̃����S������(�V���^��)�v�E(3)�u��^(10�~10)�̃V���^���v�E(4)�u�`�F�X�����ア�����̃V���^���v�̎l�̃Q�[���ł��B�`�F�X�̑��Ƀ����S�����������邱�Ƃ͗����ł��܂������A���̃����S�������̎w�����������ň�肵�Ă��Ȃ����Ƃɂ��Ȃ�������o���܂����B
�@�����炭�A�����`���I�ȃ����S��������(3)��(4)�̓�̃^�C�v�������̂��낤�Ǝv����̂ł����A�Љ��`����ɂ̓\���B�G�g�A�M�̋����e���̉��Ŗ��������݂�ꂽ�̂�������܂���B���[���b�p�̃`�F�X���D���ɂȂ��Ă����܂����B�u�V���^���v�Ƃ̓`�F�X�̂��Ƃ��Ӗ����A�`���I�ȃ����S�������́u�����S���V���^���v�ƌĂꂽ�������������悤�ł��B
�@�Љ��`�̖���\�A�̑̐������Ă���́A�����S���ł����剻���i�݁A�����̖��������ĕ]������@�^�����܂��悤�ɂȂ�܂����B���傤�ǂ��̍��ɁA�����S���̃V���^���W�̒c�̂̕��������A����K��V���^������̉����s���܂����B�ؑ���i�͂������ꂽ�̂ł��B�����炭�A�V���^���̔Ջ�Ǝw�����ɂ��ďq�ׂ�ꂽ�ŏ��̓��{�ꕶ���Ƃ����Ă悢�ł��傤�B
�@����ɔ~�ьM���́w���E�̏����x(1997�N��)�A����L���́w���E�̎�ȏ����x(1999�N���E2005�N����)�Ȃǂ��������Ŋ��s����A�����̒��ŃV���^���Ƒ�^�V���^��(�q���[�V���^��)�̎w�������������Ă��܂��B�����̏����̒��ł��A8�~8�̔Ղ�p���鏬�^�̃V���^���ɂ��ẮA�Љ��`����ɗD���ɂȂ����u�`�F�X�Ƌ�̓����������V���^���v�Ɠ`���I�ȁu�`�F�X������̓������ア�V���^���v���������Ă��邱�Ƃ��L�q����Ă��܂��B
�@���̏ꍇ�u�������ア�v�Ƃ́A�x���X(�ՁF�N�C�[��)�ƃe���[(�p�k�F�r�V���b�v)�̋�ɂ��Č����Ă���A���̑��̋�̓`�F�X�Ɠ������������܂��B�e���[�́A�ߎ��R�̓���(�`�F�X�̃r�V���b�v�Ɠ���)�̑��ɁA�߂�1�`3�}�X�܂ł����i�߂Ȃ��Ƃ����u�ア�����v�Ŏw�����ꍇ������܂��B���ɑ傫�ȈႢ��������̂́A�N�C�[���ɓ�����x���X(��)�̋�ŁA�O�ʂ�̎w����������܂��B����́A
(a)�c���ߎ��R�Ƃ����ŋ��̓���(�`�F�X�̃N�C�[���Ɠ���)
(b)�߂�1�}�X�݂̂Ƃ����Ŏ�̓���(�����̃N�C�[��)
(c)�c�����R�v���X��1�}�X�Ƃ�������(���{�����̗����Ɠ���)
�̎O�ł��B���̐}�ł�(c)�̓������Љ�Ă��܂����A���ł����ꂳ�ꂽ�w�����͊m�����Ă��܂���B�Ƃ͂����A��̖ؑ���i�̃��|�[�g�ɂ��u�����S���͐l����S���l�قǂ����A�����t�@�������āA�قƂ�ǂ̒j�����v���[����ƕ������v�Ƃ����L�q������A���̋L�q���`�F�X���w���ꍇ���܂�ł���Ƃ��Ă��A�V���^���͂��Ȃ胂���S�������ɒ蒅�����Q�[���̂悤�ł��B
�@10�~10�̔Ղ�p�����^�́u�q���[�V���^���v�ɂ��ẮA���Ɍf����Q�l�������Q�Ƃ��ĉ������B
�@�Ȃ��A�����̎ʐ^�̔Ջ�́A��f�̉��쎁���w���E�̎�ȏ����x�̒��ŏЉ��Ă������s�̖f�Չ�Ђɖ₢���킹�����čw���������y�i�̃V���^���ł��B��͂����炭�����ő���͂��e�����̂ł����A��̌`�͖��m�Ɏ��ʂł��܂��B�Ղ͏c����24cm����܂����A�܂肽���݂ɂȂ��Ă��Ă��̒��ɋ�����߂܂��B�V���^���ɂ͑��ɋ�������ؐ��̗�����������Ă��܂��B�����͍�����ł��̂ł��Ȃ荂���ł����A�C���e���A�p�̖��|�i�Ƃ��Ă̎��v������A�����S������A�o����Ă�����̂�����悤�ł��B
���V���^���̔Ջ�Ƌ�̓�������(�ʐ^�͋�̌`��������悤�ɉ�����B���Ă݂܂���)
�@
�Q�l����
������A�ȉ��̎������Q�l�ɂ��܂����B���҂̕��X�ɐ[�����Ӑ\���グ�܂��B
�� ����G��w�����T�x(�@����w�o�ŋǁA1977�N)
�� ����G��w�Տ�V�Y�x(�@����w�o�ŋǁA1978�N)
�� �~�ьM�w���E�̏����x(�����V���ЁA1997�N)�@ (����L���Ƌ����̉����ł�2000�N�Ɋ��s���ꂽ)
�� ����L�w���E�̎�ȏ����x(����o�ŁA1999�N�A�����ŁA2005�N)
�� ����L�w���m�̏����x(��㏤�Ƒ�w�A�~���[�Y�����g�Y�ƌ������A2007�N)
�� �p�����w�u���N�����v�̎�قǂ�(�����)�x(���h�����A2000�N)
�� ����L�w�`�����M���W�i��j�x(����o�ŁA2002�N)
�� �������w�����̗������x�i�߂���A1986�N�j
�� �ؑ��`���u�����S�������@�V���^���v(�w�������E�x1994�N11����)
�� �����N��u�����`���čl�v(�����l�Êw�������I�v�w�l�Û{�_���x��36���A2013�N�f��)
�`���g�D�����K�Ƃ�����́A�Ñ�C���h�̑�\�I�ȌÓT�Ƃ��Ēm���Ă���w�}�k�̖@�T�x�A�w�}�n�[�o�[���^�x�Ȃǂɂ��R���p��Ƃ��ėp�����Ă��܂��B�Ȃ��ł��I���O2���I����I����2���I���ɐ��������Ƃ����J�E�e�B�����́w�����_�x�ɂ͎l�R�̕Ґ����̑����ڂ����q�ׂ��Ă��܂��B�������A�����̌ÓT�����ɋL���ꂽ�u�`���g�D�����K�v�́A�Q�[���ƑS�����W�ł���ƌ���ׂ��ł��傤�B
���̌o�T�̖M��ł��u���ڂ̏����v�Ƃ�����ꂪ�^�����Ă�����̂�����܂��B(�w���E�̖���1�o�������o�T�E���n���T�x�u�o�Ƃ̌���(����ʌo)�v�������_�Њ��A1969�N�A521��)
�y���V�A�̌ÓT�I�����ɂ́A6���I�T�T�����̎���ɍ݈ʂ�������̉���Ǝ]����ꂽ�z�X���[1���̓������ɃC���h�̉�����g�߂��h�����ꂽ�Ƃ������b������܂��B����́A�C���h����y���V�A�ւ̏����ނ̓`�������̂ł��B���̎��g�߂́A��łł���1�g�̏����ނ̃Z�b�g�����Q���A�y���V�A���ɑǂɂ��m�b��ׂ݂܂����B������ė������̂��y���V�A���Ɏd���Ă������҂ł����B�����Q�[����S���m��ʂ͂��̔ނł������A�C���h�̎g�߂�3�ǐ���đS�����u�����̉��v�̌��Ђ�������̂ł��B���̕���̓y���V�A�œ`�����A�ÓT�I�����w�V���[�i�[��
(����)�x(11���I����)�ɂ��`����Ă��܂��B���́w�����x�ɂ�14���I���ɑ}�G���������A���݂ɓ`����Ă��܂� (����URL�������������B���̊G�ł͒������ɔՂ�����A���ɃC���h�̎g�߁A�E�Ƀy���V�A�̌��҂������đǂ����Ă��܂��B�����őǂ��ϐ킵�Ă���̂́A�����炭�z�X���[1���ł��낤�Ǝv���܂�)�B
https://metmuseum.org/art/collection/search/140006270?img=1�@
�������A���̓`���͗��j�I�������̂܂܂ł͂���܂���B�������A�z�X���[1���̎��ɑ��ʂ����z�X���[2���̎���A7���I�ɏ����ꂽ�����ɂ͏����ނ��Ӗ�����u�`���g�����O�v�̌ꂪ���L����Ă��܂��B�]���āA���̃z�X���[1���̎���ɏ����ނ��y���V�A�ɓ`�������Ƃ����b�ɂ͂��Ȃ�̌�����������܂��B
�Ⴆ�Ηa���҃��n���}�h�̏����ő�l��J���t�̃A���[(660�N�v)�̈�b�Ƃ��āA�`�F�X���w���Ă���҂Ɂu�N��������S�s���Ɍ��߂Ă������(��̂���)�͉���\�킵�Ă���̂��H�v�Ɛq�˂��̂ɑ��āA�M�k�������u����͂��ŋ߃y���V�A��������ė����Q�[���ł��B�����̋�͕����ł���A�ۂ�n���y���V�A�l�̊��K�ɂ��������Ă��̂悤�Ȏp�ŕ\�킳��Ă��܂��B�v�Ɠ��������Ƃ��`�����Ă��܂��B���̈�b�������Ƃ���A�y���V�A�ƃC�X���[�����ł͂قƂ�Ǔ�����ނ̏����ނ��������Ă����\�����傫���ƍl�����܂��B
�Ñ�C���h�ƌÑ�y���V�A�̏����ނ̋�͊m���Ȏ����j���������Ă���̂ŁA�W�������琄�肵�����̂ł��B�܂��T�}���J���h�ߍx����o�y�����A�t���W�A�u�̋��6�푵���Ă��܂����A���̋��̖��̂��L���������͂���܂���B�\�Ɏ�������̖��̂́A�����҂���̌`���琄�肵�����̂ł��B
�\���̋�̓����͂��ꂼ��قȂ��Ă��܂��B�܂��A������ނ̏����ł�����Ƌ��ɕς���Ă������ꍇ������܂��B�Ȃ��A���{�̏����Ɋւ��ẮA�F��������C�t���Ǝv���܂����A�i�C�g�ƃ��[�N�ɂ�����j�n���Ԃ̋�̗��������Ɏア�Ƃ����̂��ő�̓����ł��B
�`�����M�̋�̐}���ɂ��ẮA�ȉ���URL�������������B
http://history.chess.free.fr/changgi.htm
�܂��A�V���^���̋�̐}���ɂ��ẮA�ȉ���URL�������������B
http://history.chess.free.fr/shatar.htm�@http://history.chess.free.fr/hiashatar.htm
�V�����`�[�����N�����ɓ`�����`�����M���������������͕������Ă��܂���B���ɐV������(355�`935)�ɋ������Ă����Ƃ�����������܂����m���ȍ����͂Ȃ��A���`����������������悤�Ɏv���܂��B�ނ�������������́A�������k�v����������10�`12���I��(���N�����ł͍��펞��ɓ�����܂�)�ɃV�����`�[���`�����A��������ɂ��ă`�����M�̌��^���`�����ꂽ�ƍl���������Ó��ł��낤�Ǝv���܂��B
�����S�������E�V���^����13���I���ɂ͓`�������ƍl�����Ă��܂����A�V�����`�[�Ƃ͑S�������ŁA�y���V�A����̓`�����ƃ`�x�b�g����̓`�������������Ă��܂��B�k�����[�g�Ɏx����z�肷��A�Ƃ����̂͂��̃`�x�b�g�`�����̂��Ƃ��l�������̂ł��B�`�x�b�g�ɂ͂��āu�`�����_���L�v�Ƃ������̏���������ɋ������Ă��܂������A���݂͐l�X�ɖY����قƂ�Ǐ��ł��Ă��܂��B�����A���ċ�����ꂽ�`�����_���L�̋�̌`�̓����S���̃V���^���̋�ɔ��ɂ悭���Ă��܂��B�����ŁA���̃`�����_���L�����}���Ƌ��Ƀ����S���ɓ`�����A��������V���^�������������Ƃ��������������Ă���̂ł��B
(�`�x�b�g�̃`�����_���L�̋�̐}���ɂ��ẮA�ȉ���URL�������������Bhttp://history.chess.free.fr/chandraki.htm)
�`�����M�ɂ��ďq�ׂ�ꂽ�{�̂����A�����}���قœǂނ��Ƃ��ł������̂́A���쎁�́w�����x�̑��ɂ́A���m�̑�������i�����M���ꂽ�w�����̗������x(1986�N)�����ł����B
���N�����ł̃`�����M�̗V�Y�l���͈͌���������A��700���l�Ɛ��肳��Ă��܂��B���E�̏����ނ̒��ł́A�V�����`�[�E�`�F�X�E���{�����Ɏ����ŕ��y���Ă���Ƃ����Ă悢�ł��傤�B�������A�����Տ�V�Y�̈͌�Ɣ�r�����ꍇ�A�͌�͏㗬�K���̗V�тŃ`�����M�͏����̗V�тƂƂ炦����X��������悤�ł��B�w�����̗������x�ł́A�`�����M�̏��������������������̂ƂȂ邱�Ƃ��Љ��Ă��܂��B���Ƃ��āA����̋����鎞�Ɏ����̋��̋�ɒ@�����Ă������Ȏw����������ꍇ������܂����B���̂悤�ɂ��ċ�������̂́A�܂��Ɂu�g�����v���v�ł��傤�B�Ƃ��낪��������Ĉ�ԋ�������̂́A�ǂ���������l�X�ł����B�ނ�̓`�����M�̏����Ƀh���}�����҂��Ă����̂ł��B�����Ƃ��A���̂悤�ɋ��@������悤�Ȏw�����́A���݂̓}�i�[�ɔ�����u���K�v�ƍl�����Ă���悤�ł��B(�p�����w�u���N�����v�̎�قǂ�(�����)�x���Q�l�ɂ��܂���)
���X�ɂ́A�v���X�e�B�b�N��̑��ɖؐ��̃X�^���v�������܂����B�����A���p�`�ł͂Ȃ��A�V�����`�[�Ɠ����~�`�ł����B�܂��A���Ȃ荂���Ȃ̂ɃX�^���v��������s�N���ł����̂ŁA�v����̕����w�����邱�Ƃɂ��܂���
(��Ŗؐ���̏ꍇ�͉~�`�����邱�Ƃ�m��܂������A���̎��̓V�����`�[��Ɠ������Ǝv���Ă��܂��܂����B���m�������̂ł���)�B�Ղ������Ă��������܂������A�����ꖇ�ł���̂ɁA��������i�����Ȃ荂���A�c�O�Ȃ���ϋɓI�ɍw�����悤�Ƃ����C�����ɂ͂Ȃ�܂���ł����i���X�̕����u���ꂭ�炢�Ȃ�A���q�������ō����ˁv�ƌ����Ă����܂����j�B
�O�f�̒��ɂ��������w�u���N�����v�̎�قǂ�(�����)�x�ł��B
�Q�l���ڂɋ����������N�́u�����`���čl�v���Q�Ƃ��܂����B
����L���́w�`�����M���W(��)�x8p�A�y��52,53p���Q�Ƃ��܂����B�Ȃ��A���Ȃ�Â��ؐ��̃`�����M�Ջ�̐}���͋r��6�Ɍf�ڂ����T�C�g��URL�Ahttp://history.chess.free.fr/changgi.htm�������������B
�����S���̃V���^���̌���ɂ��āA����i���́u�V���^���̋�͓s�s�ɕ�炷�l�͂������A�c�ɂɂ����Ă������Ă���Ƃ����B�q���V���^���ɂ̂߂肱�ސl������B�����S���`�F�X�A����1930�N�Ɍ�������A1955�N�ɍ��ۘA���ɉ��������B���݁c�V���^���A�q���[�V���^���A�`�F�X�̑��N�ɉ�����J�Â���Ă���Ƃ����B�v�Əq�ׂĂ��܂��B(�w���m�̏����x161p)
�V���^���̖{�i�I�ȔՋ�̐}���́A�r��6�ŏЉ��URL�̑��ɁA���{�����A����HP�Ō��邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A10�~10�̑�^�̃q���[�V���^���̔Ջ�̐}���́A�uChess�Ə����̒��ԁv�Ƃ����T�C�g�ɂ����邱�Ƃ��ł��܂��B
�@���ĕM�҂������̃V���^������w���������ɃV���^���̖ؐ����������������̋�������Ă���ƌ����܂������A���̉��i�����ɍ����ł����B���݃C���^�[�l�b�g�ȂǂŃV���^���̋����ł��邩�ǂ����͎c�O�Ȃ���s���ł��B
��������̂������@�ԊO�҂T�F�A�W�A�̏����ނ̋�(2)�^�C�ƃ~�����}�[�̏����Ȃ�
�@�u�ԊO��2�v���琢�E�̏����ނ������Ă����V���[�Y���A����A�W�A�����̏����Ƃ��̋���e�[�}�Ƃ�������́u�ԊO��5�v�ň���ƂȂ�܂��B������M�҂̗���s���▾�m�Ȍ�肪���X����Ǝv���܂��B�\�ߓǎ҂̊F����ɂ͂����e�����肢�������܂��B
�@�͂��߂Ɂ@����A�W�A�̕����Ə����ނɂ���
�@����A�W�A�ɂ����Ă������̍��X�Ń`�F�X���������Ă��܂��B���̔w�i�ɂ͋ߑ�ȍ~���[���b�p�����������̍��X�ɐi�o���ĕ����I�ɋ����e����^�����Ƃ������j������܂��B�܂��A�V�����`�[�̑ǂ����Ȃ葽�������܂��B����A�W�A�ɂ͉؋��̐l�X�������Z��ł���A�V�����`�[���̂��̂̈��D�͔ނ炪���S�ł����A���ꂾ���łȂ��A���F�g�i���̏����u�J�[�g���v���V�����`�[�ƂقƂ�Ǔ���̃Q�[���Ȃ̂ŁA���̋��Z�l�������Z���邱�Ƃ��ł��܂��B
�@����������A�W�A�ł́A�`�F�X��V�����`�[�ƈقȂ�Ǝ��̏����Q�[�����������Ă��鍑������܂��B���̑�\���^�C���~�����}�[�ł��B���̓�̍��ł́A�Q�[���̃��[������̌`���`�F�X��V�����`�[�ƑS���قȂ鏫�����������݂��܂��B���̂����A�~�����}�[�̏����E��V�b�g�D�C����́A���ď������㗬�K�w�ɂ���������Ă��Ȃ��������ߋ��Z�l��������߂ď��Ȃ��A���̂܂܂ł͖Y�ꋎ���Ă��܂��Ɗ뜜���錩��������܂��B����ɑ��ă^�C�̏����E�u�}�b�N���b�N�v�́A�ߔN������l���������Ă͂�����̂́A�ˑR�Ƃ��ă`�F�X��V�����`�[�ɕC�G���鋣�Z�l����L����Q�[���ł��B�^�C�����݂̂Ȃ炸�ߗׂ����I�X���J���{�W�A�ł����l�̏�������������Ă���A�u���E�ܑ叫���v�̈�ɐ����������Ƃ�����܂��B
�@���̃V���[�Y�ł́A�O���ރC���h�N������O��ɂ��Ă��̓`�d���O�̓����l���܂����B�����āA���̎O�Ԗڂ��쓌�����ւ̃��[�g�ł����B����́A�k�C���h�̃K���W�X�͗���ŗV��Ă�������(�`���g�D�����K)��������̃x���K���n���A��C���h�A�Z�C�������Ȃǂɓ`�d���A���̌㓌��A�W�A���ɍL�����Ă������\����\���Ă��܂��B�^�C�ƃ~�����}�[�̏����́A���������쓌�����̌o�H�̂����ꂩ�ɂ���ē`����ꂽ���̂ł���A�C���h����������A�W�A���ɋy�ڂ����e���̈���ƍl�����܂��B
�@����ɑ��āA����A�W�A�ɂ́A���F�g�i���̂悤�ɃC���h����������������̉e�����傫��������������܂��B��ɏq�ׂ��悤�ɁA���F�g�i�������J�[�g���͒����̃V�����`�[�Ɠ��ނ̃Q�[���ł����A����ɂ͖��炩�ɒ��������̗��j�I�e��������ƍl�����܂��B�܂����F�g�i���ƃ^�C�ɋ��܂ꂽ�J���{�W�A�ł́A�^�C�����ƒ����ۊ������ɋ������Ă��܂����A���̍��͏����ނ̓`�d�ɂ����ăC���h�ƒ����̉e���̋��E�Ƃ����邩������܂���B
�@�}���[�����ƃC���h�l�V�A�̏ꍇ�A���j�����̌`���͂����Əd�w�I�������悤�Ɏv���܂��B���̌���͏��߃q���h�D�[���╧���𒆐S�ɃC���h��������e�����Ă��܂����B�������A13���I�ȍ~�ɃC�X���[�������`����ꂻ�̌�̃��X�������l�̊����Ƒ��ւ��ăC�X���[���������Z�����Ă����܂����B�����16���I�ȍ~�ɂ̓��[���b�p�l�̉��Ő��m�����̋����e������悤�ɂȂ�܂��B
�@�}���[�����ƃC���h�l�V�A�n���̏����ނ̓W�J�ƌ���ɂ��O�������̏d�w�I�e�����W���Ă���̂�������܂���B�����̍��X�ɂ��`�F�X�Ƃ͈قȂ鏫���ނ̋��������܂��B����A�`D�̐}���͂�������}���[�����ƃC���h�l�V�A���\���鏫���ނ̋�ł��BA�̓C���h�l�V�A�E�o�����̋�̎ʐ^�ł��B�`�F�X��Ƃ͑S���قȂ�O���ŁA�L���O�̋�̓V���@�_������(�K���_)�ɏ�����p�ɒ����A���̋�ɂ��q���h�D�[�����̕��͋C���������܂��B���������̋�́A�ό��q�p�̖����I�H�|�i�Ƃ��đ�����悤�ɂȂ��������ŁA�`�F�X���`������ȑO�̌Â������ނ̋�`��\���������̂ł͂���܂���B���̒n���ɂ����ăC���h�̕����̉e���������Â�����̋�����o���̂͂��Ȃ����悤�ł��B���҂̒��ɂ́A�C���h����̏����ޓ`�d�̓��́A�~�����}�[�ƃ^�C�܂łł����āA���̓�ɂ܂ł͋y��ł��Ȃ��Ƃ��錩��������܂��B
�@���}���[�����E�C���h�l�V�A�̏����ނ̋�̗� �@(������������牤�E��b�E�ہE�n�E��ԁE�����̋�)
�@�@
�Ƃ͂����A���m��������������ȑO�ɂ��̒n���ł����n�̐l�X�ɂ���ď����ނ��������Ă����A���̍ۂɃ`�F�X�Ƃ͈قȂ��p�����Ă����̂͊m���ł��B�܂��A19���I�ɂ��̒n���̖����������������m�̌����҂́A�X�}�g�����k���̐�Z�����̐l�X���Ǝ��̏����ނ���Ɉ��D���Ă����ƕ��Ă��܂��B����ɁA���̏�ŋ���đǂ���������q�ׂ��Ă��܂��B�n�ʂ⏰�ɐ��������ĔՂƂ��A�_�炩���؍ނ��葁������ċ�Ƃ��Ă����̂ł��B���̒n���Ŏ��ۂɋ�����ꂽ�����ނ̋�̌`���L�^�����̂��}��D�ł��B���̐}�����番����悤�ɑf�p�Ȍ`�ł��̂ŊȒP�ɑ��邱�Ƃ��ł����̂ł��傤�B
�@�ߑ�܂œ`�����Ă����}���[�n���̏����ނ̋B��C�ł��BB��19���I�ȑO�̃}���[�n���̏ۉ吻�̍�����ł���AC��19���I�㔼�Ƀ}���[�����̉p�ی�̃Z�����S���̖��������������l�ފw�҂�W.W.�X�L�[�g(1866�`1953)�����n�ŏN�W������ł��B���ꂼ��`�͈قȂ�܂����A�C�X���[�����Ɍ�����`�F�X��̓����������Ă��܂��B����������ƁA�}���[�����Ȃǂ̐l�X�������ނɋ�����悤�ɂȂ����̂̓C�X���[���̐l�X�̉e���������̂ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B�����A�}���[�����ŋ������Ă��������ނ͢�`���g��������͢�J�g�D����Ƃ������ł����A���̌ꌹ�̓T���X�N���b�g��́u�`���g�D�����K�v�ł����A��̖��O�ɂ��C���h�ÓT�̃T���X�N���b�g����C���h�̃^�~����ȂǂɋN��������̂��������߂Ă������Ƃ���A�C���h�����̉e���͖����ł��Ȃ��ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�������}���[�V�A�E�C���h�l�V�A�Ȃǂɂ����ẮA���݂��������`���I�ȏ����ށu�`���g���v�͖Y�ꋎ���Ă���A�̂̓`���I��p������P�[�X���قƂ�ǂ���܂���B���Č��n�̐l�X���ǂɋ������`���I�����ނ͂قڊ��S�Ƀ`�F�X������Ă��܂����ƍl���Ă悢�Ǝv���܂��B
1.�^�C�̏���(�}�b�N���b�N)�Ƃ��̋�
�@�^�C�����̢�}�b�N���b�N(�}�[�N���b�N)��Ƃ������̂ɂ͈�̋^�₪����܂��B����́A�^�C��u�}�b�N���b�N�v�̖{���̌ꌹ�̈Ӗ��͉��Ȃ̂��Ƃ������Ƃł��B�M�҂Ƃ��ẮA���������m�̕�������������������������������Ǝv���Ă���܂��B�^�C��������ʂɃC���h�N�����ƍl�����Ă���ɂ�������炸�A���́u�}�b�N���b�N�v�Ƃ������̂̓C���h�́u�`���g�D�����K�v�ƌꌹ�I�q����͂Ȃ��Ƃ���Ă��܂��B�u�}�b�N�v�͑��̃Q�[���ނɂ��܂܂�Ă���̂ŁA���炩�̃Q�[���ނ������̂�������܂���B�܂��u���b�N�v�̕��́A�u���܂����v�Ƃ����Ӗ��Ƃ���Ă��܂��B�}�b�N���b�N�̑ǂʼn�������鎞�͕K���u���b�N�v�����́u���b�N�E�N���v�Ɛ錾���邱�ƂɂȂ��Ă��܂����A����͓G�̉��ɒ��݂�����Ƃ������ƂȂ̂�������܂���B�L���O��œ|���錃�����������Q�[���ɂ������̂ł��邱�Ƃ�\���Ă���̂ł��傤���B
�@�����{�ɂ�����}�b�N���b�N�̔F�m�x
�@�����炭����A�W�A�̏����ނ̒��ň�ʂɍł��悭�m���Ă���̂̓}�b�N���b�N���Ǝv���܂��B20�N�ȏ�O����^�C���̃v���X�e�B�b�N����{�ɂ��A������Ă���A�e�Ղɓ���ł��܂����A��������o�ł����悤�ɂȂ�܂����B�܂��A�p�\�R���p�ǃ\�t�g�����삳�ꂽ���Ƃ�����܂��B
�@������1970�N�㏉���܂ł́A�䂪���ɂ����āA�^�C�ɂ��Ǝ��̏���������Ƃ������Ƃ�m��l�͂قƂ�ǂ��܂���ł���(�������M�҂��S�����̑��݂�m��܂���ł���)�B1970�N��ɏ�����厏�Ȃǂő������Ŏ��グ����悤�ɂȂ��Ă悤�₭�����t�@���Ȃǂ̊ԂɃ^�C�����̑��݂�������x�m����悤�ɂȂ�܂����B���̌�1982�N�Ɋ�������قɁu���������فv���J�ق������A���E�̏����ނƂ��āA�`�F�X�A�l�l���`���g�����K�ɉ����Ē�������N�̏����Ȃǂƕ���Ń^�C�����̔ՂƋ�����ݓW������܂����B����ɁA1986�N�ɂ͑�������i�́w�����̗������x�����s����܂����B���̖{�́A�����i���^�C�E�����E�؍��E�C���h�𗷂��钆�Ō��n�̐l�X�Ƒǂ����Ȃ��珫���̓`�d���l����Ƃ������e�ł������A6��̋�̐������Ăі��Ƃ��̖��̈Ӗ������߂ċ����ċ�̓���������}���������ƂŁA�}�b�N���b�N�̗������i�i�ɑO�i�����܂����B���1995�N�ɂ́A���̖{�����ɂ���NHK���u�A�W�A���䏫���I�s�v�Ƃ���TV�ԑg�𐧍삵�ĕ��f���܂����B�����炭���̑����i�̒�����TV�����ɂ���āA�}�b�N���b�N�������t�@�������łȂ��A�����̈�ʂ̐l�X�ɂ��m����悤�ɂȂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���}�b�N���b�N�̌���Ɨ��j
�@���݃^�C�����ōł������������Ă���Տ�V�Y�Ƃ��āA�`�F�b�J�[�ɗގ������u�}�b�N�z�b�g�v�⋲�ݏ����ɗގ������u�}�b�N�C�F�b�N�v���������邱�Ƃ�����܂��B�����V���v���ȃQ�[���ނ��y���ސl�X�̐��ɂ͋y�Ȃ��Ƃ��Ă��A�`�F�X���͂��߂Ƃ��鏫���ނ��V��Ă��܂��B�`�F�X���w���l�X�ɂ̓}�b�N���b�N���w����l�������A��s�̃o���R�N�݂̂Ȃ炸�n���̓s�s�ɂ��Ǔ��ꂪ����܂��B�ߔN�͑��s���Ȃ��Ȃ苣�Z�l�������Ȃ茸�����Ă���悤�ł����A�����v���X�e�B�b�N�̋�������X��f�p�[�g�ōL���s�̂���Ă��āA�|�s�����[�ȃQ�[���̈�ł��邱�Ƃ͊m���ł��B���Ȃ��Ƃ��T��200���l�ȏ�̐l�X���}�b�N���b�N���w����̂ł͂Ȃ����Ƃ������������܂��B����A�W�A�����œ`���I�����ނ��p�������Ă��钆�ŁA�}�b�N���b�N�̌��݂Ԃ肪�ڂ������킯�ł����A����͂�͂�A�����ɂ��A���n�x�z�̒��Őh�����ēƗ����ێ��ł������j�ɂ��ƍl���Ă悢�ł��傤�B
�@���ɗ��j�I�N���ɂ��ĊȒP�ɏq�ׂĂ݂����Ǝv���܂��B��ʂɃ}�b�N���b�N�́A�C���h�̏����ނ��쓌�Ɍ��������[�g�ɉ����ē���A�W�A���ɓ`�d�����ƍl�����Ă��܂����A���̓`���̐��m�Ȍo�H�Ǝ����ɂ��Ă͎c�O�Ȃ��疢���ɔ������Ă��܂���B���~�����}�[��}���[��������̉e�����������ƍl���邱�Ƃ��ł������ł����A���ߎ�͂���܂���B�܂��`��������12���I�̃A���R�[�����b�g��Ղɏ����ǂ̕������m�F����A�l���̓������12�`13���I����ƊӒ肳�ꂽ���Ⴊ����̂ŁA�}�b�N���b�N��12���I�ȑO�ɓ`�������\���͑傫���Ƃ����܂����A��������X�ɂ����܂ők���̂��ǂ����s���ł��B
�@�� �}�b�N���b�N�̔Ջ�Ƌ�̓�������
�@�}�b�N���b�N�̓������T�ς��Ă݂܂��傤�B���̎ʐ^�����Տ�ɏ��^�z�u�����}���ł��B
�@�@
�@�Ղ̓`�F�X�ՂƓ���8�~8�̐����`�ł����A�s���͗l�ł͂Ȃ����n�ł��B���̓_�̓C�X���[�����̏�����A�W�A�̏����ނƓ���ł��B���ɋ�̌`�ɒ��ڂ���ƁA�݂��̐w�n�̈�Ԏ�O�̗�ɂ���8�̋�̂����ŁA�L���O��N�C�[����r�V���b�v����[�N��4��́A�傫���⍂���͈قȂ�܂����A������������̌`�ɂȂ��Ă��܂��B�i�C�g�̋�͈�ԑ傫�ȋ�Ŕn�̓����̌`�ł��B��̓|�[���̋�8�ł����A�`�F�X�Ƃ͈قȂ�A��O�����i�ڂł͂Ȃ��O�i�ڂɕ���ł��܂��B�����āA���̃|�[���̋�̌`�̓V�����`�[�̋�Ɠ����悤���~�`�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��傫�ȓ����ł��B�Ȃ��A���������L���O�����ŃN�C�[�����E�Ƃ����ʒu�W�ŁA���R�̃L���O�E�N�C�[�������ɑΖʂ���`�F�X�Ƃ͈قȂ��Ă��܂��B
�@���ɉE�オ6��ނ̋�̖��̂Ƃ��̈Ӗ��A�����ċ�̓������������������̂ł��B�}�b�N���b�N�̋�̌Ăі��ɂ�����������܂��B�L���O�̋�͢�N����ł��̈Ӗ��͢�N����Ȃ킿��l�A�����͒P�ɢ�l��A�i�C�g�̋�͢�}�[��ł��̈Ӗ��͢�n����Ȃ킿�R���ł��B�������̋�́A�قڃ`�F�X�Ɠ����Ӗ��ŋ�̓������`�F�X�Ɠ���ł��B�܂��A���[�N�̋�́u���A�v�ł��̈Ӗ��́u�D�v�ł��B���̌`�������`�F�X�̃��[�N�Ƃ͑����̈Ⴂ������܂��B�������A���[�N�̋�����X�C���h�ł͐�Ԃ��Ӗ����Ă��������������L�͂ŁA����Ƀx���K���n���Ȃǂł͋�̌`���D�ɂȂ��Ă���������܂��̂ŁA���^�̔��B�����^�C�ɂ����Ă��Ԃ���D�ɖ��O���ς�����̂�������܂���B���A�̓����͏c�����R�Ń��[�N�ƑS�������ł��B�]���āA�N���E�}�[�����łȂ����A�̌Ăі����A�`�F�X�⌳���̃C���h�̏����Ƃ̂Ȃ��肪�����ł��B
�@�Ƃ��낪�A���̎O��̋�̌Ăі��́A���E���̂ǂ̏����ނɂ������Ȃ��Ɠ��Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��B�܂��N�C�[���ɓ������̌Ăі��́u���b�g�v�ŁA�^�C��ŐA���́u���v���Ӗ����܂��B���m�ł͢������A�C�X���[�����ł͢��b��A��Ɍ�����~�����}�[�ł͢��������Ӗ�����ꂪ���Ă��Ă���̂ŁA�����ł͑S���َ��̌Ăі��ɂȂ��Ă��܂��B���Ƀr�V���b�v�ɓ�����2�̋�͢�R�[����Ƃ������ŁA���̌�͢������Ӗ����Ă��܂��B���m�̃r�V���b�v�͢�m����ł����A�C�X���[�����ł��̋�͢������Ӗ����閼�O�ŌĂ�Ă��܂����B�܂��A��Ɍ���悤�ɗ��~�����}�[�ł��r�V���b�v�ɓ������͢�ۣ���Ӗ����閼�O�ɂȂ��Ă��܂��B�m���ɂ��Ă��ۂɂ��Ă��A���̍��Ƃ͑S�����̊ւ�������܂���A�}�b�N���b�N�́u�R�[���v���Ȃ킿���Ƃ����Ăі��͂���߂ē��قȂ��̂ł���Ƃ����Ă悢�Ǝv���܂��B�Ō�Ƀ|�[���ɓ����̖��͢�r�A��ŁA���̌�́u�L(�L�k)�v���Ӗ����Ă���A�����Ƃ͑S�����W�Ȍ��t�ł��B�ȉ��Ō���悤�Ƀr�A�͓G�w�ɓ���Ƣ�r�A�K�[�C��ƌĂ�A���b�g�Ɠ��������̂ł����ɏ��i���܂��B���́u�r�A�K�[�C�v�Ƃ�����́A�^�C��Ţ�Ђ�����Ԃ����L�k��Ƃ����Ӗ��ł��B���ۃr�A���G�w�ɓ������Ƃ��ǎ҂͋�𗠕Ԃ��ď��i�������܂��B���̓_�́A�䂪���̏��������������ɐ����ꍇ�ɂ悭���Ă��܂��B
�@���āA�ȏ�O�̌ꂪ��ɂȂ��Ă���͉̂��̂Ȃ̂ł��傤���B����Ɋւ��ẮA�̂����ۂɐA���̎�ƍ��A�����ĊL�k�������̋�Ƃ��ėp�����Ă�������ł͂Ȃ����A�Ƃ�����������܂��B������E���E�L�k�����ۂɔՏ�ɋ�Ƃ��Ēu����Ă����Ƃ��āA���̎��N���E�}�[�E���A�̋�͂ǂ̂悤�Ȍ`�ŕ\����Ă����̂ł��傤���B����͔��ɋ����[�����ł����A���ƂȂ��Ă͑z���̋y�ԂƂ���ł͂���܂���B
�@���ɁA���b�g�E�R�[���E�r�A�̎O��̋�̓��������ɂ��Ă��q�ׂĂ����܂��傤�B
�@���b�g�̓������ߎl����1�}�X�Ń`�F�X�̃N�C�[���̍ŋ��̓����Ƃ͉_�D�̍�������悤�Ɏv���܂��B�������A���͐��m�̃`�F�X�̃N�C�[����15���I�����܂ł͎ߎl��1�}�X���������Ȃ��ア��ł����B�]���āA���b�g�Ƃ����Ăі��͓Ǝ��ł����A��Ƃ��Ă̓N�C�[��(�C�X���[���́u��b�v)�Ɠ������Ƃ����܂��B
�@�Ƃ��낪�R�[���̋�̏ꍇ�́A�����������u�m���v�̋��u�ہv�̋�Ƃ͑傫���قȂ��Ă��܂��B�`�F�X�̃r�V���b�v(�m��)�͌��ݎߎl�����R�ɓ����鋭����ł�(���̐}A)�B�������A�r�V���b�v��15���I���܂ł��ߎl��2�}�X�ڂɂ��������Ȃ��ア���\�̋��ł����B���̎ア�����͌��X�C�X���[�����̏����́u�ہv��̓��������̂܂ܓ`����ꂽ���̂��ƍl�����Ă��܂�(���̐}B�y��C)�B�`�F�X��10���I���܂łɂ̓C�X���[�����E���烈�[���b�p�ɓ`����ꂽ�ƍl�����Ă��܂��B�]���āA��500�N�ȏ�ɂ킽���Ă��̓������������Ă������ƂɂȂ�܂��B�Ƃ��낪�^�C�����̃R�[���̓����́A���O�Ǝߎl����1�}�X�i��(���̐}D)�Ƃ����S���قȂ���̂ƂȂ��Ă��܂��B���̓����́A���~�����}�[�̏�����V�b�g�D�C����̏ۂ̋�(���̐}E)�ɂ����ʂ��Ă��܂��B���͂���ƑS������������11���I�̃C���h�̏����ނ̏ۂ̋�ɂ������܂�(���̐}F)�B����������^�C�ƃ~�����}�[�̏��������ɃC���h�����Ƌ����މ����������Ă��邱�Ƃ��m�F�ł��܂��B����ɁA�������ꂽ�䂪���{�̏����̋⏫�̋�Ƃ����������ɂȂ��Ă���(���̐}G)���Ƃɒ��ڂ���l�������ł��傤�B
�@���e�������ނ̏�(�r�V���b�v)�̓����̔�r
�@�@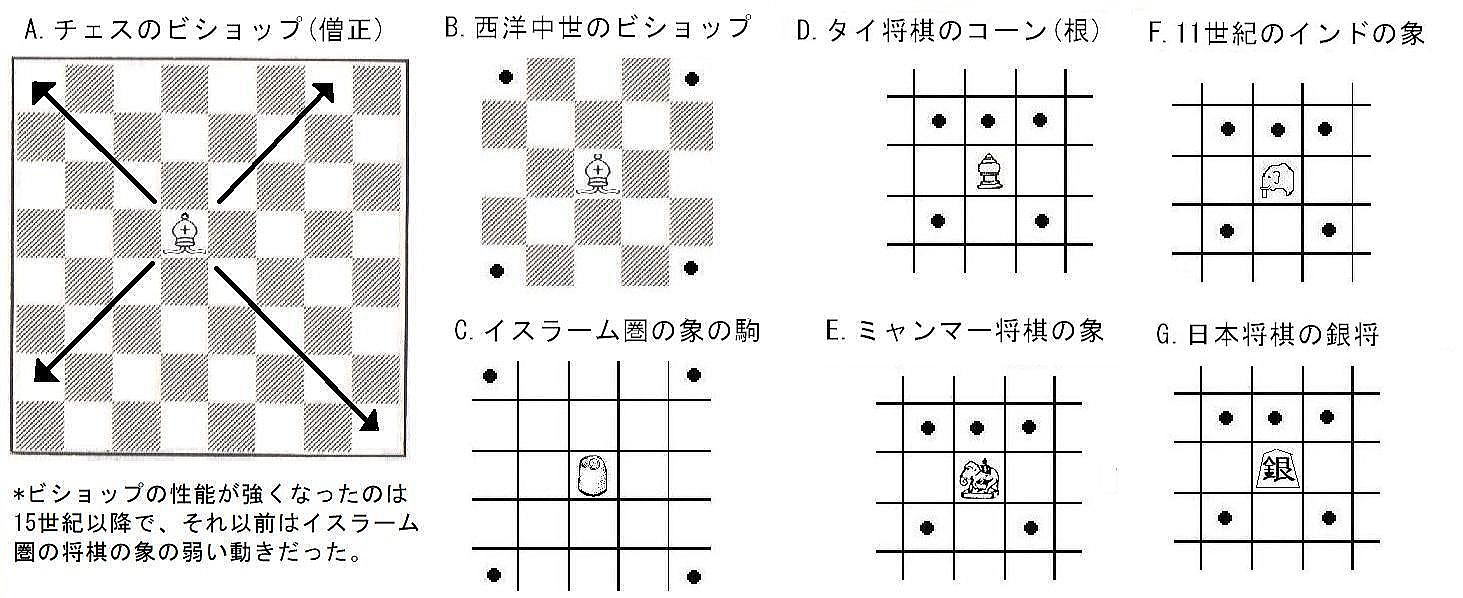
�@�Ō�Ƀr�A�̋�ł����A���̋��1�}�X�O�i����݂̂ŁA�G���ߊl����Ƃ��͎߂ɐi��Ŏ��Ƃ��������Ȃ̂ŁA��{�I�Ƀ`�F�X�̃|�[���Ɠ����ł��B�C�X���[�����̕����̋������̓����Ȃ̂ŁA�����炭�����ނ̔��˒n�Ƃ����C���h�ł����l�������Ǝv���܂��B��������ɏq�ׂ��悤�ɁA�r�A��̔z�u�́A��i�ڂłȂ��O�i�ڂɕ���ł���A�`�F�X�Ƒ傫������Ă��܂��B�܂���̏��i�ɂ��Ă��A�N�C�[���ɓ������ɏ��i�����Ƃ����_�̓}�b�N���b�N���`�F�X�������Ȃ̂ł����A�`�F�X���Ō�̗�ɒB�������ɏ��߂ď��i�ł���̂ɑ��āA�G�w�̍őO��(�O�i��)�ɓ��B�������ɏ��i�ł���̂ŁA���i�����Ȃ�e�ՂɂȂ��Ă��܂��B��q�̂悤�ɁA�O��ڂɒB�������͋�𗠕Ԃ��ăr�A�K�[�C (���b�g�Ɠ�������)�ɂȂ������Ƃ����܂��B�����������i�̎d�����\�Ȃ̂́A�r�A�̋�͝G���Ȍ`�ɂȂ��Ă��邩��ł��B
�@�ȏオ�}�b�N���b�N�̋�̓������̊T�v�ł����A���m�̃`�F�X�Ɣ�ׂċ�̓�����͈͂������A�����I�ȓ����ɓ˓�����ƔՏ�̋�ǂ�ǂ����Ă��܂��A���������邱�Ƃ��ł������������ɂȂ��Ă��܂��܂�(�������炢�̊��͂̐l���ΐ킷��Ɖ���75%�����������ɂȂ��Ă��܂��ƌ����Ă��܂�)�B�����ŁA��̘A�g���d��������Ր�Ɏ����w�������̂��邱�Ƃ������Ȃ�悤�ł��B�����̂�����͎Q�l�����Ƃ��ċ������w�^�C�̏���
�}�b�N���b�N�̎w�����ƌ��n���x�Ƃ����{�Ɋ�{�I�ȋ�g�E�Ǘ�E�l�������f�ڂ���Ă��܂��̂ŁA�������������Տ�ɍČ�����邱�Ƃ������߂������Ǝv���܂��B
2.�~�����}�[�̏���(�V�b�g�D�C��)�Ƃ��̋�
�@�~�����}�[(���̃r���})�̏����́A���Ă͍����Łu�V�r�B�C���v(�r���}��Ţ�푈�����l��̈Ӗ�)�ƌĂ�Ă��܂������A20���I�ɓ����Ă���A��R�ࣂ�\���Ƃ����Ӗ��Ţ�V�b�g�D�C����ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B�}�b�N���b�N�Ɠ��l��1970�N�㏉���܂ł͓��{�ɂ����đS���m���Ă��܂���ł������A���̌㏫����厏�Ȃǂő������Ŏ��グ�����悤�ɂȂ��Ă��̑��݂��m����悤�ɂȂ�܂����B�������c�O�Ȃ��ƂɃ}�b�N���b�N�Ɣ�r����ƁA���̌���{�ł̔F�m�x�ɑ傫�ȍ������Ă��܂��܂����B�����炭���̍ő�̗��R�́A�~�����}�[�����ł��V�b�g�D�C���̋��Z�l��������߂ď��Ȃ��A���ł̊�@�ɕm�����ɂȂ��Ă�������ł��傤�B���������ɂȂ����v���ɂ́A�����ǂ�����M���ȂLjꕔ�̏㗬�x�z�w�ɂ���������Ă��Ȃ��������Ƃ�A����k�ȗ�������Ɍ����Ă��ĉ��i�����ɍ����Ȃ��ߖ��O�ɕ��y���Ă��Ȃ��������ƂȂǂ��������܂��B
�@�V�b�g�D�C���̋�͂��Ȃ�傫�߂̂��̂������A�Ղ�1�}�X����7cm�A�ՑS�̂̃T�C�Y��60cm���炢���Ǝv���܂�(�����̎ʐ^�̋�͏����߂̃^�C�v�ŁA�Ղ̃T�C�Y��1�}�X��4cm�ՑS�̂Ŗ�35cm�ł�)�B�Ղ͖��n�ł����A�C�X���[������^�C�̏����Ƃ͈قȂ�A�Ֆʂɢ�V�b�P�`���E��ƌĂ��Ίp����������Ă��܂��B���̐��͌��X���݂����A�����̏��i���������߃r���}�ʼn��ǂ���ĉ�����ꂽ���̂Ƃ���Ă��܂��B
�@���ɋ�̌`�ɒ��ڂ���ƁA�L���O��N�C�[����|�[����3��̋�͂�������l�����ۂ��Ă��܂����A�L���O����ԑ傫���|�[�����ł���������ł��B�r�V���b�v�͏ہA�i�C�g�͔n�A�����ă��[�N�͐�Ԃ̌`�ł��B���6��Ƃ����ׂă��A���Ȍ`�ۂ̒���ɂȂ��Ă��܂��B
�@���V�b�g�D�C���̔Ջ�Ƌ�̓�������
�@�@
�@�E��́A�V�b�g�D�C����6��ނ̋�̖��̂Ƃ��̈Ӗ��A�����ċ�̓������������������̂ł��B�L���O�͢�~���W�[����Ȃ킿��剤��A�N�C�[���͢�V�b�P����Ȃ킿�������A�|�[���͢�l����Ȃ킿����(����)�ł��B���Ƀr�V���b�v�͢�V������Ȃ킿�����A�i�C�g�͢�~������Ȃ킿��n��A���[�N�́u���^�[�v���Ȃ킿�u����v�ł��B�����6��̋�̖��O�̈Ӗ��͏����ނ̋N���E�C���h�̋�Ɣ��ɗގ����Ă��܂��B�܂���̓����́A�}�b�N���b�N�ƑS������ɂȂ��Ă��܂��B
�@�������V�b�g�D�C���ƃ}�b�N���b�N�ɂ͑傫�ȑ���_������܂��B�}�b�N���b�N�̊J�ǎ��̋�̔z�u�̓|�[��(�r�A)���O�i�ڂɕ��ׂ�Ƃ����_�Ń`�F�X��C�X���[�����̏����ƈقȂ��Ă�����̂́A���͂قړ������Ƃ����܂��B�Ƃ��낪�V�b�g�D�C���̊J�ǂ́A���E�̏����ނ̂ǂ�Ƃ��قȂ���̎��R�z�u����n�܂邱�ƂɂȂ��Ă���̂ł��B�J�ǂ̑O�ɂ܂��A��l�̃v���[���[�́A�|�[��(�l)���ʒu�ɕ��ׂĂ����܂��B���̈ʒu�͉E��̐}�Ō����A����a3�`d3��e4�`h4�ɁA�Ԃ�a5�`d5��e6�`h6�ɕ��ׂȂ�������܂���B�����Ă��̌㋤��2�̃��[�N(���^�[)����Ԏ�O�̒i��(����a1�`h1�A�Ԃ�a8�`h8�̂ǂ�����)�u���A���̑��̋�����ꂼ���O����2�i�ڂ�3�i�ڂ̔C�ӂ̃}�X�ڂɎ��R�ɒu���Ă����܂��B
�@�J�ǎ��̐w�`�z�u�Ƃ��Ă悭�p������^������A������ɂ��ƌ��݂�20�ȏ�̑g����������Ƃ���Ă��܂��B�������ė����̋�g�݂��������Ă���A�Ԃ�������w���ăQ�[�����n�܂�܂��B�����Ȃ�|�[��(�l)�̌�������n�܂邱�Ƃ������A���Ղ����Ē��Ղ���w���n�߂�悤�Ȃ��̂ł��B���̂悤�ɁA���肩��퓬���n�܂��ۂł��������͒����Ԃɋy�Ԃ��Ƃ������̂ł��B���ł�1�ǂɗv���鎞�Ԃ͖�4���ԁA1����1�ǂƌ��߂��Ă���ꍇ�������A�l�X�͊F�����n�����d�˂Ďw���܂��B�Ղ̒������ł̐킢���d�v�ŁA�N�C�[��(�V�b�P)�̓����𐧂��邱�Ƃ��v�_�Ƃ���邱�Ƃ������悤�ł��B
�Q�l����
������A�ȉ��̎������Q�l�ɂ��܂����B���҂̕��X�ɐ[�����Ӑ\���グ�܂��B
�� ����G��w�����T�x(�@����w�o�ŋǁA1977�N)
�� ����G��w�Տ�V�Y�x(�@����w�o�ŋǁA1978�N)
�� �~�ьM�w���E�̏����x(�����V���ЁA1997�N)�@ (����L���Ƌ����̉����ł�2000�N�Ɋ��s�����)
�� �w���E�̃`�F�X�E�����W�x(��㏤�Ƒ�w�A�~���[�Y�����g�Y�ƌ������A2002�N)
�� �w���E�̃`�F�X�E�����W�U�x(��㏤�Ƒ�w�A�~���[�Y�����g�Y�ƌ������A2010�N)
�� ����L�w���E�̎�ȏ����x(����o�ŁA1999�N�A�����ŁA2005�N)
�� ����L�w���m�̏����x(��㏤�Ƒ�w�A�~���[�Y�����g�Y�ƌ������A2007�N)
�� ����L�E��J�b�m�w�^�C�̏����@�}�b�N���b�N�̎w�����ƌ��n���x(����o�ŁA2000�N)
�� ����L�w�~�����}�[�̏����@�V�b�g�D�C���x(����o�ŁA2004�N)
�� ����L�u�ə�����(�V�b�g�D�C��)�̕����ƌ���v(�w�V�Y�j�����x��11���A1999�N�f��)
�� �������w�����̗������x�i�߂���A1986�N�j
�� �A���b�N�X�E�����h���t�u�����ƃ`�F�X�̗��j�̈�ʁv(�w�������E�x1971�N3�����f��)
�� �������u���E�̏����v(5)�u�^�C���̏����v(7)��r���}�̏����(�w�ߑ㏫���x1972�N5���7����)
�� �������F�u�łт䂭�r���}�̏����v(�w�������E�x1985�N3�����f��)
�� �����N��u�����`���čl�v(�����l�Êw�������I�v�w�l�Û{�_���x��36���A2013�N�f��)
�� �����N��E��؈�c�E�����_���E���������EP.�^���}�v���|�`���R�[���EB.�`���C�X�����E�o���R�N��w����A�W�A�����픎���� �w�����ނ̓`�d�Ɋւ��錤���\�^�C�����}�b�N���N�𒆐S�Ɂ\�x
(���Y�Ƒ�w�A�~���[�Y�����g�Y�ƌ������A2016�N)
�� H.J.R. Murray �gA History of Chess�h , Oxford, 1913.
�� Charles Wilkinson & McNab Dennis �gChess : East and West, Past and Present�h , 1968.
�� D.B. Pritchard �gThe Encyclopedia of Chess Variants�h, Games & Puzzles Publications, 1994
�� Gareth Williams �gMaster Pieces the architecture of chess�h, Viking Studio, 2000.
���I�X�̏����́u�}�b�N�t�N�v�Ƃ������O�ł����A���݂̓��[�����^�C�����Ɠ����ŁA����^�C���̃v���X�e�B�b�N��p�����Ă��܂��B�J���{�W�A�̏ꍇ�A���ẮA�����ۊ��ƕ���Ō`�̓^�C�����Ɏ��Ă��������ۊ��̂悤�ɐ�����u�V���b�����v�Ƃ������̏������������Ă���Ƃ���������������������܂����B�������ߔN�J���{�W�A�����ł��̂悤�ȃ^�C�v�̏����ނ͂قƂ�nj����Ȃ��悤�ł��B�ŐV�̏��ł́A�J���{�W�A�̏����́u�I�[�N�`���g�����W�v�Ƃ������O�ŁA��̌Ăі��͈قȂ���̂̃��[���̓^�C�����Ƃقړ���ł���Ƃ���Ă��܂�
(�~�ьM�u�A�W�A�̏����v(�w���E�̃`�F�X�E�����W�U�x2010�N���ɏ���)�A�����_���u����A�W�A�̓`���Q�[���v(�w�����ނ̓`�d�Ɋւ��錤���\�^�C�����}�b�N���b�N�𒆐S�Ɂ\�x2016�N���ɏ���)���Q�l�ɂ��܂���)�B
����L���́A���Z�l����100���l���鏫��(�`�F�X)�́A�`�F�X�E�V�����`�[�E�V���E�M(����)�E�`�����M�E�}�b�N���b�N��5��ނ݂̂ł���Ƃ��āA�������u�ܑ叫���v�Ƃ��Ă��܂�
(�w���E�̎�ȏ����x6�`7��)�B
���̃^�C�v�̋�͖��|���̕����̕t�����s���͗l�̃`�F�X�ՂƃZ�b�g�ɂȂ��Ĕ̔�����Ă��܂��B�Ղ͐܂肽���ݎ��̔��`�œ����ɂ̓o�b�N�M�������̔Ղ��`����Ă���A���ɋ���[�ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B���n�ł��w���ł���悤�ł����A�����O�܂ł͓��{�ł��e�Ղɓ���ł��܂����B
������ނ̓C���h����L�܂藤�H�œ`������ƍl������B���R�́A���Ղ̕i�ɂ͍z���A���h���A�D���ȂǍ��l�Ŕ���镨��p���A�Q�[���̂悤�Ȃ��͓̂K���Ȃ�����ł���B�]���ē���A�W�A�̊C�㏔���ɂ͌Ñ�̏����͓`���Ȃ���������ƍl������(�O�f�E�����_�������A�W�A�̓`���Q�[���)
��|���g�K���̒T������1509�N�ɂ͂��߂ă}���b�J�ɓ��B�����Ƃ��Ɏ��̂悤�Ȃ��Ƃ��������B���鎞�w�����̃f�B�G�S����y�X�̓`�F�X�����Ă����B�����ɃW�������o�g�̐l������l�Ղ̑��ɂ���ė����B���̌��n�l�͂ЂƖڂł����ɂ��̃Q�[�������Ȃ̂������ʂ��A�����������l���p�����̌`�ɂ��āA���y�X�Ƃ�������b�����킵�����Ƃ��������(H.J.R.�}���[�w�`�F�X�̗��j�x��́u�}���[�̃`�F�X�v)
�Ⴆ�A�X�}�g�����k���̐�Z���o�^�b�N(Batak)���̎Љ��S�苭�����������t�H���E�G�[�t�F��(von Oefele )�̕����ƂɃ}���[�͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B����ׂẴo�^�b�N�l�̐��N�j�q���`�F�X�ɂ��ĉ��������̂��Ƃ�m���Ă���A���ɂ���قƂ�ǂ��ׂĂ̏W��̖̏��ɂ̓`�F�X�Ղ������Ă��飢�Q�[���͂˂ɓq���ăv���[����邽�߁A���Ɋ�����V���Ė\�͓I�ɂȂ邱�Ƃ�����̂ŁA�����Α����������ԃQ�[���s�ׂ��֎~���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��������قǂł���B�(�O�f��}���[�̃`�F�X�)
��X�}�g�����ł́A�ǂ��邽�тɐV���ɋ�邱�Ƃ͒ʗ�悭�s���邱�Ƃł���B���̏ꍇ���ɂ�10���قǗv���邾���ł���B�|�➽�q�̗t���ŋ�邱�Ƃ�����B�ǂ̋���f�����J�b�g����A�^�ǂ���Ɏd�オ��B�(�O�f�u�}���[�̃`�F�X�v)
����́A�X�L�[�g���N�W���������i�̃`�F�X��̗�������������Ă������B���̂悤�ɍ��x�Ȏd�グ�������`�F�X��́A�ߑ�ɃC���h�ŗp�����Ă������X�����̃`�F�X��̗ތ^�ɂ��Ȃ莗�Ă���B�}���[�����̐l�X�̓C�X���[�����̃X���j�h�����M�Ă���A���ۂ̌`����\�킷�悤�ȋ�̒�����͔ނ�̏@���ɂ���ċ֎~����Ă���̂ł���(�O�f�u�}���[�̃`�F�X�v)
�}���[�́w�`�F�X�̗��j�x�ɂ��A�}���[������X�}�g�������ł͘Z��̋�̂����A�L���O�E�N�C�[���E�r�V���b�v�̌��n�����T���X�N���b�g�ꂻ�̂��̂ł���A�i�C�g�ƃ��[�N�̌��n���̓C���h���쉈�݂̌���A�^�~�����e���O��ł���Ƃ���Ă��܂��B���̂悤�Ɍꌹ���猩�āA�}���[��C���h�l�V�A�n���̏����ނƃC���h�����̊Ԃɉ��炩�̊֘A�����������Ƃ͔ے�ł��Ȃ��悤�ł��B
1971�N�Ƀ`�F�X����{�����ɑ��w���������Q�[���f�U�C�i�[�̃A���b�N�X������h���t�����w�������E�x���Ɏ��M�����u�����ƃ`�F�X�@(1) �����ƃ`�F�X�̗��j�̈�ʁv�̒��Ń^�C�����u�}�N���[�N�v�Ɠ��{�����̏d��ȗގ��������邱�Ƃ��w�E���܂����B�����炭���ꂪ���߂Ĉ�ʌ����Ƀ}�b�N���b�N�ɂ��ďq�ׂ����͂��낤�Ǝv���܂��B����1972�N�Ɂw�ߑ㏫���x���ɒ����V���ϐ�L�҂̓��������ɂ��u���E�̏����v�̑�5��Ɂu�^�C���̏����v���f�ڂ���A��}�b�N���b�N��Ƃ������O�Ƌ��ɁA���̏��^�z�u�Ƌ�̓������Љ��܂����B���̌㑝��G�ꎁ��1974�N�Ɂu�����̋N��(��)�v(�w�������E�x7�����f��)�ŃA�W�A�̑��̏����ނƔ�r���钆�Ń^�C�̏����ɂ��ďq�ׂ܂����B���쎁�́w�����T�x(1977�N)�̒��ł���߂�݂��ă^�C�������ڂ����_���Ă��܂��B
��������ٓ��̏��������ق͎c�O�Ȃ���2006�N10���ɕق��Ă��܂��܂����B���ēW������Ă������E�̏����ނ̔Ջ�̎ʐ^�͍��������A����HP����{���ł��܂��BURL�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B
�@https://www.shogi.or.jp/history/world/makruk.html�@
����L�E��J�b�m�w�^�C�̏����@�}�b�N���b�N�̎w�����ƌ��n���x38p�ȉ��B
�O�f�u����A�W�A�̓`���Q�[���v���Q�ƁB
��J�b�m���ɂ��A�^�C�ł́A�}�b�N���b�N�͢�^�C�`�F�X��A�`�F�X�͢���[���h�`�F�X��Ɖp��\�L����Ă��܂�(�O�f�w�^�C�̏����x38p�ȉ�)�B
�ؐ��̋�̍w���̓o���R�N�s���ł��ȒP�ł͂Ȃ��悤�ł� (�O�f�w�^�C�̏����x55p�ȉ�)�B
�O�f�w�^�C�̏����x6p�ȉ��B�������A���݂ł͂����ƌ�����100���l�ȉ����Ƃ�����������܂��B
�O�f�w�^�C�̏����x47p�ȉ��B�������w�����̗������x58�`60p���Q�ƁB
11���I�C�X���[���̊w�҃r�[���[�j�[(973�`1048)��1030�N�ɒ������w�C���h���x�ɂ́A�C�X���[�����ƃC���h(�����炭�p���W���[�u�n��)�ł͏�����̓������傫���قȂ��Ă���Ƃ����L�q������܂��B�}���[�́w�`�F�X�̗��j�x�̒��ł��̋L�q���p�Ď��̂悤�ɏЉ�Ă��܂��B
�@�u�ނ�C���h�l�́A�`�F�X���v���[����Ƃ��A�ۂ̋���A1��ɂ��A�����̂悤��1�}�X���i�����邩 ���(����)��� �A�l���߂ɂP�}�X�i�܂��邩���邱�Ƃ��ł���B�ނ炪�����ɂ́A���̋������5�̃}�X�ځA���Ȃ킿�A���O��4���́A�ۂ̕@��4�r����߂�ꏊ��\�킵�Ă���̂ł���B�v
�@�y���V�A����C�X���[�����ɓ`����ꂽ�����C���h�����̏ۂ͂ǂ̂悤�ȓ��������������͕������Ă��܂���B�܂�11���I�����p���W���[�u�n���ł̏ۂ̋�̂��̂悤�ȓ������C���h�ň�ʓI�ɍs���Ă����̂��ǂ������s���ł�(�Ⴆ�r�[���[�j�[�́A���������̒��ŃC���h�ɂ�4�l�őǂ��鏫��������ƕ��Ă��܂����A����4�l�����́u�ہv�́u�c�����R�ɓ�����v�Əq�ׂĂ��܂�)�B
�}���[���������炱�̓����̓��ꐫ���w�E���Ă��܂��B�������ނ́u�����炭���R�I�Ȃ��́v�Əq�ׁA�^�C�E�~�����}�[�̏����Ɠ��{�����̊֘A���ɔے�I�ȗ��������Ă��܂��B���������{�̏����t�@���́A���̃^�C�̃R�[��(��)�̋�(�����ė��~�����}�[�̏ۂ̋�)�Ɠ��{�̋⏫�̋�̓���������ł��邱�Ƃɖڂ��䂩��邩������܂���B����Ɍ�Ɍ���悤�ɁA�^�C�����Ɠ��{�����ɂ͑��ɂ��A�r�A(�L�k)�̋�̈ʒu�Ə��i���[���ɂ����{�����Ƃ̗ގ������F�߂��܂��B��������A1970�N��ȍ~�A�����ނ�����A�W�A���o�R���ē��{�ɓ`�������\������N����A�L�͂Ȑ��̈���ƍl������悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�^�C�����ɂ����āA�|�[���ɓ�����r�A�̋�O�i�ڂɕ���ł���_�ƁA���̎O�i�ڂɒB�����Ƃ����Ԃ��ď��i����Ƃ����_�����{�����̕����̈ʒu�Ə��i�̎d���Ɏ��Ă��܂��B���̓_�ɂ��Ă��}���[�́A�u���̗ގ����������炭���R�I�Ȃ��́v�Əq�ׂĂ��܂��B��͂�}���[�́A�C���h���瓌��A�W�A�ɓ`�����������ނ��͂邩�����̓��{�ɂ܂œ`������\���ɔے�I���������Ƃ�������܂��B
�@�ߔN�}�b�N���b�N�̗��j�Ɋւ���d�v�Ȍ����������s����܂����B����́A�^�C�̔����قȂǂɎ�������Ă���Â������̋�Ɋւ�����̂ł�(�w�����ނ̓`�d�Ɋւ��錤���\�^�C�����}�b�N���N�𒆐S�Ɂ\�x2016�N)�B���̒��ōł��ڂ������̂́A15�`16���I�Ɛ��肳����̂����r�A(�|�[��)�ƌ������̐}�����f�ڂ��Ă��邱�Ƃł��B���̑����́A���݂̂悤�ȝG���Ȍ`�ł͂Ȃ��A�㕔�Ɋۂ݂���������ˋN��L���Ă��܂����A�����͖��炩�ɔ��]������̂ɓK���Ă��܂���B�������琄�肳���̂́A15�`16���I�����Ƀ}�b�N���b�N�̃r�A��̏��i�����݂̃��[��(�G�w�̎O�i�ڂɒB���������]�����ă��b�g�ɏ��i������)�Ƃ͈قȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����\���ł��B����Ɋւ��č��コ��ɒ����E�������i��ł������Ƃ��傢�Ɋ��҂���܂��B
1989�N�ɍ������r���}����~�����}�[�ɉ��̂���Ă��܂��B
�~�����}�[�`�F�X�A��������ꂽ�E�E�`���[�^�����ɂ������ł�(����L�w�~�����}�[�̏����@�V�b�g�D�C���x53p���Q�Ƃ��܂���)�B�����ꕔ�ł͈ˑR�Ƃ��ăV�r�B�C���Ƃ��Ă�Ă��܂����B���{�ł͋ߔN�܂Ń~�����}�[�������u�V�x�C���v�Ƃ������ŌĂ�邱�Ƃ����������̂ł����A����̓V�r�B�C���̉p��\�L���痈�����̂ł��B���݂ł͓��{�ł��u�V�b�g�D�C���v����ʓI�Ȗ��̂ɂȂ�܂����B
1970�N��Ɏ��M���ꂽ�V�b�g�D�C���̓��{�ꕶ���̑�\�Ƃ��ẮA��10�ŏЉ�����������́u���E�̏����v�A�ڋL���Ƒ���G�ꎁ�́w�����T�x������܂��B�����āw�������E�x1985�N3�����ɔ��\���ꂽ�������F�l�i(�����i)�ɂ�颖łт䂭�r���}������Ƃ����L���́A�����炭���߂Č��n�ł̒��ڎ�ނɊ�Â������̂ŁA�����ւ�M�d�ȕł����B���̖`�������Ŏ������́A���{�́u�{�ɏ����ꂽ�r���}�����̐����͂قƂ�ǂ������s��������Ă��܂��v�Əq�ׂ���A���ڌ��n�̌��`�����s�I��������A�r���}�����̔ՂƋ�E��̕��ו��E�����̏��i�@�A�����ăr���}�����̌��ɂ��ĕ�����������e�����|�[�g���Ă��܂��B�܂��������́A���͂̏I���߂��ŁA�u���N�̗��j�����邻���ł������Ɖ��\�N��������r���}�����͖ł�ł��܂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���v�A���n�̐l��������b���̂��u���N�ゾ������r���}������m���Ă���l��T���̂����s�\�������ł��傤�v�Ƃ��̍s�����������뜜���Ă��܂����B�Ȃ��A���ꂩ��13�N���1998�N�Ɍ��n�����ɖK�ꂽ����L���̕ł́A�~�����}�[�ŃV�b�g�D�C����m���Ă���l�͐l����5%�����Ǝv���A���ۂɃV�b�g�D�C�����w���l�̂قƂ�ǂ�60�Έȏ�ŋ��Z�l����1000�l��������Ă���Ƃ������Ƃł�(�O�f�w�~�����}�[�̏����@�V�b�g�D�C���x12p�Q��)�B
��̉��i�́A�~�����}�[�̕��ϓI�Ȏ����̖�ꃕ�����ɓ�����A���ɍ����ł��B���Ă͑�O�����̕��y�i�Ƃ��Ĉ����ȃv���X�e�B�b�N����삳�ꂽ���Ƃ��������悤�ł����A�Տ�ɋ��ł����錻�n�̎w�����ł͉��₷���̂Ŏs�̂Ɏ����Ă��܂���B�����A�`�F�X��̏N�W�ƂȂǂ���̎��v������悤�ł��B�܂��A�V�ׂ閯���H�|�i�ƍl����A�ό��q�����̎Y�i�Ƃ��Ė��͂�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�Ԃƍ������1�����z�u���Ă�������������A�Ԃ����ׂĂ̋��z�u�����̂����Ă��獕���z�u�������������܂��B�����z�u���I������ɐԂ�������ւ��A����ɍ�����������Ă܂�����ւ��邱�Ƃ��ł��܂��B�������čŏI�I�ɍ��̑����z�u������Ԃ�����������A�Ԃ̐��ŏ�����w���܂��B�Ȃ��A�ߔN���ł́A�Ղ̒����ɎՕ���(����J�[�e��)��u���āA���҂�����Ɍ����Ȃ��悤�Ɏ����̋��z�u���������ŊJ�ǂ���������̗p����邱�Ƃ�����悤�ł�
(���̏��͢�E�B�L�y�f�B�A��̉{�����瓾�����̂ł�)�B
��������̂������i����11�j�����A���Ìy�x���̌m�Ë�ɂ��āi�O�ҁj
�@�i�炭�����������Ă���܂����B�܂����O�R�ɂ�鏫����b�ɂ��t������������K���ł��B
�@���{�����A���Ìy�x���́A�{�蒉�Y�x�����̉���1962�N�ȗ������I�ȏ�O�O�n��ł̕��y�����̒��S�ƂȂ��Ă��܂����B2011�N�ɎO�\���N�Ԃ�ɋ�����U�^�[�������M�҂��A���N����x���ɉ����Ă��������A�{�藷�قŖ��T�s����m�Ñlj�ɎQ�����Đ�y����������炲�w�����邱�Ƃ��ł��܂����B���̌�x�������U����2014�N�܂œ�N�]��̒Z���Ԃł������A�����ɂ���ċv���Ԃ�Ɍ̗��ŕ�炷�䂪���̐l���͖L���Ȃ��̂ɂȂ�܂����B�{��搶���͂��ߋ��Ìy�x���̊F�l���ɂ͂ǂ�قNJ��ӂ��Ă�����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�@���ł���Ԃ̎v���o�́A�x���ɉ�������2012�N�̖��Ɍ��A�������ŊJ�Â��ꂽ���A�x��������̂��U���ŁA��y����̕��X�Ƌ��ɎQ���ł������Ƃł��B�S���v�������Ȃ����Ƃ������̂ł����A�����炭�����̌m�ÂɎ���̐���グ�����������őǂ��Ă����̂��搶�̖ڂɗ��܂����̂����������������̂�������܂���B
�@�����̏����W�҂ɂ͎��m�̂��Ƃł����A�{��搶�͑�R�\�ܐ����l�Ɲ፧�̊ԕ��ł����B���̉��Ţ����������t(����d�j��)��̐���グ������g��������������̌m�Âł��g���Ă����܂����B�搶����m�Âɗp���鐷��グ��̕�C���˗�����A�\�ʂ��Ă��琷��グ����蒼���Ă��[�߂������Ƃ�����܂����B�������A������Ɛق������Ƃł͉_�D�̍�������͓̂��R�̂��Ƃł����A��C�̏o���h���ɐ搶�͔[�����Ă����������悤�ł����B���̌�A���x�̌��A����Ɏ����čs���ĊF����Ɍ��Ė������ǂ����ȁc�Ɗ��߂��܂����B
�@�����Ƃ��Ă͂��̏�Ȃ��������A������͍O�R��̐���グ�𐔑g�g���Ďx�����Z�Ƌ��ɐ���Ɍ��������Ƃ��悭�����Ă���܂��B
�}1 ����̑Nj�(�ъ����グ)�@�@�@�}2 ���N�ǂɗp����ꂽ������(��C�O�ƕM�҂ɂ���C��̎p)
�@
�@����͒Ìy�x���̌m�ÑǂŎg�킹�Ă�����������(�ъ����E���グ��)�A�����́A�{��搶�����N�m�Âɗp�����Ă���������(�H�Ώ��E���グ��)�ł��B�˗��̎��_�ł́A30�N�ȏ���ǂŎg���Ă������ߏ��Ղ��������A�قƂ�ǂ̋�̎����������Ȃǂ��Ă��܂����B������g�������̐��グ��������悤�ȏ�ԂŁA������g�̕�C���˗����ꂽ�킯�ł��B�������颖�����̍�����ł��̂ŁA�ŏ��͑�ς��ȂƐK���݂��Ă��܂������A�d�˂Ĉ˗�����A���������čŌ�͈����܂����B���ׂĂ̋�グ�������Ċ��������̂���̎ʐ^�ł��B
�@���āA���A����I���A���e��������Ȃ���}�������A����Ŗ����̕��X�Ɗ��k����Ă����{��搶����菵�����ꂽ�M�҂́A�n�ӎO�Y���A����͂��߂Ƃ��邨���X�̕��X�ɑ��āA�u�Ìy�x���̐V������ł��B�p�������Ȃ����ŋ�����삵�Ă���܂��v�Ǝ��ȏЉ�Ȃ��������������܂����B���g�̐���グ����������X�ɂ͑����������L�����悤�ł����B�����炭����������܂ŊF����́A�M�҂���ō���Ă���͕̂��ʂ̒����Ǝv���Ă���ꂽ�̂��Ǝv���܂��B
�@�����ɑ��錧�A���Z�̔������܂��܂����������ƂɈ��g���ĐȂɖ߂����M�҂��ɂ�܂肵�Ď|���������ɂ��Ă���ƁA��܁A��t��Ɛ����|�����܂����B���̎�͌��A�̑�\�����̓ޗlj�������ł����B�ޗlj�����͎����ɉߕ��̂��J�߂����������A���ꂾ���ł������������̂ł����A����Ɂu�₪�ăv������ǂ�X���ɌĂ��ɋM�Z��̋���g�킹�Ă���Ȃ����v�Ƃ��������t�����Ƃ��ɂ́A�����オ��悤�ȋC���ɂȂ�܂����B����������āA����������Ă����ǁc�
�\ �ϑz�Ƃ������ׂ�����Ȗ����A���ꂩ���N�]��o����2014�N2��18���Ɍ����̂��̂ƂȂ�܂��B�O�O�s�ōs��ꂽ��63���������4�Ǔn�Ӗ������ΉH���P���O���̑ǂŖ{���ɍO�R��̋�p�����邱�ƂɂȂ����̂ł����B
�@���Ìy�x���̎v���o����b�����Ă������b�ɂȂ�܂����B�����Ȃ��A�����Ȃ��B
�@���āA���N�Ìy�n���ł̏����U���ɗ͂�s���ꂽ�{��搶��95�̓V����S�����ꂽ�͍̂�N5���̂��Ƃł����B���ꂩ����N�o���āA�搶�̂��⑰��W�̕��X����u���Ìy�x���őǂɗp���Ă����ՂƋ��𗧂ĂĂ���Ȃ����v�Ƃ�����|�̐\���o���A�䂪�鉺���O�O�x���ɓ`�����܂����B�������A��R�̋�̌��������Ă݂�ƁA���X�͂��ꂼ�ꑵ���Ă����͂��Ȃ̂ɒ��N�̑ǂ̌��ʓ��荬�����Ă��܂����悤�ł����B�����ŁA�x������̒��ő�̋�D���̕M�҂���̐������������Ɩ������グ�܂����B��̐����͂܂��r��ł����A���̒��Ŗʔ�������������o�Ă��܂��B����͂������u���Ìy�x���̌m�Ë��v�Ƃ��Ă��Љ�悤�Ǝv���܂��B
�@����\���o�̂������ˑ�Ȑ��̋�́A�����ƃv���X�e�B�b�N���Ȃ��Ă��܂����B�M�҂������b�ɂȂ������A�Ìy�x���ł̂��m�ÂɎg��ꂽ�̂͂قƂ�ǃv��������悤�ȋL��������܂��B�����A���̍��̎x���̑��y�̕��X�́A���̓v������ǐ͖̂̒����Ŏw���Ă����A�Ƙb���Ă���܂����B�X���ł��قƂ�ǂ̑��Ńv����g�p�����悤�ɂȂ������Ƃ��e�������̂�������܂���B�v����̂��Ƃ͂��Ă����A�ˑ�Ȑ��̖ؐ��̒����̕��́A1970�N�ォ��20���I�̏I��鍠�܂Ŏg���Ă������̂ł͂Ȃ����Ɛ��������Ǝv���܂��B
�@�ؐ������̑f�ނ̓c�Q��ł����A�قƂ�ǂ�����A�W�A�Y�̃A�J�l�ށA�����u�V�����c�Q�v���Ǝv���܂��B����͂قƂ�ǂ��u������v���u������v�ŁA�u�㒤��v��u������v�̋�́A���̐}���Ɍ�����|��(��|���ܘY��)��ʎR(��̋v���A�ɓ��F����)�Ƃ��������H�̍�̒[��͂��������̂́A�c�O�Ȃ��犮�S�Ȉ�g�ɂȂ��Ă�����̂����邱�Ƃ��ł��܂���ł����B
(�����̕��ނɂ��Ă͂��̃R�����́u����1�v�̒��́u�����̂��낢���v���������������B)
�@���̓�g�̒[��͂ǂ�����A���������H��̌����Ȓ���ŁA�S����Ă���c�Ɛɂ��܂�܂��B
�}3 �|���쟽�F���ƌ����������̒[��
�@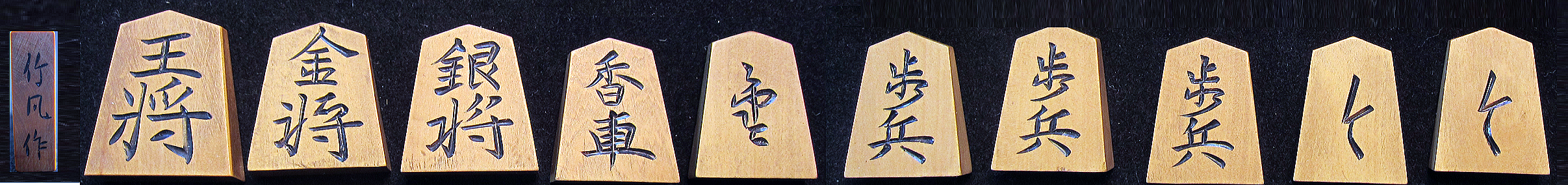
�@�}4 �ʎR��̏㒤��[��
�@
�@������ꂽ�Â���̒��ŁA�ЂƑg�����S�ɑ����Ă���̂��m�F�ł��������������������܂����B����̏��̖��͢���^��ł��B���̏��̂́A���łɁu���̂X�@�X�x������̐�����v�Œ|���t��̋���Љ�Ă���܂��B�����̍����̖�X�̎�l�������l�ŁA���ł��m��ꂽ��c�����q�̏��������ɂ��ĖL�����R���n�삵������ł��B��ʂɑNj�Ƃ��ėp�����邱�Ƃ͋H�ł����A��̏N�W�Ƃ̕��X���Ɠ��̖��킢�̂����Ɏ䂩��A��g�͎����Ă������ƍl�����Ƃ���܂��B�܂��A�A�}�`���A�̋��҂ɂƂ��Ă��A��ъ���⢐�������Ȃǂ̋������Ɉ�x�͑����Ă݂����ƍl�����Ƃ������A�B�ꂽ�l�C�������̂ł��B
�}5 �v�l��̖������E�u���^���v
�@
�@�M�҂͂���܂ŕS�g�ȏ�̋���Ă��܂����B�����������Ƃ��ẮA����ۂɏ������w�����߂̋�肽����Ƃ����v�������������������A���^���̋�͂���܂ň�g�����������Ƃ�����܂���ł����B�B��̗�O�Ƃ��ẮA�����ƈȑO�����ݏZ�̍��ɁA����^�̐��グ��̕���������Ȃ��Ȃ����̂ŁA��������Ăق�����Ƃ����˗�������A����ɉ��������Ƃ������������ł��B�������̕����̕�[�ł������A�Ȃ��肭�˂�����ۂ̓Ǝ��̋�́A��������グ���������ɂ��������Ƃ����L��������܂��B
�@���Ďʐ^�̒��^�̖�����́A�M�҂�����{�ɂ������Ǝv���悤�Ȍ����Ȏ蒤���ł����A���͉��Ƌʂ̋�K�̖��ł��B�ʗᒤ���̖��͎�������������ŕ\�������̂����ʂŁA���Ɏ��ŏ�����Ă���̂��Ɠ��ł����A�u�v�l��v�Ƃ�����Җ����ڂ������܂����B�u�}�X�g�v�����́u�G�L�g�v�Ɠǂ߂�悤�Ɏv���̂ł����A�c�O�Ȃ��Ƃɂ��̍�Җ��ɊY�������Ƃ̕������܂��ɓ��肷��Ɏ����Ă��܂���B�{��搶�Ƒ�R�搶�E�����t�Ƃ̊W���l����ƁA�����͍��������ӂ̕����ȁA�Ƃ��v���܂������������܂���B
�@�u�v�l�v�Ƃ�����t�̖��ɂ��S������̂�����́A����HP�̌f���܂��͏鉺���O�O�x���ɂ�������邱�Ƃ�S�҂��ɂ��Ă���܂��B
�@���Ìy�x���̌m�Ë�ɂ��ẮA������E�������ɂ��ƂĂ������[����Ⴊ���g������܂����B�����͌�҂ɏq�ׂ����Ǝv���܂��B
��������̂������i����12�j�����A���Ìy�x���̌m�Ë�ɂ��āi��ҁj
�@������ꂽ���Ìy�x���̖ؐ���̒��ɂ́A�ꕔ�z�I��J�G�f�ȂLj���̑f�ނ�p������������}�L(�}���~)�ނƎv���鏑������������Ă��܂������A�����͎U�킵������[���邽�߂Ɉ�A������ꂽ���̂ŁA�f�ނ̎�̂̓c�Q��ł����B�����A�u�c�Q�v�Ƃ����Ă����{�Y�̖{���k�ނ̋�͏����ŁA�قƂ�ǂ�������ɗp�����铌��A�W�A�Y�̃V�����c�Q�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�܂��A����̕��ނ��猩��ƁA�命�����������ŁA���ƎO�g�قǒ���������܂����B
�@�܂��O�҂ŏЉ���悤�ɁA�������͒��^��(��v�l��)����g�̂݁A���ɒ|����̖������ƋʎR��̏㒤���̒[����������������ł����B
�@����痪������̒�����́A���\�N�Ԏx������̌m�Âŗp����ꂽ��A���X�̏������ɑ݂��o���ꂽ�肵�āA�ˑ�Ȑ��̑ǂ��o�Ă����Ƒz������܂��B�ǂ̓x�ɋ������o���Ǝ��[���d�ˁA��̎U�����Ⴆ���������ł������Ƃ��Ă��s�v�c�ł͂���܂���B���ۍ���𗧂Ăĉ������Ɛ\���o������������A�����̂��߂Ɋm���߂�ƁA�قƂ�ǂ̋�A��̒��Ɉ�g40���������Ă��Ă��A�����ɑ����Ă����Ԃ̋�͂���܂���ł����B������ƒ����肪�������Ă�����̂�����܂����B�܂��A����������ł����ꂼ��̍�҂̒�����̓�����O���ɒu���Ċώ@����ƁA�ʂ̒���t�̑�������������Ă����ۂ���ꍇ������܂����B���g��a�����Ă���ԂɁA������x����ւ��đ��������Ă݂܂������A��͂��g�����ɑ����邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B
�@���̒��œ��ɐS�Ɏc���������Љ�܂��B�܂��A���̍�����̐}�����������������B
�}1 �V�R��̕������(���a40�N��ȑO�̍삩)
�@�@
�@������������̒��ł����炭�ł��Â��A�m���ɔ����I�ȏ�O�ɑ���ꂽ�ƍl�������ł��B����͕�����ŁA�ގ��̓V�����c�Q���낤�Ǝv���܂��B��ɂ͕ʂ̍�҂ɂ���Đ��삳�ꂽ�������Ɣ��f��������������Ă��܂������A��̌`�E�����E����ꂽ��Ȃǂ��r���āA���25����������҂ɂ�鐧��ł͂Ȃ����Ɛ��肵�܂����B
�@���́A�ʏ����ԥ������⏫��j�n����ԥ������7�킪����܂������A��Ɉꏏ�ɓ����Ă����p�s�̋�͎c�O�Ȃ��疾�炩�ɕʂ̗��������(������)�ł����̂ŏ��O���܂����B������ꂽ�������́A���ɂ�����������Ƃ������ƂȂ̂ŁA���̋�̒��̊p��⥕��̕������̒��ɂ����`�œ��l�̒���̋�����Ă��Ȃ����ǂ����m���߂Ă݂悤�Ǝv���Ă��܂��B
�@���̋�̍�҂͒N�ł��傤���B�ʏ��̋�K�ɂ͢�V�R��̖������܂�Ă��܂��B���_���ɉ]���A�M�҂́A���̓V�R���̋�̍�Ƃ͐X�R�c�O�t(1900�`80)���Ɛ��肵�܂����B�X�R���́A���ɂ��̃R�����́u����8�v�́u3. �蒤��̖��H�����̖��Z�v�̒��ł��Љ������̖��H�ł��B1973�N��NHK�e���r�ŕ��f���ꂽ�u�V���{�I�s�v�ł́A�u��������v������V���̒����̖��H�Ƃ��Ď��グ���Ă��܂����B�X�R���̒�������́A�e���r���f���ꂽ���͂܂��u�ō��N���X�̖���v�Ɛ�^����Ă͂��Ȃ������悤�ł��B�������v���40�N�o�������ł͏N�W�Ƃ������玊���̒����Ƃ����]������悤�ɂȂ��Ă��܂��B�X�R��̋���́A���݁u���R�v���悭�m���Ă��܂�(���̃R�����ł��A�u����10�E�鉺���O�O�x���̐��グ���v�Ŏ��グ������A�u���R��v�̖��䂦�ɐX�R�t�̍�Ɛ��肵�܂���)�B�������A�V���s���s���Y�ۂ�1998�N�ɔ��s�����w�V���Ə�����x�Ƃ������q�ɂ��A�X�R���͕��R�̑��ɂ��u�V�R�v�̖����p���Ă����܂���[�P]�B�����炭���̋�̌����Ȓ��肩��l���Ă��A�X�R���̍삾�Ƃ����\�����傫���Ǝv���܂��B
�@���Ìy�x���̌m�Ë�ɂ́A���ɂ��u�V�R�v�̖������钆����������܂����B�܂��A�������������Łu���R�v�Ƃ������̂�����̂�����܂����B�������t���̂����g�̒������ɂ́A���̋���������Ă��葢������Ԃ��̂܂܂ł͂Ȃ������Ǝv���邱�Ƃ��c�O�ł��B
�}2 �V�R�E���R���̒������
�@�@�@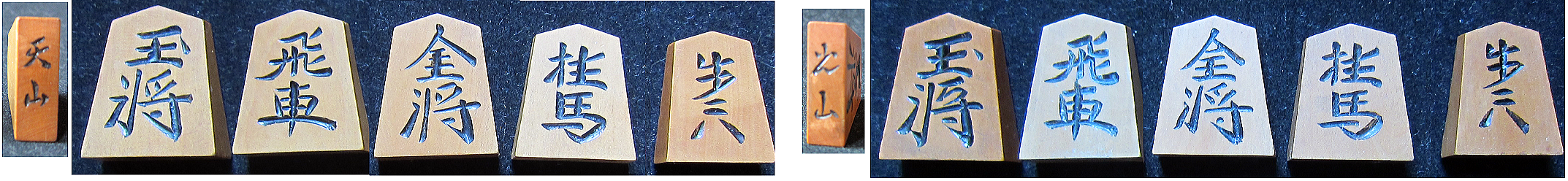
�@����ɁA�u�����v�Ƃ������̕���������A����͌��X�̈�g�������Ă���悤�Ɍ����܂����B���Ԃ̖��́A���݂͘V�܋�X�̋@�B�����ɒ����Ă��܂����A������́A�@�B����ł͂Ȃ��蒤�莞��̌��ԋ�ł͂Ȃ����ƍl���܂������A���Ă������ł��傤���B
�}3 ���Ԗ��̕������
�@�@�@
�@���̂悤�ɁA�Ë�̐����͕M�҂ɂƂ��ċ����̐s���Ȃ���ƂŁA���ł��p�����ł��B
�@�������A�Ղ��������Ɏg���Ă������l������܂��B������ꂽ�Ջ�����̂܂ܖ��点�Ă������̂łܑ͖̂Ȃ����Ƃ͂����܂ł�����܂���B���鉺���O�O�x���ɂ͌m�×p�̔Ջ�ɂ͂�Ƃ肪����܂��B�����Ŏx�������̓��̒��ɁA�����x���̌m�ÂɎQ������Ă���O�O��w�������̊F���w���őǂ��鎞�ɂ��ǂ��Ջ���g���Ė������ǂ����A�Ƃ����A�C�f�A�����̂ł����B
�@�������Ďx�����Ō����������ʁA�r�t���ՂƋ��A�c�Q�̒������O�叫�����Ɋ��邱�Ƃ����܂�܂����B�c�Q��͒���������荇�킹�ĎO�g(���̂�����g�͌��ԍ�̖�������܂�)�A���ɑO�҂ŏЉ���A�v�l�쒷�^���̖����������܂��B
�@���đ�R�\�ܐ����l�́u�ǂ��Ջ�Ŏw���̂��A��B�̑����ł��v�ƌ���Ă����܂����B�O�叫�����̊F����w�����ɐ��i����A�Ăь������đS�����ő劈��邱�Ƃ����҂��Ă���܂��B
�@�x���ł́A����10��30��(�y)�̗[���̗��ɍ��킹�āA�O�叫�����ւ̔Ջ�掮�����{�������܂����B�����͒n���̗����V��̕�����ނɗ����A11��8���ɔՋ��̗l�q�����ʂ�����܂����B���̃R�����������̊F�l���}���قȂǂŗ����V�������ǂ���������Ί������v���܂��B
�}4 �O�O��w�������Ɋ��ꂽ�Ջ�̈ꕔ
�@�@�@
�@�@�r�t���ܐ��Փ�ʂƊ��ꂽ�����B���͉v�l�쒷�^���������A�E�͒������B
�@�܂��A���ĒÌy�x���ł��w���������������M�҂Ƃ��ẮA�������ĔՋ�����������������ł������Ƃ��{��搶���V���Ŋ��ł�����ƐM���Ă���܂��B
�t�^�@���̗��������ɂ���
�@����������Ƃ����A�V���Ǝ��́u������E������E�������v������܂��B����������炪������̑S�Ăł͂���܂���B���n���ł��l�X�̃^�C�v�̓Ɠ��̗��������[�Q]���p�����Ă��܂����B
�@���͂Ɖ]���A�����̗�������̕�����ɐ������Ă���A�V���̗�������͂����͕킵�����ƂŐ��������̂��낤�Ǝv���܂��B
�@����x����������̊����̒�����q������@�����܂����B����́A�u���u�v�Ƃ��������ł��B�u���u�v�Ƃ́A���X��������吳���ɂ����đ��Ŋ������c�J�i���̎�l��������t�E���c��O�Y[�R]�̖��Ƃ���Ă��܂��B���c�͍]�˖������瑱��������̓`�����p���Ŏ��ɑ����̋�𐧍삵�܂����B��O�Y�A�q���̑��c�Б�(���u�����v)�E���́u�M���v�̑���������́A���݁u����W���v�Ƃ����T�C�g�Ŋӏ܂��邱�Ƃ��ł��܂��̂ŁA�������������̕��͂�����������������B(https://jade.co.jp/kigu/index)
�@����鉺���x������̕����猩���Ă������������̒����́A������c�J�i�������삵����ł͂Ȃ����낤�Ǝv���܂��B�������A��K�́u���u�v�̎��̂��Ɠ��Ŗʔ����A������V���̗�������Ƃ͂��Ȃ�قȂ閡�킢�������Ă��܂��̂ŁA���Ђ����������B
�}5 ���̒����E�u���u�v
�@�@�@
[�P] �V���s�ό����Y�ەҁw�V���Ə�����x(1998�N��)26�ł��Q�l�ɂ��܂����B�܂��A�{��וv�u�V��������Y�n�̕ώ��v(�w���m�����w������ 41 �Љ�Ȋw�ҁx1992�N)14�łɂ��A����t�X�R���̗p�������Ƃ��āA�u���R�v�̂ق��Ɂu�V�R�v�E�u�V��v�̍����Љ��Ă��܂��B
[�Q] �F�V�Ǒ����ɂ��A���Ċ��n���ł́A��̈����𐳋K�Ȏ���Œ���������u����(�ԂЂ傤)����v�A�ȒP�ɋL���̂悤�Ȏ��̂Œ���������u����v���Ă�ł����A�Ƃ������Ƃł��B�u���v�Ƃ������t�ɂ́A���ŋC�܂���Ȓj�A�Ƃ����Ӗ�����������A��������A���K�̎���ɂƂ��ꂸ�������ł�������ƒ���������w�����Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B�F�V���͂������̑�\�I�ȁu����v�̏��̂��Љ�Ă��܂�(�u����T�K�@��18��@��㒤��E����v(�w�����}�K�W��1995�N6�����x90�ňȉ�)���Q�l�ɂ��܂���)�B
[�R] ���������Ɋ��s���ꂽ�w�؍ރm�H�Y�I���p�x(1912�N�A����{�R�щ�s)�ɂ́A�u������v�̍����L�ڂ���ۂ̋��͎҂Ƃ��āA�u�勴�@�j(�@��)�v�ƕ���Łu���c��O�Y�v�̖����L����Ă��܂��B��O�Y�͏������ł͂����Ƃ������Ȑl���̈�l���������Ƃ�������܂��B
��������̂������i����13�j�K�c�I���Ə����i����1�j���U���������D�����I���搶
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@����́A����܂łƂ͈�]���A�ߑ���{�̕����E�K�c�I��(1867�`1947)�Ə����̊ւ������グ�Ă݂����Ǝv���܂��B�I���Ƃ����A�u�g�I疉�[�P]�v�ƕ��̂���ꂽ�l�ŁA�M�҂��Ƃ������������͈̂ꑽ����搶�ł��B�����A�������L�̋��{�l�ł��锽�ʁA�Ⴂ���k�C���]�s�ɓd�M�Z�t�Ƃ��ĕ��C���Ă������ɂ́A���n�̌|�ҏO�ɐl�C���������Ɠ`�����A���Ȗʂ��������l�ł����B�܂��A��̏����D���ŁA�V������̖�����\��N(1896)�ɁA�����Ă��܂��������̎w����̂��Ƃ��l���邠�܂茴�e�̎��M�܂őa���ɂȂ�A���ɍȂ����|�߂���قǏ����ɔM������[�Q]���Ƃ�����܂����B���̍e�́u�����Ɋւ��邱�ƂȂ牽�ł��e�[�}�ɂ��悤�v�Ƃ��������{�ʂ̎G���䂦�A�����̂��Ƃ͓V���̘I���搶��������������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�I��(�{���E���s)�́A�c���O�N(1867)�ɖ��b�E�K�c�����̎O�j�Ƃ��āA���̉��J�ɐ��܂�܂����B�K�c�Ƃ́A��X�喼�̎掟������u�\��V��O�v(�����钃�V��)���߂Ă���A�L�E�̎���w�|�ɉ��̂���ƌn�ł����B�\��̉��Ɍf�ڂ����I���̏ё��ׂ̗ɂ��開���̍��̐؊G�}������ƁA���J�ɂ������K�c�Ƃ̋ߗׂɂ́A�\�y�t�E�����̌��t�E��t�E���l�ȂǁA�����Ɋւ��l�X�̖����L����Ă��܂��B�����āA���̒��ɂ͏����̑勴�{�Ƃ̏\�ꐢ�@�j(1804�`74)�̖�������܂�[�R]�B�I�������w�E�j�`�E�l�̕���Ŋ��A���ɉ䂪���ŏ��߂ď����̗��j�ɂ��Ă��l������悤�ɂȂ����̂́A�K�c�Ƒ�X�̉ƌn�⏭�N���ォ��̎��ӂ̊�����������̉e����^���Ă���̂�������܂���B
�@���ĘI���́A�Ⴋ���ɐV�Ȃ��|���������āu�������牓������v�悤�ɂȂ����A�ƐU��Ԃ��Ă��܂����A�����炭���̋ސT�͒����������A�₪�Č��ǂ��菫�����y���ނ悤�ɂȂ����̂��낤�Ǝv���܂��B�������̎���E嗋����ɂ́A���M�̖T��A���q�Ƒǂ��y���݈�l�������ׂɋ��ޘI���搶�̓��X�����������Ƃł��傤�B
�@�����ō�Ƃ̍K�c��(1904~90)�́A�����炭����������吳����̕��̎v���o�Ƃ��āA�u�Â����������āA�������A���̂��݂����A�Ƃɂ����O�����ЂƂ�ŋ�����������Ă��邱�Ƃ�����A���ɂ͋ߏ��̘V�l�����ŋ����Ă������Ƃ�����A�Ղɂނ����Ă��镃�̎p�́A���܂����̖ڂɎc���Ă���v�Əq�ׂĂ��܂��B���̐��z�̒��ŕ��́A�c�����ɕ����珫���̋��p�����V�т������Ă���������Ƃ�U��Ԃ�A�u���Ƃ��c���̂��Ƃ�����A�����ŗV�ԂƂ����Ă��A�ӂ菫���A�ςݏ����A�͂��������A�Ƃя����ȂǂƂ��������̂Ȃ����ƂŁA�����ȏ�͕����ꏏ�ɗV��ł����y�����������낤���v�ƒԂ��Ă��܂�(�Ƃ��ɍK�c���u�ӂ菫���v[�S]���)�B
�@�����ׂ����Ƃł����A���������Ƃ̏����V�тɂ��I�����p�̋M�d�ȔՋ�p�����Ă��܂����B�u�����Ղ͕��̑厖�ȕ����̂ɁA�q���ɂ͂��Ȃ�Ȃ��������̂ƌ�����B�V���Ƃ͒��J�ɟT���̂���Ŕn�q��@������ꂽ�v(�K�c���u���ڂ�ځv�A�V�����Ɂw����Ȃ��Ɓx���)�B
�@�I���Ə�����ɂ��ẮA���X��ŏq�ׂ邱�Ƃɂ������Ǝv���܂��B
���q�������̏����V��(��V��)�ɂ���
�Z�K�c�I���@�w�����G�b�x�u���������ėV�ԕ��@�v ���@
���̏��������ėV�ԕ��@�́A�{���̂ق��ɂ����Ƒ����B�ӂ菫���A���������A�͂��ݏ����A�ǂ������A�Ƃя����A�ʂ��ݏ����A
�͂��������A���͂֏����Ȃǐ��Ȃ�B�����A�ӂ菫���A�ʂ��ݏ����A�͂��������͏����̋Y��ɂ��đ�l�ׂ̈��Ɋ��ւ�����̂Ȃ�B���������ł��������낭�A�ǂ������ł�����������ށB
�Z���c�K���w�]�˂̎q���V�ю��T�x���
�u�c�q�������̊ԂŗV����V�т́u���ݏ����v�u�e�������v�u���ݏ����v�u�U�菫���v�ł���B�ȏ�́u�����V�сv���q�������́u�����v�ƌ����A�{�i�I�ȏ������u�{�����v�ƌ����ċ�ʂ��Ă����B�{�����́u�{�v�͖{���A�{���́u�{�v�ŃE�\�̔��Όꂩ��t�������̂ł���B�v
�@�@�@�@�@�@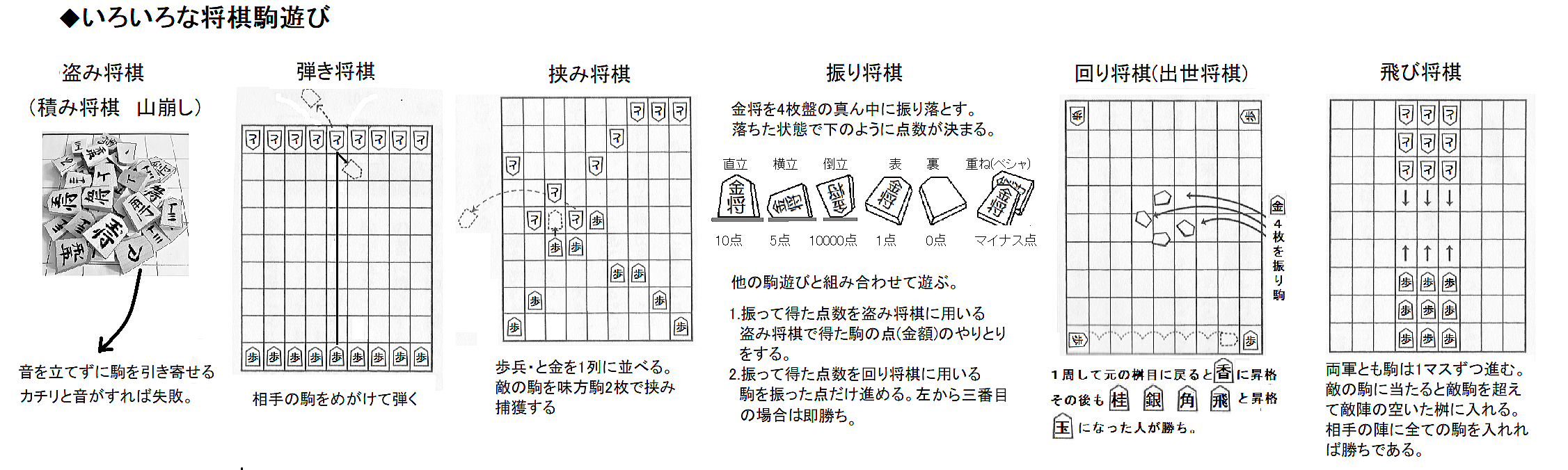
�@�������A���Ƃ̏�����V��[�T]�͖��ɂƂ��Ċy�����v���o����ł͂Ȃ������悤�ł��B���Ԃ̐e�͎q���ƗV�ԂƂ��͏������Ă��̂����ʂ��Ǝv���̂ł����A�I���͏����̌������������悤�Ƃ����̂��A�q�������Ƃ̗V�тł������ď������肹���A���������������Ă��܂��l�ł����B
�@���ꂾ���ł͂���܂���B�����\��ɂȂ��ĕa��Ȍp��ɑ����ĉƎ������Ȃ��悤�ɂȂ���������A�I���͕��ɑV�𐮂������A�������݂Ȃ���������ׂ��y���ނ悤�ɂȂ�܂����B
�u�����Ղ͑V�ƂȂ�ׂ��Ēu�����l�������͂��܂�A���ɂ͏������Ȃ���Ղ̖{����������B���Ղ͎����ǂ�ł������A���Ղɓ����Ă��낻��r��Ă���ƁA���̕������X�̕����낤�Ƃ����X�̋����낤�ȂǂƓ��Ăɂ�����B���X�Ǝv�Ă��Ă��̂��]��Ȃ��B�܊p�̑䏈�̐S�Â��������ɂ��āA�����Ȃ��₦��ɂ܂����A�����u������ӂ��ށB�c(����)�c�������̂��̂��h���������Ƃ���֎����Ă��āA���̉A�C�ȉs����ɑ������āA����Ƃ��]���Ȃ��߂����A�܂�������V�Ȃ��Ƃł������B���̑���͂��т��т�����ꂽ�B�c���āA��т����ȂǂƂ������Ƃ�m��悵���������A���v���Ă݂Ă����Ȃ����悤�ȋ�C��������B�\�l�܂̂���A�����Ȃ݁E�y���݂̂��߂Ɂu�n�q��(���܂݂�)���炢�͖����Ă����Ȃ��Ắv�Ƌ����Ă���悤�Ƃ������A�E���ۂ��Ă͂����肢�₾�Ƃ��Ƃ�����B�ςȊ�����������͋����Ȃ������B�v(�O�f�E�u���ڂ�ځv���)
�@�\��O���̖��ɂ���Ȉ��������镃�e�́A���̐��ł���u�����s�ҁv��掂���邩������܂���B�܂��A�������������������n�߂��������������ɂ��Ă��܂������Ƃ́A�����t�@���̈�l�ł���M�҂��猩�Ă��A�{���Ɏc�O�łȂ�܂���[�U]�B
�@����͂Ƃ������A���̂悤�ɖ����������ׂɗ�ނ��������āA�I���̊��͂͂Ȃ��Ȃ��̂��̂ł����B���݂Ɣ�ׂĒi�ʂ̔F�肪�����������Ǝv����吳����Ɏl�i�ʂ�F�߂��Ă��܂��B�ӔN�ɂ͖ؑ��`�Y�\�l�����l�Ƃ��u�p�����v�ł����Αǂ������Ƃł��m���Ă��܂�[�V]�B
[�P] �����܂ł��Ȃ��u�g�v�͔���g�t�A�u疁v�͒ؓ�疗y�A�u���v�͐X���O�̂��ƂŁA����4�l�͖��������\���镶�����Ƃ����Ӗ��ł����A���̎O�l����呲�������̂ɑ��āA�I���͉ƌv�̎���Œ��w��ފw������܂���ł����B���ތ�16�ŋ�����w�������M�Ȃ̓d�M�C�Z�w�Z���o�āA�k�C���]�s�œd�M�Z��Ƃ��ċΖ����Ă��܂������A21�Œؓ�疗y�́w�����_���x�Ȃǂ�ǂ�ŕ��w�ɖڊo�߂ď㋞�A2�N���23�ŕ��d�ɓo�ꂵ�܂����B����ɂ���3�N���1892�N�w�d���x�ňꗬ��ƂƂ��Ă̒n�ʂ��m������Ɏ���܂��B
�@���Ғ��u���������v�́u�����v�͊��ɂ���ĕ\������Ȃ����߁A�c������̗��������������u���v���g�p�����������܂����B���������������B
[�Q] �u������������鏫���̈�g�肩�ȁv�́A���̎��̂��Ƃ��r��傾�Ƃ���Ă��܂��B�u�����ɕ����A���ɂ��Ă����ɂ����Ė���Ȃ��B�[��܂ōl���āA����Ƃ̂��Ƃŋl�ߎ肪������B��т̂��܂�ɑ吺���グ���Ƃ���A�u���e���������ɁA����Ȃɖ{�C�ɂȂ��Ă���̂��������Ƃ͂Ȃ��B�{�Ƃł��Ȃ������ɖ����ɂȂ��āA�n�������吺���o���Ƃ͏�Ȃ��v�ƁA�V�Ȃ��猵�����|�߂�ꂽ�Ƃ����b�́A�Ⴍ���ĖS���Ȃ����Ȃ̎v���o�Ƃ��āA�����ΐe�����l�Ɍ���Ă���v(�z�q�M�`�w�����̔����w�x�O�ꏑ�[�A1995�N���A87��)�B
�@�M�҂��܂ߑ����̏����t�@���ɂ��A����ɗނ���o�������ЂƂ͑����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
[�R] �������A����G�ꎁ���w�E�����悤�ɁA�؊G�}�̖��͒n��܂��͉Ǝ����������̂Ŏ��ۂ̏Z�l�ł͂Ȃ��ꍇ������̂ł��̓_�͗��ۂ��ׂ����Ƃ����ׂ��ł��傤�B���ۑ勴�{�Ƃ̏ꍇ���A�q�̒n�ɉƎ�(���)��u���đ��l�ɑ݂��A�����͂�������ꌬ�u������k�O�̒��c�����Ɏ؉Ƃ��Ă��܂��� (�����w���R�Ɓu�����w����v�@�����@�Ə\���́u�勴�ƕ����v��ǂށx�m��ЁA2005�N���A124�ňȉ����Q�Ƃ��܂���)�B
�@�����A���Ȃ��Ƃ��I���̗c�����ɂ͏����̑勴�Ƃ������ɏZ��ł������Ƃ͊m���ł��̂ŁA�ނ������ɐe���ނ��������ɂȂ����\���͂���ƍl���Ă悩�낤�Ǝv���܂��B
[�S] ���|�t�H�ҁw�u�҂����v���������@�������\��b�x(���t���ɁA1988�N��)210�`211�ŁB���̐��z�́A���X�w�������E�x1971�N8�����Ɍf�ڂ��ꂽ���̂ŁA��Ɂw�K�c���S�W��19���x�Ɏ��^����Ă��܂��B
[�T] ���́A���̍��I�������������o��ƗV�юU�X����������V�тƂ��āu�ǂ������v�Ƃ����Q�[���������Ă��܂��B�I�����g���A�w�����G�b�x�̒��́u���������ėV�ԕ��@�v�̍��ŁA�ǂ��������u�ł��������v(������m�I�ɖʔ���)�ƍ����]�����Ă��܂��B�������A�c�O�Ȃ���M�҂����ׂ�����ł́A���ݒm���Ă���q�������̏����V�т̎�ނ̒��ɂ́u�ǂ������v�̖��O�͌�������܂���B���̈���A�I�������������V�тƂ��Ă悭�m���Ă���͂��́u��菫���v�̖��������Ă��Ȃ��̂ŁA����������Ɓu�ǂ������v�́u��菫���v�̂��Ƃ������Ă���\��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B���ۉ�菫���ł́A���̋��Z�҂̋��ǂ��z���Đi�ގ��ɂ��̋�������1�}�X�u�ǂ��āv�ǂ��z�����Ƃ�����܂��B
[�U] ���̈��݂Ȃ���̊������ׂɌJ��Ԃ��t�����킳��āA������x���������匙���ɂȂ����̂͊m�����Ǝv���܂��B�����������D�����������I���̎p�����łȂ��A���Ԉ�ʂɒm���邱�Ƃ��w�ǂȂ���������\���l�̎v���o�܂ŏ����L���Ă��镶�͂Ȃ�(�w��ށx�u�k�Е��|���ɁA1994�N��)������ƁA��͂蕶�搶�́A���̌�������ɂ��Ȃ�S�������Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���ĂȂ�܂���B�w�K�c���Θb�x(��g���X�A1997�N��)�ɂ́A���������������I���̎v���o�̐��X��ؑ��`�Y�\�l�����l�ƌ�荇���Ă��܂��B
�@�Ȃ��A���̑Θb�W�ɂ͑���ł������āA������̕��ɂ͊p�쏑�X�В��̊p�쌹�`���Ɓu�G�k�j�n�v�Ƃ����ʔ����薼�̑Βk�����^����Ă��܂��B�I�������Ɂu���܂��͂ǂ����j�n�Ɋ�������悤������A�l�Â������͂�قNjC�������v�ƒ��ӂ����Ƃ����b(�K�c���w�݂��������x��g���ɁA48��)������A�v��ʕ��p�ɔ��ł���������������߂�Ȃ��Ƃ������j�n�Ƃ�����̓��ِ��ɂ��ẮA�����̊ԂŃC���[�W�����L����Ă����悤�ɂ��v���܂��B���̑Βk�ɂ͋������䂩��܂��̂ŁA�@�������̑���ł̑Θb�W�����Ј�x�ǂ�ł݂����Ǝv���܂��B
[�V] �I����50�̎��A�吳�ܔN(1916)�ɏ���\���l���珉�i���A�����N�Ɉ��`�Y���i�����i��������܂����B�����56�ɂȂ����吳�\��N(1922)�ɂ͊֍��\�O�����l����l�i��������Ă��܂��B�܂����a��\��N(1947)�ނ���������ƁA���{�����A���͘Z�i�ʂ�Ǒ����܂���(�O�f�E�w�����̔����w�x84�ŎQ��)�B
�@�ؑ��\�l�����l���I���@�����߂ĖK�ꂽ�̂́A���a6�N���̂��Ƃł����B�ؑ��͓���20��̔��ŁA���łɔ��i�ɏ��i���Ă��܂����B�I���͎Ⴋ�V�˂̖K�����сA���瑬���̃J�N�e���������Ă����߂�Ȃǂ��đ傢�Ɋ��҂��܂����B���Ζʂ��������̎��ǂ͂���܂���ł������A���̌㏺�a8�N1������́A����ɏ����Ċp�����őǂ���悤�ɂȂ�܂����B���̍ŏ��̊p������̋L�^�́A�ނ̎��㏺�a26�N(1951)�ɔ�������Ă��܂��B�ؑ��͘I����S���瑸�h���Ă���A�I���Ƃ̏����͐����s���Ďw���܂�������A���ʂ͘A��A�����������Ƃ͂����܂ł�����܂���B�������A���̂悤�ɖ��l���S�͂�s�������̂ɁA��ǂ����ł����I���̏����ɂȂ������Ƃ�����܂����B�I���́u���̂Ƃ������͔����E��k�킹�Ă������Ɋ��������������Ƃ����v(�w�ǔ��V���x���a26�N2��29���t�̋L�����)���Ƃł��B���l�͘I���̖��̕��Ɂu�搶�͂������̍őP�̎���w���Ă��܂����ˁB�킽���͐搶�ɂ͈��������Ȃ�����Ŏw���܂�������Ԃ��炢�͕����Ă��܂��ˁv�Ɖ�z���A�f�l�̐��������I���̊m���Ȋ��͂��،����Ă��܂�(�O�f�w�K�c���Θb�x106�E107��)�B
��������̂������i����14�j�K�c�I���Ə����i����2�j���{���̏����j�����E�w�����G�l�x
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�O��q�ׂ��悤�ɁA�K�c�I���́A�V������ɏ����ɔM�������������ߍȂ����|�߂��āA�����̏����������ނ����Əq�ׂĂ��܂��B�������A�₪�ď����ւ̊S�����߂��Ƌ��ɁA���̖ʔ����Տ�Q�[���̗����ɋ������o���A�����j�������������ƍl����悤�ɂȂ����̂�������܂���B
�@�����O�\�O�N(1900)�I���́A�G���w���z�x�ɏ����̔��˂Ɠ`�d���e�[�}�Ƃ����w�����G�l�x�\���܂����B���̍l�@�ȑO�ɁA���̃e�[�}�Ɍ��y���������͂���߂ď��Ȃ��A��O�I�Ȏ���Ƃ��āA�]�ˊ��́w�l�όP�}�b�x(1690)��w�{�������u�x(1747)�ŁA�V������ɋg���^������������{�ɏ�����`�����Əq�ׂ��L����A�w�ۊ��Z��V�}���x(���\���Ȍ�Ƃ���Ă���)�őv�ɗV�w�����m�����`�����Ƃ�����������Əq�ׂ��L���Ȃǂ�����܂����A������������ȒP�ɏЉ����x�̕����ɉ߂��܂���B
�@����ɑ��ĘI���́w�����G�l�x�́A�����j�Ɋւ���䂪�����̖{�i�I�Ș_�l�Ƃ���Ă��܂��B�I���S�W�̑�19��(�u�l�v)�Ɏ��߂��Ă���A���݂��ǂނ��Ƃ��ł��܂��B�@
�@�w�G�l�x�́A�S�W�ł�47�ł��߂Ă��܂��B���̂���14�ł����m����(�`�F�X)�̗��j�A18�ł��x�ߏ���(�����̏����E�ۊ�)�̗��j�A5�ł����҂̗��j�̔�r�ɏ[�Ă��Ă���A�����܂ł������̏����j�Ɋւ���_�l�ł��B����ɔ�ׂē��{������_���������͋͂�10�ő��炸�ŁA���e�I�ɂ�╨����Ȃ���ۂ������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����͏����j�����̐�l���F���ɋ߂��A���w�̘I���搶�ɂƂ��Ă��A�M���ł��镶�����Ȃ��Ȃ���������Ȃ������̂�������܂���B
�@�Ȃ��w�����G�l�x�́A�����̕���̂ŏ�����A�i���������Ƃ͊������܂����A����̉�X�ɂ͂��Ȃ�ǂ݂Â炢���͂ł��B�����ŕM�҂́A�{�e�ŘI���̌������ł��邾������ɋ߂��`�ɓǂݑւ��ė������悤�Ƃ��܂���[�P]�B
�@��������̗����ɂ͑��X��肪�܂܂�Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����ł��̎G�������ǂ݂̏����ցA��肪����ǂ����������������܂��悤�A���肢�\���グ�܂��B
�@�Ȃ��A���E�̏����̗��j�ɂ��Ă͓��R����������܂Łu�ԊO�ҁv�̌`�ŐF�X�Əq�ׂĂ��܂���(���m����(�`�F�X)�ɂ��Ắu�ԊO��2�v�ŁA�����̏ۊ�(�V�����`�[)�ɂ��Ắu�ԊO��3�v�ŁA�Ñ�C���h�̏����ɂ��Ă͢�ԊO��4��ŏq�ׂ܂���)�B�܂����s���������ȑO�ƌ����鏬�^�̏����Ƒ�^�̏����Ɋւ���w�����G�l�x�̓��e�𗝉����邽�߂ɂ́A�u�ԊO�҂P�v(�u�������Ƒ叫���̋�ɂ��āv)���𗧂�������܂���B�S���������̕��͂�������������K���ł��B
1�D���m�̏���
�@���āA���m����(�`�F�X)�Ɋւ���m���́A�������{�ɂ�鉢������̈ꎖ�ƂƂ��Ċ��s���i�߂�ꂽ�S�Ȏ��T�ɂ���Ĉ�ʂɂ��m����悤�ɂȂ��Ă��܂����B���̕����Ƃ��āu�����V�Y(Indoor Amusement)�v���������w�S�ȑS���@�˓��V�Y���x(1879)���a��E�o�ł���A���̒��Ń`�F�X�͢�ۊ���Ƃ��ďЉ��Ă��܂��B
�@�`�F�X(�ۊ�)�̋N���Ɠ`�d�ɂ��Ă��A
�@��������N�O�A���s�z�R(�q���h�X�^��)�j���e�p�������V�R�g�L���B�c�R����g�z(�y���V��)�j�`�d�V�A����c���h��(�A���r�A)�l�y���[���j�`���A�����[���l�������lj�(�X�y�C��)�j�`�t��A����ɂ��̖��̂�
�@��`���^�����K�(�C���h)�@���@��`���g�����O�(�y���V�A)�@���@��V���g�����W�(�A���r�A)
�ƕω����Ă������A�Əq�ׂ��Ă��܂��B��ʂɘI���́w�����G�l�x�����M����ɓ������āA���m�̕S�Ȏ��T�i�w�G���T�C�N���y�f�B�A�E�u���^�j�J�x�Ǝv���܂��j�̒��́u�`�F�X�v�̍��̋L�ړ��e���Q�l�ɂ����ƌ����Ă��܂�[�Q]�B�������A�����D���̘I������q�́w�˓��V�Y���x��ǂ\�����\������A���ꂪ�����̗��j�ւ̋����������������ɂȂ����̂�������܂���B
�@�܂��A��ɏq�ׂ܂����A�ނ͂���玖�T�ނ��炳��ɐi��ŁA���ڐ����̍ŐV�w���ɂ��������ă`�F�X�̗��j�I�N����T�����Ƃ������Ă��܂��B
�@�w�G�l�x�̒��ŁA�I���͂܂��A�`�F�X�̋N�����o�r���j�A�A�G�W�v�g�A�M���V�A�A���[�}�Ȃǂ̌Ñ㕶���ɋ��߂����A�Ñ㒆���ɋ��߂�������邱�Ƃ��Љ����ŁA�����̐��ɔے�I�ȗ����\�����Ă��܂��B�����āA19���I�㔼�܂łɐ����̊w�҂����\���������Ɋ�Â��āA
�@�`�F�X�̋N���̓C���h�ɔ�����Ƃ����u�C���h�N�����v���ł��L�͂ł���
�ƍl���Ă��܂��B����͈ȉ��̂悤�ȓ��e�̊w���ł��B
���`�F�X�̍ŌÂ̌��^�̓C���h�̏�����u�`���c�����K(�`���g�D�����K)�v�ł���
���`���c�����K�Ƃ́A�C���h�ł͏ۥ�n��ԥ���Ƃ����l�̌R���Ґ��̂��Ƃł���
���`���c�����K�́A�����l�R��\�����p���ď����𑈂��Q�[�����w���悤�ɂȂ���
���`���c�����K�́A6���I���Ƀy���V�A�ɓ���u�`���g�����O�v�ƌĂ�A7���I�ɃA���r�A�l�̊Ԃɗ��s���u�V���g�����W�v�ƂȂ���[�R]
���o�H�͕s�������A10�`11���I���Ƀ��[���b�p�ɓ`�d����
�@�����Č��݂̉�X�ɂƂ��ċ����ׂ����Ƃł����A�w�����G�l�x�ł́A���̃C���h�́u�`���c�����K�v�̍ŌÂ̌`�Ԃɂ��āA19���I�㔼�����ɍŐV�Ƃ��ꂽ��̊w�����Љ��Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@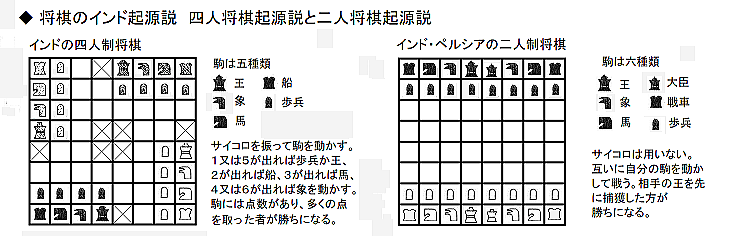
�@��́A�ŌÂ̏����̌`�Ԃ��A�T�C�R����p���Ďl�l�ŗV�ԁu�t�H�A�n���f�b�h�E�Q�[��(�l�l���̃T�C�R������)�v�������Ƃ������ł��B���̎l�l�������Ƃ́A18���I�㔼�ɉp���l�C���h�w�҃E�B���A���E�W���[���Y��(1746�`90)�����������x���K���n���̗V�тł����B�W���[���Y�����{�l�́A�����̓C���h�ł��ŏ������l�ŗV��Ă���A�l�l�������́A��l�ŗV�ԏ������y���V�A�ɓ`����ꂽ��ɁA�V���ɋ�������悤�ɂȂ����Q�[�����ƍl���Ă��܂����B�������A���̌�p������r���}��x���K���n���Ɋ����������Z�̃n�C�����E�R�b�N�X(1760�`99)�́A�W���[���Y���̔��������l�l��������������l�������̑c��ł���Ƃ������������܂����B�����āA���̐����̗p�����̂������h����w�����̃_���J���E�t�H�[�u�X
(1798�`1868)�ł��B�������āA��R�b�N�X�E�t�H�[�u�X��[�S]��19���I�㔼�Ɉꎞ���`�F�X�̎n���Ɋւ������Ƃ����悤�ɂȂ�܂���[�T]�B
�@�����c�O�Ȃ���A�R�b�N�X�E�t�H�[�u�X���̌��Ђ͒����͑����܂���ł����B1874�N�ɁA�C���h��y���V�A�����̒�����O�O�ɐi�߂��I�����_�̐w���@���E�f�A�E�����f(1833�`97)�́A�l�l�������ɂ��ďq�ׂ����ꕶ��������قnjÂ�����ɏ����ꂽ���̂ł͂Ȃ����Ƃ𖾂炩�ɂ��āA��q�́u�l�l�������N�����v�͑S���������Ȃ��ƒɗ�ɔᔻ���܂���[�U]�B
�@���@���E�f�A�E�����f�̌����́A���́w�����G�l�x����������20�N�O�ɔ��\���ꂽ���̂ł��B���ꂩ��150�N�o���܂����A�`�F�X�̋N���͓�l�������Ȃ̂��A�l�l�������Ȃ̂��Ƃ����_���͍����Ɏ����Ă����S�ɂ͌������Ă��܂���[�V]�B������120�N�O�̂��̎��_�ŁA�����̊w�҂����̍ŐV�̌�������w�ڂ��Ƃ���I���̒T���S�ɑ��āA�M�҂͐[���������o������̂ł��B
�@������ɂ��Ă��A�`�F�X�̃C���h�N�������ŗL�͂Ȃ̂͊m���ł��B�`�F�X�̓C���h����y���V�A�A�A���r�A���o�ă��[���b�p�ɓ`�d���A�����ʼn��ǂ���đ嗬�s����悤�ɂȂ�܂���[�W]�B
2�D�����̏����ɂ���
�@�I�������m�����̎��ɘ_����̂́A��������(�ۊ�)�̗��j�ł��B
�@�����ł͂��̋N�����ɒ[�ɌÂ�����ɂ܂ők��悤�Ȍ���������܂��B�������I���́A���w�̊m���Ȓm���Ɋ�Â��Ă����������������ے肵�Ă��܂��B
�@�Ⴆ�Β����̌Â������`���ł́A��3000�N�O�Ɏ��̕������u���@���������ɏۊ�������ꂽ�ƌ���邱�Ƃ�����܂������A����͑S���r�����m�ȑ��B�ɉ߂��܂���B
�@�܂��A�퍑����̌ÓT�̒��ɂ́u�ۊ��v�Ƃ����ꂪ�����܂����A���̌�́u�ۉ吻�̃Q�[���̋��v�Ƃ����Ӗ��ŁA���̃Q�[���͏����Ƃ͑S�����W�ȗV�т��Ƃ���Ă��܂��B
�@6���I�ɖk���̕���(543�`578)���w�یo�x���u�������Ƃ����j���ɋL�^����Ă��܂��B�����ł́A����������ɁA�ۊ��̋N���ɂ��āu���邪�ۋY�����͏ۊ���n�������v�Ƃ���������������悤�ɂȂ�܂����B�������A����̍u�����Ƃ����w�یo�x�͎U�킵�Ă���A���̎��̂͑S���s���ł��B���Ƃ����邪�u�ۋY�v�Ƃ������̃Q�[����n�����Ɖ��肵�Ă��A���ꂪ���s�����ۊ��̃��[�c���ƌ�����킯�ł͂���܂���B�I���́A�ۊ��̕���n�����ɂ��u�k���ɕ������Ƃ��ׂ��炸�v�Ɖ��^�I�ȗ���������Ă��܂��B
�@�������I���́A����̎���ɑ���ꂽ�Ƃ����u�ۋY�v�����s�̏ۊ��ƑS����ނ̈قȂ�Q�[�����Ƃ��Ă��A���̓������łɏۊ��̌��^�ƂȂ�悤�ȏ����ނ���������������Ȃ��Ƃ����\�����u�����ɂ����v�ƔF�߂Ă���悤�ł��B
�@����͂��Ă����A���݂̒����ۊ��̑c�^�Ɍ��y�����ŌÂ̕������ƘI�����l�����̂́A���邩��2���I�ȏ�o����������̍ɑ��E���m�}(779�`847)��Ƃ���������w�����^�x�ł����B���̒��ɂ́A���l�����̌R�����푈���J��L����Ƃ��������ꂪ����܂��B���̐푈�Ő���Ă���҂Ƃ��āA�u���v�u���ہv�u�R�t�v�u�㏫�v�u�V�n�v�u�n�ԁv�u�����v�Ȃǂ��������Ă��܂��B�����̒��ɂ͐i���̗l�q�����s�ۊ��̋�(���E�ہE�n�E�ԁE���Ȃ�)�̓����Ƃ̗ގ����v�킹����̂��������܂��B�܂�����̌����ł́A��l�����肽�Ƃ���ۊ��̔Ջ���@����A���錩�Ă����푈�Ƃ��������̌����͂��̔Ջ����[�X]�Ƃ������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂��B
�@������̕��ꂻ�̂��̂͑S���̃t�B�N�V�����ł��B�������A����̌���Ɉ����̏����ނ��������Ă������Ƃ������Ă��邱�Ƃ͊m���ł��B�������A���̎���̏����̔Ջ��[�����ǂ̂悤�Ȃ��̂��͎c�O�Ȃ���s���ł��B
�@���̂悤�ɓ���ɋ������Ă����ۊ��̑c�^�Ǝv���鏫���ނ��A���̌�̖k�v����ɂȂ��ĉ��ρE�C������܂����B���̌��ʁA���s�ۊ��Ƃ͈قȂ���̗̂ގ����������ނ�����ނ����o����Ă��܂��B�Ⴆ�Ζk�v����̊w�҂Ő����Ƃ̎i�n��(1019�`86) �╶�l�E�薳��(1053�`1100)�Ȃǂ̑�������^�̏ۋY�ނ����̒��ɐ������܂��B�����ĘI���́A13���I��v�̎��l������(1187�`1269)�̏����c���������Љ�Ă��܂�(�w�I���S�W19�x27�ňȉ�)�B�����ł́A
�@�� �u�ۚ�v��32�̋�ŗV��Ă���
�@�� �C�����ۥ�ԥ�n��m����̑S����̋���y����Ă���
�@�� �Ղ͉͊E�œ���Ă���@���X�̂��Ƃ��q�ׂ��Ă���A
�@����܂łɌ��ꂽ�l�X�̌^�̏����ނ���������A���s�ۊ��̌��^���قڐ�������Ƃ���܂Ői���Ƃ�������܂��B�����̏ۊ��͖k�v����̏I��荠�܂łɂ͊m�������\�����傫���Ǝv���܂��B�������ĘI���́A�����̏ۊ��ɂ��Ĉȉ��̂悤�Ȍ��_�Ɏ���܂���(�w�I���S�W19�x30��)�B
�@�� �ۊ��͑v�̎���Ɍ��s�Ƒ卷�Ȃ��`�ŗV��Ă���
�@�� ���s�ۊ��̐�l�ƌ���ׂ����̏ۋY�͓��̎���ɍs���Ă����Ɛ���ł���
�@�� ���̏����O�̎���ɂ��ۊ��̐�l����ۋY���V��Ă����\�����S���Ȃ��Ƃ͂����Ȃ�
�@�� ����Ɏ����k���āA�ۋY�������Ñ�ɂ����݂��Ă����Ƃ����؋��͑S���F�߂��Ȃ�
�@����ɁA�w�����G�l�x�ł́A���m�����ƒ����ۊ����A��̖��̂�\�E�����̔z�u�Ȃǂ��r���Ă��܂��B����ƁA�ӊO�Ȃ��Ƃɗ��҂����Ȃ�ߎ������Q�[���ł��邱�Ƃ�������܂��B�I���́A���������ނ̗��j�I�W�ɂ��Ď��̂悤�ȍl�����q�ׂĂ��܂� (�w�I���S�W19�x37��)�B
�@�� �����ۊ��Ɛ��m����(�`�F�X)�ɂ͌n����̊W������
�@�� �ۊ��͒����l�̑n�Ă������̂ł͂Ȃ��A�C���h����(�`���c�����K)�̎q���ł���
�@�� �����ۊ��Ɛ��m�����Ƃ̊W�́A���q�̊W�ł͂Ȃ��A�Z��̂悤�ȊԐړI�W�ł���
3�D���{�̏���
�@�I���̋L�q�́A�܂������E�ۋY�E�ۊ��Ƃ������̂���n�܂�܂��B�����ł́u�ۋY�v�u�ۊ��v�ƌĂ�Ă���A���{�ł̌Ăі��u�����v�͗p�����Ă��܂���B�䂪���ɂ����āu�ۋY�v�̎��ɂ͑S���a�P(�P�ǂ�)�������A����͉̂��ǂ݂����ł��B�ۋY�̋N���͕s���ŁA����V�c������9���I�Ɍ������Ҏ[�������a���T�́w�a��������x�ɂ͓���A�ş{�A�R�f�A����A�����A�����s���ȂǂȂǗl�X�̎G�|�ނ��L����Ă��܂����A�ۋY�͍ڂ��Ă��܂���B�������A�f�ڂ��ꂽ�G�|�ނ́A����́u�ڂ����v�A�ş{�́u�܂肤���v�A�R�f�́u�܂肱��v�A�����́u���肤���v�A�����s���́u�₳������v�Ƙa�P���L����Ă��܂��B�w�a����x�ɂ͏ۋY���ۊ����������L����Ă��Ȃ����A���̌���ۋY�Ȃǂ��P�ǂ݂���邱�Ƃ͂���܂���ł����B
�@��������I���́A�䂪���̏����͂����炭�ŏ�������{�l���l�Ă��đ���o���ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�����E�����E���N�Ȃǂ���`����ꂽ���̂ł͂Ȃ����ƍl���܂���[10]�B
�@�䂪���̕������ŏ����Ɍ��y�����o�T��Ƃ��āw�����G�l�x�������Ă���̂́A12���I�A����b��������(1120�`56)�̓��L�w��L�x�̍N����(1142)�N9��12���̎��̂悤�ȋL���ł�[11]�B
��Q�@�A����O�A�o�t�����b�w�叫��A�]����@
(�����@�ɎQ�サ�A��O�Ō��t���Ƒ叫�����w���B�]�̕���)
�@�������w��L�x�̂��̋L���́A�䂪���ŏ����Ɍ��y�����ŌÂ̋L�^�ł͂���܂���B�ŌÂ̋L���́A�����肩�Ȃ�O��11���I�ɓ������t�̒������w�V���y�L�x�̒��Ɍ�������̂ł��B�����ł͗l�X�̌|�\�ɏG�ł��l�����Љ��Ă���A�ނ̓��ӂƂ��鏔�|�Ƃ��āA�͌饙ԘZ��e���Ȃǂƕ���Ţ��������������Ă��܂��B���͏������w�V���y�L�x�̒��Ō��y����Ă��邱�Ƃ́A���łɍ]�˕������́w��V�Η��x�̎l�V���ŏq�ׂ��Ă��܂�(��g���ɔŁw��V�Η�(��)�x383��)�B�Y���ȘI���搶������������m�Ȃ������Ƃ͎v���Ȃ��̂ŁA����������ւ�ӊO�Ɏv���܂��B�܂��A�w��V�Η��x�ɂ͏�����Ă��܂��A���Ɂw��L�x�̋L����13�N�O�ɂ��A���t���́w���H�L�x�̑厡�l(1129)�N5��20���̏��ɁA���H�@�������̋��p���ĕ����̐肢���������Ƃ����L��������܂��B�����I�����A�w�V���y�L�x�Ɓw���H�L�x�̋L���̕�����s���Ă���̂�m��Ȃ���A�������������w��L�x�̋L�����Љ�����R������Ƃ���A�叫�����w�����L������������Ȃ̂�������܂���B���ہw��L�x�̏Љ�̎��ɁA�I���͓�����Ƃ̓��L�w�����L�x�̒��̏����L������叫���Ɍ��y�����Ǝv������̂��Љ�Ă��܂��B�����������犙�q�����ɑ�^�������w����Ă����Ƃ������Ƃ���A�I���́A���P���ȏ��^����������ȑO���狻�����Ă������Ƃ����������������̂�������܂���B
�@��������܂łɍl�Ă��ꂽ�e��̑�^�����ނ��Љ����ŁA�I���͌��s�̏����ɂ��āA
�u���̕��ʂɍs�͂�鏫���͑����߂Đ��ɓ`�͂肵�����炩�Ȃ炸�B�l�����͈��ւ炭�A���̏����͒��������o�ŁA�������͑叫�����o�ÂƁB�R��ǂ������đ��m����ɂ��炸�c(����)�A�c�\�͍��̏����̓`���̕K�������叫�����������̌�ɂ��炴��ׂ���z�ӂ��̂Ȃ�B�R��ǂ�������Ƃ̐����̂݁A�{�炭���������̓���҂ׂ���B�����\�������̏����������c�v�Əq�ׂ����ƁA���{�����̓`���Ɋւ��Ĉȉ���7�̗v�_���u�����v�Ƃ��Čf���Ă��܂��B
�@�� �䂪���̏����́A�������璼�ڈ��͊Ԑڂɓ`���������̂Ƃ��킴��Ȃ�
�@�� �叫���Ȃǂ̔ώG�ȏ����ނ́A�����l�̑n��ɂ��Ă͋�̖��̂���т������̂ł͂Ȃ����Ƌ^����B�]���Ē����ł͂Ȃ��䂪���Ő����������̂ł͂Ȃ����ƍl������
�@�� �Â�����̏����̒��Ɂu�叫���v���������ȂǂƑ咆���̎��������鏫����������̂́A�����ʂ̏��������������Ƃ��������̂ł͂Ȃ����ƍl������
�@�� ���s�����̋�̂����A�����A���ԁA�j�n�͂��̌Ăі��������ۊ��̕��A�ԁA�n�ƈ�v���A���̈ʒu���I�݂Ɉ�v���Ă���B�⏫�͂��̎��̂��ۊ��̏ہA�����͎m�Ɠ��l�ł���B�܂茻�s�̏����͒����ۊ��ɋ߂�
�@�� ���s�����̋�́u�����āv�ł͂Ȃ��͂Ȃ͂������ۊ��Ƃ͈قȂ��Ă���B��������́A��ޗǓV�c�����߂����߂ł���Ƃ������肪����B��̏����ނ́A���߂͂���قlj����Ȃ��������A���̍��ɂ��̈Ⴂ�͐������Ƃ��l������
�@�� ���s�̏ۊ��́w�����^�x���Î����铂�̏ۋY�Ƃ�⑊��_������A�ނ���䂪���̌��s�����̕��������^�̕��ɑ���������̂�����B�Ⴆ�u�V�n�Δ�x�O���v�Ƃ͌j�n�̔@���A�u�㏫���s���l���v�Ƃ͔�Ԃ̔@���A�u�n�Ԓ��������āv�Ƃ͍��Ԃ̓����ɋ߂��悤�Ɏv����
�@�� ���Ɠ��{�̌�ʂ͕p�ɂŁA�e���̂悤�Ɍ�ɒ����l���V�ѕ��������ł��Ȃ��Ȃ����V�Y����������{�ɓ`�����Ă����B�ۋY��������`�����Ă��Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��͂��ł���
�@�ȏ�I���̓��{�����N�����́A��������̏����`�������Ƃ����Ă悢�ł��傤�B�������A�]�ˊ��܂łɌ��ꂽ���Ƃ͈قȂ�A�L�����w�̑f�{�Ɋ���̂ł����B
�@��L7�̉ӏ������̂����A���ɕM�҂̊S�������̂́A����́w�����^�x�̎�����̓��������{�����ɋ߂����Ƃ��q�ׂ���6�̂�����ł��B���{�̍��Ԃƌj�n�̓����́A���E�e���̐��(���[�N)��R�m(�i�C�g)�ɔ��4����1��������������܂���B���Ɏア��ɂȂ��Ă���A���ꂪ���{�����̓��ِ��������Ă��܂��B����̏ۊ�(�ۋY)�̔n��Ԃ����s�̂悤�ȋ��������ł͂Ȃ������Ǝア�����ł����āA���ꂪ�䂪���ɓ`����ꂽ�̂��Ƃ���A���Ԃ�j�n�̓����̎コ������ł����̉����ɂȂ蓾��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�����܂ŘI���́w�����G�l�x�̓��e��e�q���܂������A�����ɏq�ׂ�ꂽ���m�����E���������̗��j�̊T���́A���ݒʐ��Ƃ���Ă��邱�ƂƑ����̕����ŏd�Ȃ荇���悤�Ɏv���܂��B���̏���120�N�O��1900�N�Ɏ��M���ꂽ���Ƃ͋����ׂ����Ƃ��ƍl����l�������ł��傤�B�������́w�����G�l�x�������̓��m�j�E���m�j�̊w�҂����ɒ��ڂ���Ă���A�`�F�X��ۊ�������Ȃǂ̗��j�������j�̈ꕪ��Ƃ��Čp���I�Ɍ�������Ă����\�����������̂ł͂Ȃ����Ɛɂ��܂�ĂȂ�܂���B�������1900�N���M�Ƃ��������邱�Ƃ͔ے�ł��܂���B�Ⴆ�Ό��X��������̓��{�ɂ͏��^�Ƒ�^�̓��ނ̏��������������Ƃ�m�邽�߂ɂ́A�w���x�̒��́u��\�O�E�������v�Ƃ����L�����K�{�̎j���Ƃ���Ă��܂����A�I���́w�����G�l�x���M�̎��_�ł����ڂɂ��邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B�O�c���݉Ƃɏ�������Ă����w���x���A���߂ď����̏d�v�����Ƃ��ďЉ���̂́A�I������15�ΔN���̌���w�ҁE���c�ꋞ��(1882�`1971)�ł����B�ނ�1910�N�ɎO�ȓ����犧�s���ꂽ�w���{�S�ȑ厫�T�x�̢������̍������M����ۂɑO�c�Ƃ́w���x�̎ʖ{�ɒ��ړ����Ă��̓��e��c�����Ă��܂����B
�@30�N�߂����1938�N�ɂȂ��āA�I�����O�c�Ƃ́w���x�������̖ڂŌ��邱�Ƃ��ł��܂����B�ނ͓ǔ��V���ɢ�����A��̕����Ƃ��Ċ��q���ȑO�ɑ�����Ƃ����L���\���܂����B���̋L���́A��Ɂw�ۋY�]�k�x�Ƃ��Ē����Ɏ��^����A���ݘI���S�W�œǂނ��Ƃ��ł��܂��B�I���̂��̕��͂�ǂ����j�����Ƃ̉z�q�M�`���́A�u�Ⴋ���A�w�����G�l�x���q�̂Ȃ��Őς݂̂������u�l�ւ̌��āv���A���\�ɂ��āA�w���x�̂Ȃ��Ɍ��o���B���U���ɓO����I���̉�S�̔����ł������낤�v[12]�Ǝ]���Ă��܂��B�M�҂��z�q���ɐ[��������\���������Ǝv���܂��B
�@����͘I���҂̍ŏI��ł��B���R�����̖{��u�I���Ə�����v���q�ׂ����Ǝv���Ă��܂��B
[�P] ����̂ŏ����ꂽ�w�����G�l�x�̌���u���R��v�����݂��̂��A�I���̏���A�I���S�W��K�c���S�W����|�������J�^(1916�`77)�́w�I���ƗV�сx(�n���ЁA1972�N��)�ł��B��łŏ��X�ł͓��肪����ł����A�X�����ł͍O�O�s���}���قŏ�������Ă��܂��B
[�Q] �z�q�M�`�w�����̔������x(�O�ꏑ�[�A1995�N��)�A91���B
[�R] �����̂�����́A�w�I���S�W��19���x (��g���X�A1979�N��)4�`5�ł����Q�Ɖ������B
[�S] ���̐����u�R�b�N�X�E�t�H�[�u�X���_�v�ƌĂ�A�ȉ��̂悤�ɒ莮������܂����B
�@(1) �C���h�ł͉���N���O����A�u�`���g�D�����K�v�����T�C�R����p�����l�l�`�F�X���V��������B
�@(2) �������̌o�߂Ƌ��ɁA��l�ŗV�ԕ�����A�T�C�R���Ȃ��ŗV�ԕ��������݂�ꂽ�B
�@(3) ��������̔z�u�����������A�T�C�R���Ȃ��œ�l�ŗV�ԐV�����`�F�X�����܂ꂽ�B
�@(4) ���̓�l���̃`�F�X��6���I�ȍ~���y���V�A�⃀�X�������`�d����悤�ɂȂ����B
[�T] �w�I���S�W��19���x5�`6�ł��Q�Ɖ������B
[�U] �w�I���S�W��19���x6�`7�łɎ��̂悤�ȋL�q������܂��B
�u�����甪�S���\�l�N�t�H���E�f���E�����f���͑����͂�s�������钘���w�����̗��j�y�ѕ��w�x�тɂ����Ĕ������A�����̋N����_�������X�����̑��r�����m�Ȃ邱�Ƃ��]�ւ�B�������������̋Z�͈�x���o�łĔg�z�ɓ`�͂��Ƃ�����̂Ȃ邪�A�t�H���x�X���̋ΘJ���ė��Ă���u�`���c�����K�v���́A���ׂ̈Ɋ�F��������Ɏ����B���H���A�u�`���c�����K�v�Ƃ��ӌ�͈�x�̌Î��l���ɌR���̏̂Ƃ��ėp���ꂽ���Ƃ͔V����A�V�Z�̖��Ƃ��ėp���ꂽ�邱�Ƃ������ĂȂ��A�^�̈�x�̌ÓT�Ђɏ����̎��̌�������͞��T���w�ׂ���̂̊F���ɔF�m����Ƃ���ɂ��āA�ނ́u�v���i�X�v�̔@���͜n�O��Â̏��Ƃ��ĐM�ꂽ��ǂ��A�ߗ��̌������S��Ă��̖�h�I����\���I���ȏ�̂��̂��炴��͖����Ȃ�A�����u�u�n�C�V���E�v���[�i�v�̓��{�̉p�������ًy�ѓƍ��}���قɑ���������̂ɂ́A�t�H���x�X���̈�������L���̏��A��X������������Ƃ���̂��̂ɑ�������ׂ��L���́A�����甪�S���\��N���x�b�N���̖���x�̏��u���O�i���_�i�v�Ɍ���Ƃ����ǂ��A�u���O�i���_�i�v�́A�s���������̈ӌ��ɋ���Ζ�h�I����\�Z���I�̂��̂ɂ��āA���͋���Ȃ����������炴����̂Ȃ�ƁB�v�B
[�V] 20���I�ł͎l�l���N�����Ɠ�l���N���������ї����A�l�l�����̕����D���������������������悤�ł����A���I��������21���I�����ɂȂ��Ă���́A��l�����̕��������҂̑����̎x����悤�ɂȂ��Ă��܂��B���̓_�ɂ��ċ������������̕��́A����G��w�`�F�X�x(�@����w�o�ŋǁA2003�N��)�������������B
[�W] �w�I���S�W��19���x9�`14�ł��Q�Ƃ��ꂽ���B
[�X] �u���A���Ԉ�杂��^����Ƃ���ɜn���������������B�H���A�����N��웨���A����l��b��H�A�������R�o�V�ߑ����D�A�����C�����V�A�锼�㓌�Ǒl���������A�L���R��w�����A���ފ���A�R�t�i�H�A�V�n�Δ�x�O���A�㛒��s���l���A�n�Ԓ��������āA�Z�b����s���s�A�����۔V�A���R���L�n�A���O�ڎ~�A���۔V�A�e�L�������A��s��ځA���۔V�A�Ԑi�A�{�k�C�������A�]�X�A��Ɛl�o�����F�S�ܜ��A�����@���ǁA�T�����L���Y�ǁA�Ԕn�����B�v(���܁w���Ԉ�杁x(���̕��l�E�Ӊ��ق̒���)�ɂ��q�ׂ悤�B���N����������Ƃ����҂��Q�Ă���ƁA���̒��ɊZ�𒅂����j������āA���ۏ��R���V�߂̑���Ɖ�풆���Ɠ`���Ă����B�����́A�C�𖾂邭���Ċϐ킷�邱�Ƃɂ����B�锼�ɂȂ��āA���̕ǂɍ݂����l�̌������ɕς��A���R���w��g��ő����A��������܂����B����ƌR�t���i�ݏo�ĉ]�����A�u�V�n�͎߂ɎO�Ƃщz����B�㏫�͉��ɐi�ݎl�������āB�n��(��)�͒��i���Ĉ����Ԃ��ȁB�Z�R�͏����𗐂��ȁv�ƁB���ۂ���Ɨ��R�Ƃ��ɔn���o�Ď߂ɎO�ڍs���Ď~�܂����B�܂����ۂ����ĕ�������ډ��ɍs�����B�܂����ۂ����ĎԂ��i�݁A�B�b�����ĖC�������A�]�X�B��ɉƐl�́A�����̊�F���Ђǂ��ܜ����Ă����̂ɋC�Â��A���̕ǂ�ł��ʂ��ƁA�����ɂ͌Â��˂�����A������͎Ԕn�Ȃǂ̋��������ۋY�Ղ����������B)�w�I���S�W��19���x23�`24��
�@�w�����^�x�̒��̉���杁u�����v�͌��ݎ����Ă��܂��B�������I���́A���Ȃ���16���I�㔼�̏��w���Ԉ�杁x�����ɏЉ�Ă��܂����A�ȗ������߂���悤�ł��B���͂��̕���͂قڑS�҂��k�v����́w�����L�L�x(978�N)�Ɏ��^����Ă��܂��B�����̘I���搶�ɂ��Ă���������m�Ȃ������Ƃ����͈̂ӊO��ӊO�Ƃ�������������܂��B����͂Ƃ������A�w�����L�L�x�������u�����v�́A�����w�҂̈ɓ��ό����ɂ���đS�����a��1986�N�w�����W���[�i���x���ɔ��\����Ă��܂��B���̎G���͔p���ɂȂ��Ă��܂��܂������A�ɓ�����u�����v�̕���́A���m�̖ؑ��`����i�̏����ꂽ�w����g�p�̓�@���{�����̋N���x(2001�N�A���{�����A����)��50�ňȉ��Ɏ��߂��Ă���A�������͍��ł������ǂނ��Ƃ��ł��܂��B�S�������ꂽ���͈�ǂ������߂��܂��B
[10] �u�E�̓ɘa�P�S���������ĉ����Ȃč����ĂԂɏƂ炵�l�ӂ�A��M�̏E���܂��{�y�̐l�̑z���ɏo�ł����āA�x�߂̏E���Ύx�ߎႭ�͗����A���N�����B�ւ����A���͎x�߂̏E�ɖ{�Â��ĖM�l����ʂɐV�ӂ��o���V�肵�Ȃ����A��篂ɔV��m��\�͂��B�c(����)�c��M�̛����͓ߖM��肩�炳�ꂽ����̂Ƃ�����ׂ��炸�A�R�炸��Ύx�ߏE�ɖ{�Â��ĖM�l�V���Ƃ�����ׂ��炸�B
�@ (�ۋY�̓��ɂ͌P�ǂ݂͑S���������ł����ǂ݂����ł���B����ɏƂ炵�čl����A�ۋY���䂪���̐l�X���v���t���Đ��܂ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�����A�����A���N�Ȃǂ���`����ꂽ���̂��A�����͒����ۋY�����ɂ��ĖM�l���V���ɉ��H�������̂������ꂩ�ɂȂ炴��Ȃ��B)�v(�w�I���S�W��19���x38��)
[11] �䂪���̕����ŏ����Ɍ��y�����ŌÂ̋L���́A11���I�̓������t��́w�V���y�L�x�̒��Ɍ�������̂ł��B�����ł͗l�X�̌|�\�ɏG�ł��`�{�P�V�Ƃ����҂��Љ��Ă���A���̓��ӂƂ��鏔�|�Ƃ��āA�͌饙ԘZ��e���Ȃǂƕ���Ţ��������������Ă��܂��B(���͏����̋L�������łɁw�V���y�L�x�̒��ɂ��邱�Ƃ́A�]�˕������́w��V�Η��x�ŏq�ׂ��Ă���A�I���搶�������m�Ȃ������Ƃ͎v���Ȃ��̂ł����ւ�ӊO�ł�)
�@�܂������́w��L�x�̋L����13�N�O�ɂ��A���t���́w���H�L�x�̑厡�l(1129)�N5��20���̏��ɂ��A���H�@�������̋��p���ĕ����̐肢���������Ƃ����L���������܂��B
[12] �z�q�M�`�w�����̔������x(�O�ꏑ�[�A1995�N��) 92�ŁB
�ҏW�@�����_��
�@






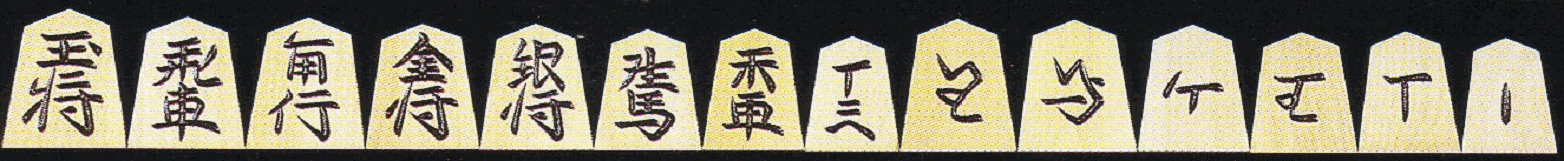





 �@�@
�@�@




 �@�@�@
�@�@�@
 �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@

 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@








 �@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@


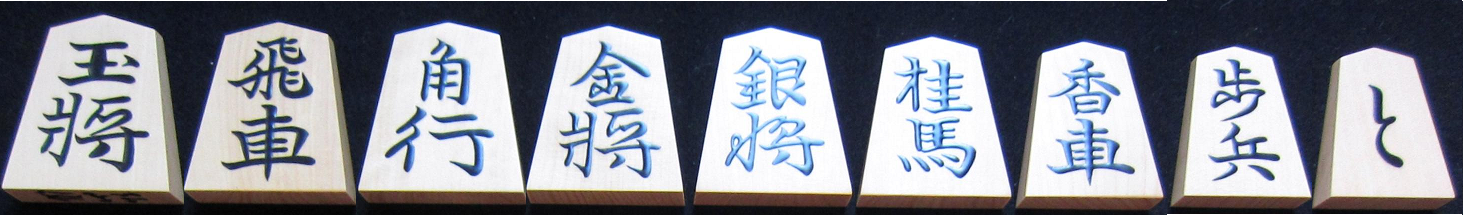




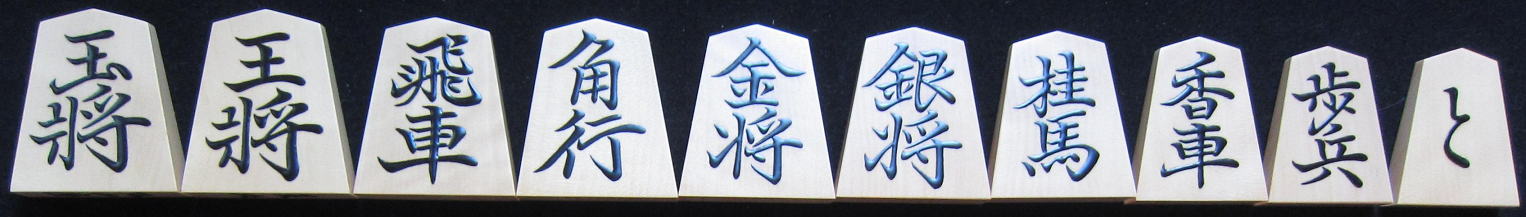








 �@�@
�@�@








 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@


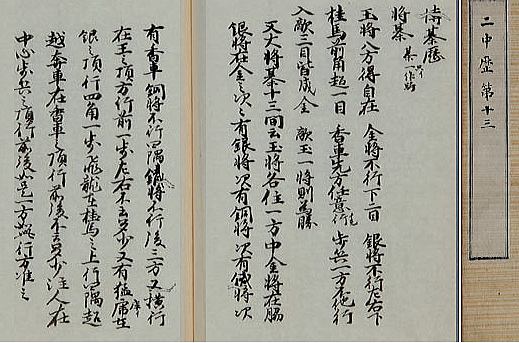
 �@
�@





 �@�@
�@�@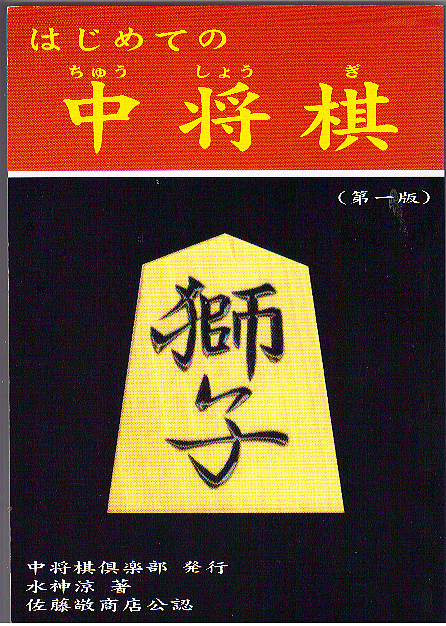 �@�@
�@�@

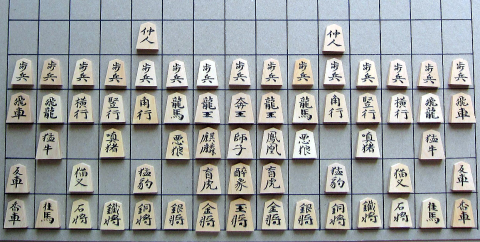
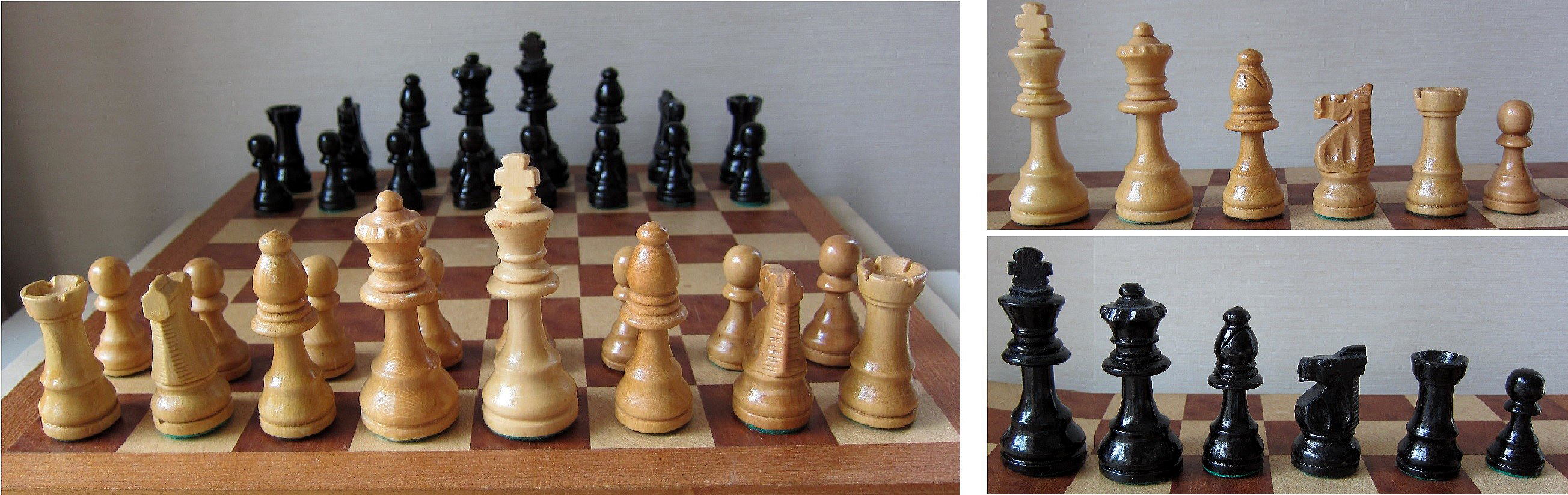

 �@
�@